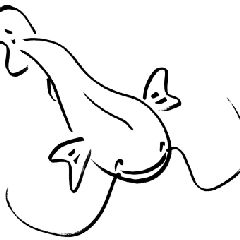尾池和夫の記録(194) 小豆島の猿団子を詠む
尾池和夫
猿団子を1度見たいとずっと思っていた。寒い時期に、日本猿が押しくら饅頭をしながら暖まるということを聞いたのは、ずいぶん前のことであるが、まだ見たことがなかった。松沢哲郎さんたちとの視察旅行で、幸島の猿を見たときにも、その猿団子を詠んで、冬の季語に登録されるといいなと話した。
俳句で詠む季語は、歴史の中で磨き上げられた日本の宝であり、歳時記にそれが集約されているが、その歳時記に新しい季語が登場するためには、歴史に残るほどの名句が詠まれることが必要である。まずはそのために猿団子の現場を見てその様子を俳人たちに広く紹介することにしたいと思っていた。
俳句の基本の中に、私が3現則と呼ぶ基本がある。「現在の現象を現場で詠む」という3現則である。自分の目で現象を観察して、そこに発見した瞬間の感激を、自分の言葉で切り取るというのが重要で、写真家が写真作品を残すのとまったく同じ基本である。
このような背景があって、1度猿団子の現場を見たいと思っていたが、京都造形芸術大学の文明哲学研究所の所長に就任した松沢哲郎さんの提案で、小豆島の猿団子を見に行く計画がまとまり、その旅行に参加したのである。
猿団子は体温を保持するために役立つという。体を寄せて冷気に触れる体表面積を少なくするのである。京都大学の研究者によると、猿のエネルギーの節約に役立つ現象で、約1割は節約していると推測したという。テレビのニュースでも毎年のように、猿団子が見られるようになったと、冬の風物詩として映像で紹介する。小豆島の銚子渓自然動物園にある「お猿の国」がとくに知られている。たまには街の動物園で撮影されたものもある。大分市の高崎山自然動物園に近い茶店では、「おさるだんご」と名付けた団子もある。宮崎県都城市柳田酒造の樽貯蔵麦焼酎には、猿団子剛と猿団子柔があるということも聞いたが、まだ試飲する機会がない。
さて、2017年2月16日、木曜日、ようやく小豆島へ行く機会ができて、京都駅を14時52分発ののぞみ号に乗り、岡山、高松、小豆島と移動した。土庄港では小豆島町の塩田幸雄町長らが待っていてくれた。ベイリゾートホテルに宿泊し、明日は寒くなってほしいという話題で盛り上がった。翌日、港の倉庫の壁画とヤノベケンジさんの作品を見た。作品に鳶がとまっていて、ヤノベさんも喜んでいた。東北芸術工科大学出身の画家、近藤亜樹さんがいて、猿を一緒に見に行くことになった。「二十四の瞳」を撮影した現場である映画村を見て、「野の花」で昼食をとり、いよいよ「お猿の国」である。
入園するとすぐ「今日は猿団子ができてますよ」というガイドさんの声があり、皆は坂道を駆けるように登っていった。すぐに猿の集団が目につき、さらに登ると大きな猿の塊が見えた。全員、そこから動かなくなって時間が経過した。その間、たまに1匹だけ団子から離れたり、また寄ってきたり、何かをきっかけに解散してはまた別の塊になったり、変化のたびに歓声が上がった。猿のうちの何匹かは私の方を見るが、まったく無関心の様子の猿も多い。ひたすら毛繕いに忙しいのもいれば、ただじっと目をつむっているのもいる。
猿団子を見る目的の初めての旅で、しっかり目的を果たしたという満足感があって、猿たちの関心が焼き芋に移って大移動したのをきっかけに、私たちも「お猿の国」を後にした。
俳句は季語を詠む文芸である。歳時記にない猿団子を詠むときには、だから季語を入れなければならない。それを試みた句を一句あげる。
みな同じ雪の山向き猿団子 和夫
無理を承知の上で、猿団子を季語と想定して詠んでみたが、まだ成功していない。
大地から猿の湧き出る猿団子 和夫
いずれにしても猿団子をみごとに観察できてうれしかった。寒くなった気象状況に感謝し、オリーブ園に立ち寄ってハンドクリームを買い、船で高松に渡って、駅の讃岐うどんを食べてようやく暖かくなった。岡山経由、松沢哲郎先生と猿についての四方山話のうちに京都駅へ着いたのは23時過ぎであった。猿団子の見られる気象のおかげで、少し風邪気味で就寝した。
ヤマロク醤油の5代目の木桶職人復活プロジェクトに感激した帰りに買った特製の味噌が今回のお土産の中でいちばん好評だった。
作画:小野塚佳代