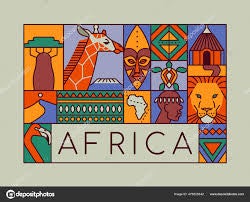今回は、上司が体験に基づいた考え方を示して
部下を鼓舞するケースをご紹介します。
今回も
https://ameblo.jp/c-b-collaboration/entry-12848082621.html
でお伝えした“五段展開”の構成になっていますが、
冒頭部分は、通常の会話から“物語り”へと
“導入”する一言が入っています。
また、元々共有がある上司-部下間の会話のため、
Context とBefore は、ワンセンテンスで語られています。
<導入>
会社が数字数字と言うのは当然だよ。だけど、営業マンが顧客に“買って買って”と言っても、結果が出るわけがないだろう。顧客が求めているのは、信頼できる情報源でありアドバイザー。そう認められない相手から購入する方が不思議じゃないか。
<Context & Before>
と、かく言う僕も、随分試行錯誤を繰り返したんだ。営業マンとして中々芽が出ずに、入社3年目の時、結果が出なければ会社を辞めようとまで思ったんだよ。
<GONG>
僕はそこで腹を括り、とにかく顧客に役立つ情報を集めることに徹してみたんだ。明らかにウチに不利になる情報を見せるかどうかで悩んだりもした。けれど、まずは信頼を得るためにと、顧客の立場で徹底して考える様にしてみた。
本も随分読んで、工夫してお客に喜んでもらえる資料を作ったりもした。数字としてはそれでも鳴かず飛ばずが続いたけれど、頼ってくれるお客は徐々に出て来てくれたんだ。
<After>
劇的に数字が上がった訳では無かったけれど、この経験を通して自分流の信頼構築術が形成されたんだと思う。お客に接する上での僕なりの“正解”が見えてきた、という感じ。これは教えてもらえるものじゃないんだね。試行錯誤しながら掴んでいくしかないと思う。結局営業マンとしての自分のスタイルは、自分でやりながら作っていくしかないんだと思う。
<Message>
君も今、まさに自分流のスタイルを作っていく時期だろう。現実を正直に言えば、数字が出ないなら、担当を外されることもありうるけれど、顧客と信頼関係を作っていくための君らしい方法を模索する機会と、この際割り切ってやってみたらどうだ。今のまま同じことをやっても変化が望めないのなら、自分のスタイルをつくるべく今後1年間徹底してやってみてもいいと、僕は思うんだけど。
Stp
営業マンとして結果が出せずに悩んでいる部下に対して、
一発奮起を促すべく発したメッセージです。
https://ameblo.jp/c-b-collaboration/entry-12848660453.html
でご紹介した四要素ですが、
① と②は
“入社3年目の時、結果が出なければ会社を辞めようと“
の一文が兼ねています。つまり話者である上司のキャラクターと
当時の感情を、ここのワンセンテンスで示しています。そして
GONG後の感情は、“鳴かず飛ばずが続いたけれど、
頼ってくれるお客は徐々に…“で表しています。
③ “ウチに不利になる情報を見せるかどうかで悩んだり“
“勉強し、工夫してお客に喜んでもらえる資料を作ったり”
といった部分に、リアリティーが感じられると思います。
④ “本も随分読んで勉強し、工夫してお客に喜んでもらえる
資料を作ったり…“
四要素については、上記の様に重複部分があってもOKです。
このメッセージで大事なところは、
部下が自ら考え、主体的に行動を起こしていける様な
動機付けです。
そこでポイントとなるのは、
上司の物語に触発されて、
部下自身の物語が創造され始めることです。
このケースで言えば、部下流の“信頼構築物語”が、
彼(女)の頭の中に生成し始めること。
上司のケースが触媒(参考)となって、
部下がこれから自分流をどうやって作っていくか、まさに
自分の意志と想像力で模索を開始することです。
上司が自らの苦闘の跡を開示し、
そのうえで“一人前”の途上にある部下の主体性を尊重し、
その部下の彼(女)らしい行き方を考えさせる。
その取り組みに、エールを送れるメッセージが、
ここで目指すべき内容です。