ヴェトナム新時代
 | ヴェトナム新時代―「豊かさ」への模索 (岩波新書 新赤版 (1145)) 坪井 善明 岩波書店 2008-08 売り上げランキング : 15402 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
岩波新書で1994年に出したものの続編という位置づけらしい。岩波は最近、「エビと日本人」も続編を出したけど、前作では既にドイモイが軌道に乗っていた時代であったから、「エビ」ほど構造的な変化がベトナムにあった訳でもなかろう。著者は団塊の研究者ということで、ベトナム戦争世代。最初はいきなりべトちゃんドクちゃんの話から入る。べトちゃんのべトはベトナムであろうが、ドクちゃんのドクはドイツだとは知らなかった。冬至の東ドイツが援助した病院に置き去りにされたからだという。しかし、べ平連の残党でその後もベトナムに関心を持ち続けている人って少ないのかな。戦争が終われば、もう関係ないよということなのだろうが、イラクでもチベットでも、その国に本当に感心を持っている人は安易なデモ集団とは一線を画すものではあろう。著者もべ平連に共感した無名の若者の一人だったらしいが、ベトナム研究の道にまで進んだというの数少ない例であろう。ベトナムで現調をしていた時に、小田実の訪問を受けたという話も唐突に出てくるのだが、「私の祖国は世界です」の小田嫁が、やはり「民族主義者」であったことを小田が告白したりしているのは面白い。著者にとって小田がヒーローだったのは、あくまでも若いときの話らしく、岩波なのに「共産主義国家」にはかなり懐疑的である様だ。あまり報じられることがないベトナムの少数民族弾圧問題についての記述もある。興味深いのはホーチミンの思想の礎を「共和国思想」としている論考で、この「共和国」とはフランスの共和国思想。著者は今こそベトナムは「共和国」の理念に立ち戻るべきとまで主張している。「ホーチミン思想」は40以上のバージョンがあるらしいが、一般的に考えられている「社会主義」とか「儒教」ではなく、「共和国思想」ではないかとういうのは、ホーチミンが政治的に覚醒した地を鑑みれば自然なことなのかもしれない。
★★★
「チベット問題」を読み解く
 | 「チベット問題」を読み解く (祥伝社新書 119) 大井 功 祥伝社 2008-06-26 売り上げランキング : 50523 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
これも「チベット騒乱」の後、慌てて作った新書っぽい。著者は聞いたことがない人だが、売り込みなのかどうか分からんが、これが初著作みたいだ。元々「ビジネスマン」として、リゾート開発を担当し、現在は実務者の体験を生かして、現代アジア情勢を分析した講義をしてる人とのこと。ダラムサラを訪れたことがあるらしいが、特にチベットの専門家ということでもない様だ。入門としてはイイのかもしらんが、このテーマに関心がある人は、著者が参考にした(と思われる)サイトがすぐ分かるというものだろう。単に「中国」を悪者にした短絡的見方は賢明でないというのだが、自らその言葉を裏切っている様な感じがしないでもない。少なくともチベットが「善」であるという立場には変わらないので、巷に溢れる「フリチベ」の声と同質のものであり、それ以上の「何か」がある訳でもない。この前に読んだ密教の人が書いた本はその辺が大変面白かったのが、こちらの著者は「チベット仏教」については全く無知とのこと。中国人留学生の声なども紹介しているのだが、どうも作ったような台詞で、始めに結論ありきだから先が読めてしまう。チベットを知らずに偏見の眼でみる中国人も問題だろうが、ダラムサラに行っただけでチベットが分かったつもりなる日本人はもっと問題かと思う。今枝由郎みたいに確信的に行かないならいざ知らず、中国について一家言あるなら、せめてラサくらいは行って然るべきだろう。長野でも中国人がフリチベ勢を挑発してたのは「お前はチベットに行ったことがないくせに、余計なことを言うな」という言説だった。つまりチベットを知らない者同士が、自分の方がチベットを知っているという認識の上で、互いに相手は情報操作されていると思っている茶番劇なのである。
★
ロシア 語られない戦争
 | ロシア 語られない戦争 チェチェンゲリラ従軍記 (アスキー新書 71) (アスキー新書 71) 常岡 浩介 アスキー・メディアワークス 2008-07-10 売り上げランキング : 85088 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
副題が「チェチェンゲリラ従軍記」であって、前半部分はその様な話。著者は地方局の報道部記者からフリーになった人らしく、アフガニスタンやイラクなども取材している「戦場ジャーナリスト」とのこと。「ポスト・ベトナム」としてのゲリラ戦取材も冷戦の終わりと共に幕を閉じるか、大幅に縮小して名目だけの形骸化になるかなどで、「戦場ジャーナリスト」も山岳ではなく、「都会」で活動するものとなってしまった感もある。その意味ではチェチェンは最後の秘境なのかもしれない。著者曰く、アフガニスタンやパレスチナなどとは比較にならない程の殺戮と緊張の日々だったそうだ。ただ、イスラームに改宗して従軍した著者にとって、チェチェン側に立つことは自明であり使命である。そこに客観とか公平なんてものを持ち込むこと自体がナンセンスであって、圧倒的な現実を見よというのが著者の趣旨なのだろう。それはそれで理解できないものではないのだが、こう侵略者の悪と抵抗者の正義という正論を滔々と語られると、読者に思考停止を迫るものではないかという気もしてくる。その辺、著者も気がついたのか、チェチェン・ゲリラに麻薬中毒者が多いことも記しているのだが、一方的な情報を一方的な情報で撃つ的な思考が気にかかる。ロシア大使館員がNHKにチェチェン首切りビデオを持ち込む話なども出てくるのだが、このテーマに関して日本では、著者が言うようにロシアに情報操作されえているとは思えない。むしろ「東長崎機関」か何か知らないが、「チェチェンシンパ」の情報発信の方が日本では優位にある様に思える。私もロシア本を多く読んでいる方だと思うのだが、日本でプーチンを評価している人間は元NHKの小林某くらいしか思いつかない。後は尽くプーチンの情報作戦を批判している人たちばかりだ。別にロシアの肩を持てと言うつもりはないのだが、グルジア紛争などみても、どうもこの地域は一筋縄ではいかない。現場の臨場感もよいが、舞台裏の攻防の方が知りたいものである。リトビネンコが語ったことが真実とも限らないだろう。
★★
裸形のチベット
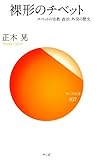 | 裸形のチベット―チベットの宗教・政治・外交の歴史 (サンガ新書 27) 正木 晃 サンガ 2008-07 売り上げランキング : 198214 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
サンガの本で、著者は密教の人らしい。その方面の知識がないので、学問的にどうなのかは分からんが、これは結構面白いチベット史であった。サンガはダライ・ラマ本なども出しているのだが、著者がいみじくも言うように「チベット・ファンの期待を裏切ってしまう」可能性がある本なのかもしれない。たしかに単純な「かわいそう」という意識だけはチベットを救うことなどはできないし、それは14世の望むところでもないだろう。「裸形のチベット」を受け止めることが、都合の良い「歴史認識」という鎧で固めた「中国」と対抗する術でもあるはずだ。西川一三の証言を引用するのも、西川が「チベットもチベット人も嫌い」と公言する人であったからだそうで、最後の「生きる伝説」の人だった西川はチベット支持者が集まる集会で、その旨の発言をし場内を凍りつかせたこともあったそうだ。侵略する「人民解放軍」と抵抗するチベット人という構図は、一見、崇高であり、同情を集めやすいのだが、それは実のところ、「中国」とか「共産主義」の論理の裏返しでもあろう。その様な文脈でチベットを語ること自体が、「中国とチベットを特別な関係」にすることに貢献しているとも言えよう。チベットはセックス狂であった乾隆帝に性的ヨーガ獲得を売り込んで、乾隆帝をチベット仏教に傾倒させたという著者の仮説が妥当なものかどうか分からんが、「歴史」とはその様な大胆な視点が必要ではないかとも思う。朝貢についても、チベット側の大幅な黒字になるので喜んでホイホイ出掛けたとのことだが、「華夷秩序」の実態なんてそんなもんだろうし、チベットの多額の経済援助を施してるのに恩を仇で返すという漢人の現在の不満に通じるものもある。ただ、ダライラマの選定方法もそうだが、そうした屁とも思っていなかったことに付け込まれてしまったのが現在の悲劇の始まりなのだろう。「漢字」で多民族が入り乱れるカオスを統一し、「歴史」を「正史」として武器にしてきた「文書」の国に、精神的修行を武器とした「宗教」の国が最終的に破れ、その軋轢が解消されないというのは、何か日本と中国の歴史にも通じるものがある。最近も共同文書を中国側が勝手に改ざんして発表した事件があったが、こうした手段でチベットもどこでも併合してきた中国にとっては手持ちの「手段」を行使したに過ぎないのだろう。もはや日本の外交はなす術がない状態なのだが、国交回復時に中江の様なチャイナスクールの妨害に関わらず、「反覇権条項」に徹底抗戦した当時の「条約課」には戦前の「支那通」の遺産がまだ残っていたのかもしれない。
★★★
男の子のための軍隊学習のススメ
 | 男の子のための軍隊学習のススメ (ちくまプリマー新書 (089)) 高田 里惠子 筑摩書房 2008-08 売り上げランキング : 55165 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
これもちくまの「太っ腹」8月商戦なのか。
元ネタは丸山真男をひっぱたく話だろうが。
★
ドキュメント死刑囚
 | ドキュメント死刑囚 (ちくま新書 736) 篠田 博之 筑摩書房 2008-08 売り上げランキング : 3964 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
宮崎、小林、宅間の話か。獄中の宅間に二人も求婚って。
★★
公務員の異常な世界
 | 公務員の異常な世界―給料・手当・官舎・休暇 (幻冬舎新書 わ 2-1) 若林 亜紀 幻冬舎 2008-03 売り上げランキング : 60943 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
まあ声を上げる必要はあるだろうが、この問題が解決されたら、公務員専門ライターの運命は如何に。
★★
イタリア貴族養成講座
 | イタリア貴族養成講座―本物のセレブリティとは何か (集英社新書 449D) 彌勒 忠史 集英社 2008-06 売り上げランキング : 40005 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
著者の本業は声楽家らしい。「在日本フェラーラ・ルネサンス大使」という肩書きもある様だが、イタリア政府奨学生としいう身分は現地で「貴族」に相当するのだろうか。ヴィスコンティの映画ではないが、共和制になって久しいし、イタリアの貴族というと没落のイメージなのだが、著者が指南するイタリア貴族とは華やかし中世の時代のもの。食とダンスと音楽がその三本柱みたいなのだが、この辺の知識はオペラ歌手としては必須なのだろうか。「本物のセレブリティ」とは遠く離れている様な文体ではあるのだが、日本人がイタリア貴族の真似事をすること自体、パロディだと分かってのことだろう。ヨーロッパで活発な音楽活動をした末に帰国した事情はよく分からないが、このタイトルには十分、皮肉が込められているとみた。
★
変わる中国 変わるメディア
 | 変わる中国 変わるメディア (講談社現代新書 (1951)) 渡辺 浩平 講談社 2008-07-18 売り上げランキング : 198156 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
著者は広告会社(博報堂かな)から研究者に転じた人の様で、現在は北大院准教授とのこと。親中ポチのサーチナ文化人、高井潔司が上司に当たるのか。同僚には極左ノモサの玄武岩もいる。となると、「読み方注意」のメディア論かと思いきや、わりとマトモな話だった。新聞、放送、広告の3本立てで、現在の中国メディアの現状を説明しているのだが、元広告マンだけあって、新書の役割を十分に意識したタイムリーな企画だと思った。そのポイントとして「メディア・グループ」を挙げている。これは人民日報、新華社、中央電視台という「特殊3社」の存在を浮き彫りにし、「党」と「民」、「社会主義」と「資本主義」、「宣伝」と「競争」という二項対立が中国メディアの本質であることを明確にする狙いからかもしれない。当然ながら、今の時代、「宣伝」に人民が満足する訳はなく、特殊3社の「影響力」を残しながら、メディアの市場経済化も推し進めなくてはならないという矛盾の延長線上に「ダンボール肉まん」や「中国青年報事件」があるのだろう。湖南電視台の「超女」については話には聞いていたのだが、よく整理されていて興味深かった。著者は欧米のリアリティ番組がそのモデルとしているのだが、湖南だし、ヒントは香港のミスものだろう。「紅衣教主」の雛形はウィリアム・ハンより宮雪花ではなかろうか。「終章」では中国人留学生の長野騒動の見方などを紹介しているのだが、これも高井とは違う見解だ。政府に演出された「親日」などより、自然発生の「反日」の方がまだ健全なものなのかもしれない。
★★★
社会主義後のウズベキスタン
 | 社会主義後のウズベキスタン―変わる国と揺れる人々の心 (アジアを見る眼 110) ティムール・ダダバエフ アジア経済研究所 2008-07 売り上げランキング : 150733 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
このアジ研の新書「アジアを見る眼」はジェトロに合併されて以降、消滅したとばかり思ってたのだが、生き残っていたのか。これで通算110タイトルめらしいのだが、約2年ぶりの刊行みたい。さすがに独立行政法人仕事らしく、まるで新書ブームに逆行する形だが、過去に良書もあるので、何とか続けていってほしいものだ。そういえばジェトロも新書やってたけど、最近みないな。「アジアを見る眼」とかいってガーナ本を出すくらいなら、ジェトロ新書を吸収合併して、もっとイキなタイトルで再出発したらどうだろうか。で、そんなアジ研には珍しく、非日本人の自国出身者が著者。訳者のクレジットがないけど、日本語原文なのか。著者は20代で東大助教授に就任した人らしいが、年齢的にモスクワ送りではなく、独立エリートとして養成された様だ(ウィキによると20で大学卒業)。ウズベキ本も中山恭子以来だから貴重なのだが、歴史とか地理とか、かったるいものは省いて、当のウズベク人の生活というところに的を絞っているので、ありがたい。中でもウズベキスタン人が抱くロシアへの愛憎といったところが大変興味深い。独立時に15歳ということはソ連時代も知る「戦前の教育」を受けた最後の世代といって良いかと思うが、この地域は地政学的にも、その複雑な民族構成的にも、単純に「教科書に墨を塗る」という訳にはいかなかった様だ。現在でもロシアに対するイメージが悪くなっていないのも、ソ連教育を受けた世代が当分は磐石であるからなのだが、特にソ連崩壊後の混乱期を知る者にとっては、ソ連という時代は「三丁目の夕陽」でもある様だ。とはいえ、著者より下の世代の「独立っ子」にはそんな意識はないそうで、5歳くらいの年齢差で「世代の断絶」があるらしい。もっとも、アプレたちによって、グルジアみたいな状況が生まれることはなさそうだ。グルジアにおける西洋型民主主義の影響はウズベキスタンにおいては、イスラームや「アジア」がストッパーになっている感じ。カリモフが政権を維持できたことについての説明もなるほど。著者は別に独立エリートとしてカリモフを擁護している訳ではないのだが、たしかに「欧米型」見地で単純に独裁者と決め付ける訳にはいかんだろう。最後に日本に対する好感度が韓国の後塵を喫していることに苦言を呈しているのだが、ウズベキスタン人の好感度はロシア、韓国に次いで3位というのは微妙なところだ。人間ごと浸透している両国に比べれば、まあ健闘していると言っていいんじゃないかな。
★★★