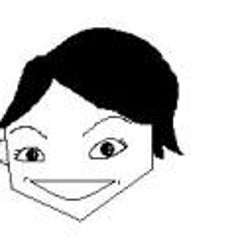6月中旬に帰国し、ワークショップ・イベントを開催することになりました。
是非お出かけください![]()
井戸の管理、あなたの村はどうしてます?
~村人になりきってワークショップを体験!~
毎日数キロ歩いて、数十キロの水を取りに行く。
そんな経験をしたことはありますか?
ミャンマーの「中央乾燥地域」という場所では
自分の村に井戸がないことが多く
そういった光景が日常的に見られます。
BAJは
「1つの村に1つの井戸を 」
」
を目標に、井戸を掘ったり、修理をして
水へのアクセスを簡単にするお手伝いをしています
また、ライフラインである井戸を長く大切に使ってもらえるよう
上手な井戸の管理をしてもらえるよう
ワークショップを通したトレーニングも行っています。
ミャンマーのワークショップを体験する今回のイベント。
TOTO(株)の助成金で現地で実際に実施したワークショップをみなさんにも体験してもらいます。
ミャンマーの村人が「水」に対してどのような考え方をもっているのか
村の井戸をどう管理しているのか
一緒に考えてみませんか?
みなさんからの新しい、おもしろいアイデアが
現地の井戸管理に役立つかもしれません![]()
当日は、懇親会も予定しています。
ワークショップだけの参加、懇親会だけの参加もOKです
<ワークショップ体験>
日時:2010年6月17日(木)19:00~20:30
場所:ソーシャルエナジーカフェ
アクセス:小田急線経堂駅徒歩5分
地図:http://ameblo.jp/socienecafe/theme-10020773315.html
参加費:1,000円(ワンドリンク付き)
ファシリテーター:森晶子(BAJミャンマー・チャウパドン事務所プログラムマネージャー)
<懇親会>
日時:2010年6月17日(木)20:30~
場所:ソーシャルエナジーカフェ
参加費:実費(3,000円程度)
お問い合わせ:
(特活)ブリッジ エーシア ジャパン
担当:平井
TEL:03-3372-9777
メール:toiawase[a]baj-npo.org
([a]を@にして送信してください)