表題作「五十鈴川の鴨」他9編が収録された、竹西寛子さんの短篇集です。
派手さはありません。静かに、人の心のやわらかいところにそっと入ってきます。
例えば、「挨拶」という話に次のような場面があります。
もう何代も続いてきた屋敷がありました。しかし、栄華が続かないのは、はかない人の世の常。この家も取り壊されることになりました。
主を失った家を最後まで見届けたのは、その家でかつて働いていた執事でした。
明日、取り壊されるという日、彼は、酒屋から届けられた一升瓶を手に、庭に立ちます。
さあ、飲んでくれ。別れだ。
老人は、骨にすぐ皮のついているような腕を力いっぱい振って、惜し気もなく庭木や下草に酒を注いだ。
ありがとう。どんどんやってくれ。
西陽を受けて撒かれる酒は、老人の目に、散る花とも、霧とも、吹雪ともうつった。ありがとう。勘弁しておくれ。ありがとう。ありがとうよ。さあ、もっと、もっと・・・
間もなく消えていくさだめのものに対して、ひとかたならぬ思いを込める老人の姿に心打たれます。
通り慣れた道を車で走っていると、つい最近までそこにあった家が壊され、更地になっていることがあります。見逃してしまいがちなのですが、そこには、住んでいた人、一人一人の思い出があったはずです。
『五十鈴川の鴨』は、そのような大切にしたい人の心に気付かせてくれる短篇集です。
 |
五十鈴川の鴨 (岩波現代文庫)
814円
Amazon |
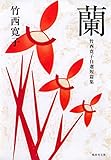
![シザーハンズ<特別編> [ ジョニー・デップ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9329/4988142909329.jpg?_ex=128x128)
![君たちはどう生きるか (岩波文庫) [ 吉野源三郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5811/9784003315811.jpg?_ex=128x128)
![「言葉にできる」は武器になる。 [ 梅田 悟司 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0751/9784532320751.jpg?_ex=128x128)