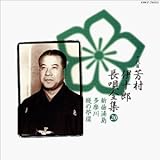| 1845年弘化二年四月 | 二世杵屋勝三郎 |
悪評高い天保の改革をした水野忠邦。一度失脚したにも関わらず、弘化元年に老中筆頭に返り咲いた。
しかし、年齢的問題か昔の面影ゼロ。いやいや、土井利位や鳥居耀蔵らに裏切られての失脚。裏切られたものの心の傷は深い。御用部屋でボーとしている事が多い。でも恨みの二人にはしっかり報復。剛腕を望まれて再就任したのですが、本人にとってはそんな事はどうでもよくて、ただただ報復のみしかなかったのかもですね。
弘化二年三月に水野君は強制隠居。悪の根源が消えて江戸庶民は万々歳。
その昔、中央区新川あたりは多くの酒問屋で繁盛していたそうです。
摂州をはじめ様々なところで作られた新酒が船で運ばれ、各酒問屋は大茶船いうものを出して、競って瀬取して、それぞれ河岸に積み帰って、新酒○○と銘打って市中に売り出したそうです。
この曲はある問屋(歌詞から推察して「内田屋」という説もあるが実のところは不明)が『軒端松』という新酒を売り出した。その酒問屋の依頼により誕生した宣伝曲なのだそうです。
「軒端の松」と検索すると、百人一首を選定した場所と言われている二尊院にある松(軒端の松)がヒットします。
百人一首を選定に活躍した、藤原定家の「偲ばれむ物ともなしに小倉山 軒端の松ぞなれてひさしき」という有名な歌がある。当初はこの歌から『軒端松』と命名されたのかと思いました。
しかし、歌詞冒頭で
酒豪で、またまた詩人として有名な李白が、自宅の軒端に松を植えたという事から『軒端松』と銘を打たれたようです。定家かと思ったけれど、李白だったんですね。
李白という人は“詩仙”と呼ばれ、また“酒仙”とも呼ばれた人と言われています。
この曲は二世杵屋勝三郎が二十七歳の時に作ったものだそうです。それも処女作だったとか。
この同じ時代に三世杵屋正治郎、十一世杵屋六左衛門という天才がいました。三人合わせて明治の三傑と言っている人がいました。
二世勝三郎は「鬼勝」と呼ばれたそうです。巨躯長身の上、あばた面ということで容貌が恐ろしかったのだそで、芸の凄さとあわせてこう呼ばれたのだそうです。
歌舞伎の伴奏曲であった長唄を「新たな需要」として、こういったCMソングを作ったとか。
その他、『廓丹前』・『喜三の庭』のように花柳流のお浚い会用の曲を作ったり、『菖蒲浴衣』のような名披露目のための曲を作るなどしたお方だそうです。
そうそう、十一世六左衛門も大薩摩復興に力を入れるなど、脱歌舞伎の動きがあったとか。
時代が長唄に対して歌舞伎外の需要を求めていたのかもですね。またそれにあわせて、歌舞伎も何気に不景気な時代だったのかも知れないですね。
この曲には、当時の銘酒がたくさん読まれています。
『男山』・『剣菱』・『七ツ梅』・『白菊』・『花筏』
男山・剣菱・七ツ梅は内田屋の新酒だったそうです。花筏はどこのお酒か不明。白菊は白酒という事で、『軒端松』は内田屋のお酒ではないかと淺川玉兎氏は仰っていますが・・・どこのなんでしょうね。
『男山』は北海道のお酒ですが、その起源は兵庫県伊丹市。『剣菱』も現在は神戸のお酒ですが、当時は伊丹市に酒蔵があったようです。
面白いのが、どちらのお酒も「赤穂浪士の四十七士が蕎麦屋の二階で最後に酌み交わした酒」という言い伝えがあるそうです。実際、どちらのお酒を呑んだのかは不明。
まあ、どちらもそんな昔からあるお酒なんですね。どちらもとっても美味しいお酒です。
余談ですが、
高校生の時に郵便局でアルバイトをしていました。その時の初給料で「御屠蘇に」と両親にプレゼントしたお酒が剣菱でした。そして、今、一番好きなお酒は男山です。
・・・偶然ですね。
そうそう、呑んだことがありませんが『七ツ梅』も現在も残っているお酒だそうです。これも今は兵庫。当時は伊丹のお酒。ところで、白菊は岡山のお酒にあるんですが、創業が明治後半なんですね。ですから、この歌詞に出てくる白菊とは違うようです。
花筏は同じものか不明ですが伊賀の地酒に同じ名前のものがあります。
こうして調べると、それぞれお酒には歴史ありなんですね。
後半、「神酒と聞く~」と謡曲の『猩々』からも歌詞を引用。まあ、とにかくお酒尽くしの曲であります。