今日はとにかく暑かった!
そんな日に、着物着てお稽古に!さすがバテました。
『大原女』の解説を書きたいけれど・・・
一服しよう!
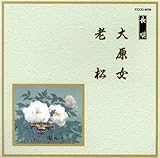
わしが在所は風雅に出でて
むくつけに寝まるべいと
語らうならば嬉し
甘露の桃や柿がぶらさがり
九十九疋の意地悪猿に
おっ立てられてもわらわれても
根こんず惚れたが性根じゃえ
黒木買わんせ黒木召せ
恋には八瀬の里育ち
軒の簾の床しさは
玉だれ髪を取上げて
誰に見しょうとて夕化粧
わしが器量は褒めもせで
姿がよいの生際が
宵の口舌に無理なひぞり言
わしほど優れた女子をば
嫌うお前の気が知れぬ
気が知れぬ
エエ女子冥利が尽きようぞえ
機嫌直して君と我
倶に落ちよもの我が里を
兎角思う様になア
浮世がならば
可愛 殿御と野の末までも
糸も繰ります機織虫よ
誰を松虫
焦がれてすだく
つづれさせちょう
馬追虫の永き夜すがをなき明かす
誰を松虫
焦がれてすだく
つづれさせちょう
馬追虫の永き夜すがをなき明かす
草葉にすだく鈴虫のふるやふる野の
振りやれお振りやれ
剽軽男の又とない
又とない一代奴
ありゃんりゃりゃ
こりゃんりゃりゃ何でもせ
国で評判男山
御国堺の
松の木の下り枝
あぶないあぶない
お腰をかがめて
お腰をかがめて
振れやれ振れやれ
其の月雪や花の槍
見事にさ
開いてさ
見事に開いた振りもよし
引かば靡かん
松の木越よ振れさ
振れさ
振れ振れ振れ
お先揃えて殿はしょち入り
だめな事ばし言わしゃるな
明日は関東さえ
まかるべいちゃな
やれさてナ
主さ別れちゃなア
伊勢路へ
あんちうちくだぶん抜きやるさア
池のどん亀なら
むんぐるべいとは実だんべい
実だんべい
いけすか女郎衆の旅立さ
主さ別れちゃア
なあ伊勢路へ
あんちうちくだ
ぶん抜きやるさア
池のどん亀なら
むんぐるべいとは
実だんべいだんべい
掛け奉る宝前に
名筆名画の徳は目前
今目の前に
外に中村人のやまやま
| 1828年文政11年 | 十世杵屋六左衛門 |
この曲も化政文化の産物ですね。
二世瀬川如皐は1753年生まれ。三代目瀬川菊之丞の兄である。1779年二十三歳の時に河竹新七の門下となる。その後、1787年初代中村仲蔵に誘われて上方に行き修行する。翌年に江戸に戻る。1794年二代目瀬川如皐を襲名。三代目瀬川菊之丞付きの作家となる。また三代目中村歌右衛門や五代目松本幸四郎に作品を書き下ろしていた。
彼のライバルは鶴屋南北。鶴屋南北は金井三笑の弟子。三笑は如皐にも劇作法や処世法などを教えたと言われる。如皐は南北の二歳年下なのですが、当時の江戸歌舞伎を支えた人気の二人である。
如皐は変化舞踊を得意としていて、多くの作品を残している。
さて『供奴』は、文政十一年三月の江戸中村座において、二世中村芝翫(後の四世中村歌右衛門)が演じた、「拙筆力七以呂波(にじりがきななついろは)」という七変化の所作事の中の一つ。振り付けは、西川扇蔵・藤間大助・市山七十郎というメンバーだったそうです。
この演目、七変化ですから、ほかに六曲あるんですよね・・・
『傾城』・『ごみ太夫』『乙姫』『浦島』『瓢箪鯰』『石橋』と長唄・常磐津・富本の三流で演ぜられた。
このうち長唄は『供奴』『傾城』『浦島』『瓢箪鯰』です。
十世六左衛門の作曲したものの中に『石橋』がありますが、この演目の『石橋』とは違うようです。
そうそう、『石橋』の注釈に、ほかの『石橋』と区別するために『大石橋』あるいは『外記石橋』と呼ぶというのがありました。
ストーリーは非常に間抜けているもので
「だんなのお供で吉原に出かけた奴。しかし、吉原近くでだんなを見失ってしまう。こりゃ大変と、台提灯を持って吉原田圃に差し掛かり、更に急いで揚屋の門を行過ぎるその間の所作を演じる」というもので、非常に軽快で非常にコミカルな仕立てとなっています。
ところで、奴さんって何でしょうね。
奴というと、冷奴♪・・・これは食べ物で、奴さんとは関係ないでしょう。いえいえ、奴さんに関係あるんですよ。
奴さんには二通りあります。奴さんは、中間とも呼ばれます。武家の奉公人で一番下の奉公人を下男と呼びます。この人たちは武士ではありません。武士で一番下は足軽です。で、下男と足軽の中間に存在しているから“中間(ちゅうげん)”と呼ばれたのだそうです。この人たちは、基本的には武士ではないのですが、いざ戦争となると人手不足を補うために足軽になって戦場に出ちゃったりするのだそうです。さて、この中間にも二通りあってですね、常勤の奴さんと季節雇いの奴さんといるんですね。
季節雇いというのは、例えば参勤交代の時とか、何かの行事の時とか、常勤の奴さんだけでは足らない時に口入やを通して派遣してもらうのですね。
武家の台所。とにかく小さくても大きくても、その規模によって必要経費は掛かります。
常時、必要なだけの奴さんを雇うことなんて無理だったようです。
奴さんの給料は非常に安かったようです。当時、年収十両ないと一家を構えて家族を養う事はできなかったようなのですが、奴さんの年収は二両だったそうです。季節雇いの奴さんなんてもっと酷い。日給が米五合ですって。
まあ、とにかく給料が悪いのでその他で彼らを引きとめなくちゃいけない。という事で、中間屋敷で賭博所を開いても見て見ぬ振りとか、多少の悪さも見て見ぬ振りをしていたらしいです。
「あそこの大名家は待遇が悪いし、俺は辞めた」という感じで、彼らはすぐとらばーゆしちゃうのだそうです。
彼ら動揺、薄給の業界にいる私ですからよく分かります。これを読んだ時に「まるで看護師の業界みたい」と思っちゃいました。
ところで冷奴と奴さんの関係は奴さんたちの制服にあります。
季節労働者の人たちは、常にその大名家に方向するわけではない。今回はA家だったけれど、次回はB家という感じで奉公先が変わります。という事で、どこの家中でも使えるように、紋がただの四角だったんですね。この切り口に似ているからという事で「冷奴」なのだそうです。
この『供奴』にも賭博の事を唄っているなという箇所があります。
奴といえば賭博。とにかくガラの悪い人たちが多かったみたいです。
先にも言いましたが、奴さんたちは給料が安いので、とにかくお小遣い稼ぎをしたいのですね。
という事で、その藩の下屋敷の中間部屋に賭博所を開いて、賭け事をやって小遣いを稼ごうとしたりしていたんですね。胴元は場所代を稼げますしね。
賭博は江戸時代でも禁止の遊戯でした。でも、武家の屋敷はそういった事を取り締まる町奉行が介入する事ができなかったんですね。
また、下屋敷というのがミソ。表屋敷だとまずいのですが、下屋敷というのは別荘みたいなもので、藩主がそこにいる事は少ないし、管理が手薄なところなんですね。藩の方も奴さんが辞めちゃうと困ってしまうので、まあ大目に見てやろうという感じだったみたいです。
この『供奴』の歌詞に
「リュウチェーパマデンス」なんていう不思議な言葉がでてきます。あきらかに賭け事に関連している事場だなと分かりますが、意味がさっぱり分かりませんでした。
で、ネット検索したら、ありました!

今でも、身近にジャンケンなる遊びがありますが、その一種らしいです。
『本拳』あるいは中国から長崎に入った遊びなので『長崎本拳』とも言われるそうです。で、このジャンケン様の遊びで負けた人がお酒を飲むという罰ゲームが「拳酒」という遊びらしいです。
この曲の見所・聴き所はやはり「足拍子の合方」でしょうね。
踊り手・三味線・小鼓の掛け合いです。
この中村座の興業の途中で、タテ三味線の杵屋六左衛門が足を痛めてしまい欠勤をしたのだそうです。
代役に八世杵屋喜三郎が勤めました。
ところが、この足拍子で踊り手の芝翫が、「呼吸が合わないからあんたの三味線じゃダメだ」とクレームが入ったのですね。こりゃ大変だ!
看板の役者さんに臍を曲げられてしまったら大変です。座頭は六左衛門に駕籠を差し向け、無理を押して演奏してもらうことにした。
しかしですね。一度頼んだタテ三味線を「やっぱりいいです」とは言えないですよね。という事で、六左衛門のために別の山台を用意して座らせたのだそうです。
と、それを見たタテ小鼓の初代宝山衛門は「なんで三味線に別座があって、小鼓の別座が無いんだ」になったのですね。本当に、皆さん我がままですね。まあ、三味線・小鼓の掛け合いですからね・・・言われても仕方がないか・・・
という事で、小鼓にも別座を設けたのだそうです。はあ、座頭さん・・・お疲れ様です。
何だかんだ言っても役者が一番なんですがね、それでもそれぞれの職分の人たちはそれなりにプライドを持っていますから、なかなか調整が難しい。昔も今も変わらない。そして、邦楽の世界だけでなくどんな世界でも似たような話があなたの職場にもあるんじゃないですか。
歌詞の中にも「成駒屋」と中村芝翫屋号が含まれていますが、今は色々な方がこの曲を踊っています。
子どもの出し物としても人気の高い演目だそうです。
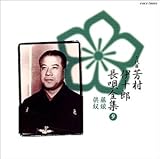

仕て来いな。
やっちゃ仕て来い今夜の御供。ちっと遅れて出かけたが、
足の早いに、我が折れ田圃は近道、見はぐるまいぞや、合点だ。
振って消しゃるな台提灯に、御定紋付でっかりと、ふくれた紺のだいなしは、伊達に着こなしやっこらさ。
武家の気質や奉公根性、やれ扨ていっかな出しゃしょない。
胼や皸かかっとや臑に、富士の雪程有るとても、何時限らぬお使は、かかさぬ正直。
正道者よ、脇よれ、頼むぞ、脇よれと、急ぎ廓へ一目散、息を切ってぞ駆けつける。
おんらが旦那はな、郭一番隠れないない、丹前好み、華奢に召したる、腰巻羽織、
きりりとしゃんと、しゃんときりりと立股立の袴つき、後に下郎がお草履取って、夫さ、是さ
小気味よいよい六法振が、浪花師匠の其の風俗に、似たか。
似たぞ、似ましたり、扨々な。寛濶華麗な出立。
おはもじながら去る方へ、ほの字とれの字の謎掛けて、解かせたさの三重の帯、解けて寝た夜はゆるさんせ、
ああ、ままよ浮名がどうなろと、人の噂も七十五日、てんとたまらぬ、小褄とりやった其姿。
見染め見染めて。目が覚めた。醒めた夕べの拳酒に。
ついついついついさされた杯は、りうちえいぱまでんす。
くわいと云うて払った。貼った肩癖ちりちり身柱、亥の眼灸がくっきりと。
ねぢ切りおいどが真白で、手ツ首掌しっかりと握った。
石突、こりゃこりゃこりゃこりゃ、成駒やっことこよんやさ。
面白や、浮かれ拍手に乗が来て、ひょっこり旦那に捨てられた、狼狽眼で提灯を、
つけたり消したり灯したり、揚屋が門を行き過ぎる。
| 1811年文化八年 | 九世杵屋六左衛門 |
化政文化は文化・文政の時代に発展した町人の文化です。社会や政治の出来事、日常生活の事などを風刺するような川柳が流行ったり、写楽・北斎など有名な浮世絵の作家たちが活躍したりしたのはこの時代です。
これから幕末にかけて暗い話題が多い世の中になりますので、江戸時代後期としては一番良かった年代ではないでしょうか。
九代目杵屋六左衛門は、三世田中伝左衛門の次男として誕生する。名前を万吉という。田中伝左衛門は歌舞伎囃子方の田中流宗家家元というお家ですね。つまりこの人は、囃子方から長唄の方に転向した方なんですね。
八世杵屋喜三郎の養子となる。が、八世杵屋喜三郎に実子が誕生してしまう。という事で、実子が九代目喜三郎を継承。万吉は九代目杵屋六左衛門を1797年に継承する。まあ、どちらも杵屋宗家(長唄宗家)の名跡。
「小糠三合あるなら養子には行くな」と養子の苦労の多いことの例えとして言われるけれど、せっかく養子に入ったのに・・・。でも、格としてはぜんぜん負けない六左衛門の名前を継承できてよかった。よかった。
この九世杵屋六左衛門は文化八年まで江戸中村座で活躍する。
篠田金治=二世並木五瓶。彼は1768年(明和五年)に旗本の野々山家に生まれる。野々山というお家は徳川家康が今川義元の元に人質に入っている時代からの家臣。由緒正しいお家です。きっとたぶん、次男以下の部屋住みの身の上だったのでしょうね。放蕩生活の末、初代並木五瓶に弟子入り。篠田金治を名乗り戯作者として活躍。1818年(文政元年)に二世並木五瓶を継承する。この曲のほか清元の『保名』などの作詞をしたりしている。
この曲は、越後の国(今の新潟県)から出稼ぎに来た角兵獅子のおじさんが主人公の踊りです。
角兵獅子とは、大道芸人で頭に獅子頭を被っておどったり、様々なパフォーマンスをする人です。
筝曲にも同じ題名のものがありますが、その筝曲の「越後獅子」がもととなっているそうです。
この曲について調べると面白い事がある本に載っていました。
実はこの曲、一夜漬けで作られたそうなんですよ。
江戸時代の芝居小屋で有名な中村座と市村座などがありました。
文化八年、当時の坂東三津五郎という人が七変化の踊りを出して、市村座が人気ナンバーワンの芝居小屋だったそうです。
それまで、人気が高かった中村座はお客の不入りが続いてなんとか人気を取り戻そうとして、当時の中村歌右衛門という人が自分も七変化の踊りをやろうという事で、「越後獅子」をはじめ他七曲を踊って人気を取り戻したそうなんですよ。
七変化というのは早代わりものです。
乙女を踊っていたかと思うとあっという間に厳つい男性に変身して踊ったりする。
パフォーマンス性の高い演目です。
当時の杵屋六左衛門という人が中村座から作曲を頼まれて一日で曲を完成させたそうです。
とにかく早くという注文だったんでしょうね。
当代坂東三津五郎は三代目のことです。
初代坂東三津五郎の子供で森田座にて子役デビュー。1799年寛政11年に三代目を襲名。当たり役は『伽羅先代萩』の足利頼兼、『一谷嫩軍記』の熊谷直実、『源平布引滝』の斎藤実盛など。四代目鶴屋南北と提携していて描き下ろしの芝居に出演していた。日本舞踊の坂東流の祖である。
また、ライバルであった三代目中村歌右衛門は、初代中村歌右衛門の子として1778年に生まれる。もともとは関西の役者。私たちの記憶に新しい六代目中村歌右衛門は屋号を成駒屋。この成駒屋の屋号は四代目から。三代目の屋号は加賀屋。1791年に三代目を襲名。二代目嵐吉三郎と人気を二分する人気役者となる。
1808年に江戸の中村座の所属となり、三代目坂東三津五郎と人気を二分するスターとなる。当り役は『一谷嫩軍記』の熊谷直実、『義経千本桜』の狐忠信、『仮名手本忠臣蔵』の定九郎、『楼門五三桐』の石川五右衛門、『隅田川続俤』の法界坊、『五大力恋緘』の弥助など。
二人の三代目は競って変化もの演じて庶民を楽しませたのだそうだ。
・・・ところで、中村歌右衛門というと女形の印象が強いですが、三代目は立ち役だったんですね。
ところで「越後獅子」というと、美空ひばりの歌で「越後獅子の唄」とかいうのがあるんです。
まだ美空ひばりの子供時代角兵獅子の女の子(男の子だったかな)の映画があってその映画の挿入歌。
角兵獅子というとこの映画もそうなんですけれど、その他、時代劇でも子供というイメージが強いです。
それなのに長唄の越後獅子は妻帯者のおじさん。子供じゃない。角兵獅子のイメージが…。
可愛くない。生活臭がする。オヤジ臭い。
なんか、私の角兵衛獅子のイメージを完璧に崩してくれちゃった曲。
なので私はこの曲ってあまり好きじゃありません。
でも、なぜかこの曲を演奏する事が多い。やっぱり一般的には人気の長唄の一つなんですよね。
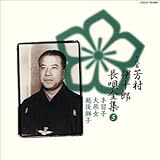
打つや太鼓の音も澄み渡り、角兵衛、角兵衛と招かれて、居ながら見する石橋の、
浮世を渡る風雅者、うたふも舞ふも囃すのも、一人旅寝の草枕、
おらが女房を褒めるぢゃないが、飯も焚いたり水仕事、麻撚るたびの楽しみを、独り笑みして来りける。
越路潟、お国名物はさまざまあれど、田舎訛の片言交じり、
獅子唄になる言の葉を、雁の便りに届けてほしや、小千谷縮の何処やらが、見え透く国の習ひにや。
縁を結べば兄やさん、兄ぢゃないもの、夫ぢゃもの。
〈浜唄〉
来るか来るかと浜へ出て見ればの、ほいの、浜の松風音やまさるさ、やっとかけの、ほいまつかとな。
好いた水仙好かれた柳の、ほいの、心石竹気はや紅葉さ、やっとかけの、ほいまつかとな。
辛苦甚句もおけさ節。
何たら愚痴だえ、牡丹は持たねど越後の獅子は、己が姿を花と見て、庭に咲いたり咲かせたり、
そこのおけさに異なこと言はれ、ねまりねまらず待ち明かす、御座れ話しませうぞ、
こん小松の蔭で、松の葉の様にこん細やかに、弾いて唄ふや獅子の曲。
向ひ小山のしちく竹、いたふし揃へてきりを細かに十七が、室の小口に昼寝して、
花の盛りを夢に見て候。
見渡せば見渡せば、西も東も花の顔、何れ賑ふ人の山、人の山。
打ち寄する、打ち寄する、女波男波の絶え間なく、逆巻く水の面白や、面白や。
晒す細布手にくるくると、さらす細布手にくるくると、
いざや帰らん己が住家へ
今残っている長唄の中で、もっとも古いとされているのが、この曲ではないでしょうか。
享保年間(1716~1736年)にはすでにあったとされています。
江戸市村座の脇狂言として演じられていたものだそうです。
「江戸市村座」
1634年(寛永11年)に村山又三郎が村山座として起こす。その後、1652年(承永元年)、市村羽左衛門が興行権を買い取り市村座とした。
1842年(天保13年)水野忠邦による天保の改革により、芝居は風俗の乱れを生じるとして、堺町の中村座・葺屋超の市村座・木挽町の河原崎坐(のちの森田座・守田座)を浅草寺裏の猿若町に転居するように命じられる。
1892年(明治25年)下谷二長町に転居。明治26年焼失。明治27年に東京市村座として再建したが、大正11年関東大震災によりまたまた焼失。その後、再興を果たすが昭和七年に焼失。それをきっかけに消滅してしまう。六代目尾上菊五郎や初代中村吉右衛門などの人気役者が活躍した劇場であった。
余談ですが、天保の改革はとにかく歌舞伎をいじめまくった改革。
当時人気の七代目市川海老蔵。手鎖の刑ののち江戸所払い。本腰を入れて歌舞伎を弾圧するぞという見せしめに彼は江戸を追われた。
歌舞伎の役者たちの日常生活の統制。一般人との交流の禁止とか、外出の際は編み笠かぶれとか。
それから、上演は江戸と大坂・京都でしか上演しちゃいけない。とかまあとにかく厳しい統制を引かれちまった。
水野君。禁断の大奥にも無駄遣い禁止で統制。当時の大奥の実力者である姉小路らに強い反発を受けてこちらは失敗。やっぱり大奥は禁断の地。大奥は強かった。けれど、やっぱり庶民は表立っては抵抗できない。天保の改革の時代、庶民は超ストレス。のちのち水野忠邦失脚。庶民は大喜び。そして屋敷に大勢の人が石を投げ込んだらしい。
さて、
脇狂言というのは、前座みたいなものでしょうね。
まだ、興行中、まだ夜が明けぬうちから、稲荷町と呼ばれる見習い俳優たちが、三味線や唄と共に序開きの所作を演じたのだそうです。
中村座は『酒呑童子』
市村座は『七福神』
守田座は『甲子待』
と演目が決まっていたそうです。
七福神というのは、現在では
大黒天・恵比寿・毘沙門天・弁財天・福禄寿・寿老人・布袋の七人の神様の事を指しますね。
しかし、このメンバー、時代によって微妙に変わっているのです。
福禄寿と寿老人は南極老人星という星の化身とされ、実は同一人物。という事で、寿老人の代わりに吉祥天や猩々が入っていた時代もあったそうです。また、誰かの変わりにお稲荷さんが入っていたり。しかし、猩々とお稲荷さんは人間の姿をしていないという事で外されたそうで。
そうそう、吉祥天というのも女性ですね。七福神は弁財天の紅一点というイメージがありますが、もしかしたら女性の神様二人だつたかもなんてすね。
母親は鬼子母神、徳叉迦竜王を父とし、兄は(夫という説も)毘沙門天。
幸福と富と美の神様と言われています。場合によって弁財天と同一視された事もあったようです。
さて、この吉祥天は貴族たちの信仰が深かったようです。しかし、弁財天は身分の上下関係なく信仰されていたそうです。
という事で、七福神の紅一点に庶民からも愛される弁財天がその座を射止めたのだそうです。
七福神は、神仏習合という日本的な集まりですね。神道と仏教は違いますし、また中国の道教も全く違う宗教です。
日本の神社仏閣に行くと、お寺さんなのに赤い鳥居があったりと神道も仏教も入り混じっていますよね。
この七人の方々。実は日本特有の神様は恵比寿さんだけ。他はインドや中国から日本に来た神様や仏様や仙人。
大黒天・毘沙門天・弁財天はインドのヒンドゥー教の神様。
布袋は中国仏教の仏様。
福禄寿・寿老人は道教の仙人。
こんなメンバーから成っているのですね。
さて、この曲は『七福神』なのに、登場人物は大黒さんと恵比寿さんだけです。
曲の前半は恵比寿さん、後半が大黒さんのお話とされていますが、一説では全体的に恵比寿さんだけが登場人物ともされているそうです。恵比寿さんは唯一日本土着の神様だからなのでしょうかね。
今も、この曲が出される時は大概、出演者は一人らしいです。
しかし、曲自体古いので、当時のまま残っているかどうかは不明。もしかしたら、他の神様の物語が唄われている部分もあったりしたかもですね。何しろ、題名が『恵比寿』とか、『大黒と恵比寿』ではなく『七福神』ですからね。
この曲は三味線の練習曲として流行した時代があるのだそうです。「早間で三回弾くと手が上がる」つまり上手になると言われていたそうで。いくら早間といって、たった三回で上達するわけないじゃん。いやいや、もしかしたら神様パワーで上達するのかも知れませんね。
この曲が演奏で出される場合は、ご祝儀曲として番組の最後に演奏されるものなのだそうです。
確かに、歌詞の最後は「引く注連縄の長き縁を」ですから、これからも宜しくという感じですよね。
しかし、いろいろ演奏会やお浚い会に足を運んでいますが、あまり馴染みのない曲です。
お稽古もした事がありません。
先日、たまたま『長唄の美学』のCDを聞いていて、この曲を初めて聴きました。
すごっく古い長唄なのに、古さを感じません。とっても賑やかで楽しい曲でした。
今度、ちょっと浚ってみようかな?!
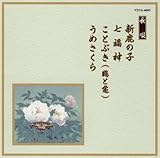
それ伊弉諾弉冊夫婦寄り合い
漫々たる和田津海に天の逆鉾降させ給い
引上げ給う其したたり凝り固まって一つの島を
月読日読 蛭子素盞鳥儲け給う
蛭子と申すは恵比寿のことよ
骨なし皮なしやくたいなし
三年足立ちたまわねば手繰りくりくる来る船に
乗せ奉れば蒼海原に 流したまえば
海を譲りに受取り給う 西の宮の恵比寿三郎
いとも賢き釣針おろし 万の魚を釣りつった
姿はいよ扨しおらしや
引けや引け引け引く物品々
様はきわずみ琵琶や琴 胡弓三味線東雲横雲
そこ引け小車 子供達に御座れ
宝引しよ宝引しよと
帆綱引っかけ宝船曳いて来た
いざや若い衆網引くまいか 沖の鴎がぱっと
ぱっと立ったは三人張強弓
よつ引絞りにひょうふつと射落とせば
浮きつ沈みつ 浪に揺られて
沖の方へ引くとの水無月なかば祇園どのの祭で
山鉾飾って渡り拍子で曳いて来た
拍子揃えて打つや太鼓の音のよさ
鳴るか鳴らぬか山田の鳴子 山田の鳴子
引けばからころ からりころり からりころり
からころからころからころや
くつばみ揃えて神の神馬を引連れ引連れ
勇みいさむや千代の御神楽
神は利生をつげの櫛
引神は利生を黄楊の櫛
引く注連縄の長き縁を