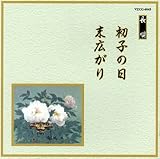| 1854年安政元年 | 十世杵屋六左衛門 |
安政元年は日本を大きく揺らした時代だ。
伊賀地震・安政東海地震・安政南海地震・豊予海峡の地震(実際には年号を改める前に起きている)、また翌年は飛騨地震・安政江戸地震。
何気に平成23年の今日のような地震当たり年ですね。
また、前年の嘉永六年にペリーが浦賀に入港して、そして安政元年に日米和親条約を締結する。
それから、1858年に起きた安政の大獄で命を失う吉田松陰が黒船に乗ってアメリカに密出国しようとして御用となってしまうという事件もありました。
日本の国土も揺れれば、政治も揺れる時代背景。
三世桜田治助は戯作者である。2代の門下で、松島半次、松島てうふを経て1833年治助を襲名。1838年四代目中村歌右衛門と提携し中村座に地位を占める。1862年に名を弟子に譲り桜田左交の名で活動、森田座につき、市村座の河竹新七(黙阿弥)、中村座の瀬川如皐 (3代目)と鼎立した人だそうです。
末広がりは、狂言の「末広がり」が題材となってできた長唄です。
数字の「八」とか扇とか傘の事を昔の人は末広がりといいました。
要を中心に広がる、即ち繁栄を示し、とても目出度い言葉なんだそうです。
今は
「ラッキーセブン」とか言って「七」という数字が良いと言いますが、昔の人にとっては「八」という数字も目出度い数字だったんですね。
主人公は、狂言で御馴染みのコミカルキャラの太郎冠者。
ある日、大名に
「末広を買って参れ」と言われて買い物に出された。
太郎冠者は迷わず傘屋で傘を買ってきました。けれど、大名が買って来て欲しかったのは「扇」だったんですよね。
何の事ないストーリー。
最初から、格好を付けずに
「扇を買って来い」と言えば良いのに…。
そんな事を言ってしまったら元もこうもありません。
まあ、太郎冠者がドジだと言いたい
そんなストーリーなんです。
実に、つまんないような日常生活のようなストーリーですがそのお陰でとっても分かりやすい曲です。
この曲は、踊りでも長唄でもお囃子でも初心者が習う曲なんです。
馴染みやすい曲だからでしょうか。
ストーリー性もあるし音楽としてもリズミカルで楽しい曲なんですよ。
この曲を演奏しているととっても楽しい気分になれるのでだから、初心者の手ほどき的曲なんでしょうね。それに演奏時間も短いし…。
私の長唄の初舞台もこの曲を演奏したんです。まだ小学校五年生でした。
だからとっても思い出のある曲なんですよ。
この曲はいわゆる「松羽目物」に分類される曲です。能とか狂言とかから題材を頂いてけっこう格式がある曲の事。
踊りの舞台背景で能舞台のように松の絵を描いた背景を設置するんです。
ですから「松羽目物」と呼ばれています。
有名処では「勧進帳」なんかそうですね。でもね、「末広がり」のような曲は変に格式ばって演奏しちゃうと全然曲想に合っていない感じ。
つい「松羽目物」=格式と思っちゃうと重くなっちゃうけれどやっぱりコミックですからね。
でもね、反対にコミカルだからとオチャラケちゃうとぜんぜん「松羽目物」としての格式が無くなってしまうから、こういった曲は実は難しい曲だと思います。
重すぎず軽すぎずというのがとっても難しいと思います。
こういった曲をちゃんと演奏できるようになるのかな。
…
頑張ってお稽古に励もう。それしかないね。