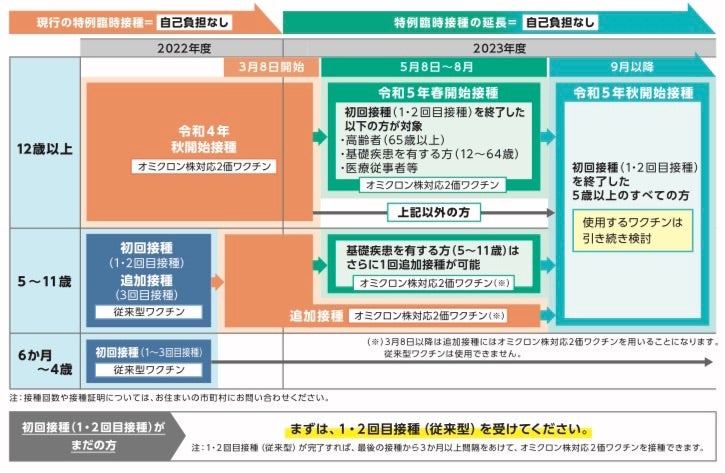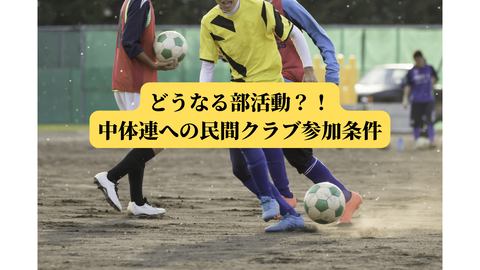堺市長選の経緯(2009~2017)
堺市長選挙の経緯を簡単にまとめました。
2009年 堺市長選挙 (2009.09.27)
・竹山氏、当時大阪府知事だった橋下徹元知事の支援を受け無所属で立候補。
・当時は大阪維新の会発足前。
2013年 堺市長選挙 (2013.09.29)
・竹山氏、堺市長選挙に再選出馬。大阪維新の会の候補を破り竹山氏当選。
・自由民主党大阪府連の支持、民主党の推薦、日本共産党の自主支援、社会民主党の支持
・関西広域連合長である兵庫県知事の井戸敏三、神戸市長の矢田立郎が竹山氏の決起集会に出席し竹山氏の支持表明
このあたりで都道府県域を越え、他地域の公選職の支持支援をしっかり受け再選。
堺を超えて反維新のシンボルのような存在に。
ちなみに本まで出版↓。
2014年 竹山氏書籍発行 「訣別 橋下維新を破った男」
2017年 堺市長選挙 (2017.09.24)
・竹山氏、再度出馬。
・自民党・民進党・社民党・日本のこころの推薦を受け、大阪維新の会候補を破り竹山氏当選。
・反維新連合が結集し、再選。
―無理やり反維新で結集した結果歪が生まれたのか、ここから歯車が狂うー
竹山市長の政治資金収支報告記載もれ(2019.02~2019.11)
2019年2月6日
・竹山市長、関連政治団体の政治資金収支報告書に記載漏れがある事が発覚
統一地方選2か月前の2月時点で1200万円以上の未記載発覚。
2019.02.15
2019年3月14日
・大阪維新の会が不信任決議案を提出。
・ところが堺市議会はこの不信任決議を「否決」
・ここで不信任決議を可決して竹山氏が辞職していれば堺市長選挙と統一地方選挙は同日実施され、選挙費用の圧縮や投票率向上に繋がったものの、議会はこれに繋がる不信任決議を否決。
2019年4月7日 統一地方選挙 堺市議会改選
・竹山氏は辞職の世論が強まる中、辞職することなく、堺市長選と統一地方選は 同日選にならず
2019年4月15日
・竹山氏が再提出した収支報告書の修正総額は約2億3000万円までにふくれあがる
2019年4月16日
・大阪維新の会代表の松井一郎は仮に不信任決議案が否決された場合はリコール運動を行うと発言
2019年4月22日
・竹山市長、ここにきてようやく市長辞職願を提出。(統一地方選(後半戦)の翌日)
2019年 堺市長選挙(2019.06.09)
その後、6月9日に市長選挙の投開票が行われ大阪維新の会公認 永藤英機が当選。
そこからの竹山氏の一連の報道↓
2019.09.12
2019.11.05
2019.11.08
竹山さんのストーリーはここまで。
ここからは今回の堺市長選が同日になされなかった経緯。
事件から2年が経過・・・
今回の堺市長選も統一選と別日に設定
2022年11月
・国において特例法が成立し、制度上、統一地方選挙と堺市長選挙の同日選挙が可能となる。
2022年12月
・堺市選挙管理委員会で自民・公明・立憲推薦の委員が同日選挙に反対
・統一地方選挙と堺市長選挙の別日実施が決定。
選挙管理委員会の委員と議論
選管の委員は地方自治法181条、182条あたりに選出方法など規定されています。
4名で構成し(181条2項)委員選任に際しては議会および長に通知(182条8項)
議会においての推薦方法は議会ごと、自治体ごとにバラバラかと思いますが、当該議会の交渉会派や所属議員の多い会派がそれぞれ推薦するケースが多いかと思います。
府議会、大阪市会、堺市議会においても同様の手法をとっています。
堺市選管においても維新推薦、自民推薦、民主推薦、公明推薦の4名が委員となっています。
最終的に選管の決定がくだされた議事録は下記URL↓
令和 4 年 第 14 回選挙管理委員会会議録
https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/senkyo/senkyo_i/sakai_senkyo_iinnkai.files/R414.pdf
堺市長選と統一地方選が同日選になった場合
(1)投票率の向上
(2)1億円を超える節税効果
は明白だったわけです。
また「同日選の課題」と言われていた、「投票所の混乱や狭小投票所対策」については、議事録をみてもその課題は解決されていたことが読み取れます。
上記議事録抜粋
(中井事務局長) はい。基本的にはですね、区の選管事務局が最終的には年明け 1 月の各区選管の定例 会において議決をして最終的に意思決定をするということでございますけれども、事務局の方で、この間 3 票になっても 4 票になってもいいようにということで調整を進めておりますので、基本的には調整の方が済んでおると聞いてございます。以上です。
特例法まで成立して同日選が可能になった。投票率向上が見込まれ経費節減にもつながる。かつ課題も解決の方向にあった。
にも拘わらず、わざわざ堺市長選と統一地方選が別日に設定された経緯を考えると本件、正当な決定とは到底思えません。
あと何が腹立つかというと、そもそも統一選と堺市長選が別日になったのは、世論の批判が巻き起こる中、上記の経過をみて一目瞭然、なんとしても市長選と統一選の同日選をさけた竹山市長、その竹山市長を支えた堺市会議員から「永藤市長が辞職して出馬しなければ同日選になったのに」という主張が見られること。この主張だけは許せない。
さてひとまずここまでの経緯を記載しました。
私より足がながくてシュッとしている永藤市長を全力で応援いたします。
いや別に悔しくないよ。愛嬌で勝ってやる!