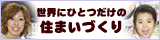違い棚
桃山時代末期の大工の秘伝書「匠明(しょうめい)」に違い棚が出てくる。違い棚とは、床脇の天袋と地袋の間の空間にある二段の棚板。通常向かって左側の棚を上に、右側の棚を下にして上部の棚には筆返しを端部に付け、上下の棚は海老束で繋がれる。
海老束
違い棚で上下の棚板をつなぐ束を「海老束(えびつか)」または「雛束(ひなつば)」という。「海老束」は通常、正方形断面で、その四隅に面を取る。面は束幅の1/7で角を残し両側に段をつける「几帳面(きちょうめん)」で取る。束の長さは柱幅1本分から柱幅の7割程度の寸法。海老束と棚板との仕口は、束の上下端とも「寄せ蟻(よせあり)」とし、海老束を棚板にはめた後、横にずらし固定する。
(古民家解體新書Ⅱ 参の二十九 床脇の部材 P257より)
筆返し
「筆返し(ふでかえし)」とは、棚板の端部に付けて、筆などが転がり落ちるのを止める役割があるが、構造的には板の反りを防ぐ吸付き桟の役目を負う。形状は、昔はのびやかなものが多かったが、次第に太く短くなった。(古民家解體新書Ⅱ 参の二十九 床脇の部材 P258より)
AD