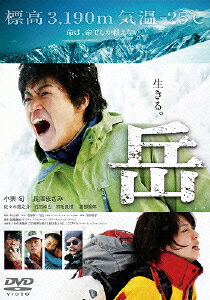我が子の体験を機に深掘り!「溶連菌」ってどんな病気?症状・対処法・そして気になる合併症まで徹底解説
先日、息子が「溶連菌感染症」に罹患したことをきっかけに、この病気について改めて深く調べてみました。子どもの間で比較的よく見られる感染症ですが、意外と知らないことも多い溶連菌。今回は、我が家の経験を振り返りつつ、皆さんに知っておいてほしい溶連菌感染症の基礎知識を徹底解説します。
そもそも「溶連菌」ってなに?正式名称と通称について
溶連菌は、正式には**「A群β溶血性レンサ球菌咽頭炎(Aぐんベータようけつせいレンサきゅうきんいんとうえん)」という、長い名前を持つ細菌感染症です。一般的には、この長い名前を省略して「溶連菌」**と通称で呼ばれています。
この病気は、A群β溶血性レンサ球菌という細菌が、主に喉や扁桃腺に感染することで発症します。
特に3歳から15歳くらいの子どもに多く見られ、飛沫感染や接触感染によって広がるため、保育園や幼稚園、学校などで集団感染が起こることも少なくありません。
一年を通して感染する可能性はありますが、冬から春にかけて比較的流行しやすい傾向があります。
溶連菌感染症のサイン!こんな症状が出たら要注意
溶連菌感染症の症状は、突然現れることが多いのが特徴です。代表的なサインをいくつかご紹介しましょう。
-
突然の発熱: 多くの場合は38度以上の高熱が出ますが、中には微熱で済むケースや、熱が出ないこともあります。
-
強い喉の痛み: 喉が真っ赤に腫れ上がり、食べ物や飲み物を飲み込むのが困難になるほどの痛みを伴います。扁桃腺に白い膿のようなものが付着することもあります。
-
イチゴ舌: 舌の表面に赤いブツブツができ、まるでイチゴのような見た目になることがあります。これは溶連菌感染症に特徴的な症状の一つです。
-
皮膚の発疹: 体や手足に、小さく赤い発疹(米粒大ほどの丘疹や紅斑)が現れることがあります。かゆみを伴うこともあります。
-
その他の症状: 頭痛、腹痛、吐き気や嘔吐といった症状を伴うこともあります。小さいお子さんの場合は、腹痛を訴えることが多い傾向があります。
これらの症状がすべて揃うとは限りません。特に小さなお子さんは、喉の痛みをうまく言葉で伝えられないため、「食欲がない」「機嫌が悪い」「ぐったりしている」など、漠然とした様子しか見られないこともあります。普段と違う体調の変化には、特に注意してあげましょう。
溶連菌感染症の対処法:早期診断と「抗菌薬の飲み切り」が絶対条件!
「あれ?溶連菌かも?」と疑われる症状が見られたら、迷わず医療機関を受診することが何よりも大切です。小児科や耳鼻咽喉科で診てもらうのが一般的です。
病院では、綿棒で喉の奥の粘液を採取し、迅速検査キットを使って溶連菌がいるかどうかを数分で確認できます。
この検査は痛みも少なく、お子さんへの負担も小さいのが特徴です。
溶連菌感染症と診断された場合の治療は、抗菌薬(抗生物質)の内服が基本となります。一般的には、ペニシリン系の抗菌薬が処方されることが多いです。
【最も重要な注意点!】
熱が下がったり、喉の痛みが和らいだりして症状が改善したとしても、自己判断で抗菌薬の服用を中止してはいけません。医師から指示された期間(通常10日間程度)は、症状が消えても必ず最後まで飲み切ることが絶対条件です。
これは、症状が治まっても体内に菌が残っている可能性があり、飲み切らないと再発したり、さらに恐ろしい合併症を引き起こすリスクがあるためです。
見過ごせないリスク!溶連菌感染症の怖い合併症
溶連菌感染症は、適切な治療を受けずに放置すると、以下のような重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
-
リウマチ熱: 溶連菌感染から2〜4週間後に発症することがある全身の炎症性疾患です。心臓の弁膜症や関節炎、神経症状(舞踏病など)を引き起こす可能性があります。
-
急性糸球体腎炎: 溶連菌感染から10日〜3週間後に発症することがある、腎臓の病気です。血尿、むくみ、高血圧などの症状が現れ、重症化すると腎機能に障害を残すこともあります。
これらの合併症は、先述の通り、医師の指示通りに抗菌薬を最後まで服用することで、ほとんどの場合予防することが可能です。
だからこそ、症状が落ち着いたからといって油断せず、しっかりと治療を完了させることが大切なのです。
家庭でできるサポートと感染予防
治療と並行して、ご家庭では以下の点に注意してケアしてあげましょう。
-
十分な休息と安静: 特に発熱時は無理をさせず、体を休ませることが回復への近道です。
-
こまめな水分補給: 発熱や喉の痛みで脱水になりやすいので、水やお茶、経口補水液などでこまめに水分を補給させましょう。
-
喉に優しい食事: 喉が痛む時は、刺激の少ないおかゆ、スープ、ゼリー、プリン、ヨーグルトなど、喉越しの良いものを用意してあげると食べやすいでしょう。
-
家庭内での感染対策: 飛沫感染や接触感染を防ぐため、手洗い・うがいを徹底しましょう。タオルや食器の共用は避け、感染者が触れた場所(ドアノブ、おもちゃなど)はこまめに拭き取るように心がけてください。
まとめ
溶連菌感染症は、子どもがかかりやすい病気ですが、その症状や適切な対処法を知っておくことで、慌てずに対応し、何よりも重篤な合併症を防ぐことができます。
もしお子さんの発熱や喉の痛み、発疹など、いつもと違う様子が見られたら、「もしかして溶連菌かも?」という可能性を頭の片隅に置いて、早めに医療機関を受診してください。
そして、処方されたお薬は、症状が改善しても必ず医師の指示通りに最後まで飲み切り、しっかりと治し切ることが大切です。お子さんの健康を守るためにも、正しい知識を持って、適切に対応していきましょう。