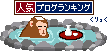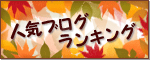「火の使い方」とは?
さて、前回の続きです。
「果たして、すみれ系の彩未もラード層で旨味を保っているのか?」
皆さんはどう思いますか?
正解は・・・
彩未未経験者の皆さんの期待を裏切ってしまう~否~でした。
純連やすみれと違って、彩未のラードはスープの表面を覆い尽くしてはいないんです。
一般的なラーメンと同程度しか油が浮いていません。
ですから、スープは普通に冷めてきます。
しかし、それにもかかわらず美味しい・・・。
ということで「火の使い方」でラーメン全体がアツアツだから美味しいという仮説は見事に崩されてしまいました。
残された選択肢はただ一つ。
そもそも温度とは関係なく、「火の使い方」が上手くて「旨味を最大限引き出すことができるから」美味しいということになります。
「純連」と「すみれ」は、その辺を上手くカムフラージュしていたのかもしれません。恐るべし純連系。
話は跳んでしまいますが、彩未入り口のボードに張ってある「RAMEN IORI」って皆さんご存知ですか?
私自身は未経験なので、もしご存知の方がいらっしゃれば、是非コメントをお願い致します。

純連系~すみれ系
まずはお約束の(^^)v⇒![]()
このブログは月寒中央周辺地区の地域ブログです。
でも、ついつい私の大好きなラーメンの話題を3話連続続けてしまいました。
ということで、話題を変えたいのですが、今変えてしまうとあまりにも中途半端ですし、せっかく「ブログランキング」ラーメン部門で9位にまで押し上げてくださった皆様に申し訳ないので、もう暫くラーメンのお話にお付き合いしてくださいm(__)m。

「麺屋彩未」は「すみれ系」です。「すみれ系」とはすなわち「純連系」です。
純連系ラーメンのUSPは「火の使い方」であるということは、ラーメン通の間では常識です。
ラーメン屋さんは普通オープンキッチンですよね。
ですからカウンター越しに調理しているところが丸見えです。
でも、純連系・すみれ系は、私の知っている限りでは調理人の手許が見えないようになっている筈です。
つまり、企業秘密です。純連系・すみれ系のみが持つ独特の強み、Unique Selling Proposition てなわけです。
確かに、そう言われてみると「麺屋彩未」も、見えそうで見えませんよね?
今から20年前の正月に初めて純連澄川店で味噌を頂いた時、私は舌と唇を火傷してしまいました。
あの漆黒の濃厚なスープ、味噌味だろうが醤油味だろうがとにかく1mm下が見えないスープの上に、透明なバリアがあるなんて思いもよらなかったんです。今でこそ有名ですが、純連名物ラード層です。このラード層があるため、湯気が見えず、湯気が見えないので熱くないんだと勝手な勘違いをして火傷するわけですが・・・。
そのラードバリアが、まるで地球の大気圏のような役割をはたしてくれてラーメン全体をチンチンの熱々状態に保っていて、ラーメン本来の旨味を逃がさないようにしているのでしょうね。あのスープの風味を美味しく引き立てて閉じこめているわけです。
創業者村中明子さんは中華料理店でのスープ修行を経て純連独特のあの美味しさを生み出したそうです。中華料理と言えば中華鍋とあの火力ですから「なるほど!」と頷いてしまいます。
「そうか、それで純連とすみれは独特の旨味があるのか・・・」「だとすると、すみれ系の彩未もそうなのか」。普通はそう思いますよね?(次回に続く)
お約束の「生姜」
さて、「麺屋彩未」の続きです。
ご存知の方も多いかと思いますが、あまりにも有名になりすぎてしまい、今では何時行っても長蛇の列です。
ごくまれに定休日以外でもお休みの日もございます(私は運悪く昨年2回続けてその日にぶち当たってしまいました)。
ですので、彩未に行く時にはそれなりの覚悟が必要です。
店主が元々「すみれ」で修行された方ですので、お約束通り「生姜」が入っています。
言われるまでもなく、見ると誰でもすぐにわかります。

ラーメンどんぶりのど真ん中に鎮座されますチャーシュー様。
ラーメンの看板娘であるチャーシュー様をあたかも座布団のように従えて、その上に「デーン」と坐っていらっしゃるのが「生姜様」でござーい。
「純連」や「すみれ」では生姜は最初からスープや細切れチャーシューと混然一体化しています。最初から砂糖とミルクが入っているイノダコーヒーのような自信と風格が滲み出ています。
ところが、彩未では、お客さんの好みに応じて加減できるよう、生姜おろしをチャーシューの上にチョンと乗せている。
謙虚な姿勢というか、カスタマーサティスファクションというか、新興勢力らしい心憎い気配りが感じられます。
ラーメンなのに百花繚乱の彩り
このお店「麺屋彩未」を某建機レンタル会社の社長に教えて頂いたのが今から遡ること8年前。
初めて口にした味噌ラーメンの味は衝撃的でした。
この当時は、「純連」「すみれ」兄弟の全盛期。このお二人のお母上様(「純連」の創業者)が再度復帰されて経営されていた「駅亭」を含めた3店舗が私にとっては札幌味噌ラーメンの三横綱でした。
この3店舗は別格として、2000年当時私が一番はまっていたラーメン屋さんは、当時地下鉄琴似駅の近くにあった山桜桃(ゆすら)という豚骨ベースのラーメン屋さんでした。
すすきのラーメン横町で一世を風靡した「ひぐま」に魅力を感じなくなり、札幌の味噌ラーメンは三横綱を除くと、チェーン展開していて何処にでもあって気軽に入れる「味の時計台」が一番美味しいかも・・・と感じていた、おりしもそんな頃。味噌ラーメンにも飽きが来始めていた私は山桜桃のとんこつ味に舌鼓をうっていました。
しかし、その山桜桃も発寒店を出店して暫く時間が経ってくると、私の味覚が変化したのか、はたまた山桜桃の味付けが変わったのか、私や私の家族の好みに合わなくなってしまいました。
そんな風に感じていた頃に出会った「彩未」の味噌ラーメンのインパクトは今でも忘れません。
そして、そのインパクトパワーを今でも衰えずに維持しているこのお店は、私にとっては札幌ラーメン界のモンスター的な存在です。(つづく)
札幌のラーメンと豊平のラーメン
まずは、このラーメンが美味しそうだと思った方は是非1クリックお願いします⇒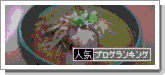
私は、最近の札幌ラーメンは、南高北低だと思います。
夏の日本の気圧配置みたいですね。
一番「人」が集まる中央区に美味しいラーメン屋さんが多いのは当然です。
札幌市は中央区を中心に、北側が北区・西区・手稲区・東区で、南側が南区・豊平区・白石区・厚別区・清田区という位置関係になっています。
全国的に有名になってしまった「純連」や「すみれ」、新興勢力の「彩未」は、いずれも南側です。
というより、「豊平区」と言った方が良いのでしょうか。
言うまでもなく味噌ラーメンは、やはり札幌が本場です。
中でも「豊平区」は、まさにラーメンの聖地と呼んでも過言ではないと思います。

「純連」「すみれ」「彩未」の純連系3店舗を筆頭に、醤油系の「らーめん佳(ヨシ)」や「ラーメン小太郎」もそうです。
ススキノに本店のある「けやき」も美園店が豊平にあります。系統は違いますが、「らーめんてつや」も美園に出店しています。
地図上で分布を見てみると、澄川~美園~月寒中央あたりに密集しています。
昔からこの辺りは札チョン族の街であり学生の街でもあったので、美味しいラーメン店が密集しているのも合点がいきます。
成城石井に月寒あんぱん?
前回、月寒あんぱんの由来を辿ってみたところ、あの木村屋創業者の木村安兵衛まで簡単に繋がってしまいました。
起業家木村安兵衛がオランダ人コックやパン職人から学んだスキルを元にあんぱん製造に成功したのが1874年頃だそうです。その翌年1875年には天皇に献上され皇室御用達の座を射止めたそうです。
木村安兵衛という「成功者」の真似をしてみた大沼甚三郎氏。そして、そこから学んだ本間与三郎氏。ビジネスモデルを真似たわけではないのでしょうけど、何時の時代もビジネスの基本は似通っていて、実際に上手くいっている人=成功者の真似をすること(モデリング)が大切ということですね。
月寒あんぱんの看板商品は当然あんぱんです。そこからアレンジしたカボチャあん・黒胡麻あん・抹茶あんや月寒あんぱんスティックというのもあります。
その他、みそぱん、ドーナッツ、月寒まんじゅう(くるみ餡入り)、北の生ショコラもち、北海道バターカステラ、北海道チーズカステラ、北海道メロンカステラ等々北海道らしい商品群が揃っています。
 実は、北海道出身にもかかわらず私自身月寒あんぱんは未だ未体験です。偶々友人が最近成城石井に行ったら月寒あんぱんを発見、早速買ってきて食べてみたそうです。こしあんがギッシリ詰まっていて高密度で甘かったとのこと。月寒あんぱんもいまや成城石井の販売網を使って全国展開している時代なんですね。
実は、北海道出身にもかかわらず私自身月寒あんぱんは未だ未体験です。偶々友人が最近成城石井に行ったら月寒あんぱんを発見、早速買ってきて食べてみたそうです。こしあんがギッシリ詰まっていて高密度で甘かったとのこと。月寒あんぱんもいまや成城石井の販売網を使って全国展開している時代なんですね。
↑興味ある方は上の写真をクリックすると成城石井の通販に繋がりますので、試食して見てください。
月寒とスイーツの歴史
前回の続きです。
何故北海道で、何故札幌で、何故月寒であんぱんなんか作ってるのか?
答えは、製造元のホームページにございました。
月寒のあんぱんは、元々は月寒に駐屯していた旧陸軍歩兵第25連隊内で菓子販売を行っていた大沼甚三郎が考案したそうです。
以下にその一部を引用させて頂きます。
---------以下引用----------
明治39年、この地に「大原屋本間商店」を開店し、連隊に日用品をはじめさまざまな物資を納めはじめた。店を創業したのは、本間与三郎若干17歳の時。
明治7年、東京芝日陰町の木村安兵衛が酒種酵母による「桜あんぱん」の製造に成功。翌年には、明治天皇にも献上され、銀座の名物として大ヒット。
これを噂で伝え聞いたのが、月寒の連隊内で菓子を販売していた仙台出身の大沼甚三郎。「あんぱん」とやらいうものを自分も作ってみようと、あれやこれや想像しながら、月餅のようなまんじゅうを作り上げた。
その製法を甚三郎から教わった本間与三郎は、その「あんぱん」を妻とともに一つ一つ手作りし、レンガの「トンネル窯」に炭を入れ、その上に鉄板をのせて下火と横火で焼き上げ、連隊に運んだ。この、ひとつ一銭の、黒砂糖でじっくりと煉ったこしあんがずっしり入った大ぶりのお菓子は、甘いものが貴重だった時代に、兵隊たちに大人気となった。
明治44年、第25連隊と住民が協力して月寒から平岸に抜ける道路を造る際、豊平町が軍に感謝を込めて毎日ひとりに5個のあんぱんを提供。あんぱんを頬ばりながら造られた道路は愛称を込めて「アンパン道路」と呼ばれ、昭和62年には記念碑も建てられた。
当時、連隊正門前の通りには7店ものあんぱん屋が軒を並べていたが、戦中戦後の混乱の中で次々と姿を消し、昭和22年、月寒地区だけでなく札幌の名物になっていた「月寒あんぱん」の製造を再開したのは「ほんま」ただ一軒だけ。」
---------引用終了-----------
うーむ、なるほど。そういうことでしたか。大沼甚三郎、本間与三郎、木村安兵衛。若き起業家、パイオニア。かっこいいですね~。
ちなみに、木村安兵衛といえば、「キムラヤのパン」で有名な銀座木村屋総本店の創業者です。皆さんご存知のあのアンパンの木村屋です。
(次回に続く)
月寒といえば、「へそ」だけあって、あんぱんでしょ
 札幌市民が月寒と聞いて真っ先に思い浮かべるのは「月寒あんぱん」かも知れません。
札幌市民が月寒と聞いて真っ先に思い浮かべるのは「月寒あんぱん」かも知れません。
そのくらい古くからの歴史があって一般受けするスイーツということでしょうか。
早速調べてみましたら、「月寒あんぱん」の製造元菓子メーカーは創業が1906年ということで、100年以上の歴史があることが判りました。
「100年?・・・」
ここは感覚が別れるところです。
京都や東京下町に行けば、100年どころが300年だの500年だのという強者が揃っています。
有名どころでは、羊羹でお馴染みの虎屋さんですね。1500年代前半に京都で創業されたらしいので、戦国以降の日本の歴史と共に歩まれてきた和菓子界の大御所です。
それに比べたら、たかだか100年と思われる方も多いでしょう。
でも、北海道の歴史は函館界隈(松前藩)は別としてまだ140年程度です。その中での100年はやはり重みがあるのではないでしょうか。
それにしても、何故北海道で、何故札幌で、何故月寒で、北海道開拓当時からあんぱんを作っていたんだろう?
素朴な疑問です。
続きは次回。
月寒公園はコストパフォーマンス№1~Part2~
前回の続きです。
月寒公園のお話です。
月寒公園の敷地面積はナント約21.8ヘクタールもあります。
東京ドーム約5個分の広さになります。
中島公園が21.0ヘクタールですので、中島公園よりも大きい公園なんですね。
ちなみに、札幌で一番大きな公園は野幌森林公園です。公園面積は2,051ヘクタールもあるそうです。
(野幌森林公園は、札幌市厚別区から北広島市と江別市の3市に跨っています)
次に大きいのが、モエレ沼公園の約188.8ヘクタール。
その他、前田森林公園50.4ヘクタール、旭山記念公園は20.8ヘクタール、手稲稲積公園18.1ヘクタールといったところです。
月寒公園は、かつて月寒に駐屯していた大日本帝国陸軍第7師団歩兵第25連隊の演習場「千城台」の跡地です
敷地内には、パークゴルフ場、野球場3面、テニスコート2面、アスレチック遊具群、プール、ボート池、スキー山等の施設がります。ナイター設備もしっかりと整っています。これだけの施設を整えた公園って意外と少ないですよね。
ちなみに、札幌市内でボート池があるのは月寒公園と中島公園だけだそうです。
知名度は低いけど、中身が充実している憩いの場。
月寒って実はとても社会インフラが発達していたんですね。グッ!! ( ̄ε ̄〃)b
月寒公園はコストパフォーマンス№1~Part1~
東京都を1つの都市と数えて、政令指定都市合計20都市の中で都市公園が一番多い都市は何処かご存知ですか?
あたりまえかもしれませんが答えは東京です。
そして、我らが札幌は横浜に次いで全国3位です。
でも、面積が一番広いのはご想像通り札幌です。
公園数でこそ東京都区部の約半分の2,500ですが、面積では約4千ヘクタールと他を圧倒する広さです。
そんな、札幌の公園の中で、一番有名なのはやはり大通公園でしょう。
一方で、北海道らしい公園というと、野幌森林公園です<http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/environ/parks/nopporo.htm >。
あの広さといい、開拓村を擁している点といい、北海道を理解するにはうってつけの公園だと思います。
地域住民の立場から意外と人気があるのが前田森林公園です<http://www.sapporo-park.or.jp/maedashinrin/ >。郊外の住宅地に溶け込んでいて、何となくお洒落で、しかもお散歩とか子供連れにとっても便利ですから分かるような気がします。
また、大地を彫刻に見立てたモエレ沼公園も外せません<http://www.sapporo-park.or.jp/moere/index.php >。公園そのものがかの有名な日系米国人の彫刻家イサム・ノグチの作品です。
景色の良い旭山記念公園や円山公園も市民の憩いの場として欠かせない存在です。
そんな公園のなかで、知名度はあまり高くないのですが、穴場的な公園が月寒にあります。
その名も月寒公園です。
続きは次回(^^)/。