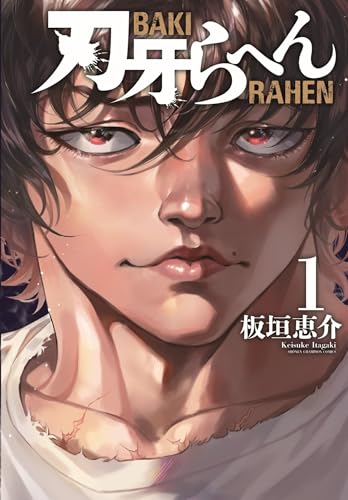第19話/父が子を誘う理由
範馬勇次郎とジャック・ハンマーの親子がホテルで会食中だ。
テーブルにはモリモリの骨付きラム肉が置いてある。ひとつひとつは小さいけど、とてもふたりで食べる量には見えない。
ウェイターが説明する前で、ふたりは勝手にはじめる。ふつうは骨を外すものだが、ジャックはポッキーみたいに骨ごと食べる。骨ごと食べるというか、骨も食べられる箇所のように当たり前にかじるのである。勇次郎はふつうに食べてるらしい。勇次郎も人間の骨格をしていないし、やろうとおもえばできそうだけど。
骨をかじり、くだく音がどういうものか知らないが、なかなか騒々しいらしい。個室で幸いだったと勇次郎はいうのだった。
食事が終わったところで、ジャックは、何故じぶんを誘ったのかと訊ねる。理由が必要かと勇次郎がいうのに対して、父親が自分について語るすべてを、余すことなく聞きたいとジャックは素直にいう。勇次郎はかなりうれしそうだ。見たことない顔だ。
勇次郎は、父親が息子を飯に誘うことのどこが不自然なのだと、わりと真顔でいう。以前ならこれはもう少し演技くさかった。刃牙との経験を通じて、これを本気でおもうに至ってるっぽい。
ジャックは笑いを隠しながら、それは普通の父と子のはなしでしょという。そりゃあ、そうだなあ・・・。範馬家では、勇次郎がどれだけ「父」になりきれたとしても、うそくささは拭い去れない。
ジャックは勇次郎の目を見ながら、特段敵意がある感じでもなく、素直な質問として、あなたはじぶんを普通の父親だとおもうのかと問う。勇次郎は「フツウ・・・か・・・」といって少し黙っちゃう。そして空を見上げ、考えたことのないと気がつくのだった。
まあ、たいがいのひとは、ふつうとはなにかなんて考えないとおもうので、こたえとしては勇次郎だからどうだというものでもないのだが、ジャックはそれを勇次郎らしい回答だという。まあ、勇次郎が「普通とはなにか、考えたことがない」というふうに読むと、たしかに勇次郎らしいかもしれない。
尊敬と憧れをこめてジャックは、人として、生物として普通ではないと勇次郎を評す。勇次郎はふつうにその言葉を受け取っているが、まともに見たら挑発文句である。ウェイターはたまらず退室だ。だが、じつはドアの外からなかをうかがっている。
勇次郎は、ふざけてるのか本気でへこんでいるのか、それを「人でなし」と言い替える。だいぶちがうとジャックはあわてるが、「尊敬と憧れ」に免じて許してやると。
だが、長いあいだジャックのはなしを聞いていた勇次郎は、いつのまにか闘争心でいっぱいになっていたっぽい。基本的にジャックは勇次郎をほめていたわけだが、そこに含まれる微量の挑発と、ジャックじしんの魅力が、勇次郎をその気にさせてしまったのかもしれない。デザートのタイミングだが、そんな柄でもないだろう、それより、何故イチバン手にしたいもののために踏み出さないのかと、勇次郎が髪を浮かせながら立ち上がる。
ジャックは落ち着いている。以前までには感じられなかった、強烈な自信が見て取れる。それは勇次郎のほうではないのかというはなしだ。あなたこそが俺を欲しいのではないかと。テーブルをまわりこんで立ち上がったジャックはほんとうに巨大だ。それを、勇次郎は泣かすぞという。ゴングも行司もない、襲いかかれば開始だと、ジャックは応じるのだった。
つづく
いまのジャックはほんとうに強い。勇次郎、バキ、ピクルと、若干例外的に武蔵が強さとして並んでいるとして、範馬一族としてようやくそこにジャックが食い込むことができた感じだ。ほんとにたたかうなら接戦だろうし、すごく長くなるだろう。つまり、本気でははじまらないと見た。
だが、本気ではないならないで、勇次郎と接触することで、ジャックの強さがほんとのところどれくらいかわかるだろう。
勇次郎が「普通」を考えたことがないというのは少し意外でもあった。なぜなら、食事のマナーやいま見せている「父親らしい」ふるまいは、「普通」の目線を想像的に獲得することでとられているものだからだ。これについては、本人が普通であるかどうかは関係ない。「普通」とは、規範のことである。規範が、動詞になって働き、ダイナミズムを帯びている状態のことである。「エエカッコしい」のはなしにも通じるこの「規範」について、勇次郎は考えたことがないというのである。
ただ、ここでの会話は、「貴方は自身を普通の父親だと」おもうのか、ということで、それを受けて、勇次郎はいちど「普通」という言葉をかみしめて、考えたことないといっている。「普通」を考えたことがないのか「普通の父親」を考えたことがないのかで意味は微妙に異なってはくる。しかしここでは、いずれにしても「どのようにふるまうべきか」という規範について考えるものとして、同一にあつかうこととする。
勇次郎が「普通」を考えたことがないという状況については、みっつのものが考えられる。ひとつは、嘘をついているということである。ジャックは父の強さを崇拝している。そんな息子の前で、彼は引き続き「範馬勇次郎」を演じてしまっているのかもしれない。ふたつめは、勇次郎じしんが気づいていないということである。彼は、地上最強という孤独のなか、それでも食事のマナーのような、社会関係の網目のなかでのみ有効な、ローカルな作法を身につけている。そうなっているからにはかつてそこに渇望があったことになる。その場所で求められるしかるべきふるまいを選びたい、ふつうのひとがしていることをしたいという欲望があったのだ。そうして、彼は、地上最強ではない市井のひとびとにとっての世界を想像し、そうしたマナーを身につけたはずなのである。この過程が、すっぽぬけてしまっているのだ。たしかに、範馬勇次郎が「渇望」するなどということは、セルフイメージ的にもあってはならないことだろう。孤独の描写じたいが、バキ戦で初めて見られたものだった。勇次郎は、じしんの孤独を、忘れないまでも、なるべく見ないようにしている。その結果、「ふつうのふるまい」を求めたという事実も、無意識に見落としてしまっているのかもしれない。
そして三つ目は、言葉のまま、「普通」について考えることなく「普通」が実現しているということだ。これは、それこそ「普通」のひとなら、当たり前のことだ。たいがいのものは、ひとのものを奪っていいかどうか検討してから奪うことをやめる、というふうには生きていない。ただ、奪わない。しかし勇次郎はそうではないだろうというのが問題なのである。
普通の父親らしいふるまい、普通の食事のマナー、骨ごと肉を喰らう息子を見て個室でよかったとする普通の感覚、これらを、それがなんであるか理解しないまま、ほんらいそこに属さないものが身につけているという状況、それがこの三つ目の解釈だ。文化資本という考え方があるが、たとえば高い教養を、「教養」というものが存在しないような世界で、特に意識せず身につけるということは不可能である。
こうしたわけで、おそらく勇次郎においては、ひとつめとふたつめの解釈が入り混じったような自己確立が行われているのではないかとおもわれる。つまり、「普通」を模倣していることを、彼自身気付いておらず、そしてなぜ気付いていないかというと、そこには「範馬勇次郎」というセルフイメージがあるからなのである。「範馬勇次郎」たるものが、「普通」を意識して、孤独から逃れようと、擬似的な「社会」を体験しようとしていることを、自他にむけて示すことに彼は耐えられないのである。だから、そのような模倣が実行されたことを彼のこころの安全弁のようなものは忘れさせるのだ。
そして、おそらくこれが、勇次郎における「エエカッコしい」の本質なのである。孤独を貫徹せず、妙なところで社会性を発揮しようとし、じっさい身につけて行使している、そのことが、範馬勇次郎という存在にわずかなゆがみを呼んでいるのだ。ゆがみといってもそれは、前回見た「強さ」目線でいったときのはなしだ。ジャックが体現する「強さ」は、ある種の子どもっぽさからきている。強さだけ、それだけがあればいいとするものは、社会性なんか必要としない。そういう目線で見たとき、それは「エエカッコしい」になるのである。
管理人ほしいものリスト↓
https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/1TR1AJMVHZPJY?ref_=wl_share
note(有料記事)↓
お仕事の連絡はこちらまで↓