From:ななころ
プライベートオフィスより
◆『人を動かす』を7回を読むプロジェクト
日本を代表する商売人が、
「この本は良い!」
「私の本を読むぐらいならこの本を読め!」
「7回は読みなさい!」
というほどの名著。
「人を動かす」(デール・カーネギー)
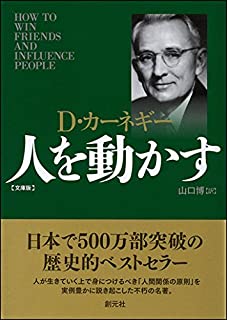
しかし、簡単なようでいて難しい。
なかなか7回も読むことができない。
さらに言うと、1回すらちゃんと読むことができない。。。
ということで、1話づつクイズ形式にしてブログでシェアすれば、ななころが本の内容を理解しながら読み進められるのではないか!?
ついでに、ブログの読者のために役立つのではないか!?
と思い立って始めたプロジェクト。
「『人を動かす』を7回を読むプロジェクト」
「不動産投資のブログなんだから、不動産投資に関して発信してよ」と文句が出そうな企画(笑)。
自己啓発系に興味の無い方や毛嫌いしている人は、どうか読み飛ばしてしまってください。
(毎週1回だけの配信の予定です。)
とはいえ、人生をより良く描くには人間関係を良好に保つことが不可欠。
「人の動かす」の原文タイトルは、
「How to win friensd and infulence people」
(友を得て人々に影響を与える方法)
ブログ読者様と一緒に「人を動かす」を読み進めながら、良好な人間関係を築いていきたいと考えている次第です。
【第二話】アメリカの最も偉大な大統領リンカーンが、良好な人間関係を保つために大切にしていた言葉は?
【第三話】人を動かすためのたった1つの秘訣とは ?
【第四話】「人の立場に身を置く」とはどういうことなのか?
【第五話】数年間ずっと断られ続けてきた営業マンが、相手の方から「買うよ」と言われるようになった秘訣とは?
【第六話】人生を強力に変える「◯◯」の効果とは?
【第七話】少年時代の成功体験にもととなる、鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの成功の秘訣は何か?
【第八話】歴史的なアメリカ女性誌を作り上げた人物が、少年時代にアメリカ中の成功者とつながった秘訣とは?
【第九話】史上最年少42歳でアメリカ大統領になったルーズベルトが考えていた「人の心をとらえる近道」とは?
【第十話】人間関係の重要な法則「相手に重要感を持たせる」その具体的な方法は?
【第十一話】相手と議論になった時、この世にただ1つ最善の解決策とは?
【第十二話】相手が明らかに間違っている時でも、意固地にさせず、誤りを認めさせて、納得してもらうには?
【第十三話】自分の非がある時、相手がすんなり許してくれるためには?
【第十四話】ことわざ「1ガロンの○○よりも、一滴の△△△△の方が、多くの□□が取れる」
【第十五話】建設的な議論をしたい場合、絶対にやってはいけないこと、やるべきこと
【第十六話】話しをまるで聞かない反抗期の娘の心を開いた母親の態度とは?
【第十七話】人が自ら進んで動くようになるには?
【第十八話】相手と意見・主張が異なる時、非難することではなく、まずは◯◯する
【第十九話】相手の敵意を好意に変えるためには?
【第二十話】成功している人ほどお金では動かない理由
【第二十一話】人を動かすには事実を伝えるだけでは足りない。◯◯が必要!
【第二十二話】鉄鋼王カーネギーが重宝した人物の優れた業績アップの方法
【第二十三話】相手を納得させるのは、過失を責めるのではなく、まず相手を○○る。
【第二十四話】対立を生まずに、相手を注意するには?
【第二十五話】相手を不愉快にさせずに注意するには?
【第二十六話】反感を生まずに人を動かすには「命令せず、○○を求める」
【第二十七話】相手の○を立てるだけで、伝わり方がまるで変わる!
◆カーネギーからのクイズ #027
次に紹介する本の冒頭は、世界中で2億冊以上が売れ、英文学の歴史上もっとも有名だとされている。
(多くの日本人が「平家物語」「徒然草」「雪国」等の冒頭を知っているように有名)
あなたは、次の冒頭で始まる本をご存知だろうか?
「それはすべての時代の中で、最良の時代であり、最悪の時代でもあった。英知の時代であるとともに、愚鈍の時代であり、信念の時代でもあったし、不信の時代でもあった。それは光の季節でもあれば、暗闇の季節でもあったし、希望の春でもあれば、絶望の冬でもあった。」
ご存知だった方は素晴らしい!
もちろんご存知なかった方も、うっかりと忘れてしまった人も、まったく問題ない。
これはイギリスの作家・チャールズ・ディケンズが1859年に出版した「二都物語(A Tale of Two Cities)」という本の出だしだ。
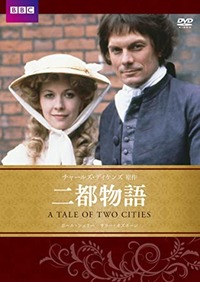
この他にもチャールズ・ディケンズが書いた「クリスマス・キャロル」や「大いなる遺産」といった名著は、今でも語り継がれている。
しかし、世界的に有名な作家チャールズ・ディケンズは、少年時代、何一つ恵まれていなかった。
両親とも金銭感覚に乏しく、家計は崩壊。
少年期は病弱であり、学校は4年間しか通えなかった。
父は刑務所に入ることになり、12歳で一人暮らしとなり、靴墨工場で働かされた。
この工場での仕打ちはひどく、彼の精神に深い傷を残した。
そんな彼が、後々世界的な名著をいくつも世に送り出すことなったのは、”ある1つのきっかけ”からだった。
その”きっかけ”には、人が大きく成長して飛躍するヒントが隠されている
その”きっかけ”とは何だろうか?
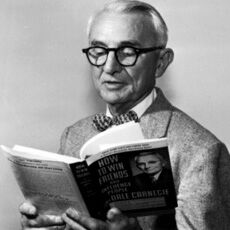
◆答え
心理学者のジュス・レアーは、次のように書いている。
「ほめ言葉は、人間に降り注ぐ日光のようなものだ。それなしには、花開くことも成長することもできない。我々は、事あるごとに批判の冷たい風を人に吹きつけるが、ほめ言葉という温かい日光を人に注ごうとはなかなかしない。」
わずかなほめ言葉で、その後の人生がすっかり変わった経験をした人もいるのではないだろうか?
チャールズ・ディケンズもその一人だった。
ディケンズは、貧しい生活を強いられながらも、人の寝静まった頃をにはからってそっとベッドを抜け出し、書き上げた小説の処女作を郵送していた。
次々と作品を送っては、すべて送り返される日々を送っていた。
しかし、転機が訪れる。
ある作品がとうとう採用されたのだ。
原稿料は一線ももらえなかったが、編集者から褒められたのだ!
彼は感激のあまり、あふれる涙をぬぐいもせずに、街を歩き回った。
そして、そこから彼の人生が大きく変わり、世界的な名著を次々と生み出すこととなったのである!
「ほめる」という行為には、人を動かすどころか、人の人生を大きく動かしてしまうほど強力な方法なのである。
人を変える原則⑥「わずかなことでも惜しみなく心からほめる」

◆ななころの体験談と実践
先日、旅行先のホテルにある屋内プールの話し。
泊まったホテルには屋内プールがあるということで、子供たちも大喜び。
温泉に入る前にプールで遊ぼうということになりました。
泳いでみたり、水中の中で逆立ちしてみたり、キャッキャと騒いでいると、隣からものすごい怒鳴り声が聞こえてきたのです。
「やる気がないんだったら帰れ!」
「そんなんじゃ泳げるようにならないぞ!」
小学2年生ぐらいの男の子とそのお父さんが、泳ぎの特訓をしているのです。
しかし、その叱咤激励が異常。。。汗
子供の顔を鷲掴みにしたりして怒鳴っているのです。
思わず止めに入ろうかと思ったほどでした。
子供は泣きながら、それでも健気にお父さんの言うことを聞きながら泳いでいます。
これでは泳ぎげるようになるどころか、「水泳が嫌いになってしまうだろうな」と思いました。
ななころも、母親が音楽教師だったこともあり、ピアノの練習をしていると良く怒られました。
ピアノが嫌で嫌で仕方がありませんでした。。。
結局ななころのピアニストとしての人生はすぐに閉ざされてしまったのです。
しかし、ななころの母も孫ができて、ババになります。
孫が可愛いババは、ななころの息子たちを決して怒ったりしません。
息子たちがピアノを弾いていても、「すごい!」「上手!」と褒めまくります。
そのため、息子たちはピアノが大好き。
iPadに入れたピアノアプリで楽しそうに弾いています。
今では私なんかよりも上手にピアノを弾きます。
私たちの世代やもっと上の世代からすると、「ほめる」という行為が苦手だったり、抵抗があったりしますよね。
「ほめる=甘やかす」と考える人も少なくありません。
しかし、ほめ言葉が意味を持って相手の心に伝わると、ものすごい効果を発揮するのです。
私たちのその後の人生を大きく変えてしまうほどに!
◆編集後記
この章に書かれていることもとても大事で、今回は特にななころの心に響きました。
これまで、ななころは日本のスポーツの世界で生きてきて、プールで息子をひたすら怒っているお父さんのような指導者をたくさん見てきたからです。
一方で、友人でもありノルウェーで学校の先生をやっている彼の指導法は真逆。
絶対に子供を頭ごなしに怒ることはありませんし、良いところを徹底的に褒めます。
本当に衝撃を受けました。
とはいえ、「ほめる」というのは簡単なようでいて、結構難しいですよね。
上辺だけで褒めてもなにも意味はありませんし、逆に反発を覚えることもあります。
どのように褒めたらいいのか?
この章には、とても大切なことが最後に書かれていました。
「ほめ言葉が具体性を持っていてはじめて誠意の言葉、つまり、ただ相手を喜ばせるための口先だけのものではない言葉として、相手の気持ちをじかに揺さぶるのである。」
「相手の心の中に隠された宝物の存在に気づかせることができたら、単にその人を変えるだけでなく、別人を誕生させることすらできるのである。」
ななころも、もっともっと「褒め上手になろう!」と感じた次第です。
