(No.ym-057)
本ブログのメインコンテンツの4コマ単位マンガは昭和20年の物語を描く「ヨシノとミコト編」を公開しています。
今回は第二部第4幕「堕テンシ、目覚める!」を第6回めをお送りします。
<ここまでのお話のまとめページ>
★第一部★
第一幕「あの人との出会い」
第二幕「運命へのプロセス」
第三幕「動員学徒の日常」
★第二部★
<とりあえず一言>
ヨシノの刀の持ち方は、いわゆる「馬鹿持ち」と呼ばれる、剣術の心得のない人がやりがちな、両手をくっつけてしまう持ち方。
バットの持ち方と同じ感じです。
刀は両手で構える場合は右手は鍔寄り、左手は柄の先端に近いところを持つのがオーソドックスで刀さばきがやりやすいです。
余談ですが、刀だけではなく銃なども持ち方にセオリーがあります。
僕が偉そうなことは言えませんけど(笑)、戦いのプロであるはずのキャラは武器を適切に扱ってる様に注意して描かないといけませんし、逆に武器の素人であることを表すために、わざとデタラメな持ち方をさせる表現テクニックもあります。
後日、記事を追加する予定です。
マンガ本編ではなくて、メイキング的な話を考えています。
<1月22日追記>
「構図とキャラの力関係」
今回の追記は、知ってる人にとっては「まぁ、そうですね」で終わりそうですけど、創作を手がける人にとっては参考になるかもしれないと思います。
と言っても僕の説明できるのは、入門の入門って程度のさわりだけですが・・・。
最近の「ヨシノとミコト編」はヨシノと松井中尉のバトルを描いていますが、原則として「有利なキャラクターは(どちらかと言えば)画面の右側にいて左を向く(左に向かう)」、「立場が不利なキャラクターは(どちらかと言えば)画面の左側にいて右を向く(右に向かう)」というネームを切ってきました。
なので、今回もそうなのですが、ヨシノが逆転してからは画面の右の方にいて、左を向いている構図です。
これは次のような心理的な効果を利用してみた結果です。
触りだけご紹介しますが、もっと知りたい方は記事の最後に挙げた書籍をお勧めします。
舞台には上手(かみて)から下手(しもて)に流れる力場のような物があるように思います。
(日本語の漫画の場合も右上から左下に読み進める構成がほとんどですので、やはり力場の流れがあるように思います)
上手にいるのは「上位(強くて安定した存在)」であり、下手にいるのは「下位(弱くて不安定な存在)」です。
下手のキャラクターが上手を目指すには「力場」のようなものに逆らわなければならないように思います。
上手(かみて・・・見る人からみて画面右側)にいるキャラはそれだけで強そうな印象になります。
一方、下手(しもて・・・見る人から見て画面左側)にいるキャラはそれだけで弱そうな印象になります。
この法則は、舞台や映像など画面の「枠」が固定されているときには成り立ちます。
僕のマンガも4コマのコマ割りで「枠」が固定されているようなものなので成り立つと考えました。
ただし、ストーリーマンガの自由度の高いコマ割りの場合は、この限りでもないように思います。
下手(しもて)のキャラが上手(かみて)のキャラに背中を向けてしまえば、この強弱の関係はより大きくなります。
この場合、下手のキャラクターは完全に負けキャラです。
特に上手でも、より画面の右上にいるキャラはさらに強そうに見えますし、下手でも、より画面の左下にいればさらに弱そうに見えます。
しかし!
下手のキャラクターが上手のキャラクターに挑む構図を取った時、それは(左右逆の構図と比べて)より大きなパワー感を感じさせます。
これが「主人公」の立ち位置としてかなり映えます。
ゲームのスーパーマリオや陸上競技の徒競走の映像が画面の左から右に走っていく構図になっているのも、この「挑んでいる」という心理的なパワー感がナチュラルに心地いいからではないかと考えてます。
松井中尉に突撃していくヨシノの構図は、これを踏襲しています。
これらは参考書に原則として紹介されているものです。
その原理には人間の心臓の位置の話も出てきますし、あるいは、あくまで「原則」なので、わかった上で原則破りをして、もっと高度な表現をする技術もあるそうです。
詳しく知りたい方へ、以下の参考書をご紹介します。
<参考になる本>
左:「映像の原則」
富野由悠季 著
2002年 キネマ旬報社
右:「カタルシスプラン」
樹崎 聖 著
2016年 幸文堂出版
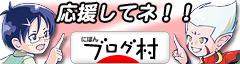
にほんブログ村
ランキングに参加しています、ぜひクリックをお願いします!!







