(No.ym-056)
本ブログのメインコンテンツの4コマ単位マンガは昭和20年の物語を描く「ヨシノとミコト編」を公開しています。
今回は第二部第4幕「堕テンシ、目覚める!」を第6回めをお送りします。
<ここまでのお話のまとめページ>
★第一部★
第一幕「あの人との出会い」
第二幕「運命へのプロセス」
第三幕「動員学徒の日常」
★第二部★
<とりあえず一言>
ブランクがあいてしまいましたが、何とか再開しました。
先日のブログで「まとめ」をアップしてますが、平常運転時は、このように4コマ単位でブログを更新しております。
ストーリーをお伝えする上では、かなりテンポの悪い方法だとはわかっておりますが、ブログの更新頻度を維持することも意図してます。
それの埋め合わせとして(埋め合わせになってないときも多々あるとは思いますが(^^;)、解説やメイキングなどの記事を併記してます。
この記事なのですが、後日追加するつもりです。
(マンガ先行で記事を後日追加するスタイルもすっかり「通常運転」になりました)
改めましてよろしくお願いいたします。
ここから1月15日追記
<軍刀のうんちく>
ウンチクと言ってもWikipediaなどを中心にネットで調べられる範囲に過ぎません。
さらに言えば僕の理解は正しくないかもしれません、その点はご容赦下さい。
話題にもなるかと思いまして、書かせて頂きます。
太平洋戦争当時の日本の軍人は一定身分以上であれば軍刀の佩用(はいよう)が認められていました。
この軍刀ですが制定や製造された時期によってバリエーションが大変に多いです。
松井中尉の軍刀は昭和10年に制定された九五式軍刀をモチーフにしています。
柄の先につけられている房の着いた紐は元来は手首を通してすっぽ抜けないようにするためのパーツが付いているのではないかと思われますが(?)、松井中尉の刀からは外されてます(なので単なる装飾となっています)。
「刀身」はいろいろな種類があります。
歴史ある日本刀そのもの、あるいは伝統的な製法で作られた刀身もありますし、工業製品として製造された刀身もあります。
一つ言えるのは、基本的に当時の軍刀はれっきとした刃物であり、「切る性能」は持っています。
(現在の自衛隊が儀礼で用いているサーベルの刀身は青銅にメッキを施した装飾品で「切る性能」は基本的にはありません)
・・・ということを踏まえて、本作では竹の棒だのズック靴だのを切ってます。
このように書くと何だか実践的な武器のように思えてきますが、近代戦において武器としては、おそらく出番はほとんどなかったのではないかと思います。
銃火器を相手にできるものではないでしょう。
もっぱら身分(権威)を示すためや指揮をとる用途だったろうと思います。
重さは厳密にはわかりませんでした。
ただし、一般的な日本刀が1.5kg程度とのことですので、同程度の重さだろうという認識でいます。
女の子でも片手で持ち上げることは余裕だと思います。
ただし、振り回すとなると全く話は別です。
たとえば金属バットは1kg前後ですが僕は片手でスイングはできません。手首を壊してしまいます。
日本刀は本来は両手で使う武器です。
松井中尉は作中で少なくとも二回は片腕で振り下ろしていますので相当な豪腕です。
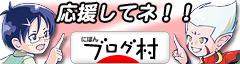
にほんブログ村
ランキングに参加しています、ぜひクリックをお願いします!!


