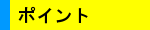概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>
日経ビジネスの特集記事(118)
社畜卒業宣言
「バブル組」が拓く新たな働き方
2015.08.03
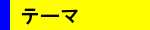
今週号の特集のテーマは
出世のためには深夜残業や休日出勤もいとわず、
家庭を犠牲にして会社に滅私奉公する──。
典型的な日本のサラリーマンを、作家の安土敏は
会社に飼われた「社畜」と表現した。
社長の指示で不正会計に手を染めた東芝社員
もまた社畜である。
だが、会社に忠誠を誓う代わりに雇用を守る暗黙の
「契約」を、会社は反故にし始めた。
世界競争にもまれる中、かつて大量採用した
「バブル入社組」を支えきれなくなってきたのだ。
捨てられるバブル組。
だがそれを「卒業」と考えれば、必ずしも不幸ではない。
今こそ、自らの意思で社畜と決別しよう。
そこから働き方の未来が拓く
(『日経ビジネス』 2015.08.03 号 P.024)
ということです。

「バブル組」が拓く新たな働き方
「日経ビジネスDigital」 2015.08.03

「日経ビジネスDigital」 2015.08.03
第1回は、
「PART1 『契約不履行』が始まった」
を取り上げます。
第2回は、
「PART2 100社調査が示す不都合な真実
6分の1がバブル組
重圧が促す裏切り」
「INTERVIEW 伊丹敬之・東京理科大学教授に聞く
『人本主義』は死んだのか」
を取り上げます。
最終回は、
「PART3 先駆者が拓く新たなキャリア
オレたち社畜 脱出組」
「PART4 社畜が消滅した後の世界
バブル入社組から始まる超サラ」
をご紹介します。
今特集のキーワードは次の5つです。

社畜卒業
バブル組
契約不履行
人本主義
超サラ
では、本題に入りましょう!
PART1 「契約不履行」が始まった
長い間、社員は滅私奉公する代わりに、終身雇用を
保証されてきました。
ところが、企業が一方的に裏切るケースが増えて
きました。
シャープのケース
(PP.026-027)
6月18日木曜日。大阪・西田辺にあるシャープ本社。
営業部門のグループリーダー、青野正(45歳、仮名)
は同僚や先輩と大きな会議室に向かった。
招集がかかったのは「2015年9月30日時点で満年齢
が45歳以上59歳以下かつ勤続5年以上」の全社員。
国内の全事業所、労働協約適用の関係会社、
健康保険組合、企業年金への出向者も各自の職場で
同じ説明を聞いた。
「『希望退職の募集』について」──。
人づくり推進部による説明は、純損失が2223億円に
及んだ2015年3月期決算の窮状から始まり、
希望退職制度の概要へと進んでいった。
シャープの連結従業員数は約5万人だから、希望退職
による人員の削減率は10%に満たない。
だが、会社が減らしたいのは固定費が高い中高年層、
中でも定年まで10年近く残っているバブル世代だ。

・特別加算金の年齢別加算月数の分布
「日経ビジネスDigital」 2015.08.03
私もリストラされた経験がありますが、社員と会社との関係は
こんなに脆いものとは、当時、考えていませんでした。
「会社が、自分たちを裏切った」(P.028)
(P.028)
青野はシャープが好きだった。シャープで働く仲間が好きで、
液晶テレビで大躍進した時にはたまらない高揚感を味わった。
最強チームの一員であることを誇らしく思った。
その会社が、自分たちを裏切った。
パナソニックのケース
携帯電話事業を売却されたことにより、転籍を余儀なく
された元パナソニックの社員の話です。
(P.029)
2014年7月20日の明け方。パナソニックの通信インフラ部門
の管理職だった田崎隆一は自宅のテレビでゴルフの全英
オープンを見ていた。3連休中日の日曜日である。
ロリー・マキロイの独走を見届け、一眠りしようと思ったところ
で携帯電話が鳴った。
「田崎さん、ノキアって本当ですか。今朝の新聞に出てますよ」
親しくしている顧客企業の調達担当者からだった。
田崎は慌てて玄関に新聞を取りに行った。
「パナソニック、携帯基地局事業をノキアに売却」と日本経済
新聞が報じていた。田崎はスマートフォンを耳と肩の間に挟み、
記事に目を走らせながら担当者に言った。
「あの、私も詳しくは知りませんが、大丈夫です。ご迷惑を
おかけすることにはなりませんから」
寝耳に水とは、このことです。
社員が知らない重要な話を新聞が報道したのです。
(P.029)
パナソニックとノキア(フィンランド)はこの分野で2007年
から提携しており、経営層からの情報が断片的に入る
田崎らベテランには、「いずれ何かがある」という予感は
あった。ただ、事業部丸ごとの売却とは思っていなかった。
その一方で、これをチャンスと捉える元パナソニック社員が
いました。
(P.029)
一方、技術者の宇吹博充はチャンスと見た。
通信がやりたくて旧松下通信工業に入社した宇吹は、
この分野でのノキアの実力を熟知している。
「彼らと組めばもっと面白いことができる」。
開き直りかもしれませんが、チャンスと捉えることは
大切なことです。
『日経ビジネス』特集班は、愛社精神に関して、
次のように書いています。
(P.029)
自分の意思とは関係なく働く会社が替わった彼らは、
パナソニックに対して持っていた愛社精神をノキア
にも持てるだろうか。答えは「否」である。
「ここで働くのは楽しいです。でも今回のことである種
の覚悟ができました。残りの人生を1社で過ごすわけ
ではないでしょう。どこへ行っても通用する力を付けて
おかなくては」(宇吹)
社員は企業の都合で振り回される事態に陥っています。
「雇われている」者の弱みです。
(P.029)
三洋を買収したパナソニックは通信インフラ事業を
ノキアに売り、ノキアは携帯端末事業を米マイクロ
ソフトに売った。そしてマイクロソフトは通信部門で
約7000人の削減を決めた。
元パナソニックの社員は開き直って、次のように語って
います。
(P.029)
「ノキアの人たちを見ていると、会社から与えられる
のを待つのではなく、スキルや経験を奪い取ろうと
している」と宇吹は言う。
「危険な時代」を生き抜くための心構えだ。
雇われている者の悲哀と言ってしまうと、身も蓋もあり
ませんが、悲しいかな、それが現実です。

もはや「安全な場所」はない
日本有数の企業に勤務していれば、「安全・安心」で
あった時代はとうの昔に過ぎ去りました。
これからの時代は、「個」の力がいっそう試されることに
なると思います。
「自分ブランド力」が欠かせない時代になったと考えて
います。
今特集のキーワードを確認しておきましょう。

社畜卒業
バブル組
契約不履行
人本主義
超サラ
次回は、
「PART2 100社調査が示す不都合な真実
6分の1がバブル組
重圧が促す裏切り」
「INTERVIEW 伊丹敬之・東京理科大学教授に聞く
『人本主義』は死んだのか」
をお伝えします。
ご期待下さい!
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書