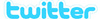掌の美に想う
はがきサイズの凝った紙に書を書くのは楽しいものである
昔は三メートルの長さの紙に一文字書いたりした
大字書の揮毫とはスポーツ的で紙の上に巨大な筆で書くが
そんなに難しいものではなく
むしろ小さい紙面に文字を工夫して書き作品を大きく見せることの方が大変である
掌の美というが手のひらサイズに作られたものは面白い
根付や鼻煙壺のコレクションなども楽しいし
ボンボニエールなどは金平糖などのお菓子を入れて楽しむものだが
宮中の結婚式などのお祝いに招待客に配られたものなどは掌の美の優雅さを示すものである
貞明皇后の時代のものなどは時代がヨーロッパの匂いと日本の古典の格調が相まって優れている
帝室技芸員などすぐれた仕事をした人が明治や大正や昭和の初めまではいたが
皇室の仕事となると想像を超える仕事ができたのは時代が影響する
宮中の晩餐会などは昔招待客のメニューを一人一人墨で書いたものだが書のレベルも使われている紙もとてもすぐれている
私が寸松庵色紙が好きなのもサイズが小さいことに由来すると思う
羊脂玉の中国の玉を昔掌に乗せて毎日磨いたことがあるが
これも面白い時間だった
西山松之助先生の名茶杓である百万遍を学生の時羽二重の布で磨かされたことがある
先生は本当に百万回磨いたと豪語されていたが
これは事実である
茶杓も掌の世界であり茶杓を削ると朝まで夢中になると先生は話されていたが
禅に通じていた西山先生の場合は夢中ではなく無中だと確信するのである
ものを通して見ること
私も写真集の題字など依頼されて書いたことがあるが
写真の力とは本物以上に輝きを増すことがある
上の写真はご縁のある日本を代表する写真家の金井杜道さんの観音の写真で教室にいつも飾ってある
金井さんは興福寺の阿修羅像を撮られた方で撮った時にすごい波動が湧き出たことを京都でお聞きしたことがある
最近は版画の評価が下がったようだが一度ものを違う技術で再現すると不思議なパワーが出るのである
私は昔ルドンが好きで多くの版画を見たが油絵よりも何か深淵な力を感じた
直接よりも間接的な陰影とは魅力的なものだ
ろうそくの光も絽や紗のようなもので透して見ると色香が増すものである
書も墨の力で陰影を出すことに心を配りはするがなかなか難しいのが現実である
書の取り合わせに思う
書家はほとんどが書いた作品を表具屋任せにすることが多い
寿司屋に行っても寿司の本質を理解していない職人がたまにいるように
表具屋もセンスのない仕事をする人がいるものだ
しかしこれは大変困るのである
苦労して書いた作品もかわいそうだし気に入らない表具にお金を払うことはさらにつらい
だから私は表具屋任せにはせず使う裂の好みから軸先の選定また天地の配分と細かく表具屋の仕事場まで行って注文する
注文が多い書家は厄介のような気がするが逆に表具屋はその方が楽であり
すべての責任は書家がとる訳なので書家は出来上がりに文句が言えないのである
鳥海青児は洋画家であったが自分で表具までした人である
洋画家は案外額にこだわる人が多いので須田剋太や中川一政なども作品と額や表具の色使いにうるさかった
写真は絵画の額に風の一字を入れた小品だが
部屋に飾るにはこの方が面白くおしゃれな気がする
書道専門の表具屋はステンレスの額が大好きでありよく用いるが
少し冷たい感じがして私は好まない
日本橋の三越で取り合わせの妙のお話をしたことが何度かあるが
取り合わせは室礼にはとても大切で
何と何が合うかなどいつも色使いなど考えることが大切である
古い李朝の家具に備前の徳利に活けた椿の花一輪などは姿の良いものである
どくだみの花が盛りだが弥生の壺の陶片や中国の漢の瓦当などにとても合うもので
どくだみの花の白さが渋い色に際立つものである
梅雨の紫陽花を見るたびにまた自分勝手の取り合わせの遊びを楽しんでいる今日である