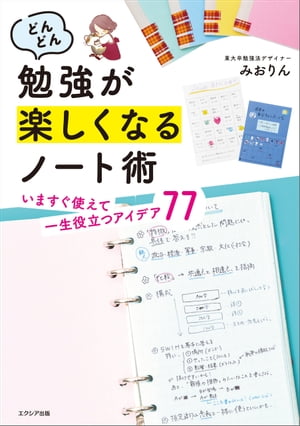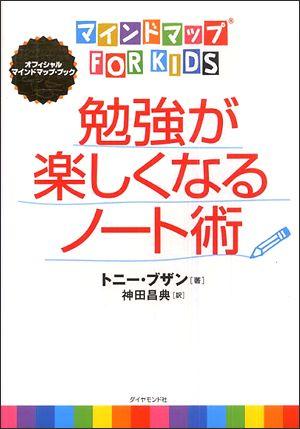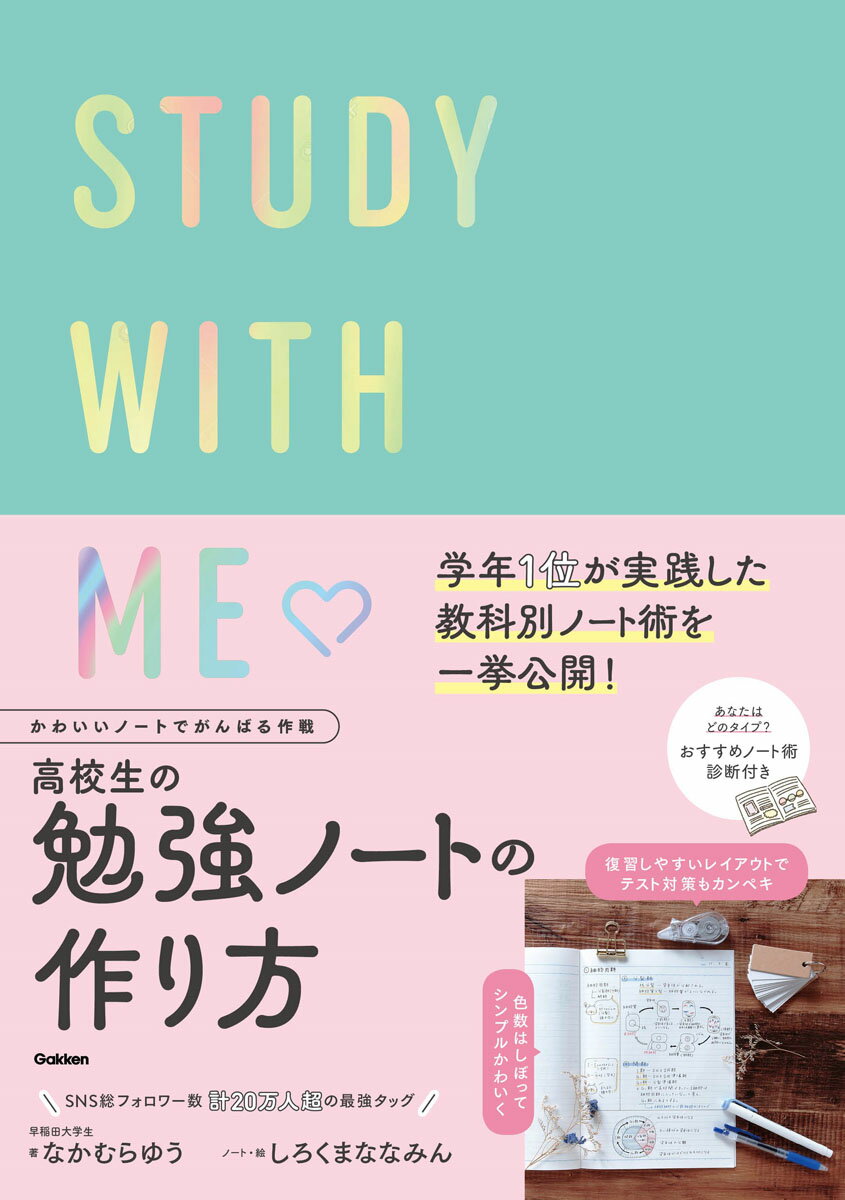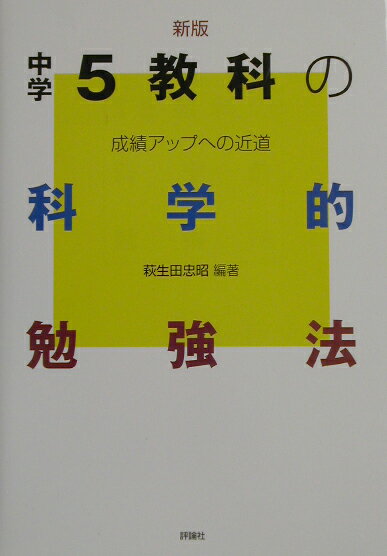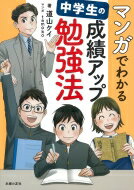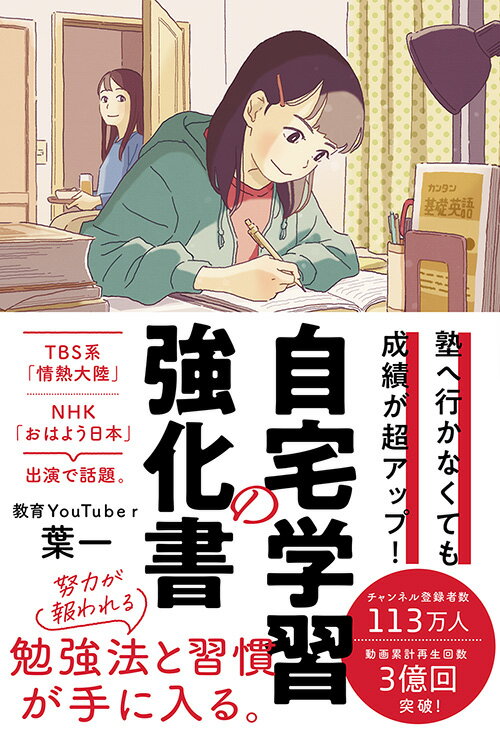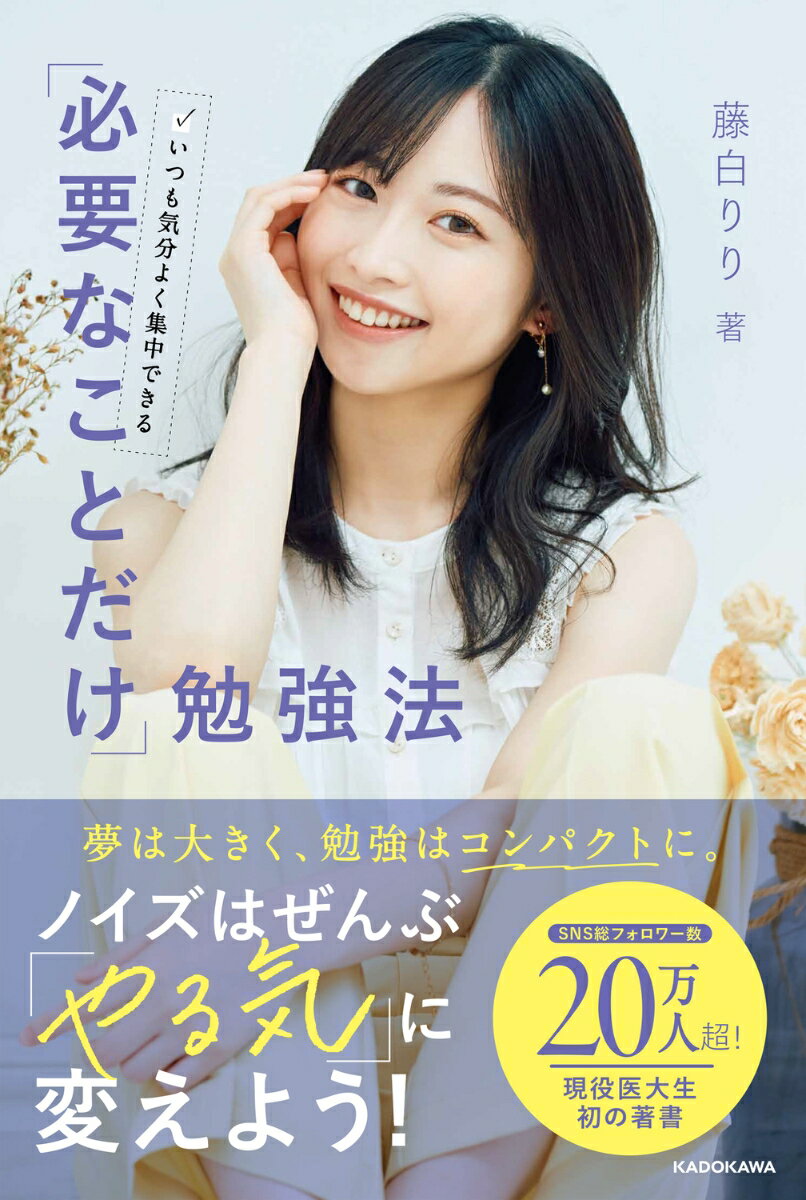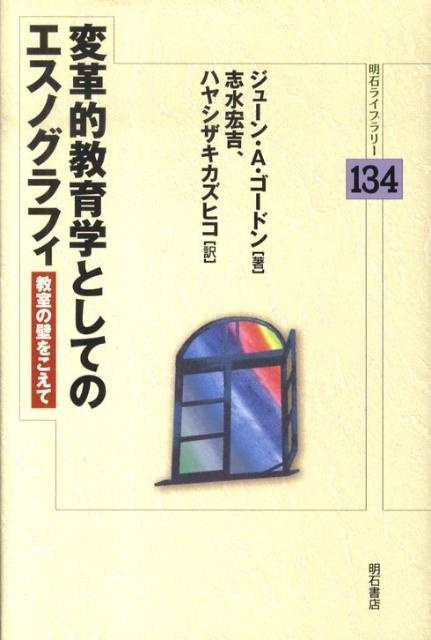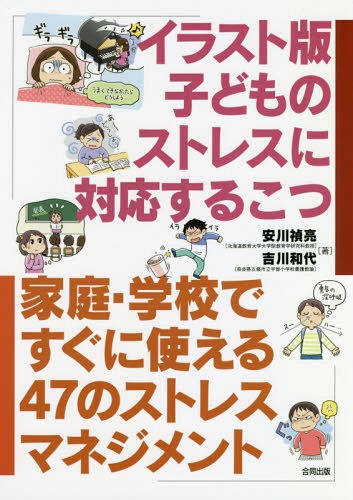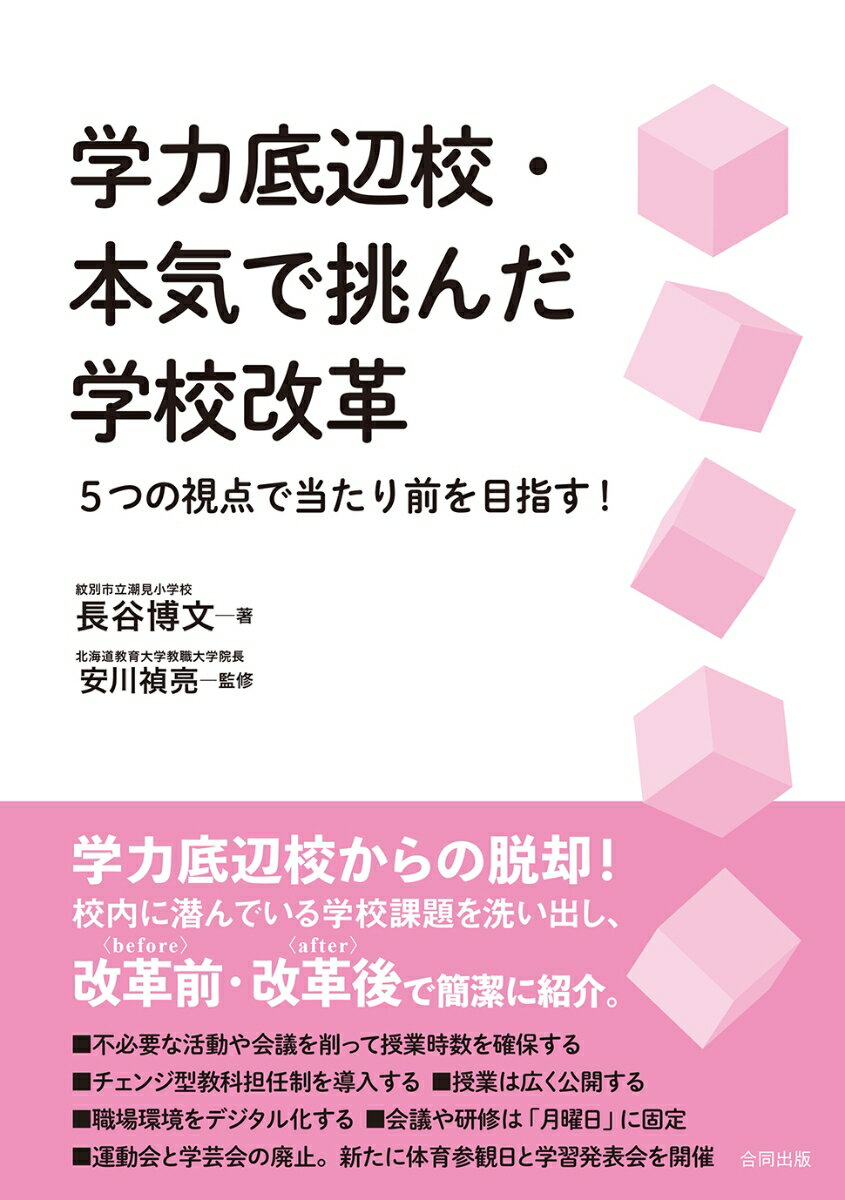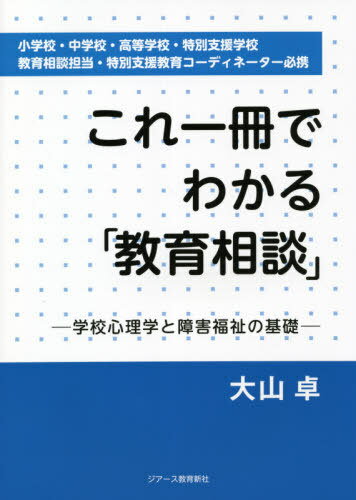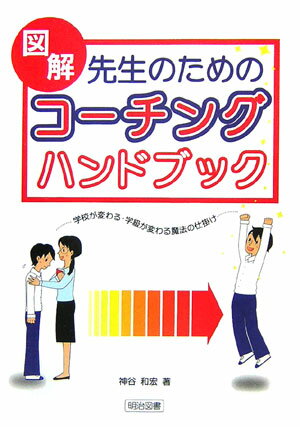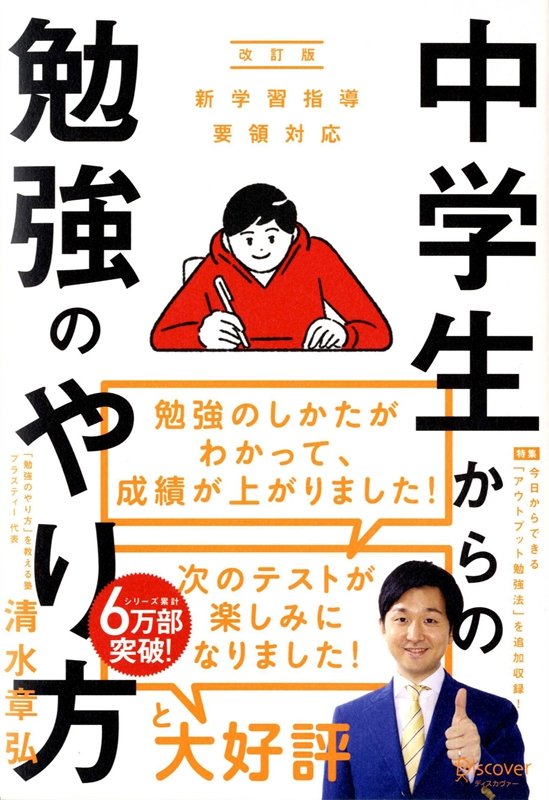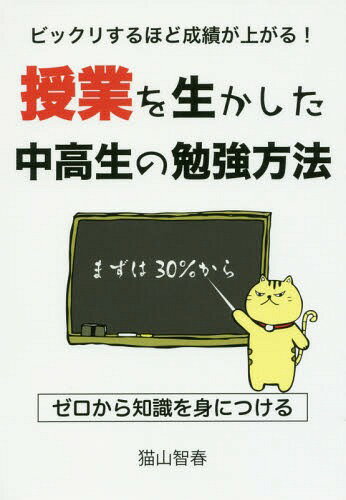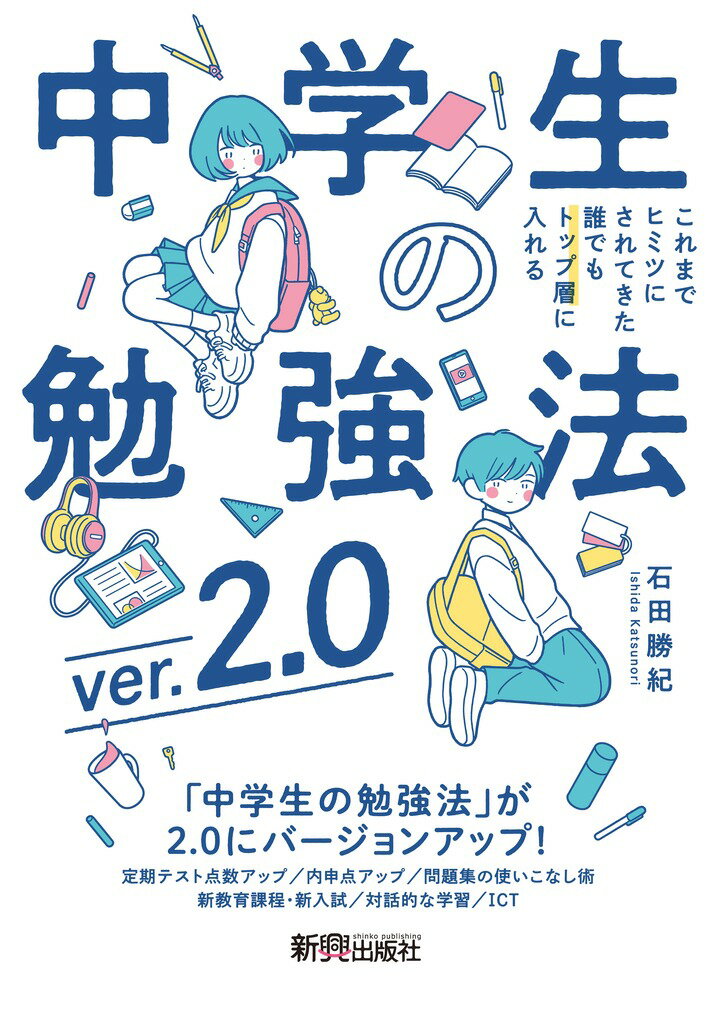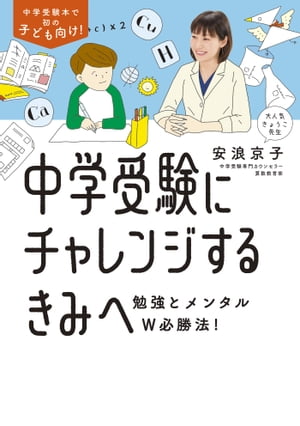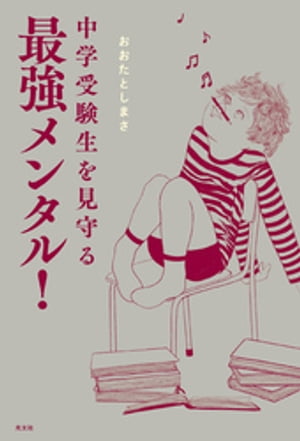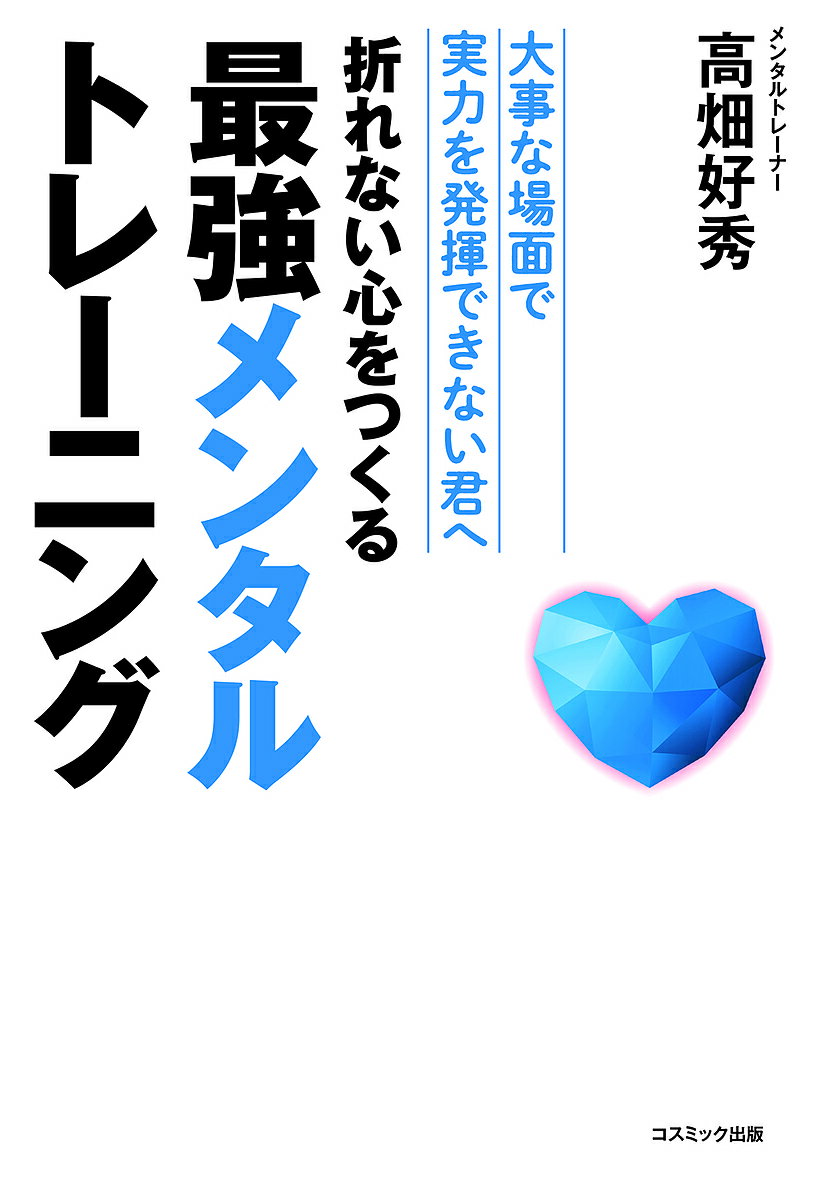「成績表に2があるので無くしたいのですが…」という問合せが時々あります!
ま、経験上で述べると、これは凄く簡単なことなのです。
(1⇒2は、もっと簡単なのですが)
が・・・、一般的にはすぐに上げられることなのですが、勉強な苦手な子供にとっては、結構大変かもしれません。
というのも、勉強の理解度がどこまでできているのか、それによって授業の取り組みが変わって来るからです。
・定期考査の点数にもよりますが、30~40点位が取れる事。(平均点にもよりますが)
・授業中、寝ないでしっかり起きて先生の話を聞けるかどうか。
・提出物は出しているか、小テストは、30%くらい取れるか。

この辺りができれば、これで3になるかな…と思います。(笑)
勿論、学校のレベル、個人の状況にもよりますが。。。
後は、覚えられるかどうかですね。苦笑
やっている授業内容(公式とか単語とか)が覚えられるかなのですが、苦手な子は、このやり方が判らない感じなので、実際に覚えることを一緒にやってみます。
・5個でも10個でも良いので、何か単語とか漢字とか年号などを、ちょっとした解説をしたあとで短い時間で覚えてみます。
・実際に書いてみて書けなかった、覚えられなかった、間違えた奴を中心に再度覚えます。
・また全てを書いてみます。
これを2~3回繰り返すと、短い時間で覚えることができます。
また、本当に勉強が苦手な子供は、授業内容が判らないため(理解度が凄く遅れている場合)、どうしても寝てしまうことになります。汗
当然、小テストでは点数が取れませんし、提出物も、何を書いて出せば良いかが判らず、結果未提出ということになってしまうことになります。
定期テストはその結果になりますので、なかなか期待ができない状態になります。
ここが改善できれば、すぐに2から3に上げる事ができます。
平常点が低いメンバーは、まずこれを改善して、
「定期試験の点数を、ちょっと上げれば3になる」という安心感と自信をつけさせれば、自分で前向きに取り組めるようになり成績を上げることができますので、是非、チャレンジして下さい。
------------------------