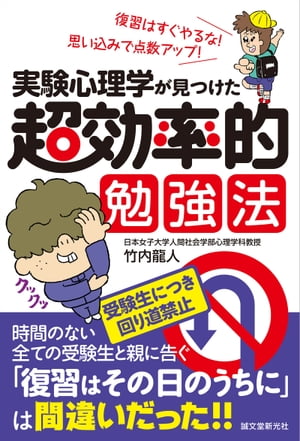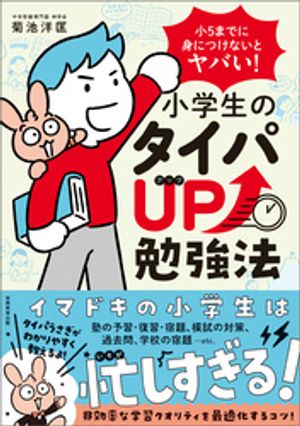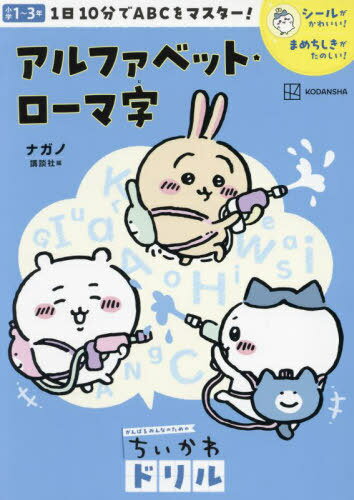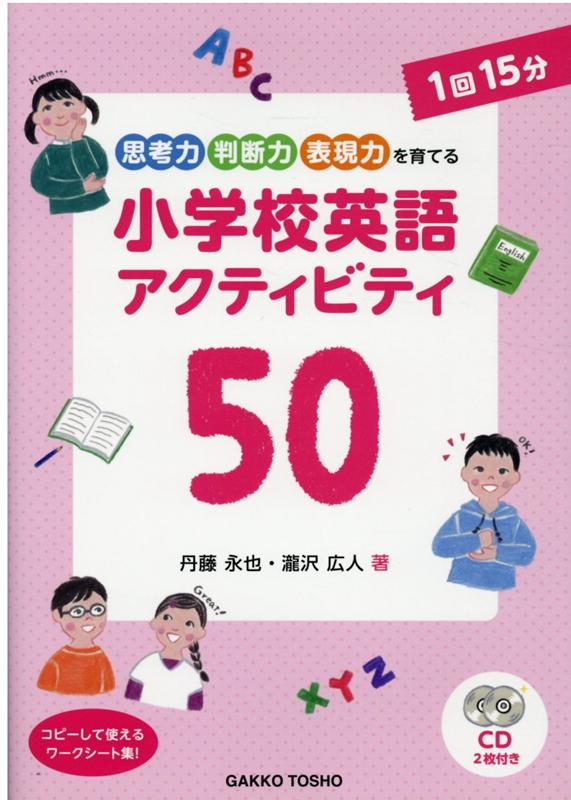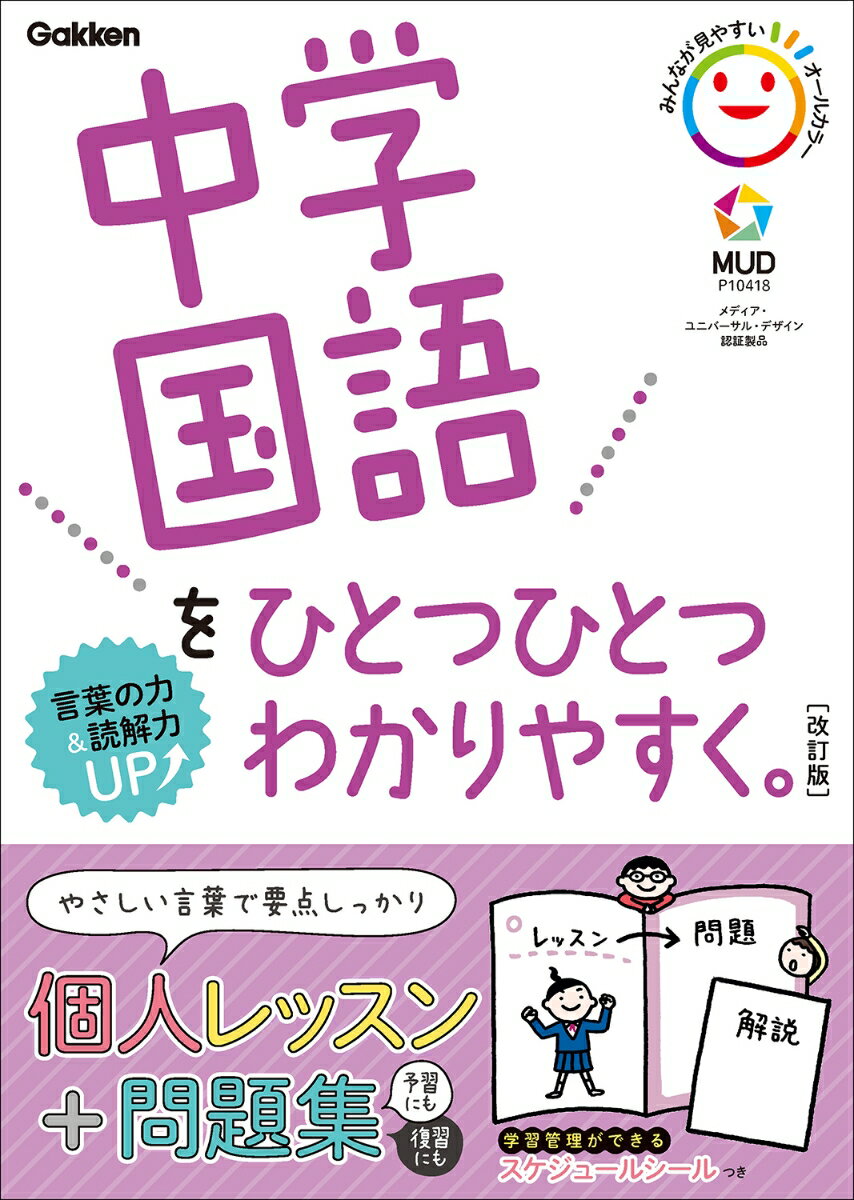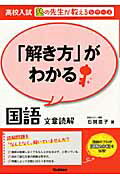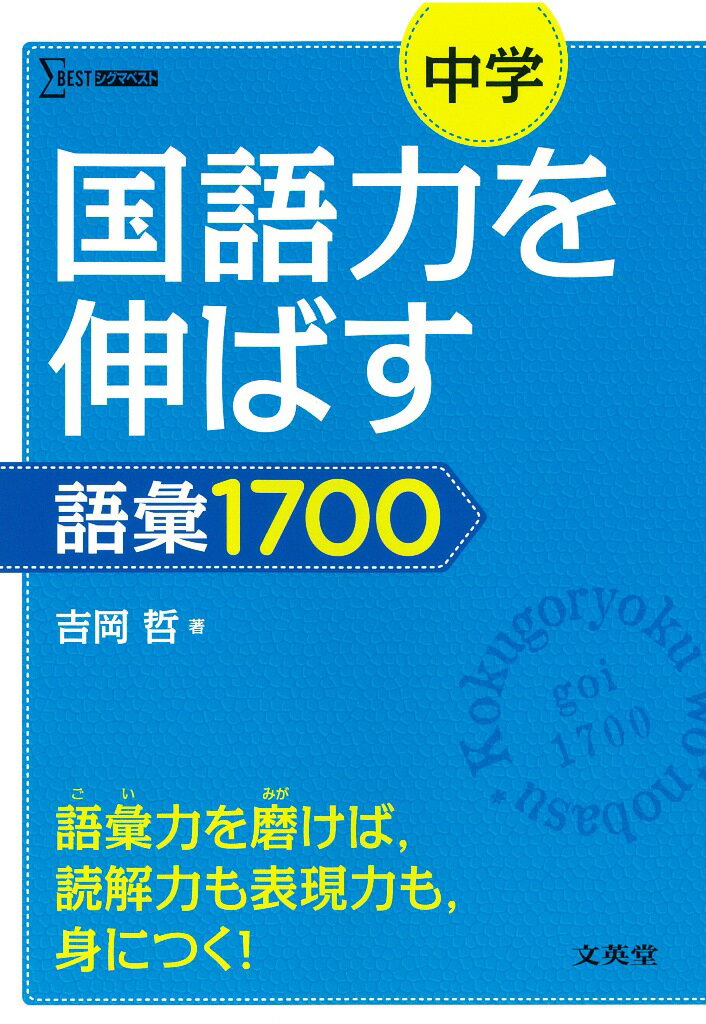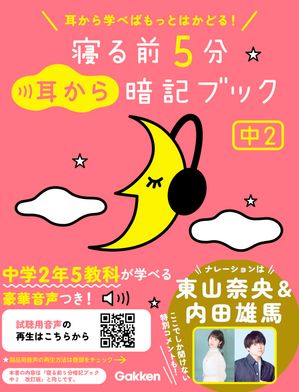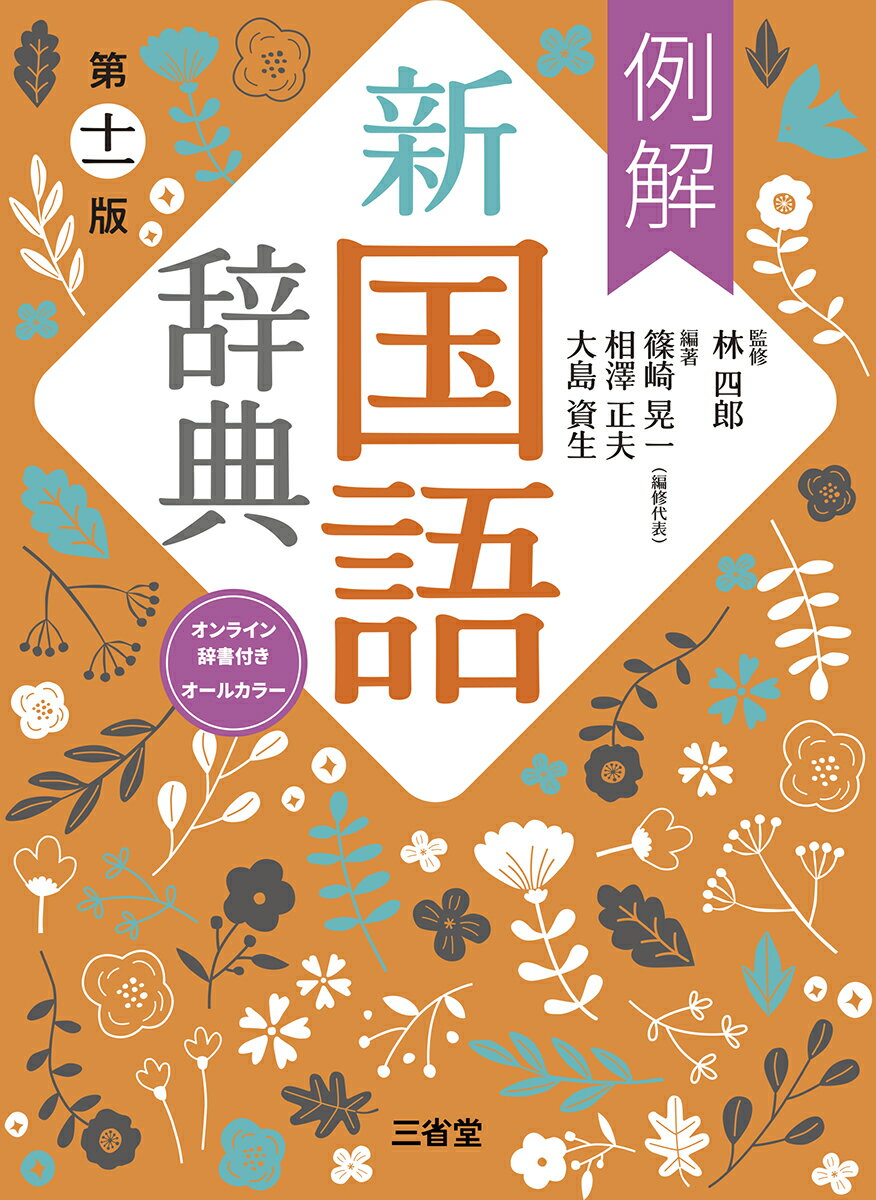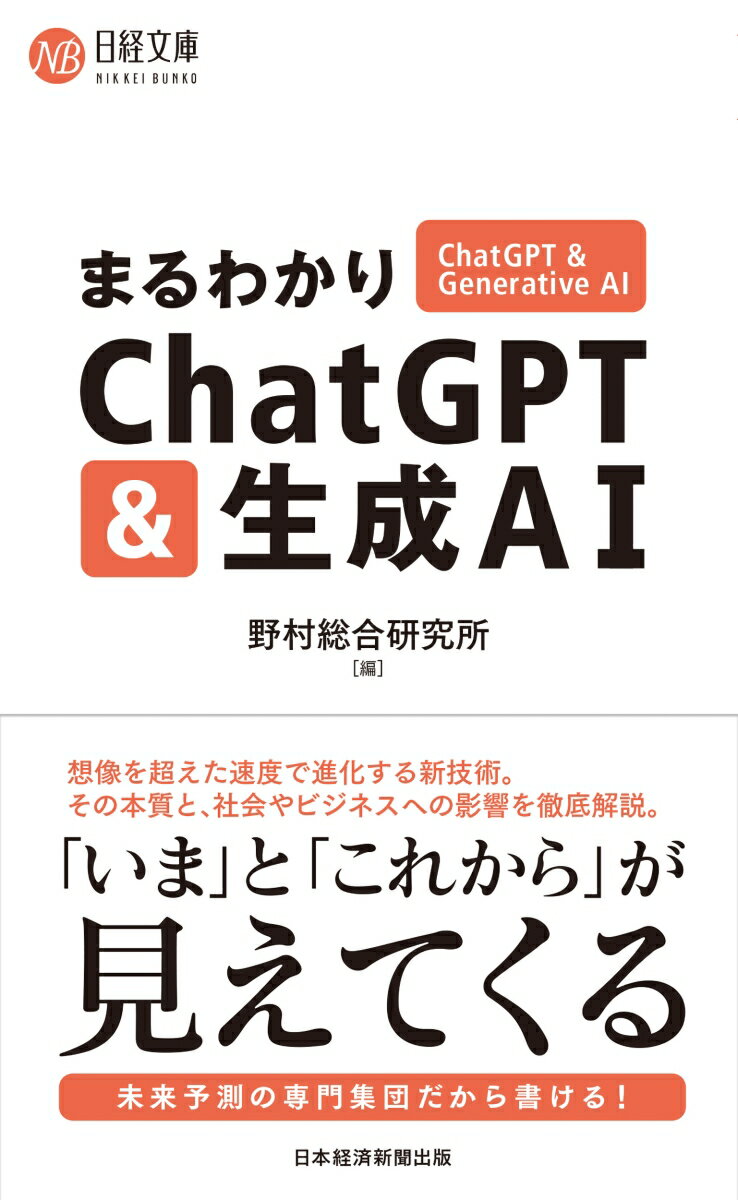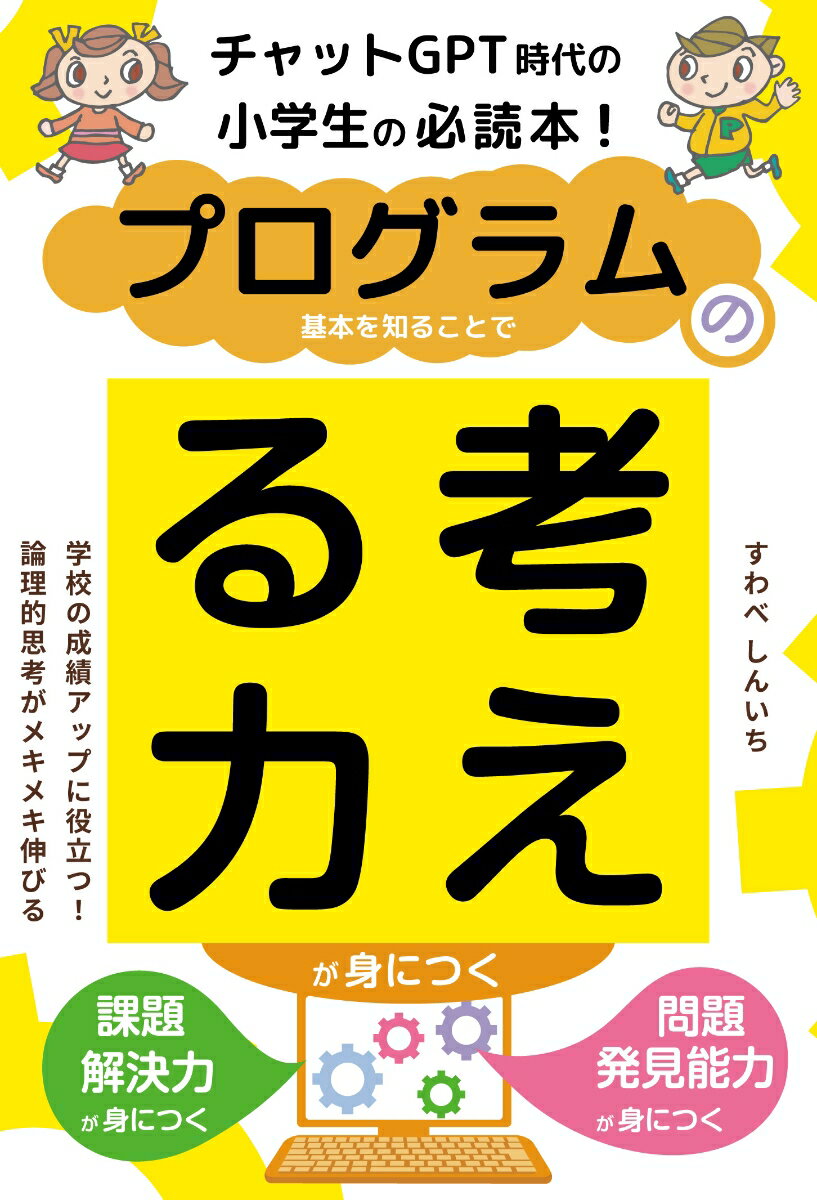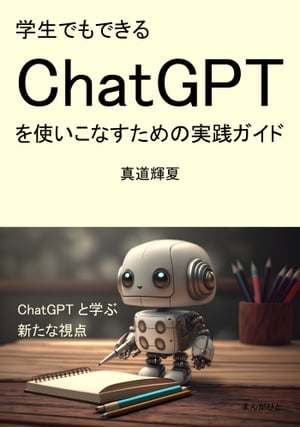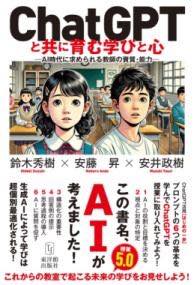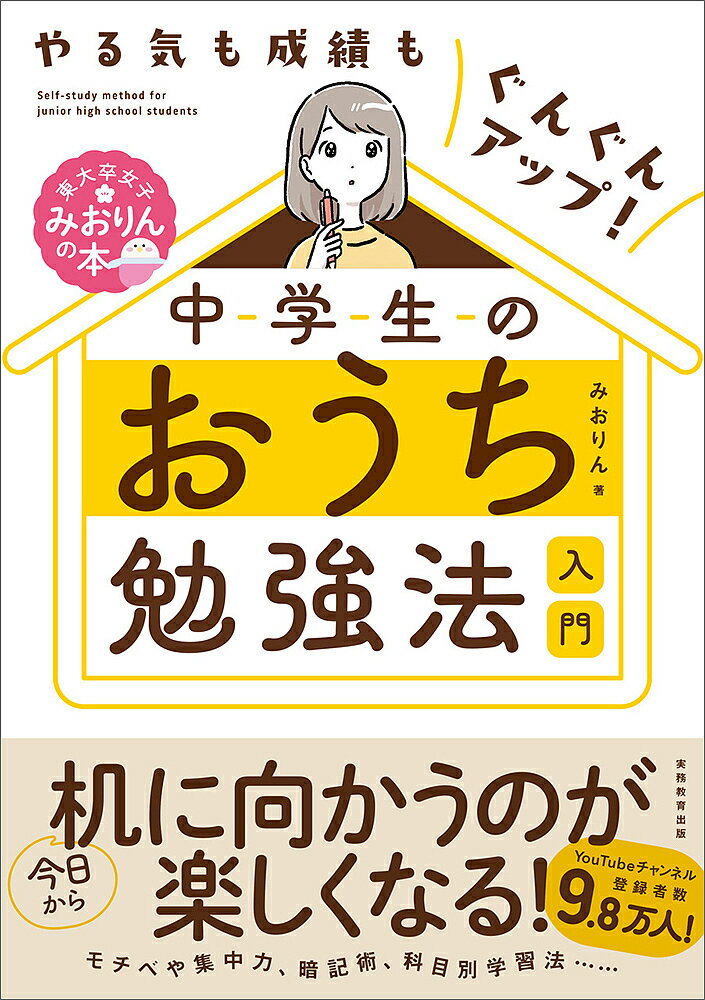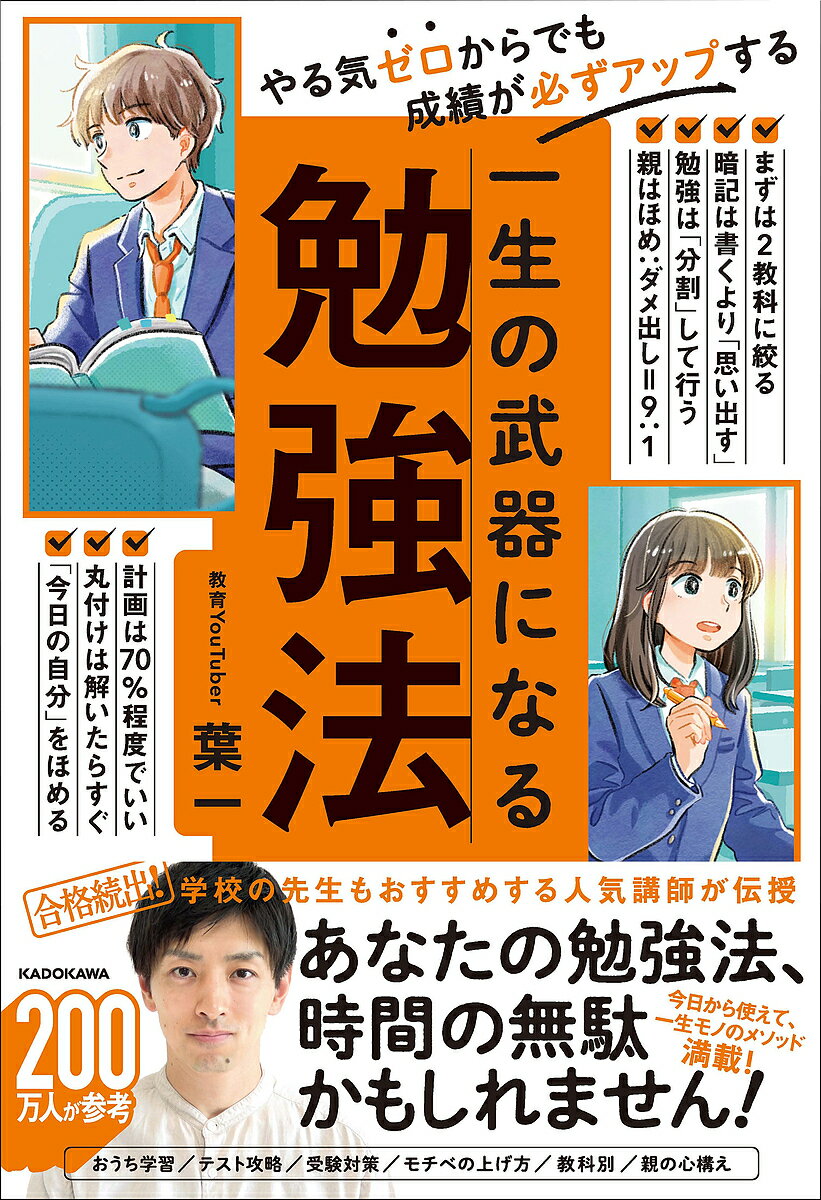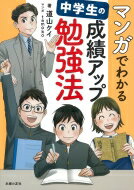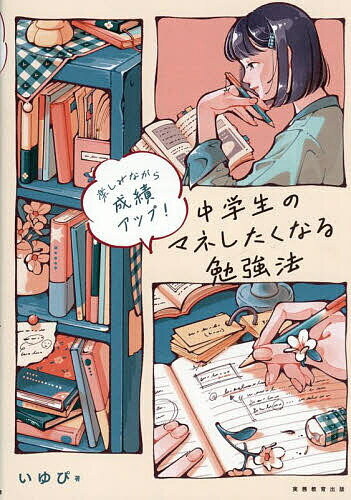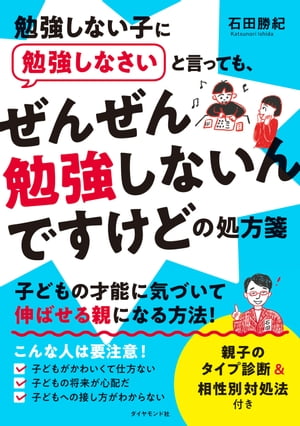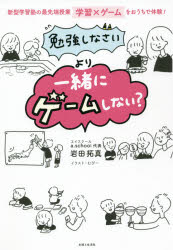子供達に教えていると、このような反応の言葉が出てくる時あります。
本人が「納得した瞬間」です!(笑)
他にも、
・「あ~~~」(納得の頷き)
・「そうか」
というのもありますが、やはり
・「なるほど~」というのが圧倒的に多いですね。
解説をしている時に、本人が「理解しているな」というのは、目を見ていれば判ります。(笑)
『うんうん、、、ここまではわかったぞ』という顔をしています。

なので、一通り説明が終わって、顔を見た時、納得の表情をしている時は、完全に理解をした時で、若干、反応が遅かったり、リアクションが少ない時は、多分理解をしていないでしょうね。(笑)
で、「判った??」と聞くと、大概「判ったと答えます」。
が、、「じゃ、説明してご覧」というとほぼ出来ないです。
子供達に言うのは、
「忘れても、判らなくても良い。
どこまでが判って、どこからが判らなくなったか教えて。
99%判っていても、残り1%が判らないというときも「判らない」って言って!」
ということで、また最初から解説をして、判らないところが来たら教えてと言ってやると、
「あ、、この部分が・・・」などと言ってきますので、そこを中心に色々話をします。
少しずつ進めて、
「ここまでは判る?」と細かく聞いていき、最後まで行くと、「判った」となります。
この「理解できた」という状況を、覚えて貰います。
※これが判ったということか!と。(笑)
----------------------------