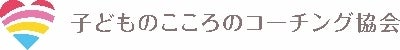こんにちは、さとさんです。
保育園くらいまでのころは、何を考えているのか?わかったりするよね。
でも、小学生になるとかわってくる。
そうなってくると、親としての悩みが出てくる。
子どもが何を考えているのか…わからない。
親は不安になる
でもね、
とても普通なことです。
子どもが成長しているという証拠でもある。
先日、「不登校の先にあるもの」ガイドのみょんちゃんのオンライン「子育てハッピーセミナー」を受講しました。
その中でね。
甘えと反抗を行ったり来たりして、子どもは成長するってあった。
このサイクルを子どものペースで循環することが大切なんだって。
こうやって、成長の一番土台になる「自己肯定感」を育んでいる。
本当にそうだなー。
この反抗というところに、親はつまずきを感じてしまう。
反抗してしまった子どもは、もう戻ってこなくなるような不安になるのかなー。
それとも、親なのに子どものことがわからないのは、親としてダメ認定されると思ってんのかなー。
いろんな気持ちが渦巻いて、不安になってるんだよね。
不登校の原因はわからないもの
不登校の当事者である子どもが、自分で原因がわからないということも、実はよくあること。
実際、17歳息子も学校に行けない時期に、何が原因だったかはいまいちわかってなかったみたいだ。
2年たって振り返れば、これが原因だったかなーってことは話す。けど、よくわからないけど、体が拒否反応を示していて、学校に行けないんだ。
「明日は学校に行く」と言いながら、登校1時間前くらいになって、体調が悪くなって、結局行けない。なんてことは、本当によくあった。
つい親や学校は、その原因を突き止めようとする。そうすれば、学校に行けるはず…
そういう意図は、子どもからするとこう感じるんだよ。
「認めてもらえないんだな…」
それは、子どもの今を受け止めて、不安な気持ちや苦しい気持ちそのものをわかってあげる。そんな、あなたでも大切な存在なんだってことを、スキンシップや言葉かけをする。
私がこのブログでよく書いている言葉に変えると…
子どもの話を聞く
それに尽きる。
聞き出すじゃないよ。