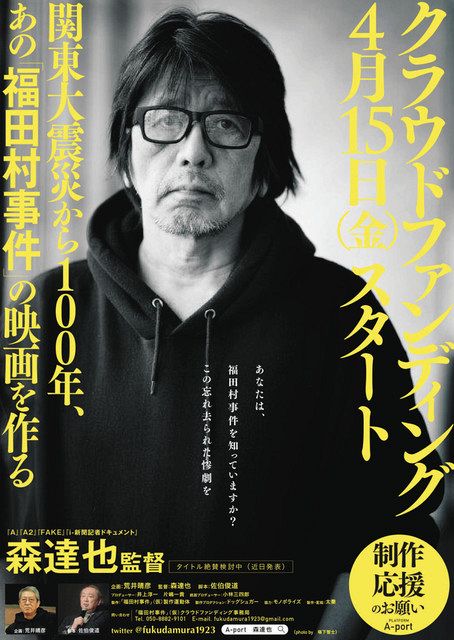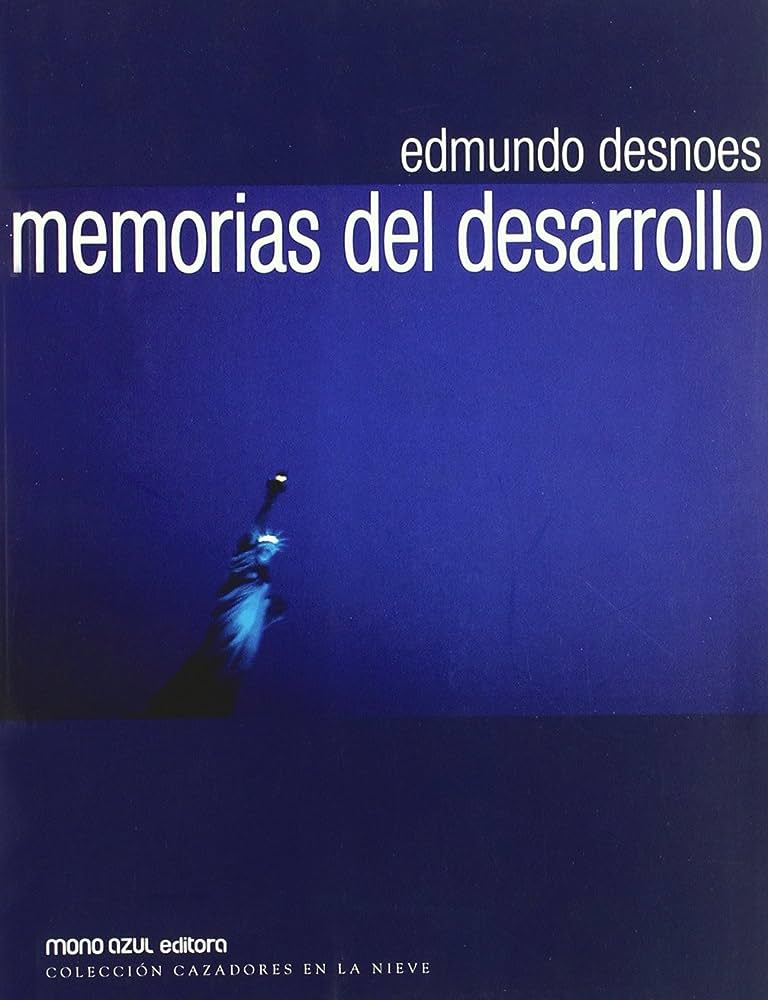『グァンタナメラ』(1995年製作)の見どころは、1990年代前半の経済的非常時下のキューバの様相を、ロードムービーにして、ユーモアや機知、それに風刺を交えて描いているところ。
ただ、キューバの事情に通じていないと、その面白さが分からないので、以下に要点を挙げて解説してみました。
☆参考にした論評:Anatomía del régimen de Castro en "Guantanamera" - Código Cine | Código Cine (codigocine.com) ほか
★「グァンタナメラ」という歌について
1935年、ソンの歌手ホセイート・フェルナンデス(1908-1979)が、ラジオでこの歌を披露し、やがて彼のバンドを代表する曲となる。1943年、ラジオ番組「El suceso del día(その日の出来事)」で、事件を歌詞(10行詩=デシマ)にして「グァンタナメラ、グァヒラ、グアンタナメラ🎶」のリフレーン入りで彼が歌うと、たちまち大人気を博す。1957年の番組終了後も、何か事件が起きたり、誰かが亡くなると、人々は「グァンタナメラが歌われた」と言った。
ちなみに、ホセイート・フェルナンデスいわく「『グァンタナメラ』はプロテストソングだ。民衆の悲しみや不幸を拾いあげ、豊かさや正義を求めているからだ」。
本作では「グァンタナメラ」の曲に乗せて場面や心情が歌われ、ストーリーが展開していく。
尚、映画のオープニングで、タイトルソングを録音する声が流れるが、「これは作り話じゃないよ。本当にあった事だ」と言う声はアレア監督で、「バカ言うな、ハッハッハ」と答えているのはタビオ監督の声だとか。
★90年代初めの経済的非常時(時代背景)について
*下線部分は映画でも描かれている。
東欧社会主義圏崩壊(1989年)とソ連崩壊(1991年)を受け、キューバ経済は1990年から急激に下降線をたどり、どん底の93年には34.8%のマイナス成長を記録。エネルギー節約のため1日最高20時間にも及ぶ停電、牛・馬車による輸送・耕作、交通手段としての自転車導入が広く行われた。
93年には、それまで禁じられていたドルの所有が認められたうえ、ドル獲得を狙って在外キューバ人家族との相互訪問の許可や、個人事業職種の拡大などの政策がとられた。
☆参照:伊高浩昭著「キューバ変貌」ほか
本作では、ガソリン不足の打開策として〈遺体の通る各州が霊柩車とガソリンを提供する〉というリレー方式(アドルフォのアイディア)でグァンタナモからハバナのコロン墓地まで送り届ける。
道中のシーンでは、ヒッチハイクする人の群れ、闇物資の売買(ドルでないと買えない)、パラダール(ドル払いのみ)など、90年代を象徴する事象が描かれている。
また、葬儀社の運転手のトニーは、道中で闇物資を買い、転売しているし、マリアーノも大学卒のエンジニアでありながら、トラック運転手として稼いでいる。どちらも副業の方が儲かっている。
よって、ドルを持たないアドルフォは、道中で食事に不自由する。
葬儀場では、会葬者のための飲食サービス(クーポンが必要)目当てに来る人もおり、トラブルが起きる。
★規制(→発展への妨げ)への反発と自由思想
バヤモのシーンで、観光ガイドは次のように語る。「16世紀から18世紀のバヤモは、キューバで最も密輸が盛んな所だった。スペイン本国による規制や独占の裏をかいて何でもやった。違法であっても、誰もがイギリス人やフランス人、オランダ人と商売していたし、役人や軍人、聖職者も取り引きしていた。異端とされたプロテスタントとの付き合いは、経済面のみならず、文化や政治にも影響を与えた。こうして異端審問所が禁じた書物や自由主義的で進歩的な思想が入ってきた。バヤモが、キューバの発展を阻止する植民地支配に対して、最初に武器をもって立ち上がったのも偶然ではない」*この史実は、アレア監督の『悪魔と戦うキューバ人』を彷彿させる。
★プロパガンダ(教条主義)
*本作に登場するスローガン
①文化は不滅だ(LA CULTURA ES IMMORTAL) @祝賀会場
このスローガン(フィクション?)は、1973年のフィデル・カストロの演説で発せられた「人間は死ぬが、党は不滅だ(Los hombres mueren, el Partido es inmortal)」を想起させる。
②社会主義か死か (SOCIALISMO O MUERTE)@壁 *そこにイクの姿が見える
③貴方に忠誠を(TE SERÉ FIEL)@橋
④今こそ我々の夢を護るときだ(ES EL MOMENTO DE PRESERVAR NUESTROS SUEÑOS)@建物
*団結の強調(個の犠牲)〈我々の〉は独裁者が多用するフレーズ。
★〈農産物の収穫が好調〉と伝えるラジオ放送
★マチスモと権威主義:アドルフォはその象徴
アドルフォという名前は、独裁者ヒットラーの暗示か?
人々から崇拝されることを望む
国民的歌手の遺体を迅速にハバナに運び、名誉回復(出世)を企む
左遷された理由は、娘のマイアミ移住のせいか?→妻を責める
妻の髪型・服装、すべて自分の思い通りにしようとする。
実務の遂行を優先し、他者への配慮や遺体への敬意を欠いている
彼の考えたリレー方式は、問題の根本的解決にはなっていない
★自由思想(反教条主義):ヒナとマリアーノが象徴
ヒナは大学で経済を教えていたが、彼女の〈自由に考えさせる授業〉や批評精神が問題になり辞職。夫に気を使いながら主婦業に専念しているが、マリアーノと再会し、人生をやり直す決意をする。
印象的なセリフ:「考えないのはもうまっぴら!(Me cansé de no pensar!)」
マリアーノは大卒のエンジニアだが、生活のためトラックの運転手をしている。
行く先々に愛人がいるが、ヒナに再会し、かつて諦めた恋を取り戻す。
★官僚主義終焉への願い:終焉=死(十字架)、墓地、イク(謎の少女)
本作は、アレア監督の大ヒット作で官僚主義を風刺した『ある官僚の死』(1966年)の延長線上にある。前作に込められた「役人を絞め殺したい」ほどの思いは、本作でより明確に表現されている。
★過去の浄化と再生の象徴:雨
批評精神と自由な思想を若い世代に託す。
トリビア情報
・フィデル・カストロを怒らせた⁉
1998年2月の演説でフィデル・カストロは名指しはしなかったものの「遺体の搬送を扱った映画が、この国で革命と国民の資金で製作されたにも関わらず、ある種の傾向のせいで、反革命的映画へと逸れた」と批判した。(このフィデルの演説については様々なバージョンがあり、特定できていません)
・アレア監督の娘、オードリー・グティエレスが、カフェのウエイトレス役で出演している。
(現在はアルゼンチン在住らしい)
・メインの脚本家はエリセオ・アルベルトだが、彼は1990年にメキシコに移住し、彼の地で亡くなった。
エリセオ・アルベルトの自伝を映画化したドキュメンタリー:
En un rincón del alma (仮:魂の片隅で)/2016年/ドキュメンタリー | MARYSOL のキューバ映画修行 (ameblo.jp)