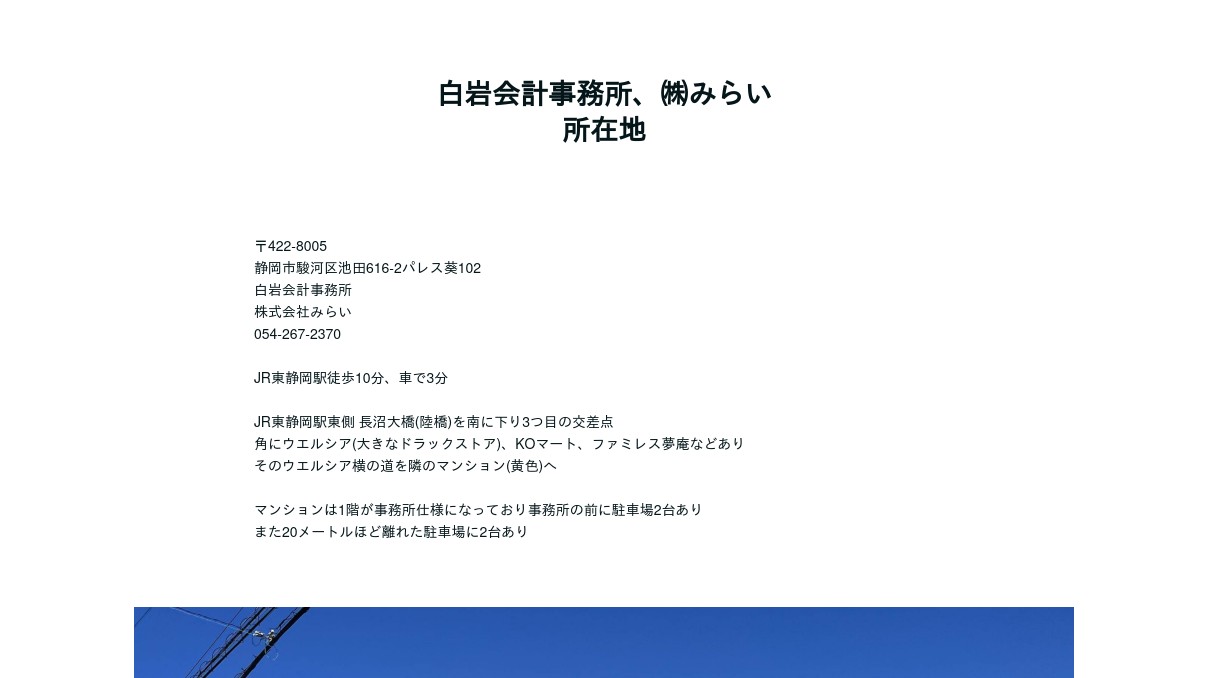こんにちは。
公認会計士・税理士、そして「高齢親の囲い込み 解放アドバイザー」の白岩俊正です。
このブログでは、YouTubeでも発信している「高齢親の囲い込み問題」について、より詳しく、文章で深掘りしています。
今回のテーマは、「兄弟姉妹のトラブルによって、親が一人の子に囲い込まれてしまう」というケース。
これは、財産や介護だけでなく、「家族の関係性」そのものが崩れていく深刻な問題です。
◆「親に会わせない兄弟」に直面して
- 実家の住所がわからない
- 電話しても無視される
- 「親は会いたがっていない」と言われる
- 会いに行ったら警察を呼ばれた
このような経験をされた方が、実際に私のもとに数多く相談に来られます。
◆なぜ兄弟で「親の取り合い」になるのか?
きょうだい間で親の介護や財産をめぐって争いが起きるのは、珍しいことではありません。
しかし「囲い込み」にまで発展する背景には、こんな心理があります。
- 「自分こそが親を一番大事にしてきた」という自負
- 他の兄弟に親の財産を渡したくないという独占欲
- 幼少期から続くコンプレックスや優越感・劣等感
- 認知症や体調不良の親を“味方”につけたという優位感
親を守っているように見えて、実は“自分の思い通りにできる存在”としてコントロールしていることも少なくありません。
◆囲い込みで傷つくのは、親と兄弟全員
囲い込まれた親は、自分の意志とは裏腹に孤立し、他のきょうだいたちは「親に会えない苦しみ」に置き去りにされます。
家族の絆が分断されることで、
・親の死後、取り返しのつかない後悔
・兄弟姉妹間の断絶
・相続での激しい争い
につながることも少なくありません。
◆専門家として伝えたいこと
私は、会計や相続のプロとしてだけでなく、実際の家族関係のもつれ、介護と法律のはざまにある苦しみに向き合ってきました。
その中で実感するのは、「囲い込みの問題は、感情と制度の両面から解決しないと前に進めない」ということです。
次回以降のブログでは、
・囲い込みの兆候を見抜くチェックポイント
・話し合いでは通じないときの法的対応
など、実践的な内容もお伝えしていきます。
大切なのは、「親を守る」ことと「家族をつなぐ」ことを、どちらも諦めないこと。
一人で悩まず、専門家や第三者の知恵と手を借りながら進んでいきましょう。
ご相談・お問い合わせは下記まで
→(連絡先)