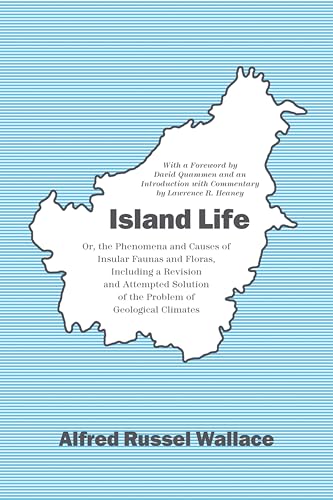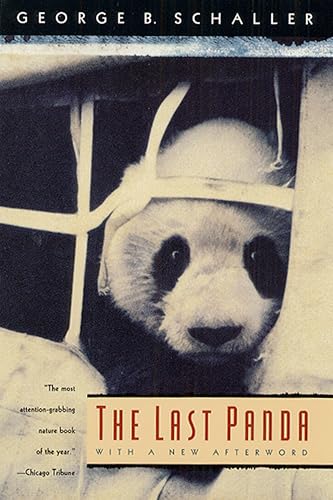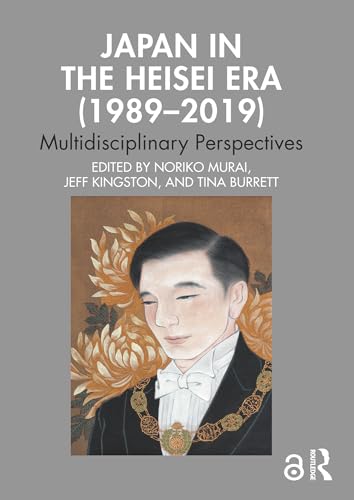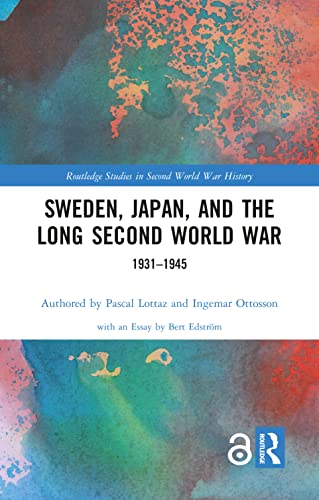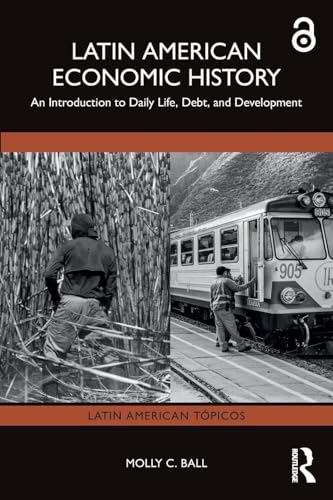【警告】記事中の作品のネタばれにご注意ください!
期日前投票2026
2日だか3日だかにやっとのことで投票案内用紙が届き、候補者一覧が載った選挙公報が届いたのは昨日の5日(木)だった。
絶賛ボケ進行中のお子ちゃまジジイとしては、忘れぬうちにということで、今日6日の午後にその期日前投票を済ませてきた。 (^^;
従来の選挙ではワン・フロアの会場だったものが、今回は2フロアに倍増していたのは、選挙期間の短さからの当然の帰結か? 確かにけっこうな人出ではあった。
私の場合、比例は迷うことなく某小政党に一票を投じ、最高裁判所判事の国民審査では初めて1名に✕をつけた。小選挙区については正直なところ迷っていたのだけれど、最終的には、前回とは異なる非自民政党を選択した。
今回の選挙はいろいろな意味で興味津々で、開票速報や事後の政局分析などのお供に、コーラやポップコーンの買い置きを進めているところだ! (^^;
はやく来い来い 開票日🎶
The University of Chicago Press ①:大型書店洋書ご担当の皆さま!
ご安心ください。Routledge 社の話はもうしません! (^^;
でも、国内の大型書店洋書ご担当の皆さま方のために(?)この洋書キンドル爆安本の話題は続きます!
【注意:以下のキンドル本関連情報は次の瞬間には新たなものに更新されているかもしれません!】
※
お堅そうな出版社といえば、お子ちゃまジジイの私が思い浮かべるのは大学出版局ぐらいか。以前、18円という価格が表示されたサイエンス本があったことを思い出して、その版元 The University of Chicago Press のキンドル本をちょっと調べてみた。
たまたま、チャールズ・ダーウィンや彼と時を同じくして、あるいは彼に先んじて進化論のアイデアにたどり着いたとされるアルフレッド・ラッセル・ウォレスに興味があったこともあり、最初に目についた古生物学関連本を出発点としてさらっていくと、18円、20円、110円といった爆安本が次々と現れてきた!
なお、シカゴ大学出版局とも爆安本とも関係ないけれど、ウォレスに興味のある方は、以下の本のこともお忘れなく!
※
さて、ウォレスも進化論も古生物学も興味はない。でも、生きものにはまあ親しみを感じるかなという方なら、ヘビとかパンダなどはいかがでしょうか? (^^;
ブログタイトルに “The University of Chicago Press ①” とあるのを見て悪い予感がした方、あなたは素晴らしい予知能力をお持ちです! (^0^)
回転寿司のスシローで……
27日(火)の昼どき。渋谷のかつやを覗くと、当然ながら店内は満席、券売機には長蛇の列。移動中のランチなので早速方針を変更して私はスシローへ向かった。
インバウンド観光客の流れらしく、ここもまた順番待ちのスペースは外国人でいっぱいだった。でも、ひとり客には意外に早く席が空くことが多いので、登録を済ませて少し待つと、2コール目のアナウンスで呼び出された!
私の席はカウンターのいちばん左端だった。しばらくして右隣の若い女性客が去り、中年の男性客がそこに座った。メガネをかけたその男性はスーツ姿ではなく普段着だった。隠居身分ではなさそうだけれど、FIRE のおひとり様か? まあ、私よりは若そうぐらいのことしかわからなかった。
※
ふと気がつくとその男性はスシを食べながら本を読んでいた。角背のかなりがっしりした上製本でカバーを外していたが、私の側からは表紙の右側も背も見えず、題名はわからなかった。今思えば、デザイン化され一面に並べられた数字でタイトルは一目瞭然だったわけだが。
男性は時おり注文を追加したり、湯呑みに熱湯を注ぎ足したりするのだが、その都度読んだところを見開きのままカウンターの上に伏せるのを見て私は悲鳴を上げたくなった! (T0T)
ページが汚れてもいいのか!
もちろん、客が去ったあとテーブルの上は拭かれてから次の客が誘導される。でも、自分でお茶に湯を注ぎ足したときの飛沫とかが飛んだりしていないのか? 私だったら決して本を直に置いたりはしない。
男性はそんなことお構いなしに、時おり本をテーブルに伏せながら、食事と読書を続けていった。
やがて男性は食事を済ませてレジへと向かっていった。
※
当初は本を雑に扱う人もいるのだなぐらいに思っていた私だが、すぐに考えをあらためた。男性はほんとうの読書好きだったのだろう。高価な上製本のページが汚れてしまうことなど気にもせず、ひたすらページをめくり続けていたのだ。
それにひきかえ、物理的な本のコンディションばかりに目が向いていた私の情けないこと! 恥じ入るばかりであります。 <(_ _)>
その男性が読んでいた本は、村田沙耶香の『世界99』。ちなみに、下巻だった!
地元に大型書店がやって来る?
夕刻地元の書店に寄って驚いた。正面のガラス扉にポスターが貼り出され、近く店名が変更されるというのだ。それも全国に展開する大型書店の名前に!
この近辺は低層家屋が密集する住宅街で、大規模マンションが林立する余地などなく、人口の急増とは最も縁遠い地域だ。
ただ、高齢者層が厚そうな印象はあるし、近場に競合店は見あたらない。でも、名だたる老舗書店がこの1店舗をわざわざ……いやいや、この1店舗ではなく、私鉄沿線に点在するこの書店チェーン全体を引き継ぐのだろうか?
まあ、この店にはコミックはもちろんのこと、「文藝春秋」や「オール讀物」などが毎月平積みされるし、主要出版社の文庫・新書も置かれている。もう大幅な伸びは期待できないかもしれないけれど、なんらかの成算あっての動きなのだろう。
レジにいるのはバイトっぽい男女ふたりだけで、細かな事情を訊いてもしょうがないだろう。NHKラジオ講座のテキストを買った私はとりあえず
今いちばん気になる点を質問した。
「変更後の書店のポイントカードも使えるようになるんですか?」
その点はまだ不明なのだという。(^^;
現在その書店は、近くの私鉄系スーパーのポイントカードを相互共有している。大型書店のポイントカードとの調整はやはり厄介なことだろう。
ドラマ「もしがく」のモデル “しぶや百軒店” をチラと覗く
少しさかのぼるのだけれど、16日の金曜日に、フジテレビ制作の2025年秋ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」のモデルとなったしぶや百軒店(ひゃっけんだな)横丁をちょっと覗いてきた。
横丁の入り口付近からも、道頓堀劇場のネオンサインはよく目立っている。
ドラマのWS劇場のモデルとされるここの入り口の上には、Wonderful Strip ではなく、STRIP LIVE THEATER とある。
その先に見えてくるのが名曲喫茶ライオン。
今年創業100年の歴史を誇る喫茶店だ。
入店すると、その月の演目が記されたプログラムを手渡される。
営業時間は午後1時から午後8時まで。なお、店内は撮影禁止だ。
灯りと “営業中” の札がなければ、ちょっと入りにくいと感じるのは、私がお子ちゃまだからか。(^^; 店内の様子については別途あらためて取り上げてみたい。
その先を進んだドン突き右手に千代田稲荷神社がある。
ここは渋谷のはず。なぜに千代田? 以下の「千代田稲荷神社由緒」を読もう! 「江戸名所図絵」にも載っていたのか。
境内はドラマに描かれた神社よりずっと小ぢんまりとした雰囲気である。
浜辺美波に激似の巫女さんはどこにいらっしゃるんだろうか? (^^;
お隣にはこんな建物が……。
この界隈を仕切るカラスの親分か?
横丁を出て左方向に坂を下っていけば、あのスクランブル交差点だ。
セフェム系?
この先も洋書キンドル本の話が続きそうなので、ここでちょっと気分転換。(^^)
※
私が高校生の頃だった。
左前歯の歯茎のところに膿が溜まってしまった。「歯根嚢胞」というものらしい。私は、歯科医院で外科的な手術を受けた。乱暴に言うなら、歯茎の横に穴を空けて問題の部分を取り除いたのだ。
担当の先生は、切除して小さなガラス瓶に収めた嚢胞を眺めながらこう言った。「こんなに大きなものはなかなかないから見本としてもらっておくね」 (^^;
しばらくはかなり腫れるという話で、結果そのとおりの腫れ具合になったわけだが、私の場合、それに加えて両ひざの裏側に湿疹が出た。
その旨を先生に報告すると、「アレルギーの有無を問われたときのために、“セフェム系のブリセフ” という薬名を覚えておくように!」と告げられた。
※
以来、アレルギーの既往を訊かれるたびに、バカの一つ覚えよろしく、“セフェム系のブリセフの薬で湿疹が出たことがあります” と繰り返してきた。さすがにブリセフ(Bricef?)という薬はもう使われていないらしいが、セフェム(Cephem?)系は依然として、この申告儀式に重要な意味を持っている。
現に、地元の医院だけでなく、大学病院で処方された薬が(お薬手帳の該当欄を確認した)薬局段階で却下され、非セフェム系のものに変更されたこともある! 「アレルギーといっても、大昔にちょっと湿疹が出ただけのことですけどね」と軽口をたたくと、「2回目の反応のほうが深刻になることもあるんですよ!」と薬剤師の方にたしなめられてしまった。
その意味で、抗生物質の処方箋を出すたびにアレルギー既往の確認を怠らない現在の歯科担当の女医さんは基本に忠実ということなのだろう。
※
さて、話は変わるけれど、レアアース以外に中国への依存度が高い品目に関心のある方は、以下の PRESIDENT Online の記事(2026/01/15 17:00)をご覧になってみてください!
◆ 現役医師「レアアースよりもっと深刻」|PRESIDENT Online
“ラウトレッジ” の謎解明求む! (^^;
無料本から爆安本の話題に移る前にもうひとつ補足情報を。
【注意:以下のキンドル本関連情報は次の瞬間には新たなものに更新されているかもしれません!】
Routledge 社の Japan and Japonisme: The Self and the Other in Representations of Japanese Culture のキンドル版が現在のところ無料で公開(?)されている。
その本の編著者が、上智大学 国際教養学部国際教養学科・グローバル・スタディーズ研究科の村井則子教授である。
◆ 村井 則子 (Murai Noriko) - マイポータル - researchmap
彼女は、Japan in the Heisei Era (1989–2019): Multidisciplinary Perspectives の編集にも参画しており、これもまた Routledge 社から2022年02月21日に刊行されている。
だが、そのキンドル版のほうは8,149円で販売されているのだ。 (>_<)
同じ出版社から出ている同じ人物の電子書籍だというのに、この有料・無料の恣意的な(としか思えない)設定! いったいどういうルールがあるというのだろうか? お子ちゃまジジイの私にはさっぱり見当がつかない!
世の本格推理小説愛好家の皆さん、お願いです! どうかこの不可解きわまりない謎を解き明かしてください! <(_ _)>
“ラウトレッジ” と日本? (^^;
“お堅くお高い” と私が勝手に呼んでいる、英国の老舗出版社のひとつ、Routledge(ラウトレッジ)社の書籍のキンドル版にゼロ円=無料のものがあるといったところで、それがどーしたと言われるのがオチだろう。(^^;
ただ、その無料のキンドル本タイトルを眺めていて、オヤと気になったものがいくつかあったので、念のためここに記しておきたい。
【注意:以下のキンドル本関連情報は次の瞬間には新たなものに更新されているかもしれません!】
残念ながらアメバの Pickシステムでは、出版社の書籍目録など無料(=価格ゼロ円)の商品には未対応らしく、以下の紙書籍へのリンクを開いたあとにキンドル版の価格をご確認ください。
なお、私が確認作業を重ねることが、純粋に書籍に関心を寄せる人からのアクセス数の増加と出版社に誤解されることを避けるため、以下のアマゾンでの商品情報(価格など)は、2026年01月12日(10:35:00)に書きかけた記事のママにしてある(どうか大幅に更新されていませんように)。
どれも日本にまつわる本と思われるのだけれど、私自身が読んだわけでもなく、内容のほどはなんとも言えないので悪しからず!
ちなみに、最後の Japan and Japonisme: The Self and the Other in Representations of Japanese Culture の発売日は2025年12月31日となっている。いったい何がどうなってるんだか……(^^;
【2926年1月17日(23:06)追記:上記の発売日は書籍版のもので、キンドル版の発売日は “2025年10月24日” となっている。】
そうそう、日本がらみといえば、もう1冊大事なものを忘れていた!
Robert Matthew の Japanese Science Fiction: A View of a Changing Society である。
あっ、でも、このキンドル版は無料じゃなかった!
たいへん失礼いたしましたぁ!
<(_ _)>
“ラウトレッジ” の異変? (^^;
アマゾンの電子書籍のキンドル本については、日々さまざまな販促キャンペーンがおこなわれている。
あるときは価格を大幅に下げたり、アマゾンポイントを大盤振る舞いしたりする。それがアマゾン主導によるものか、出版社側の意向によるものかはなかなか判断しにくいところではある。そして、和洋を問わず、そうしたキャンペーンとは縁遠い出版社というものもある。
たとえば、人文科学系、社会科学系のお堅い専門書の出版で知られる、英国の Routledge 社などはその筆頭に挙げられるのではないだろうか? いや、英国出版界の事情に(も)疎いお子ちゃまジジイの根拠レスな印象を無責任に述べただけではあるのだが。
ただ、その “お堅くお高い” Routledge 社のキンドル本に意味不明な現象が見られることに最近気がついたのだ。まあ、業界内ではとっくに周知の事実なのかもしれないけれど。
【注意:以下のキンドル本関連情報は次の瞬間には新たなものに更新されているかもしれません!】
たとえば、Robotics, AI and Criminal Law: Crimes Against Robots という本がある。Routledge Contemporary Issues in Criminal Justice and Procedure シリーズの1冊らしい。
ペーパーバックが今のところ9,914円なのだけれど、リンク先のキンドル版の価格をご覧ください。
また、Latin American Economic History: An Introduction to Daily Life, Debt, and Development という本もある。ペーパーバックが7,923 円。そして、そのキンドル版は……
キンドル版はまだ無料のままだろうか? そう、紙書籍は依然として “Routledge 価格” ながら、キンドル版はゼロ円となっているのだ!
【※本当は、実際にゼロ円であることをここで見せたいのだが、アメバの Pick機能はショボいので、ゼロ円商品を直接表示できないのだ 】
こんなことになる日が来ようとは夢にも思わなかった。これはただの幻で、もう一度しっかり見れば、キンドル版は有料に戻っているのだろうか?
実は、このブログ記事を書いている間にも、紙書籍の価格が値下がりして、何度も書き直しを余儀なくされてしまったのだ。ほぼ無風状態だったなかで、閲覧数が(私ひとりによって?)若干増えたことが影響しているのだろうか?
しろうと考えながら、関心が増えているなら、キンドル版の価格は100円とか200円に上げるという考えは出てこないのだろうか? まあ、Routledge はそんなケチなことを考えるような出版社ではないか。(^^;
【2026年1月15日(01:35)追記:もう書き直すのは諦めたけど、Robotics, AI and Criminal Law については、100円とか200円どころではない “Routledge 価格” に戻ってしまったらしい。 (^^;】
それにしても、同社のゼロ円キンドル本はたった2例だけなのか? いやいや、そうでもないのだ。
そのお話はまた次回に。<(_ _)>
“ラウトレッジ” と私 (^^;
【注意:今回を含め、Routledge(ラウトレッジ)社にかかわる記事内容は、限られた分野の非常に特殊なケースについて記すもので、極めて一般性を欠くものです。また記事中のキンドル本に関わる諸情報は次の瞬間には新たなものに更新されている可能性があります】
Routledge 社という出版社名を初めて見かけたのは大学生の頃だった。もしかしたら、当時は Routledge and Kegan Paul という名前だったかもしれない。人文科学系、社会科学系の専門書を扱う出版社で、私なんぞには無縁の存在だった。
ただ、たまたま海外の SF研究書の類いのリストを眺めていてその名を知り、その後、日本橋の丸善とか神保町の北澤書店などにも出入りするなかで、Routledge は “お堅くお高い出版社” というイメージが私のなかに定着していったのだった。
その硬派の出版社に再び関心が向いたのはインターネット時代に入ってからだった。
※
英語のディベートの関連書を探していたとき、Pros and Cons: A Debater's Handbook という本の版元が Routledge 社と知って私は驚いた。あの硬派な出版社がそんなベタなハウツーものっぽい本を出していたのか! (@@;
ディベートというのは、かつては大学のESS(English Speaking society)のサークル活動(英語でのSpeach や Discussion など)のひとつとして知られ、ひとつの命題(たとえば、「死刑制度は廃止すべきである」など)をめぐって肯定側・否定側に分かれて英語で討論を行い、そのスキルを競いあうものだった。
その後このディベートの概念はビジネス界にも浸透していったわけだが、それについては “英語の達人” として一世を風靡した 松本道弘の布教活動も大きかったかもしれない。
そのディベート活動が盛んな米英では、主要なテーマごとに肯定・否定それぞれの論点を列挙したアンチョコ本が多数刊行されているが、1896年の初版刊行以来版を重ねて最新第19版では140ものテーマをカバーするに至った Routledge 社の本書には圧倒的な存在感がある。
日本国内では一部の英語上級者のあいだで、検定試験の面接試験対策本として活用されてもいるようだが、ペーパーバックで6,987円、キンドル版でも6,745円と、さすが “Routledge 価格” 健在である。(^^;
※
徳仁親王が1983年から約2年間のオックスフォード大学での留学体験を回想した『テムズとともに――英国の二年間』は、まずは学習院創立125周年記念として学習院教養新書のかたちで刊行された。
その後、紀伊國屋書店から新版が(ハードカバーで)出た後、2023年4月に並装版と電子版がリリースされている。
これについては英国にも翻訳されていたのだが、オリジナルの和書よりも高く、私はどちらも価格面でパスしていた。それが、昨年の10月に Routledge 社が新版を刊行したのだ! その The Thames and I: A Memoir by Prince Naruhito of Two Years at Oxford はペーパーバック版で7,994円、キンドル版でも7,684円。英国版には若干プラスアルファのコンテンツがあるものの、こちらでも “Routledge 価格” は健在といったところだろうか。(^^;
だが、最近、この “Routledge 価格” の一部に激変が起こったのだ!
そのお話は次回に。<(_ _)>