こだわりのつっこみ -14ページ目
レベル: 若干長めですが中学2~3年生レベルなので1日くらいで読めると思います。
ジャンル: ノンフィクション小説 あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★★★☆
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
The Elephant Man: Level 1 (Oxford Bookworms Lib.../Tim Vicary
¥565
Amazon.co.jp
内容:
1884年のある日、医者のTreve は自身が勤める病院の近くのある店で、奇妙な写真を見つけます。Joseph Merrick を病院で検査をしようと連れ出します。
感想: なんという不運な運命、そして悲劇的な結末 私の敬愛する、愛すべき巨匠デヴィッド・リンチ とのこと。 1996年に公開された市川準監督、本木雅弘主演の日本映画です。 駆け出しの 漫画家たちの青春を描いたフィクション映画です。 ストーリー★★★★ ★★★★ (おそらく、今では考えられない豪華な布陣です)★★★★☆ ★★★☆
スタッフ キャスト 「トキワ荘」というアパートには、 「マンガの神様」と言われる手塚治虫が住んでいたことから、やがて彼を慕った漫画家たちがこのアパートに住み着くようになります。藤子不二雄 、石森章太郎 、赤塚不二夫 。寺田ヒロオ 、この映画の主人公、彼もまた漫画家であり、このトキワ荘の古株として、 また兄貴分として 、若き才能たちを時にやさしく、時に厳しく見守っていました。「古い」タイプの寺田の作風は次第に 、時代から遅れだしてきた のです。同じトキワ荘に住む漫画家たちの卵も、すでに頭角を現し始めた藤子不二雄や石森章太郎たちと、なかなか芽の出ない赤塚不二夫や森安直哉 、鈴木伸一 たちの売れない漫画家に二分されつつありました。 さて、この作品は、あくまでもフィクションとして作られたものなので、若干現実とは異なる部分があるとは思うのですが、あの時代の雰囲気、今は取り壊されてしまったマンガの聖地「トキワ荘」と、そこに暮らす若き漫画家たちの青春を見事に描いたなぁ と感激いたしました①ストーリーについて 作品に流れる雰囲気は非常にもの静かで、盛り上がるという場面はほとんどありません 。それだけに寺田の心理描写、活躍していく漫画家とそうでない漫画家の悲哀を良く伝えている のです。 なんだか「新漫画党」の結成の場面や飲み会の場面では、おどろくほどあっさりした関係で、ぜんぜんべたべたしていないのですが、寺田はかわいそうな人ではなく、プライドをもって漫画を描き、その漫画が多くの人に愛されていたのだ 、ということがひしひしと伝わるのです。 ②キャラクターについて 森安直哉役の古田新太さんの憎めない感じと、赤塚不二夫役の大森嘉之さんの才能を開花させきれない感じの演技はすばらしいですよ 主人「やめとけ、売れない漫画家なんか。やめろやめろ。」 森安「これがなかなかやめれんのですわ。」 この森安直哉に、監督の伝えたかったことがあるんじゃないかなぁ、という気がしてなりません。寺田ヒロオ役の本木雅弘さんの演技もすばらしい です。 ③音楽について 演出としての音楽の使い方もすばらしい 。(1) (2) この映画を観ながらなんだかふと、あの映画史に残る大傑作『アマデウス』を思い出してしまう のでした。「才能があり、それなりに尊敬もされているが、その才能は天才的とは言えず、身近に現れた天才が作る潮流に、次第に離されていく」 レベル: 若干長めですが中学2~3年生レベルなので1日くらいで読めると思います。
ジャンル: 冒険・歴史 あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★★☆
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
The Coldest Place on Earth (Oxford Bookworms Li.../Tim Vicary
¥542
Amazon.co.jp
内容:
1910年、南極点到達競争 が始まりました。スコット隊 と、6月6日にFram号でノルウェーを発ったアムンゼン隊 との競争です。競争のほうですが、アムンゼン隊が1911年12月14日に南極点に人類初到達 。遅れて翌1912年1月17日にスコット隊が到着 するのでした。スコット隊の帰路、それは悲しい悲しい最後でした 。
感想: だって、スコット隊の悲劇がものすごく胸にくるものがあるのですから。 帰路にオーツ大尉は足に重度の凍傷を負ってしまい、切り落としてくれとスコットに嘆願するほどにひどい状態に陥ってしまいます。 デポ(前進基地)に戻っても極々わずかな食料しかなく、さらに寒さも増してきます。 「ちょっと、外に行ってくるよ。すぐ戻ってくる。」 という言葉を残し、テントを出て行方不明になるのでした。 ----------------------------------------------------------------- さあ、前回紹介した上巻に続き、今回燃えよ剣 の下巻の紹介です。こちら あらすじ いきます 新選組副長として、京の街を震撼させるまでなった 土方歳三 。七里研之助 との対決が待っていました。七里の策略によりあわや命を落としそうになるものの、辛くも七里を討ち取ります。お雪 と契りを交わし、京での生活も安泰かと思われますが、次第に時勢は新選組、幕府には反するものとなっていくのです。近藤勇 が銃により負傷(のち、捕捉されて斬首)、沖田総司 も病により参戦できず(のち、病死)、いよいよ後退をはじめます。 では以下は感想です。
燃えよ剣〈下〉 (新潮文庫)/司馬 遼太郎
¥780
Amazon.co.jp
~1回目 2010.4.3~ いや~、上巻でも書いたとおり、下巻は非常に面白かった です優勢だった旧幕府軍がどうして新政府軍に負けていったのか、という点に関して非常に細かくその流れがつかむことができた のです。時勢 」という言葉がよく出てきましたが、「時勢」に取り残されると、あらゆる面で不運であったり、タイミングが悪かったりするんだなぁということがひしひしと感じます。西昭庵でのお雪と土方の、切ない切ないストーリー 。皮肉にも局長の近藤勇が負傷により戦線離脱したことにより、土方の勇猛果敢な戦いっぷりが浮き立ち 、よかった。相変わらずの「凡人 」のように描かれています(むしろ、局長というより、土方の親友のような感じです)。「歳、自由にさせてくれ。お前は新選組の組織を作った。その組織の長であるおれをも作った。京にいた近藤勇は、いま思えばあれはおれじゃなさそうな気がする。もう解きはなって、自由にさせてくれ。」(p333) 個人的には近藤勇が凡人だとは思っていません 。近藤勇という男は、カリスマ的な存在で荒くれ共の集まる新選組をまとめあげた非凡の人 だと思っていました。お雪との仲、ひっぱりすぎ 西昭庵で別れた、あの感じで終わっても良かったんじゃないかなぁ と思うのです。下巻は必読に値するほど、熱の入った文章とストーリーで、読んだが最後、一気に読んでしまうことうけあい ★★★★ ★★☆ キャラ:★★★★
読み返したい度:★★★☆ ----------------------------------------------------------------- さて、今回は歴史小説の古典といってもいいほど、有名で名作として知られる、燃えよ剣 です。外国人を追い出そう、という考え 攘夷 ① 武力によって外国人を追い出す過激な攘夷。つまり即刻開国をやめよう という考え方。② 現状では開国したままでよい という考え方。(1) 天皇に政治の権力を戻す ことで日本一丸となって改革をすすめようという考え方。これを尊王 といいます。この考え方によると、つまり幕府を倒そうということになります。(2) あくまでも幕府が政権を保ったまま 、改革をしていこうという考え方。これを佐幕 といいます。① と(1) の考え方を持つならば、武力によって外国を追い出し 、さらに幕府を倒して政権を天皇に戻すことで日本を一新する 、という思想になります。例えば、今の山口県である長州藩 はこの考え方をもつひとが多かったようです。② と(2) の考え方を持つならば、武力によって外国を追い出したいが現状では不可能なので 、幕府による改革で日本を打開していくべき だ、という思想になります。例えば、今の鹿児島県である薩摩藩 や福島県である会津藩 は当初、この考え方の人が多かったようです。①→ ② に、薩摩は(2) → (1) に変えていきます。お互い② と(1) の考え方になった こと武力によって外国を追い出したいが、現状では不可能なので 、幕府を倒して天皇のもとで日本を改革して、外国に追いつくようにしよう という考え)新選組の立場 はというと、攘夷の考え方としては最初ははっきり① を掲げましたが、それよりもあくまでも(2) を主張し、幕府を守ろうとするのです。あらすじ いきます バラ ガキ(不良少年)だった多摩の百姓の子、土方歳三 。近藤勇 や沖田総司 と共に道場で剣の腕を磨きます。七里研之助 という男が後ろにいて、以後、土方を必要以上に付け回し、狙うのです。お雪 と出会い、今までの女とは違う何かを感じるのでした。 では以下は感想です。
燃えよ剣〈上〉 (新潮文庫)/司馬 遼太郎
¥780
Amazon.co.jp
~1回目 2010.3.25~ 感想ですが、この作品は新選組の小説の定番となっていて、それだけに非常に期待が大きかったのですが、なんとなく可もなく不可もなく という印象を受けました。立ち合いシーンが面白い 。鬼の副長土方が、かわいらしい一面をのぞかせる 、ということ。局長である近藤勇が凡な人物にえがかれているという印象が強い ことです。「インテリと権力が大好きで、インテリに憧れる、迫力はあるが強いのか弱いのかはよく分からない女好き」 としか思えません別に本筋とはかすりもしないサイドストーリーが結構多いのかな?という印象を受けたこと です。『男子の本懐』
は、同じ史実をもとにした小説でありながら、登場人物を極力抑えて浜口雄幸と井上準之助の2人にスポットをあてているので、焦点がぼやけず、当時の時勢も伝わって来たなぁと思ったのです。七里との決闘の行方や、新選組・土方歳三の末路、お雪との恋愛の結末など、下巻にもちこされたものが多いので、楽しみです ★★☆ ★★☆ キャラ:★★★☆ 読み返したい度:★★☆ Copyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved.




 ストーリー
ストーリー
 感想と見所
感想と見所


 )
)


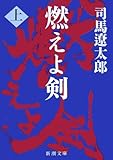

 とも思えてしまいます。
とも思えてしまいます。