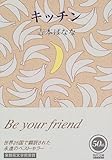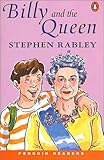こだわりのつっこみ -15ページ目
レベル: 若干長めですが中学2~3年生レベルなので1日くらいで読めると思います。
ジャンル: 恋愛物 あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★★★☆
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
From the Heart/著者不明
¥648
Amazon.co.jp
内容:
オクスフォード大学に入学するAnna。父のDerekや父の女友達のJaneに見送られ、オックスフォード行きのバスに乗ります。
感想: なかなか面白かった です。不満もあります 。 ----------------------------------------------------------------- 今回は、直木賞を受賞した青春恋愛小説、GO です。主人公の高校生、杉原が在日朝鮮人(のち韓国人)だということ 新しい視点 で描かれているなぁというのが第一印象です。朝鮮学校内の学校生活 が描かれていて(もちろん、小説というからには若干の誇張が入っているとは思うのですが)、これもなかなか面白いですあらすじ いきます杉原 は、一般の私立高校に通う高校生。桜井 は杉原を見つけると、2人で会場を抜け出します。 では以下はネタバレ含むので、いやな方は見ないで下さい。 GO (講談社文庫)/金城 一紀
¥470
Amazon.co.jp
~1回目 2010.3.25~ さて、あらすじの続きですが、自分は日本人ではなく、在日韓国人である ということ。感想 です個人的にはあまり面白く感じません でした「ご都合主義」 を感じてしまいます。桜井の「血が汚い」とか「なんだか怖い」という反応は、在日の方々に対する、日本人のある種典型的な反応で、おそらく作者も言われた経験があるんじゃないか、と思えるくらい、リアルに問いかける部分 で、ここはすごく読むべき箇所ですその後の桜井の身の軽さ 。 杉原の告白の際、絶望的な、それまでの楽しい恋人としての時間や杉原のアイデンティティを否定する言葉を吐いて別れたにもかかわらず、数ヵ月後に電話をかけて杉原と会うなんてどんな神経なんだ と「俺が国籍を変えないのは、もうこれ以上、国なんてものに新しく組み込まれたり、取り込まれたり、締めつけられたりされるのが嫌だからだ。もうこれ以上、大きなものに帰属してる、なんて感覚を抱えながら生きてくのは、まっぴらごめんなんだよ。」(p231) 「俺は《在日》でも、韓国人でも朝鮮人でも、モンゴロイドでもねえんだ。俺を狭いところに押し込めるのはやめてくれ。俺は俺なんだ。」(p246) それを棚上げしておいて、「俺は俺」なんていう、ある種のコスモポリタニズムを発揮されても頷けません 桜井の「ご都合主義」、杉原の「ご都合主義」により、なんだかなぁ~ という読後感でした。 ★★ ★★★ キャラ:★☆ 読み返したい度:★★ レベル: 若干長めですが中学2~3年生レベルなので1日くらいで読めると思います。
ジャンル: ヒューマン あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★★★☆
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
Christmas in Prague (Bookworms Series)/Joyce Hannam
¥599
Amazon.co.jp
内容:
オクスフォードに暮らしていたキャロル、夫のジャン、そしてジャンの父親であるジョセフ。
感想: あなたは家族のことについて、全てを知っているだろうか?
家族はあなたについて全てを知っているだろうか?
どんな家族でもなにがしかの秘密を持っている。それは大きな秘密、小さな秘密、笑ってしまうような秘密、そして、それは悲しい秘密かもしれない。
ジャンは妻のキャロル、そして父のジョセフとオクスフォードに住んでいる。
ジャンはプラハで生まれたが、父と共に幼い頃にイギリスに来たのだ。
母親は彼が生まれたときに死んだので母のことをまったく知らない。
また父も母について多くを語らない。
しかし、ジョセフは未だに妻の写真を持ち歩いているのだ。
キャロルはオーケストラのハープ奏者で、クリスマスにプラハでのコンサートをすることになった。 プラハは義父と夫のゆかりの地であり、 キャロルはジャンとジョセフと一緒に行きたかった。
しかし、プラハでは彼らの秘密が待ち受けているのだ。
素敵な、幸せな、そして悲しい秘密が。 なんすか、秘密って~ ----------------------------------------------------------------- 角川文庫に所収された『キッチン』の最後の短編です。愛する者の「死」 を扱っているという点で共通したものがあります。等 を事故で亡くしたさつき 。うらら に声をかけられ、仲良くなるのです。冒頭に引用した部分はこの女性、うららとさつきの会話です。 柊 という弟がいました。柊にもゆみこ さんという恋人が。百年に一度の見ものとは? では以下はネタバレ含むので、いやな方は見ないで下さい。 キッチン (角川文庫)/吉本 ばなな
¥420
~1回目 2010.3.17~ 結果を言ってしまえば、七夕現象 といって、大きな川のところで、死んだ人の残した思念と残された人の悲しみとがうまく反応することでかげろうとなって、残された人の目の前に死んだ人が現れる、というものなのです。予想できたのですが、予想できたとはいえ、なかなかその部分の記述が素敵 です。「 等がいた。 川の向こう、夢や狂気でないのなら、こっちを向いて立っている人影は等だった。川をはさんで――なつかしさが胸にこみ上げ、その姿形すべてが心の中にある思い出の像と焦点を合わせる。 彼は青い夜明けのかすみの中で、こちらを見ていた。私が無茶をした時にいつもする、心配そうな瞳をしていた。ポケットに手を入れて、まっすぐ見ていた。私はその腕の中で過ごした年月を近く遠く、想った。私たちはただ見つめ合った。二人をへだてるあまりにも激しい流れを、あまりにも遠い距離を、薄れゆく月だけが見ていた。私の髪と、なつかしい等のシャツのえりが川風で夢のようにぼんやりとなびいた。 等、私と話したい?私は等と話がしたい。そばに行って、抱き合って再会を喜び合いたい。でも、でも――涙があふれた――運命はもう、私とあなたを、こんなにはっきりと川の向こうとこっちに分けてしまって、私にはなすすべがない。涙をこぼしながら、私には見ていることしかできない。等もまた、悲しそうに私を見つめる。時間が止まればいいと思い―しかし、夜明けの最初の光が射した時にすべてはゆっくりと薄れはじめた。見ている目の前で、等は遠ざかってゆく。私があせると、等は笑って手を振った。なつかしい等、そのなつかしい肩や腕の線のすべてを目に焼きつけたかった。この淡い景色も、ほほをつたう涙の熱さも、すべてを記憶したいと私は切望した。彼の腕が描くラインが残像になって空に映る。それでも彼はゆっくりと薄れ、消えていった。」 (p193-194より) 吉本ばななさんの瑞々しい文章が相成って、非常に苦しくも救いのある内容に仕上がっている ように感じました全然納得のできない点が1点 あります。「川ではなく、夢うつつの中で柊もゆみこを見た」 ということ。それ以外のストーリーはすごくすごく好き で、個人的には『キッチン』や『満月』以上に楽しめました ★★★★ ★★★★★ キャラ:★★★ 読み返したい度:★★★ レベル: 中学2~3年生レベルで1時間以内に読めると思います。
ジャンル: ユーモア あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
Billy and the Queen (Penguin Joint Venture Read.../Stephen Rabley
¥613
Amazon.co.jp
内容:
新しい自転車が欲しかったビリーは、「女王と一緒に自分を写真をおさめる競争(1番早い人に500ポンド)」という記事を見つけ、姉のロックスと女王との写真を撮りに行きます。
感想: 全然納得できません 蝋人形とはいえ女王陛下に肩をくむとは何事か Copyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved.
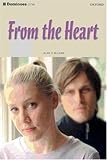




 という杉原にも若干の違和感がありますが、それよりなにより、ヒロインの桜井に対して思うことがあります。
という杉原にも若干の違和感がありますが、それよりなにより、ヒロインの桜井に対して思うことがあります。