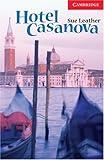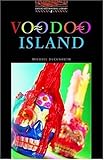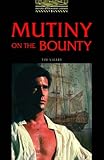こだわりのつっこみ -12ページ目
レベル: 若干長めですが中学2~3年生レベルなので1日くらいで読めると思います。
ジャンル: 愛憎劇 あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★★☆
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
Hotel Casanova Level 1 (Cambridge English Readers)/Sue Leather
¥632
Amazon.co.jp
内容:
イタリア南部の田舎町ロッチェッラから、北部の都ヴェニスにやってきて、ホテル・グラントのレセプション係としてあくせく働くディノ 。カーラ が現れます。あなたのために、夫アレッサンドロを殺した 」とのこと。マリア 。
感想: ただ、逃げるディノですが、結構自分勝手だなぁという気がしないでもない。まあ、夫を殺してまで惚れさせたディノが魅力的なのかな レベル: 若干長めですが中学2~3年生レベルなので1日くらいで読めると思います。
ジャンル: ファンタジー あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★★★★☆
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
Voodoo Island (Oxford Bookworms Library)/Michael Duckworth
¥639
Amazon.co.jp
内容:
やり手の建設会社社長コンウェイ は、飛行機でハイチに向かっていました。カレン 。彼女は医者ですが、ハイチの民俗信仰であるヴードゥーに関心があり、それに関する本を書くためにハイチに訪れるのです。 しかし、コンウェイはヴードゥーについてまったく興味をもたず、それどころか全く信じなかったのです。キー の家です。 、キーの大切な祖父が眠る、 大切な場所である墓を案内します。
するとコンウェイは「多くの部屋がある大きな家に住み、掃除も食事もしてくれる人がいて、銀行には大金があり、働かずいたい」 「多くの部屋がある大きな家(病院)に住み、掃除も食事もしてくれる人がいて、銀行には大金があり、働かず」 にいれる場所だったのですから。
感想: ヴードゥの使い手の本気の呪いは恐ろしい… レベル: 若干長めですが中学2~3年生レベルなので1日くらいで読めると思います。
ジャンル: 冒険 あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★★★
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
Mutiny on the Bounty (Oxford Bookworms Library)/Tim Vicary
¥678
Amazon.co.jp
内容:
バウンティ号 には船長ブライ をはじめとして、彼の友人であり副船長のクリスチャン 、船員のアダムズ やヘイウッド などが乗船しており、彼らは母国イギリスのためにタヒチのパンノキの実を西インド諸島に運ぶことを任務としていたのです。反乱は実行されます。 しかし、多くの船員は原住民に殺されたり、バウンティ号すら発見できなかったりと、なかなか彼らの消息をつかめません。 感想: さてさて、この事件、現実にあったものだったらしいですね レベル: 若干長めですが中学2~3年生レベルなので1日くらいで読めると思います。
ジャンル: ホラー あらすじ(背表紙から):
面白さ: ★★★
※以下、結末まで話します。嫌な方は見ないでください。
The Monkey’s Paw: Best-seller Pack (Oxford Book.../W.W. Jacobs
¥639
Amazon.co.jp
内容:
ホワイト氏 と夫人 、それから息子のハーバート は来客を待っていました。トム氏 。
さて、夫人がドアを開けます。 感想: 結果的に、ホワイト氏の3つめの願いは、「(自分の身の丈に合わないような)物事を変えようとすることに良いことは一つもない」 という命題が突きつけられたわけですが、さて、どう感じますか 前回は、楽譜がレシピ という喩えをしましたが、今回はそのレシピから料理を作る料理人について説明をしようと思います。楽譜(レシピ)通りに演奏(料理)する人はなかなかいない 。(というかクラシックを人前で語るということをした経験がほとんどありません) (笑)楽譜に書かれたことを解釈して演奏する 、というのは、料理で喩えるならば、レシピに書かれたことを自分なりにアレンジして料理する 、ということとなります。指揮者が料理人 に置き換えられます。の指揮者の解釈によって、同じ曲でも瑞々しくなったり、重々しくなったり、憂いを秘めたり、快活になったりする のです。ラヴェル作曲の「亡き王女のためのパヴァーヌ」 です。カッコは個人的な印象です。小澤征爾指揮・ボストン交響楽団の演奏
(テンポはオーソドックス、若干硬い印象を受けます。) Gian-Philip Toro指揮・Collégiale Notre Dameの演奏 (テンポは小澤よりも若干遅めで、各旋律が比較的よく歌っている印象。しかし、若干歌いすぎて間延びする感があり、また伴奏の音の一体感が乏しいです。) カラヤン指揮・(恐らく)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏
(こちらも遅いテンポ。非常にバランスがとれていて、特に弦楽器の鳴りが甘美です。ハープが他の演奏よりも表に出てきているので、一層優美な感じがします。しかし最後の5:35からは弦楽器を主体にメロディを構成してほしかったなぁ。) フェラーリ指揮・ニュー・アートフィルハーモニー管弦楽団の演奏
(テンポは遅めですが、他の演奏と比べると、最も特徴的です。例えば、2:38からの2回目の旋律に入るタイミングがこの中では最も早く、強弱の差がもっともついている演奏だと思います。最後の5:35からは弦楽器を十分に歌わせており、この部分に関しては個人的には好きです。しかし、あまりにもドラマティックすぎてこの曲には仰々しく感じてしまう部分も。) オーマンディ指揮・フィラデルフィア管弦楽団の演奏
(なんとも早い演奏です。しかし、作曲者のラヴェル自身はこの曲を早く演奏した方がいいとも語っており、それに忠実ではあるのか。こちらはこちらでいかにも「小品」という感じで良いです。しかし、音を出すところは出していますよね。) 6.ペデロッティ指揮・チェコ・フィルハーモニー管弦楽団の演奏
(録音状態が残念ですが、テンポはゆっくりめで、ぜひともステレオ録音で聴いてみたかったと思う演奏です。特に、最後の5:55~の部分は、いい弦の響きだと思っています。) 当たり前ですが楽譜は一緒 です。今回のポイントは 指揮者は料理人である。 Copyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved.