半端な人助け
僕は人にものを頼んだり頼まれる際、思う事があります。
ボランティアとは施しの心をもって人の助けをする。
そう云うことですが、心に施しと思う心を持ったままでは
本当の人助けは出来ないのではないでしょうか。
して上げる。だから感謝されて当たり前。
そんな気持ちがあってはボランティアは務まりません。
最初から犠牲を覚悟で応じれば、思い上がりの心は消え、
人助けを全う出来るのです。
僕は、犠牲を払わない行為は心からの人助けとはどうしても思えないのです。
実は今日は都合が悪いので、と云われると、
都合の良い時にする行為は人助けではない。
そう思い、都合が悪いのを押して行う行為こそが
人助けの精神と信じるからです。
犠牲を伴わない行為は、それが思った以上に大変な作業であれば、
心に不平、不満がおこるのものです。
それは相手にも自分自身にも宜しくないマナーではないでしょうか。
犠牲が払えないならば、中途半端に人助けなど考えないことです。
葉隠塾 成嶋弘毅

にほんブログ村
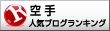
人気ブログランキングへ
ブログをご覧下さる方々へのお願い;
葉隠塾ホームページ http://www.yoin-juku.com/
コラム&武士道の欄を設けております。
ご覧下さいました方よりコメントなりメッセージを
ブログの方に頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
ボランティアとは施しの心をもって人の助けをする。
そう云うことですが、心に施しと思う心を持ったままでは
本当の人助けは出来ないのではないでしょうか。
して上げる。だから感謝されて当たり前。
そんな気持ちがあってはボランティアは務まりません。
最初から犠牲を覚悟で応じれば、思い上がりの心は消え、
人助けを全う出来るのです。
僕は、犠牲を払わない行為は心からの人助けとはどうしても思えないのです。
実は今日は都合が悪いので、と云われると、
都合の良い時にする行為は人助けではない。
そう思い、都合が悪いのを押して行う行為こそが
人助けの精神と信じるからです。
犠牲を伴わない行為は、それが思った以上に大変な作業であれば、
心に不平、不満がおこるのものです。
それは相手にも自分自身にも宜しくないマナーではないでしょうか。
犠牲が払えないならば、中途半端に人助けなど考えないことです。
葉隠塾 成嶋弘毅
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
ブログをご覧下さる方々へのお願い;
葉隠塾ホームページ http://www.yoin-juku.com/
コラム&武士道の欄を設けております。
ご覧下さいました方よりコメントなりメッセージを
ブログの方に頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
日本人を形作る”たが”
道徳とは何でしょう。
もしかしたらそれは時代により変わって行くものかも知れません。
僕の子供の頃、大人は親切を通り越し、大きなお世話とも思えるほど、
よその子にまで干渉したものです。
その中から、してはいけない事やしなければならない事なども教えられたのです。
昔、1950年代から60年代にかけて僕が少年時代に教えられたことは:ー
◎男は男らしく、女は女らしく
男は弱いもの虐めをしてはいけない。
卑怯なことは男として恥ずかしいことだ。
男は強く、動物や弱い人間を守って上げなさい。
それを虐めるようなことは恥ずかしいこと。
そうして恥と云う感覚を植え付けられたように思います。
今の時代にはあまり見かけませんが、
例えとして使われることの良くあるのが桶です。
桶はバラバラの板が、”たが”と云う帯で回りを
締められ桶として使える道具になるのですが、
その”たが”が外れればただの板きれに戻ってしまいます。
昔、男の子を形作っていたものは恥の精神だったのではないでしょうか。
恥の精神が男の子達の”たが”だったのです。
恥ずかしいことをしてはならない。そのことです。
しかし、もしかしたら恥の精神はすでに
現代の道徳には入らないのかも知れない。
そう思わされることを見受けます。
恥としての概念が変わってしまったことは確かにあるでしょう。
しかし、如何に時代が変わっても
恥の精神は我々日本人の徳目として残しておきたいと思っています。
それは子供だけに限らない、人間を形作る”たが”にもなるからです。
”武士道”はそれらを内臓した日本人を形成する”たが”と信じてます。
葉隠塾 成嶋弘毅

にほんブログ村
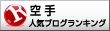
人気ブログランキングへ
ブログをご覧下さる方々へのお願い;
葉隠塾ホームページ http://www.yoin-juku.com/
コラム&武士道の欄を設けております。
ご覧下さいました方よりコメントなりメッセージを
ブログの方に頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
もしかしたらそれは時代により変わって行くものかも知れません。
僕の子供の頃、大人は親切を通り越し、大きなお世話とも思えるほど、
よその子にまで干渉したものです。
その中から、してはいけない事やしなければならない事なども教えられたのです。
昔、1950年代から60年代にかけて僕が少年時代に教えられたことは:ー
◎男は男らしく、女は女らしく
男は弱いもの虐めをしてはいけない。
卑怯なことは男として恥ずかしいことだ。
男は強く、動物や弱い人間を守って上げなさい。
それを虐めるようなことは恥ずかしいこと。
そうして恥と云う感覚を植え付けられたように思います。
今の時代にはあまり見かけませんが、
例えとして使われることの良くあるのが桶です。
桶はバラバラの板が、”たが”と云う帯で回りを
締められ桶として使える道具になるのですが、
その”たが”が外れればただの板きれに戻ってしまいます。
昔、男の子を形作っていたものは恥の精神だったのではないでしょうか。
恥の精神が男の子達の”たが”だったのです。
恥ずかしいことをしてはならない。そのことです。
しかし、もしかしたら恥の精神はすでに
現代の道徳には入らないのかも知れない。
そう思わされることを見受けます。
恥としての概念が変わってしまったことは確かにあるでしょう。
しかし、如何に時代が変わっても
恥の精神は我々日本人の徳目として残しておきたいと思っています。
それは子供だけに限らない、人間を形作る”たが”にもなるからです。
”武士道”はそれらを内臓した日本人を形成する”たが”と信じてます。
葉隠塾 成嶋弘毅
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
ブログをご覧下さる方々へのお願い;
葉隠塾ホームページ http://www.yoin-juku.com/
コラム&武士道の欄を設けております。
ご覧下さいました方よりコメントなりメッセージを
ブログの方に頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
初恋 の1番
この文章はピアノ教本 ”バイエル” に因み番号をふり、
続きもののシリーズにさせて頂きます。途中不評でしたら打ち切ります。
どうか、ご支援頂きたく存じます。
・・・ 初恋 の1番 ・・・
いつからか気付いたのですが、僕が恋をするのには必ず周期があるのです。
それはまさに四季を感じさせるものです。
春に始まり、夏に燃え、秋に翳りを見せ始め、冬に終わると云うものでした。
初恋も例外ではありませんでした。
ある爽やかな早春の頃、歌声が聞こえて来ました。
それは”サフランの歌”だったと思います。きれいな声でした。
それまでさほど気にもならなかったご隣の家なの
ですがそれからピアノの音も、かすかに聞こえる会話も何か気になり始めたのです。
ピアノは初心のバイエルでした。
聞こえた番号の曲をこちらもリピートしたのです。
するとそれに気付き、また返して来るようになりました。
他のご近所もそれに気付いたはずです。
次は、その歌声の主とピアノの弾き手を見たくなりました。
それとなく、犬の散歩を装いあちらの様子を伺い始めたのです。
そんなある日、その家の門から明らかにその娘に違いないと思われる子が出て来たので
何故かドギマギし目を逸らせてしまったのです。
しかし、その一瞬の間に僕は脳裏に鮮明な映像を映していたのです。
それからの毎日は、庭に花が咲いたように明るく楽しくなって行くのです。
次回は、二人の認識をお伝えします。
葉隠塾 成嶋弘毅

にほんブログ村
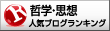
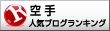
人気ブログランキングへ
ブログをご覧下さる方々へのお願い;
葉隠塾ホームページ http://www.yoin-juku.com/
コラム&武士道の欄を設けております。
ご覧下さいました方よりコメントなりメッセージを
ブログの方に頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
続きもののシリーズにさせて頂きます。途中不評でしたら打ち切ります。
どうか、ご支援頂きたく存じます。
・・・ 初恋 の1番 ・・・
いつからか気付いたのですが、僕が恋をするのには必ず周期があるのです。
それはまさに四季を感じさせるものです。
春に始まり、夏に燃え、秋に翳りを見せ始め、冬に終わると云うものでした。
初恋も例外ではありませんでした。
ある爽やかな早春の頃、歌声が聞こえて来ました。
それは”サフランの歌”だったと思います。きれいな声でした。
それまでさほど気にもならなかったご隣の家なの
ですがそれからピアノの音も、かすかに聞こえる会話も何か気になり始めたのです。
ピアノは初心のバイエルでした。
聞こえた番号の曲をこちらもリピートしたのです。
するとそれに気付き、また返して来るようになりました。
他のご近所もそれに気付いたはずです。
次は、その歌声の主とピアノの弾き手を見たくなりました。
それとなく、犬の散歩を装いあちらの様子を伺い始めたのです。
そんなある日、その家の門から明らかにその娘に違いないと思われる子が出て来たので
何故かドギマギし目を逸らせてしまったのです。
しかし、その一瞬の間に僕は脳裏に鮮明な映像を映していたのです。
それからの毎日は、庭に花が咲いたように明るく楽しくなって行くのです。
次回は、二人の認識をお伝えします。
葉隠塾 成嶋弘毅
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
ブログをご覧下さる方々へのお願い;
葉隠塾ホームページ http://www.yoin-juku.com/
コラム&武士道の欄を設けております。
ご覧下さいました方よりコメントなりメッセージを
ブログの方に頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
日本刀と使いこなす技術
刀と日本人、そのは何処かで必ず繋がりを持っているのです。
波紋、美しいディザインではないでしょうか。
鋼を重ねて鍛えた日本刀にはロマンを感じます。
まさに工芸品です。その美しさは実に日本的でもあります。
いまの製鉄技術からすれば、刀の鋼はひどく不純物も多く、
出来不出来が打つ刀工によって大きく変わると聞きました。
そこがまた日本刀らしく感じませんか。
僕は良く思うのです。
日本人は与えられた道具を用い、技術を駆使してそれを使います。
良い例が日本の弓です。技術を要します。技術がなければ飛びません。
当然当たるわけもありません。だから弓道なのです。
古代中国で使用した石弓や、
西洋のクロスボーは(ロビンフッドの敵役、代官の兵が使用した弓)
鉄砲のように狙いを付け、
引き金を引けば飛んで行くので和弓のような技術はいりません。
だから”道”にはほど遠いのです。
日本では使い難い道具なら、技術を磨きそれを使うことを良しとして来ました。
全てにその考えが行き渡り、従って使い難い道具を改良するのではなく、
それを使いこなす技術を重んじたのです。
それは自ずと道に通じました。
日本では何年経っても種子島は種子島のままで、
改良され連発銃には発展しなかったことでしょう。
しかし、砲術は砲道になって行ったでしょう。
云って見れば刀も同じ。折れる、曲がる、切れなくなる。
それを技術で補ったのです。
しかし、反りが多少変わっただけで、他には一切改良や改善
は施されなかったのです。
しかし、それを上手に使う名人、達人が現れ剣術となり、
剣道が生まれたのです。
その我々が世界に誇った零戦と云う現代の武器がありました。
その戦闘機さえもパイロットの技術により性能が引き出され、
支えられたと聞きます。
さらに、外国の戦闘機とは異なりパイロットの命を守る
機能は殆ど施されてはいなかったのです。
操縦士の腕がなければ成り立たない兵器であったようです。
そこで我々日本人は技術と精神力が高められたと云うことになります。
果たして現代の日本人はそれを受け入れるのでしょうか。
いま、恐ろしいと感じるのは、
福島の原発にアメリカとフランスから技術者が
応援に駆けつけてくれているそうですが、
まさか日本人はそこでも技術と精神力で頑張っているとは思いたくありません。
それは日本人の良いところでもあり変えて行かなければならないものです。
特有の精神力を維持しながら、対応するのが日本人だと信じております。
葉隠塾 成嶋弘毅

にほんブログ村
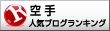
人気ブログランキングへ
ブログをご覧下さる方々へのお願い;
葉隠塾ホームページ http://www.yoin-juku.com/
コラム&武士道の欄を設けております。
ご覧下さいました方よりコメントなりメッセージを
ブログの方に頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
波紋、美しいディザインではないでしょうか。
鋼を重ねて鍛えた日本刀にはロマンを感じます。
まさに工芸品です。その美しさは実に日本的でもあります。
いまの製鉄技術からすれば、刀の鋼はひどく不純物も多く、
出来不出来が打つ刀工によって大きく変わると聞きました。
そこがまた日本刀らしく感じませんか。
僕は良く思うのです。
日本人は与えられた道具を用い、技術を駆使してそれを使います。
良い例が日本の弓です。技術を要します。技術がなければ飛びません。
当然当たるわけもありません。だから弓道なのです。
古代中国で使用した石弓や、
西洋のクロスボーは(ロビンフッドの敵役、代官の兵が使用した弓)
鉄砲のように狙いを付け、
引き金を引けば飛んで行くので和弓のような技術はいりません。
だから”道”にはほど遠いのです。
日本では使い難い道具なら、技術を磨きそれを使うことを良しとして来ました。
全てにその考えが行き渡り、従って使い難い道具を改良するのではなく、
それを使いこなす技術を重んじたのです。
それは自ずと道に通じました。
日本では何年経っても種子島は種子島のままで、
改良され連発銃には発展しなかったことでしょう。
しかし、砲術は砲道になって行ったでしょう。
云って見れば刀も同じ。折れる、曲がる、切れなくなる。
それを技術で補ったのです。
しかし、反りが多少変わっただけで、他には一切改良や改善
は施されなかったのです。
しかし、それを上手に使う名人、達人が現れ剣術となり、
剣道が生まれたのです。
その我々が世界に誇った零戦と云う現代の武器がありました。
その戦闘機さえもパイロットの技術により性能が引き出され、
支えられたと聞きます。
さらに、外国の戦闘機とは異なりパイロットの命を守る
機能は殆ど施されてはいなかったのです。
操縦士の腕がなければ成り立たない兵器であったようです。
そこで我々日本人は技術と精神力が高められたと云うことになります。
果たして現代の日本人はそれを受け入れるのでしょうか。
いま、恐ろしいと感じるのは、
福島の原発にアメリカとフランスから技術者が
応援に駆けつけてくれているそうですが、
まさか日本人はそこでも技術と精神力で頑張っているとは思いたくありません。
それは日本人の良いところでもあり変えて行かなければならないものです。
特有の精神力を維持しながら、対応するのが日本人だと信じております。
葉隠塾 成嶋弘毅
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
ブログをご覧下さる方々へのお願い;
葉隠塾ホームページ http://www.yoin-juku.com/
コラム&武士道の欄を設けております。
ご覧下さいました方よりコメントなりメッセージを
ブログの方に頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
『心得』
『心得』
最近朝ヒゲを剃る時、必ず思い起こす風景があります。
それは、昔のサムライが湯をわかし、桶に入れ、膝に手ぬぐいを載せ月代を湿し
手にしたカミソリで延びた月代の毛を剃る図です。
そう思うとヒゲを剃る面倒な作業も楽しく、
さほど時間がかかるように思えず出来るのです。
何しろ現代の我々は水道の蛇口を捻ればお湯も出るのですから。
独身のサムライは毎朝出仕(努めに出る)する前に、
袴にコテを当て(アイロンと同じ)
髪には香を効かせ(今で云う整髪料)整えるさまを思い浮かべると、
普段の面倒と思う所作も楽しくなるのは何故でしょう。
広い狭いは別にし、掃き清められた庭に残った桶の湯を捨て、
打ち水の変わりにする仕草なども同時に思い浮かべます。
昔の日本家屋は、内も外も掃き清められ、濡れふきの後、
乾拭きを重ね、それは清潔でした。
畳は古く、廊下の木は古くとも清潔感は漂っていたのです。
思いますに、お寺と神社を比較した場合、
神社にこの雰囲気を感じますのは僕が神道だからでしょしょうか。
清楚、清潔は規律と秩序を感じさせるものです。
池波正太郎さんが、物語の中で、「その衣服は質素だがどこか垢じみてない」
その台詞が物語っているように感じます。
昔から日本人の心にはこの心得が何処かに染み付いているのではないでしょうか。
大切に取っておきたい徳目です。
葉隠塾 成嶋弘毅

にほんブログ村
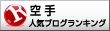
人気ブログランキングへ
ブログをご覧下さる方々へのお願い;
葉隠塾ホームページ http://www.yoin-juku.com/
コラム&武士道の欄を設けております。
ご覧下さいました方よりコメントなりメッセージを
ブログの方に頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
最近朝ヒゲを剃る時、必ず思い起こす風景があります。
それは、昔のサムライが湯をわかし、桶に入れ、膝に手ぬぐいを載せ月代を湿し
手にしたカミソリで延びた月代の毛を剃る図です。
そう思うとヒゲを剃る面倒な作業も楽しく、
さほど時間がかかるように思えず出来るのです。
何しろ現代の我々は水道の蛇口を捻ればお湯も出るのですから。
独身のサムライは毎朝出仕(努めに出る)する前に、
袴にコテを当て(アイロンと同じ)
髪には香を効かせ(今で云う整髪料)整えるさまを思い浮かべると、
普段の面倒と思う所作も楽しくなるのは何故でしょう。
広い狭いは別にし、掃き清められた庭に残った桶の湯を捨て、
打ち水の変わりにする仕草なども同時に思い浮かべます。
昔の日本家屋は、内も外も掃き清められ、濡れふきの後、
乾拭きを重ね、それは清潔でした。
畳は古く、廊下の木は古くとも清潔感は漂っていたのです。
思いますに、お寺と神社を比較した場合、
神社にこの雰囲気を感じますのは僕が神道だからでしょしょうか。
清楚、清潔は規律と秩序を感じさせるものです。
池波正太郎さんが、物語の中で、「その衣服は質素だがどこか垢じみてない」
その台詞が物語っているように感じます。
昔から日本人の心にはこの心得が何処かに染み付いているのではないでしょうか。
大切に取っておきたい徳目です。
葉隠塾 成嶋弘毅
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
ブログをご覧下さる方々へのお願い;
葉隠塾ホームページ http://www.yoin-juku.com/
コラム&武士道の欄を設けております。
ご覧下さいました方よりコメントなりメッセージを
ブログの方に頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。