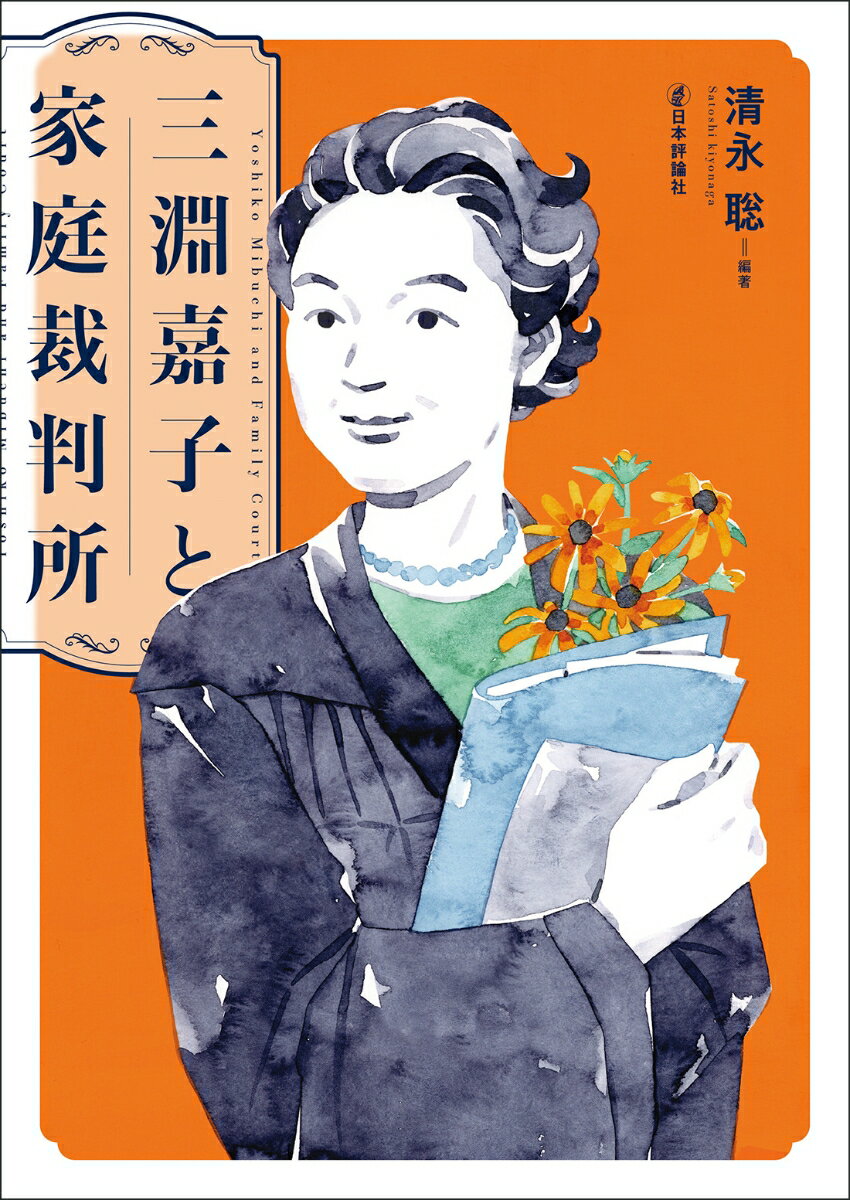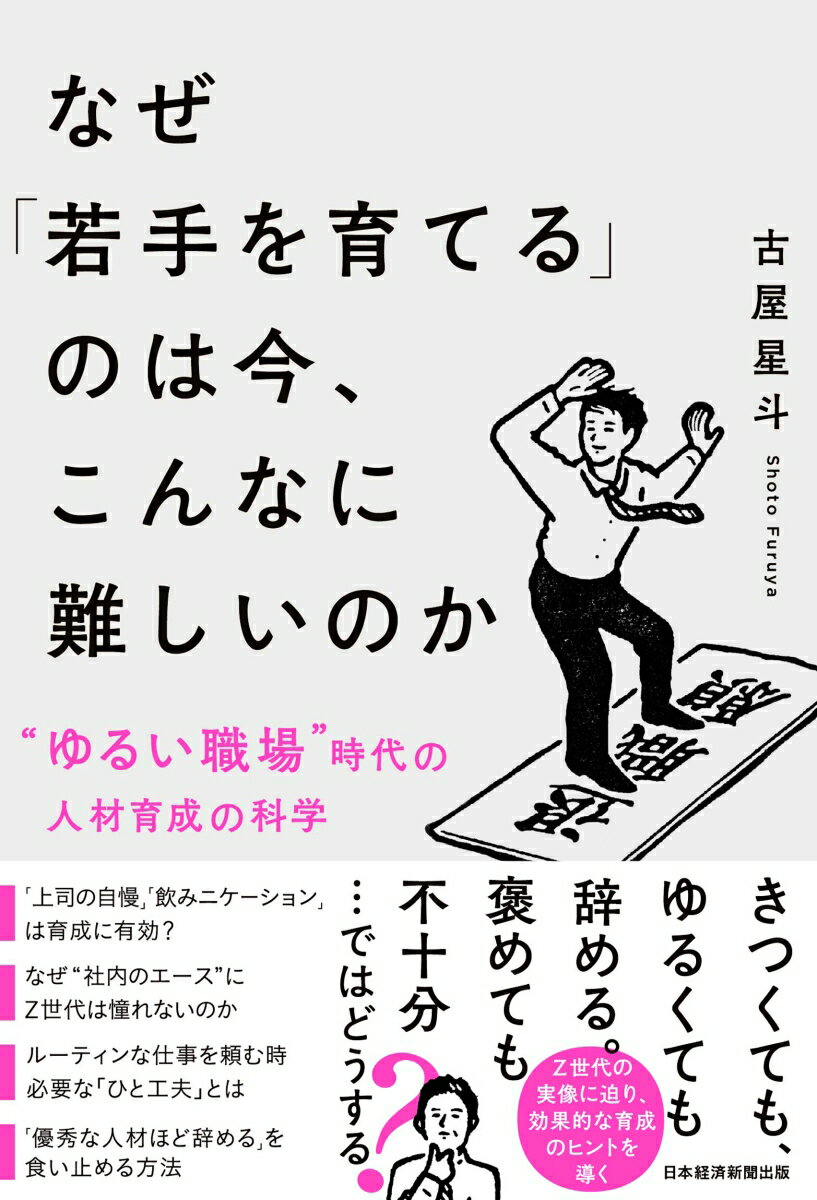こんにちは![]()
地方で中古住宅住まいのブログです![]()
怒涛読書📖⛄🌃🌛✨

そういう意味では私も傾聴できたのかな
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
さて。
伊藤さいりさんが人気なのはわかるし
ひよっこの米屋のよね子も人気だったし
でもちょっと観るの躊躇してた朝ドラ、
虎に翼。
戦後、日本で初めて女性の判事・裁判所長となり、家庭裁判所創設にもかかわった三淵嘉子さんのお話し。
法廷もの、木曜から金曜への「続く」が気になり過ぎて、早くもすっかり虜です![]()
三淵嘉子さんと一緒に働かれていた方が
事前の特集番組に出てて、
「調査官には決して事情を話さなかった、犯罪を犯した少年達が、三淵さんと対峙したら涙を流して反省して刑期を終えていく」
というようなことをおっしゃっていて、すごく気になってはいたのです😢
始まったばかりの先週分は観ないまま録画を消してしまったけど、楽しく観ています![]()
ちなみに日曜深夜に10話一挙放送やるみたい![]() 気になる方はぜひ
気になる方はぜひ![]()
昨日の話これから観る人、
以下スルーで🙇♀️

臨死!江古田ちゃんの作者さんも以下のようにポストしてました。
DV夫が持つ思考回路に対する解像度の高さ!
DVは激しい執着と支配欲であることを徹底して表現している。脚本も演出も、とてもよく調べて考えて作られている
そして大好き仲野太賀さん、我らが平岩 紙さん、松山ケンイチさん、そして小林薫さんも大好きでキャストも良き![]()
![]()
![]()
小林薫さんは最近はコタツのない家も良かったですが、高橋一生さんが演じる研究者をあたたかく見守るこのドラマも好きでした![]()
さてレビュー📖
まだこちらのレビュー中ですが
ゴマさんやろくちゃんの読まれた本がおもしろそうで、予約の順番待ちしていた私の図書館にも到着🏫🚚
人気なようで次の予約も入ってて返さねばならないので、割り込みレビュー🎾
内容盛りだくさんで、こちら前編の続きです📖
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 「ゆるい職場」時代の育て方改革5つのヒント:質的負荷をいかに高めるか
「ゆるい職場」時代の育て方改革5つのヒント:質的負荷をいかに高めるか
ゆるい職場:若手の期待や能力に対して、著しく仕事の質的負荷や成長機会が乏しい職場
→質的負荷の高い仕事を、いかに量的負荷や関係負荷なく与えるか
※現状では、「質的負荷の高い仕事」は、「関係負荷が高い」
・「最低必要努力投入量」(金井名誉教授):一つの分野で優位性を持てる専門性を確立するには、一定の時間・一定の努力量が必要(単に量のみならず質×量による努力量と解される)
→働き方改革以降の職場においては、何年経っても最低必要努力投入量に達しないことを踏まえ、以下のポイント
①企業がもたらす機会だけでは育てきれない、若手の自主性が尊重及び要請される:
若手の自己開示をいかに促すか
→外の経験について開示を受けなければ、効果的な支援や外部経験を活かしたアサイメントが不可能なため
②上司やマネージャーだけに若手育成の責任を押し付けない:
若手育成の難易度が跳ね上がったため、社内横断的な視点や外部のキャリアコンサルタントの意見も取り入れた仕組みに変革する必要がある。さらには、職場の外で育てる仕組みを導入すべき
![]() 副業・兼業だけでなく、勉強会や若手コミュニティといった社内だが職場の外という場も活用できる
副業・兼業だけでなく、勉強会や若手コミュニティといった社内だが職場の外という場も活用できる
若手育成についても「支援者支援」が必要で、管理職をいかに支えるかが組織の課題
③若者が何かを始めるためのきっかけが重要:
Z世代の二極化、自主性のある若手とない若手の間で大きな機会格差が生じる。「やりたいことを見つけろ」というだけでは変わらない、やりたいことを探すための最初の一歩をどう促すかがポイント![]() スモールステップを促すためのきっかけ(言い訳の提供)が必要
スモールステップを促すためのきっかけ(言い訳の提供)が必要
「同僚に誘われたから参加した」「上司に行けと言われてセミナーに参加した」など周りが仕掛け、一歩踏み出した若手を評価してもいい
※「自律」は行動の結果に過ぎず、自律性・自主性を生み出すための体験・経験を支援について議論しなければならない
④若者だけに考えさせない:
・「自己責任論」にしてはならない、昔は育つ環境があった
・本人の合理性を超えたジョブアサインが必要:本人の希望に沿ったキャリアパスを用意する限り、その個人の想像する以上の機会や経験は得られないから![]() 偶発的な出来事がキャリア形成において大きな役割を果たす
偶発的な出来事がキャリア形成において大きな役割を果たす
かつての日本企業が強制的に人事異動を発令していた偶発性には、前近代的なものも多いものの、全てが悪い経験だったと切り捨てるのは難しい。当事者の合理性には当然ながら、主観的な認識の持つ限界があるため、本人の納得感を得ながらいかにそれ以上の機会や経験を付与していくかが最大の育成論題となる
⑤「ゆるさ」に対する主観と客観の問題:客観的にはゆるくても本人的にはきついこともある
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
入社前の社会的経験が予想以上に広がっており、これが若手育成の非常に厄介な状況を浮き彫りにしている
→同じ社内でも若手社員の企業・職場観の多様になり混在している。入社前の社会的経験により、会社に対する見切りの早さが判断材料に(入社前の社会的経験が多い層ほど、離職率が高いことからも証明されている)
=自社のことを高く評価し、活き活きと業務に向かっているハイパフォーマーな若手が、必ずしも定着しているわけではなく辞めやすいという厄介な複雑性を表している
※バックグラウンドが全く異なる、効果的な育成アプローチが全く異なる若手が交じり合っており、学歴などでは判別がつきづらい状態
①囲い込み策は無意味
・外の世界を見せないことは、エンゲージメントを低める
副業・兼業や社外活動の経験者は、未経験の者よりも自社への評価が高い
=他社と比べて初めて、自社の良いところがわかるから(人間にとって当たり前のこと)
・会社が自分の挑戦を後押ししてくれた信頼感から、現職の会社に本気で貢献したいと思う気持ちも出てくる(give&takeの循環が回り出す)
・外から自社を客観的に見ることで、自社の強みを再確認することもある、外の経験がもたらした視点は、自社の見方をも変える力がある
②短距離走にする
20代のうちの他社選択のタイミングが来てしまうZ世代にとって、目に見えるところにゴールテープを張らないとハイパフォーマーな若手の職業人生プランには組み込まれがたい
③褒めるだけでなくFBする
データでは、たくさん若手を褒めたたえたりしているが、FBや指導はあまりしていないマネージャー層が存在。褒めないよりは褒めた方がいいが、それだけでは不十分。褒めるだけのマネージャーより褒めないがFBや指導だけ行うマネージャーの方が若手育成の成功率が高くデータで証明されている
・業務で用いる技術やスキルについての教育・訓練
・業界知識や無事ネス教養といった基礎知識の提供
・人事評価に基づいた仕事で改善すべき点についてのコミュニケーション
・今度のキャリアづくりに関するアアドバイス
④本人の合理性を超えた機械を提供する
やりたいことがある若手の弱点は、「現在地と目標の間にあると本人が認識している機械が、本人が“機会”と認識できないこと」
早期の段階で明確なキャリアビジョンがあること自体は努力の証であり、内発的動機付けも強いのでよいことだが、問題は、企業側が「やりたいこと」を若手に要請することが完全無欠の解決策ではないということを、まだ企業側も若手側も認識できていないこと
その時々では本人にとって必要でなかったり、合理的でなかったりする機会だとしても、後々のキャリア形成に効いてくる経験はけっこうある。転勤先で出会った企業や人をきっかけにキャリアが拓けた経験を、どうやって若手に提供していけばよいか
やりたいことは尊重しつつ、加えて本人の視野に入っていない機会を経験するきっかけを身近なマネージャーが提供すること
→キャリア形成における「行動」には、「やったもん勝ち」に近いような利益があるが、それを実感できるのは行動したことがある人だけ。最初の一歩を踏み出したことがない人には何といっても伝わることはない。やればわかるが、伝わらないジレンマがある
→スモールステップをするための言い訳を与えてあげること
・キャリア自律が重要だからこそ、最初の一歩目は自律性に依拠しない方策が必要となる
・やりたいことが「ない」若手にとってはつらく苦しく、やりたいことが「ある」若手との差が広がる一方。本人の意思だけを行動の動機にするのではなく、本人の力のせいだけにしない仕掛けをつくること。モヤモヤした不安を抱えるものの行動できない若手を動かすための処方箋
・他律でも良いので、まずは行動量を増やす
・若手のわがままを聞くだけでは若手の不安は解消されない
⑤一緒に悩み、行動すること
・若手育成実感が高いマネージャーは、「自身も越境しているマネージャー」という特徴を持っている
・職場で仕事をしているだけでは若手のロールモデルにはなれない
・バリバリ仕事ができることもすごいことだが、キャリア形成上、職場だけで仕事ができることの魅力は低下。「職場の外でも活躍できる変な人と働けて刺激的でハッピー」という若手の声
※大事なのは、越境活動していることを開示していること。マネージャー側が開示しないと、若手はオープンにしない、開示した方が得なんだという状況をつくること。さらに、越境活動に至るための悩みを開示できていることが重要。マネージャー自身も悩みながらキャリアを作ってきた結果、越境して自身のキャリアを太くしている姿を見せる。近年のリーダーシップ像は変容しているので、上司のキャリア形成の悩みまで共有ができれば、若手側も開示しやすくなる
⑥伴走ではなく「ひと手間」かける
1ヶ月に2Hコミュニケーションをとるよりも1週間に30分話す方が放置感は低い
→1日5分間のコミュニケーション習慣は究極のアンチ放置手法
時間コストは変わらない。内容はなんでもいい
⑦マネージャーだけでは若手を育てられない、育成専門職の設置が必要
⑧ハイメンバーシップ型組織
・アルムナイ(卒業生=退職者)のコミュニティ化に着手する会社も増加
・自社にメンバーシップを感じている人財のすそ野を広げる
・その会社が活かせる人材は、別にその会社に毎日通っている社員に限らない
・「ポジティブ退職者」を関係社員と活用することで、辞めてもその会社に参画できる、育てたことが絶対に無駄にならない組織になれるというブレイクスルーを起こせる
なぜ自分は辞めないのかを考えて「転職しないことを選ぶ」という選択的在職の重要性が浮上する
今日もお読み頂きありがとうございます![]()