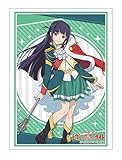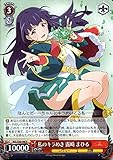今日の一曲!露崎まひる、愛城華恋「恋の魔球」【'18夏アニメ・アニソン(格好良い系)編・その1】
【追記:2021.1.5】 本記事は「今日の一曲!」【テーマ:2018年のアニソンを振り返る】の第十四弾「夏アニメ・格好良い系」編・その1でしたが、後に『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』編に改めました。【追記ここまで】
第十三弾までにはなかった「その1」が付されていることからも察せるように、本記事は特殊な内容となっています。従来に行っていた冒頭での趣旨説明 ― 2018年の夏アニメ(7月~9月)の主題歌の中から、「アニソン(格好良い系)」に分類される楽曲をまとめて紹介します。本企画の詳細については、この記事の冒頭部を参照。 ― に間違いはないのですが、筆が乗りに乗った結果、ひとつの作品を取り立てるだけで限界文字数に達してしまったため、【'18夏アニメ・アニソン(格好良い系)編】は二記事に分割することにしました。
説明通りの内容となるのは寧ろ次の第十五弾で、今回お送りする第十四弾は【少女☆歌劇 レヴュースタァライト編】であるとご理解いただければ幸いです。
―
メインで取り上げる「今日の一曲!」は、露崎まひる(CV:岩田陽葵)、愛城華恋(CV:小山百代)の「恋の魔球」(2018)です。アニメ第5話の劇中歌で、上掲の『「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」劇中歌アルバムVol.1「ラ レヴュー ド マチネ」』に収められています。
公式に「ミュージカル×アニメーションで紡ぐ、二層展開式少女歌劇」と謳われているだけはあって、その音楽のクオリティは非常に高度なものでした。実は一昨年の振り返りでも【CM編】としてスタァライト九九組の「Star Divine」(2017)を簡単にレビューしていて、同曲は作品の持つポテンシャルの大きさを充分に感じさせる素晴らしい出来でしたが、この時に覚えた期待を上回る良曲の数々が、アニメでは披露されていたと評しています。
従って、本記事は「特集」のスタイルで書き進めていくのがベターだと判断しました。タイトルに据えた一曲に限らず、作品の音楽について全般的に紹介していこうという意味です。そうなるとブログテーマの分散は好ましくないため、通常であれば「格好良い系」以外に分類するであろうナンバーも、例外的に本記事にてまとめる形でレビューすることにしました。とはいえ、作品に於ける殆どの楽曲が確かな格好良さを備えているので、逸脱するものはそう多くないはずです。
重ねて注意喚起しますと、僕は舞台版を観劇したことはありませんし、ゲームアプリ版(略称『スタリラ』)もプレイしたことがないため、特集と言っても作品理解については浅く、あくまでも音楽とアニメにフォーカスした内容であることを予め断っておきます。「それなら'全般的'と銘打たなければいいのでは?」と思われたかもしれませんが、未経験ながらに舞台およびゲームの楽曲にも言及するため、このような言い回しとなりました。
筆者の立場を明らかにする意味でも、こうして一応の予防線を張っておきましたが、少なくともアニメ版に関しては知識があるため、楽曲のレビューに入る前に簡単な作品語りをします。録画をざっとは確認しましたが、半年前の記憶を呼び起こしつつとなるので、設定や時系列に反した変なことを書いていたらすみません。
また、自分でもややこしいと思ったゆえに解説しておきますと、本記事に登場する「レビュー」と「レヴュー」は異なるものを指しているとご了承願います。前者は「批評・評論」を表す一般的な語彙使用(英:review)で、後者は本作に於いて「秘密の公演」を意味する用語(仏:revue)です。詳細は【公式サイト → ストーリー → ページ下部のKEYWORDの項】を参照してください。
アニメの第1話には素直に引き込まれました。てっきり王道のミュージカルモノというか、現実的な世界観に基いて演劇を描く作品かと思っていたので、地下劇場に入り込んでからのフィクションが極まった展開および画作りには、アニメという表現媒体を存分に活かした良さがあって、面白そうな予感を抱かせるのには充分のつかみだったと言えます。レヴュー名と曲名が文字情報として大きく表示されるのも、『新世紀エヴァンゲリオン』的な美学のある好みのタイポグラフィでした。
しかしその後、具体的に言うと第6話までは、内容に不安を覚えていたことを白状します。ここまでの言葉を借りれば、「現実的な」要素(=聖翔祭へ向けての表向きの描写)と、「フィクションが極まった」要素(=キリンのオーディション)が、関連性がよくわからないままに同時進行していくため、「一体この娘たちは何を目指して何をやっているんだ?」との疑問が話毎に強まっていたからです。ただ、偏見も込みの自論ですが、この手の突飛さがあるのもミュージカル作品の魅力だよなという思いも持ち合わせていたので、「どう着地させる気なんだろう?」といった類の期待は継続していました。
このように途中まではやや斜に構えた観方をしていたのですが、そんなもやもやは第七話で全て吹き飛ぶことになります。ネタバレになるので詳しいことは書きませんが、自分が想定していた「フィクション」のレベルを優に超えてくる文字通りの超展開を前にして、作品へのそもそもの向き合い方が間違っていた(誉め言葉)と、態度を改めざるを得ませんでした。ファンタジー要素があるのは重々承知ながらも、視聴者に求められる水準は更に高かったということに対する驚きです。なお、ここまでに使用してきた「極まった」という表現は、第七話以降の展開も含めての語彙選択だと補足しておきます。
そこから先は毎話が楽しみとなりました。作中設定や舞台背景が明らかとなり、各人がキリンのオーディションで何を得た、或いは得ようとしているのかを把握した上で鑑賞して、初めて真の面白さに迫れる仕掛けが施されていたことに感服です。周回視聴が推奨される作品だったとも換言出来るため、前半で脱落してしまった人や、ミュージカルモノに苦手意識がある人でも(僕は元々そういうタイプでした)、まずは通しで観てみることをおすすめします。
ここからが漸く「恋の魔球」のレビューです(上掲動画内3:21~)。冒頭にも記したように、同曲はアニメ第5話に使用されたレヴューソングとなります。その時点での作品に対する評価は先に書いた通りですが、同エピソードに於けるレヴューの描き方にはある種の狂気じみたものを感じたので、実は真に引き込まれたのはこのタイミングだったのかもしれません。
そんな第5話はまひるがメインのお話で、演目名は「嫉妬のレヴュー」でした。作中のまひるの台詞「元に戻ってよ。神楽さんが来る前の華恋ちゃんに。」が示しているように、両者の信頼関係に対する彼女の嫉妬心が爆発した回ですが、この時の対戦相手は華恋であったため、ひかりのへの敵愾心よりも華恋への想いの丈にフォーカスした描き方になっていた点が、より一層の切なさを演出していたと言えます。
それはレヴュー冒頭のまひるによる一人芝居からも犇々と感じられ、アーティスト名こそまひると華恋のデュエット曲を思わせる表示ですが、均等配分のナンバーというよりかは「まひるのキャラクターソング」と認識するのが据りがいいであろう、パーソナルな仕上がりです。"まわるまわるデュエットで/疲れるまで踊りましょう"や、"キミがいなきゃ私は/なんにも無くなるんだよ/ゲームを終わらせないで"などの歌詞も、あくまでもまひるからのサジェストに主軸が置かれた内容なので、一方通行の向きが強くグサッときます。
…と、このような書き出しにすると「なんて切ない曲なんだ!」といった感想が優勢になりそうですが、登場人物間の事情や歌詞の機微とは裏腹に、本曲から受ける印象は寧ろ明るいものであるところが真に面白いポイントです。
まひるの嫉妬心が開き直りに近い段階にまで進んでいたことや、矛先がひかりではなく華恋に向いていたこと、そして楽曲およびレヴューのオチが「まひる自身が気付いていなかった己の価値を華恋に説かれることで救われる」というポジティブなものであることも加味すれば、暗い楽想にならないであろうことには得心がいきます。ラスサビ以降は素直に二人のデュエットソングと言っていいでしょうしね。
しかし、本曲にアッパーなステータスを付与した最大の功労者は「野球要素」だと分析していて、ここまでに提示した下地に対しては意外とも言える方面からのアプローチが(実際はまひるの野球観戦好きを解釈したからでしょうが)、レヴューの狂気性やカオスを助長していたと見ています。アニメ語りに記した「突飛さ」にも関係することですが、「嫉妬のレヴュー」は思わず笑ってしまうほどに野球の演出が冴えていたので、良い意味で「このアニメ頭おかしい」と、視聴を繋ぎ止めてくれた好リリーフだと評しています。笑
「恋の魔球」という曲名もまさにですが、歌詞には"敬遠"、"消える魔球"、"空振り"、"ゲーム"、"ストレート"、"芝生"などの野球に関連するワードが登場しますし、ブラスが印象的なグルーヴィーな編曲は吹奏楽による応援を彷彿させ、「嫉妬」をテーマにしているとは思えないほどの爽やかなギャップが心地好いです。更に補強をするならば、まひるが幼い頃からバトンをしていたという設定も、応援のファクターとして解釈されたのかなと妄想しています。こうしてあれこれと取っ掛かりは見出せますが、作品の持つスポ根的な側面にマッチしたことが功を奏したのではないでしょうかね。
歌始まりまで2分以上ある焦らす楽想も好みで、これはアニメに於いては歌唱の前に口上や会話のパートがある(先の「まひるによる一人芝居」もその一部)からこその産物ですが、アニメ放送前の発表会で語られた内容をソースとするに、本作には「フィルムスコアリング」という「映像のほうに合わせて音楽を作る手法」が採用されているようなので、より正しく評価するには映像も込みで語ることが推奨されます。
しかし、敢えて楽曲のみを取り立てた好みを主張しますと、2分近く溜めた後に来る第一声(最初の歌詞)が、"ちょっと待って"であることに良さを見出していて、楽想に対する自己言及的な可笑しさも勿論ありますが、まひるの「変わっていく華恋のスピードに追い付けないもどかしさの顕れ」のようにも解釈出来るので、素晴らしい立ち上がりだと絶賛したいです。"ちょっと待って"の後にまた少し間が空くのも意味深で、この歌詞だけが独立していることを考慮すると、すぐに次の言葉を継げない「息切れの感」を滲ませているとも受け取れます。
この素敵な歌詞を手掛けたのは中村彼方さん。今回の振り返りでは第七弾にもお名前を出していますが、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』の関連楽曲の殆どは彼女によって作詞されています。
中でもこの「恋の魔球」の歌詞には衝撃を受けました。当該の一節は2番サビに登場する、"ねえ 私だけを見ててよ/ほら小さな光なんて/真昼になれば消えてしまう"です。華恋を変えてしまったひかりに対するまひるの言葉としては、これ以上の宣戦布告はありませんよね。ここだけは「ひかりのへの敵愾心」も「嫉妬」も剥き出しでゾクっときたのですが、名前を使った比喩表現に落とし込んでいるのが巧くて、黒い感情を上品に曝け出す鮮やかさに惚れ惚れしました。
素直に言葉だけを読み解いても味があって、並の感性であれば"小さな光";換言して夜の星は「希望の象徴」として扱うのが正道だと思いますが、「そんなものは太陽が照らしてしまえば等しく無に帰す」という、より大きな存在をぶつけて覚醒を促すやり口に、まひるの愛の強さを見た気がします。
外見的なデザインや作中での立ち回り方で露崎まひるというキャラクターを判断すると、個人的には正直あまり好きなタイプではなかったのですが、本曲の出色の出来栄えが好材料となって、今では彼女を応援したい気持ちすら芽生えているため、この変遷は音楽による成功を如実に示していると言えないでしょうか。
作編曲のクレジットを見ると、作曲には小高光太郎さんとUiNAさんの二名が、編曲には藤井亮太さんと小高さんと谷ナオキさんの三名が掲載されていて、携わっている人数の多さが作品随一であることからも、「恋の魔球」に対する全力投球のほどが伝わってくるというものです。ちなみに小高さんに関しては、過去にこの記事の中で氏が手掛けた音楽について言及したことがあるので、参考までにリンクしておきます。
今回のレビューではあまり音楽的な観点からの掘り下げを行いませんでしたが、聴けば聴くほどに各楽器が奏でているフレーズの細かさや、主旋律に宿る熱さと美しさが共に際立ってくるような高い完成度を誇っているため、全ての要素が華麗に噛み合った名曲だと評すほかありません。
主に格好良さに焦点をあてた書き方をしてきましたが、最後の爽やかでキュートな"ハイ"に全て持っていかれるといった感想もまた真なりと思う自分も居るので、「嫉妬」に絡む全方向の感情(芽生えから解消まで)が内包されているとまとめます。
―
続いて紹介するのはアニメのOP曲・スタァライト九九組「星のダイアローグ」(2018)です。作品の顔として、もしくは主題歌としての役割が意識されてか、ミュージカルらしい複雑な楽想を持っていた劇中歌とは異なり、わかりやすい格好良さと聴き易さを兼ね備えたナンバーだと言えます。
作編曲を担ったのは本多友紀さんで、一昨年の振り返りで取り上げた「Star Divine」も氏が手掛けた楽曲でしたが、リンク先の記事中に記した「こういう世界観の作品にとっては王道(中略)正統派の良い仕事」との評は、本曲に対しても異論はなしに適応可能です。
上掲記事ではふれ損ねていたのでついでに補足しておきますと、「Star Divine」はCメロの格好良さをいちばん買っていて、特に"それは運命(さだめ) それは本能"の華麗過ぎる旋律は、イヤガズムを覚えるほどであると、本多さんの手腕に信頼を置くに至ったパートです。より細かく言えば、二回目の"それは"に宿る陶酔感が神懸っていて、こちらのナルシズムまで刺激されるところが好みでした。「星のダイアローグ」に関しても、メロの流麗さに光るものを感じたため、作品に必要なトラックメイカーの一人であることに疑いはないでしょう。
アレンジ面でも本多さんの構成力が冴えていて、イントロから受ける文字通りの幕開け感、木管を経てから走り出すトラック、鼓笛隊然としたドラムスによってビートが印象を変えるBメロ、ストリングスとコーラスワークが主旋律の流麗さに溶け込んでいるサビ、2番後間奏~ラスサビにかけての物語性、荘厳なクロージングが醸す余韻等々、こちらが期待する'らしい'要素はおさえられているといった印象です。
歌詞ではラスサビのものが最も好みで、"あの頃には戻れない/何も知らなかった日々/胸を刺す衝撃を/浴びてしまったから/あの時キミも見たでしょう/弾けた星のキラめき"から伝わる、不退転の決意とその意識の共有は、歌劇の世界の厳しさと美しさを表しているようで、非常にエモいと思います。
―
本多さんが制作に携わったナンバーを補足的に紹介しますと、2018年中にリリースされた楽曲の中では、他に「舞台少女心得 幕間」(作曲)と「ディスカバリー!」(作編曲)もお気に入りでした。
前者はアニメ第11話の劇中歌で、スタァライト九九組の「舞台少女心得」(2017)を元としたアナザーバージョンです。上掲の『「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」劇中歌アルバムVol.2「ラ レヴュー ド ソワレ」』に収録されています。
ひかりの不在や歌詞の省略による違いもありますが、異なるアレンジャーによって歌唱と旋律を際立たせた編曲になっていることも大きく、既出曲であることも忘れて新鮮な心持で聴き惚れてしまいました。メロディの端麗さと歌詞の直向きさが、一層の輝きを放つようになったと感じます。ひかりの喪失を埋めようとする形で、それらが強まっているのかもしれませんね。
後者は『星のダイアローグ』のc/w曲で、アプリ版の主題歌です。冒頭にも書いた通り僕は『スタリラ』未プレイ勢ですが、CMで少し聴いただけでも同曲のキャッチーさには惹かれるものがありました。ゲームらしいバトルやアドベンチャーの要素に重きを置いたのかなと想像させる未来志向の仕上がりで、敢えて言えば普通のアニソンっぽい気もしますが、出す曲出す曲全てに歌劇の趣を付与しなくともいいと考えているため、こういう方向性もアリだと判断します。
他に「スタァライトシアター」と「キラめきのありか」も2018年の本多友紀ワークス(どちらも作曲者にクレジット)で、ここでは曲名の紹介だけにとどめますが、何にせよ先述の「作品に必要なトラックメイカーの一人である」とのクリエイター評は、既に揺るぎないものになっていると思います。
―
お次は神楽ひかり(CV:三森すずこ)、大場なな(CV:小泉萌香)の「RE:CREATE」(2018)をレビュー。アニメ第8話の劇中歌(上掲動画内0:00~)です。昨年リリースされた2枚の劇中歌アルバム、『マチネ』では「恋の魔球」が個人的なトップヒットナンバーでしたが、『ソワレ』での最大のお気に入りは本曲で、僕の中ではこの両曲が一二を争っています。
プログレッシブな楽想を持った実にミュージカルらしいトラックで、長めの間奏を挟んで次々と新しいメロディが顔を出しては消えて行くストーリー性に富んだ展開は、音楽だけには収まりきらない熱量を多分に含んでいることの証左だと絶賛したいです。
この複雑性はアニメでの使われ方を観れば納得で(以降では少し突っ込んだ言及をするのでネタバレ注意)、「ひかり vs ばなな」はある意味ラスボス対決と見てもいいカードであるため、強大な思い同士が激突するレヴューに於いては、刻一刻と状況は変化して二度と同じ様相を呈することはない…というような美学が、楽曲にも反映された結果だと解釈しています。
そんなアニメでの描かれ方ですが、これが途轍もなく格好良くて痺れました。まずこのカードが「孤独のレヴュー」の題字で幕を開けることからして鳥肌ものです(ばなな回の次なので余計に)。両者の剣戟の応酬から始まり、次第にばななが優勢となって赤く燃え盛る舞台。このままひかりが折れるかと思いきや、華恋との約束の成就に意外な解が存在すること(=華恋からの言葉)を糧にして、青き光を纏いし短剣が進化。まさかの第二幕「華、ひらくとき」が開演し、逆様に着水する東京タワー(=約束の象徴)によって上がった巨大な波柱で、画面を支配する色彩が青へと塗り替わっていく鮮やかな舞台演出。「キラめきの再生産」を果たしたひかりが、ワイヤーを使い熟してばななを圧倒し、ポジションゼロを奪取するというフィナーレ。
このドラマチックさが、レヴューソング「RE:CREATE」にも、フィルムスコアリングによってそのままパッケージされていると言いたいのでした。歌詞の流れ(前述の「二度と同じ様相を呈することはない」に寄与するもの)も、ここに示した展開を踏襲するものとなっていて、両者の思いが交錯する立ち上がり("誓った約束のため"~)、ばななのターン("悲しみで廻る世界にさよならを"~)、ひかりの回想シーン("始まりの訪れは不意で"~)…からの覚醒シークエンス("二人の夢が開くわ")、ひかりのターン("一緒に幼い日"~)と、高い戯曲性を誇る音楽であることにも納得です。
このようにどの場面を切り取っても画になる楽曲であるため、全てのセクションが好きと言っても過言ではないのですが、敢えて細かいツボを挙げるとするならば、"始まりの訪れは不意で"と、"もう負けない 諦めない"に続く旋律には、歌詞通りのドキドキやメラメラが窺えて好みのラインでした。
アレンジ面では、第一に0:30~1:03/1:47~1:57/3:06~3:24/4:34~4:47で度々登場する、電子系のサウンドによる意外性。第二に2:14~2:40で主旋律を踏襲していたピアノが、2:41から異なる展開にシフトした際に覚える、止まっていた時間が動き出した感。第三に3:25~3:33でボーカルの跳ね感を演出している、鍵盤によるグルーヴィーなバッキング。第四に4:57~5:22のオケが最も輝いている、瑞々しくシンフォニックなセクション。第五に5:40~5:50で鳴り響く、勝利と祝福を告げるような鐘の音が予感させるクライマックス。…などが、タイムを表示してまで特筆したいお気に入りの箇所です。
―
最後はその他のフェイバリットナンバーを雑多に紹介します。アニメのED曲「Fly Me to the Star」(2018)は、各話で歌い手が異なっていたため、楽曲が抱える激しい切なさを各人がどう歌い上げるのかといった観点での楽しみ方が可能でした。その中では変化球となりますが、ばなな回に歌なし(「Fly Me to the Star #7」)を持ってきたのはハイセンスが過ぎるだろうと思います。
同シングルの中では、c/wの「ロマンティッククルージン」(2018)もなかなかに好みでした。キャッチーな旋律とポップな音遣いによるアウトプットは、「ディスカバリー!」の項に書いた「普通のアニソンっぽい」感じを更に強めたような、ある意味ではらしくない仕上がりな気もしますが、嫌いではありませんし、作品のイメージを損なうものでもなかったので、作品自体の包容力と展開可能性が高いのだろうと推測します。
舞台の1stシングル曲「99 ILLUSION!」(2018)にも、CMで聴いて良いと思ったゆえに手を出してみましたが、同曲も「Star Divine」や「星のダイアローグ」に匹敵するレベルで、作品の世界観を王道に反映させた、歌劇にぴったりの良曲でした。男声も入れたコーラスの圧の強さは、流石に舞台用にチューンされているなと感じましたけどね。
―
字数制限の都合上割愛しようとしたものの、やはり言及したくなってしまったため、本当のラストとして星見純那(CV:佐藤日向)、愛城華恋(CV:小山百代)の「The Star Knows」を簡単にレビューします(上掲動画内0:37~)。同曲は幕開けから終劇までの約6分間、ただただ険しいところが魅力で、キリンのオーディションが「奪い合い」であることを序盤で示すのに効果的な楽想であったと評せるでしょう。
迫真の歌声と鋭利なメロディラインが印象的な前半は、星見純那というお誂え向きの名前を持った少女の渇望の大きさと、放たれる矢の鋭さに圧倒されるような納得の仕上がりです。華恋との応酬が始まり二つの主旋律がぶつかり合う後半も、この時点では未だ状況に翻弄されるばかりであった華恋が、愈々真剣に目覚めなければならないと自覚したからか、荒っぽいボーカルディレクションを思わせる必死さがあって好みでした。
―
以上、【'18夏アニメ・アニソン(格好良い系)編・その1】、実質的に【少女☆歌劇 レヴュースタァライト編】でした。書き出す前から長くなる予感はありましたが、まさか一記事丸々を一作品に使うことになるとは予想外です。その代わり内容は非常に濃く出来たので、悔いはありません。
以降は「第n弾」の数字が当初の予定からひとつ後ろにずれるため、本企画の終了予定記事は第十九弾に変更となります。次は同クール同テーマの【その2】を執筆しなければならないため、未だに夏から抜け出せないのがもどかしいですが、この現状では全記事が書き終わるのは2月中のこととなってしまいそうですね。…すみません。
第十三弾までにはなかった「その1」が付されていることからも察せるように、本記事は特殊な内容となっています。従来に行っていた冒頭での趣旨説明 ― 2018年の夏アニメ(7月~9月)の主題歌の中から、「アニソン(格好良い系)」に分類される楽曲をまとめて紹介します。本企画の詳細については、この記事の冒頭部を参照。 ― に間違いはないのですが、筆が乗りに乗った結果、ひとつの作品を取り立てるだけで限界文字数に達してしまったため、【'18夏アニメ・アニソン(格好良い系)編】は二記事に分割することにしました。
説明通りの内容となるのは寧ろ次の第十五弾で、今回お送りする第十四弾は【少女☆歌劇 レヴュースタァライト編】であるとご理解いただければ幸いです。
―
 | 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」劇中歌アルバムVol.1「ラ レヴュー ド マチネ」 2,700円 Amazon |
メインで取り上げる「今日の一曲!」は、露崎まひる(CV:岩田陽葵)、愛城華恋(CV:小山百代)の「恋の魔球」(2018)です。アニメ第5話の劇中歌で、上掲の『「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」劇中歌アルバムVol.1「ラ レヴュー ド マチネ」』に収められています。
公式に「ミュージカル×アニメーションで紡ぐ、二層展開式少女歌劇」と謳われているだけはあって、その音楽のクオリティは非常に高度なものでした。実は一昨年の振り返りでも【CM編】としてスタァライト九九組の「Star Divine」(2017)を簡単にレビューしていて、同曲は作品の持つポテンシャルの大きさを充分に感じさせる素晴らしい出来でしたが、この時に覚えた期待を上回る良曲の数々が、アニメでは披露されていたと評しています。
従って、本記事は「特集」のスタイルで書き進めていくのがベターだと判断しました。タイトルに据えた一曲に限らず、作品の音楽について全般的に紹介していこうという意味です。そうなるとブログテーマの分散は好ましくないため、通常であれば「格好良い系」以外に分類するであろうナンバーも、例外的に本記事にてまとめる形でレビューすることにしました。とはいえ、作品に於ける殆どの楽曲が確かな格好良さを備えているので、逸脱するものはそう多くないはずです。
重ねて注意喚起しますと、僕は舞台版を観劇したことはありませんし、ゲームアプリ版(略称『スタリラ』)もプレイしたことがないため、特集と言っても作品理解については浅く、あくまでも音楽とアニメにフォーカスした内容であることを予め断っておきます。「それなら'全般的'と銘打たなければいいのでは?」と思われたかもしれませんが、未経験ながらに舞台およびゲームの楽曲にも言及するため、このような言い回しとなりました。
筆者の立場を明らかにする意味でも、こうして一応の予防線を張っておきましたが、少なくともアニメ版に関しては知識があるため、楽曲のレビューに入る前に簡単な作品語りをします。録画をざっとは確認しましたが、半年前の記憶を呼び起こしつつとなるので、設定や時系列に反した変なことを書いていたらすみません。
また、自分でもややこしいと思ったゆえに解説しておきますと、本記事に登場する「レビュー」と「レヴュー」は異なるものを指しているとご了承願います。前者は「批評・評論」を表す一般的な語彙使用(英:review)で、後者は本作に於いて「秘密の公演」を意味する用語(仏:revue)です。詳細は【公式サイト → ストーリー → ページ下部のKEYWORDの項】を参照してください。
アニメの第1話には素直に引き込まれました。てっきり王道のミュージカルモノというか、現実的な世界観に基いて演劇を描く作品かと思っていたので、地下劇場に入り込んでからのフィクションが極まった展開および画作りには、アニメという表現媒体を存分に活かした良さがあって、面白そうな予感を抱かせるのには充分のつかみだったと言えます。レヴュー名と曲名が文字情報として大きく表示されるのも、『新世紀エヴァンゲリオン』的な美学のある好みのタイポグラフィでした。
しかしその後、具体的に言うと第6話までは、内容に不安を覚えていたことを白状します。ここまでの言葉を借りれば、「現実的な」要素(=聖翔祭へ向けての表向きの描写)と、「フィクションが極まった」要素(=キリンのオーディション)が、関連性がよくわからないままに同時進行していくため、「一体この娘たちは何を目指して何をやっているんだ?」との疑問が話毎に強まっていたからです。ただ、偏見も込みの自論ですが、この手の突飛さがあるのもミュージカル作品の魅力だよなという思いも持ち合わせていたので、「どう着地させる気なんだろう?」といった類の期待は継続していました。
このように途中まではやや斜に構えた観方をしていたのですが、そんなもやもやは第七話で全て吹き飛ぶことになります。ネタバレになるので詳しいことは書きませんが、自分が想定していた「フィクション」のレベルを優に超えてくる文字通りの超展開を前にして、作品へのそもそもの向き合い方が間違っていた(誉め言葉)と、態度を改めざるを得ませんでした。ファンタジー要素があるのは重々承知ながらも、視聴者に求められる水準は更に高かったということに対する驚きです。なお、ここまでに使用してきた「極まった」という表現は、第七話以降の展開も含めての語彙選択だと補足しておきます。
そこから先は毎話が楽しみとなりました。作中設定や舞台背景が明らかとなり、各人がキリンのオーディションで何を得た、或いは得ようとしているのかを把握した上で鑑賞して、初めて真の面白さに迫れる仕掛けが施されていたことに感服です。周回視聴が推奨される作品だったとも換言出来るため、前半で脱落してしまった人や、ミュージカルモノに苦手意識がある人でも(僕は元々そういうタイプでした)、まずは通しで観てみることをおすすめします。
ここからが漸く「恋の魔球」のレビューです(上掲動画内3:21~)。冒頭にも記したように、同曲はアニメ第5話に使用されたレヴューソングとなります。その時点での作品に対する評価は先に書いた通りですが、同エピソードに於けるレヴューの描き方にはある種の狂気じみたものを感じたので、実は真に引き込まれたのはこのタイミングだったのかもしれません。
そんな第5話はまひるがメインのお話で、演目名は「嫉妬のレヴュー」でした。作中のまひるの台詞「元に戻ってよ。神楽さんが来る前の華恋ちゃんに。」が示しているように、両者の信頼関係に対する彼女の嫉妬心が爆発した回ですが、この時の対戦相手は華恋であったため、ひかりのへの敵愾心よりも華恋への想いの丈にフォーカスした描き方になっていた点が、より一層の切なさを演出していたと言えます。
それはレヴュー冒頭のまひるによる一人芝居からも犇々と感じられ、アーティスト名こそまひると華恋のデュエット曲を思わせる表示ですが、均等配分のナンバーというよりかは「まひるのキャラクターソング」と認識するのが据りがいいであろう、パーソナルな仕上がりです。"まわるまわるデュエットで/疲れるまで踊りましょう"や、"キミがいなきゃ私は/なんにも無くなるんだよ/ゲームを終わらせないで"などの歌詞も、あくまでもまひるからのサジェストに主軸が置かれた内容なので、一方通行の向きが強くグサッときます。
…と、このような書き出しにすると「なんて切ない曲なんだ!」といった感想が優勢になりそうですが、登場人物間の事情や歌詞の機微とは裏腹に、本曲から受ける印象は寧ろ明るいものであるところが真に面白いポイントです。
まひるの嫉妬心が開き直りに近い段階にまで進んでいたことや、矛先がひかりではなく華恋に向いていたこと、そして楽曲およびレヴューのオチが「まひる自身が気付いていなかった己の価値を華恋に説かれることで救われる」というポジティブなものであることも加味すれば、暗い楽想にならないであろうことには得心がいきます。ラスサビ以降は素直に二人のデュエットソングと言っていいでしょうしね。
しかし、本曲にアッパーなステータスを付与した最大の功労者は「野球要素」だと分析していて、ここまでに提示した下地に対しては意外とも言える方面からのアプローチが(実際はまひるの野球観戦好きを解釈したからでしょうが)、レヴューの狂気性やカオスを助長していたと見ています。アニメ語りに記した「突飛さ」にも関係することですが、「嫉妬のレヴュー」は思わず笑ってしまうほどに野球の演出が冴えていたので、良い意味で「このアニメ頭おかしい」と、視聴を繋ぎ止めてくれた好リリーフだと評しています。笑
「恋の魔球」という曲名もまさにですが、歌詞には"敬遠"、"消える魔球"、"空振り"、"ゲーム"、"ストレート"、"芝生"などの野球に関連するワードが登場しますし、ブラスが印象的なグルーヴィーな編曲は吹奏楽による応援を彷彿させ、「嫉妬」をテーマにしているとは思えないほどの爽やかなギャップが心地好いです。更に補強をするならば、まひるが幼い頃からバトンをしていたという設定も、応援のファクターとして解釈されたのかなと妄想しています。こうしてあれこれと取っ掛かりは見出せますが、作品の持つスポ根的な側面にマッチしたことが功を奏したのではないでしょうかね。
 | 【露崎まひる】少女☆歌劇 レヴュースタァライト ぺたん娘 トレーディングラバーストラップ 1,380円 Amazon |
歌始まりまで2分以上ある焦らす楽想も好みで、これはアニメに於いては歌唱の前に口上や会話のパートがある(先の「まひるによる一人芝居」もその一部)からこその産物ですが、アニメ放送前の発表会で語られた内容をソースとするに、本作には「フィルムスコアリング」という「映像のほうに合わせて音楽を作る手法」が採用されているようなので、より正しく評価するには映像も込みで語ることが推奨されます。
しかし、敢えて楽曲のみを取り立てた好みを主張しますと、2分近く溜めた後に来る第一声(最初の歌詞)が、"ちょっと待って"であることに良さを見出していて、楽想に対する自己言及的な可笑しさも勿論ありますが、まひるの「変わっていく華恋のスピードに追い付けないもどかしさの顕れ」のようにも解釈出来るので、素晴らしい立ち上がりだと絶賛したいです。"ちょっと待って"の後にまた少し間が空くのも意味深で、この歌詞だけが独立していることを考慮すると、すぐに次の言葉を継げない「息切れの感」を滲ませているとも受け取れます。
この素敵な歌詞を手掛けたのは中村彼方さん。今回の振り返りでは第七弾にもお名前を出していますが、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』の関連楽曲の殆どは彼女によって作詞されています。
中でもこの「恋の魔球」の歌詞には衝撃を受けました。当該の一節は2番サビに登場する、"ねえ 私だけを見ててよ/ほら小さな光なんて/真昼になれば消えてしまう"です。華恋を変えてしまったひかりに対するまひるの言葉としては、これ以上の宣戦布告はありませんよね。ここだけは「ひかりのへの敵愾心」も「嫉妬」も剥き出しでゾクっときたのですが、名前を使った比喩表現に落とし込んでいるのが巧くて、黒い感情を上品に曝け出す鮮やかさに惚れ惚れしました。
素直に言葉だけを読み解いても味があって、並の感性であれば"小さな光";換言して夜の星は「希望の象徴」として扱うのが正道だと思いますが、「そんなものは太陽が照らしてしまえば等しく無に帰す」という、より大きな存在をぶつけて覚醒を促すやり口に、まひるの愛の強さを見た気がします。
外見的なデザインや作中での立ち回り方で露崎まひるというキャラクターを判断すると、個人的には正直あまり好きなタイプではなかったのですが、本曲の出色の出来栄えが好材料となって、今では彼女を応援したい気持ちすら芽生えているため、この変遷は音楽による成功を如実に示していると言えないでしょうか。
作編曲のクレジットを見ると、作曲には小高光太郎さんとUiNAさんの二名が、編曲には藤井亮太さんと小高さんと谷ナオキさんの三名が掲載されていて、携わっている人数の多さが作品随一であることからも、「恋の魔球」に対する全力投球のほどが伝わってくるというものです。ちなみに小高さんに関しては、過去にこの記事の中で氏が手掛けた音楽について言及したことがあるので、参考までにリンクしておきます。
今回のレビューではあまり音楽的な観点からの掘り下げを行いませんでしたが、聴けば聴くほどに各楽器が奏でているフレーズの細かさや、主旋律に宿る熱さと美しさが共に際立ってくるような高い完成度を誇っているため、全ての要素が華麗に噛み合った名曲だと評すほかありません。
主に格好良さに焦点をあてた書き方をしてきましたが、最後の爽やかでキュートな"ハイ"に全て持っていかれるといった感想もまた真なりと思う自分も居るので、「嫉妬」に絡む全方向の感情(芽生えから解消まで)が内包されているとまとめます。
―
 | 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」OPシングル 星のダイアローグ 1,499円 Amazon |
続いて紹介するのはアニメのOP曲・スタァライト九九組「星のダイアローグ」(2018)です。作品の顔として、もしくは主題歌としての役割が意識されてか、ミュージカルらしい複雑な楽想を持っていた劇中歌とは異なり、わかりやすい格好良さと聴き易さを兼ね備えたナンバーだと言えます。
作編曲を担ったのは本多友紀さんで、一昨年の振り返りで取り上げた「Star Divine」も氏が手掛けた楽曲でしたが、リンク先の記事中に記した「こういう世界観の作品にとっては王道(中略)正統派の良い仕事」との評は、本曲に対しても異論はなしに適応可能です。
上掲記事ではふれ損ねていたのでついでに補足しておきますと、「Star Divine」はCメロの格好良さをいちばん買っていて、特に"それは運命(さだめ) それは本能"の華麗過ぎる旋律は、イヤガズムを覚えるほどであると、本多さんの手腕に信頼を置くに至ったパートです。より細かく言えば、二回目の"それは"に宿る陶酔感が神懸っていて、こちらのナルシズムまで刺激されるところが好みでした。「星のダイアローグ」に関しても、メロの流麗さに光るものを感じたため、作品に必要なトラックメイカーの一人であることに疑いはないでしょう。
アレンジ面でも本多さんの構成力が冴えていて、イントロから受ける文字通りの幕開け感、木管を経てから走り出すトラック、鼓笛隊然としたドラムスによってビートが印象を変えるBメロ、ストリングスとコーラスワークが主旋律の流麗さに溶け込んでいるサビ、2番後間奏~ラスサビにかけての物語性、荘厳なクロージングが醸す余韻等々、こちらが期待する'らしい'要素はおさえられているといった印象です。
歌詞ではラスサビのものが最も好みで、"あの頃には戻れない/何も知らなかった日々/胸を刺す衝撃を/浴びてしまったから/あの時キミも見たでしょう/弾けた星のキラめき"から伝わる、不退転の決意とその意識の共有は、歌劇の世界の厳しさと美しさを表しているようで、非常にエモいと思います。
―
 | 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」劇中歌アルバムVol.2「ラ レヴュー ド ソワレ」 2,700円 Amazon |
本多さんが制作に携わったナンバーを補足的に紹介しますと、2018年中にリリースされた楽曲の中では、他に「舞台少女心得 幕間」(作曲)と「ディスカバリー!」(作編曲)もお気に入りでした。
前者はアニメ第11話の劇中歌で、スタァライト九九組の「舞台少女心得」(2017)を元としたアナザーバージョンです。上掲の『「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」劇中歌アルバムVol.2「ラ レヴュー ド ソワレ」』に収録されています。
ひかりの不在や歌詞の省略による違いもありますが、異なるアレンジャーによって歌唱と旋律を際立たせた編曲になっていることも大きく、既出曲であることも忘れて新鮮な心持で聴き惚れてしまいました。メロディの端麗さと歌詞の直向きさが、一層の輝きを放つようになったと感じます。ひかりの喪失を埋めようとする形で、それらが強まっているのかもしれませんね。
後者は『星のダイアローグ』のc/w曲で、アプリ版の主題歌です。冒頭にも書いた通り僕は『スタリラ』未プレイ勢ですが、CMで少し聴いただけでも同曲のキャッチーさには惹かれるものがありました。ゲームらしいバトルやアドベンチャーの要素に重きを置いたのかなと想像させる未来志向の仕上がりで、敢えて言えば普通のアニソンっぽい気もしますが、出す曲出す曲全てに歌劇の趣を付与しなくともいいと考えているため、こういう方向性もアリだと判断します。
他に「スタァライトシアター」と「キラめきのありか」も2018年の本多友紀ワークス(どちらも作曲者にクレジット)で、ここでは曲名の紹介だけにとどめますが、何にせよ先述の「作品に必要なトラックメイカーの一人である」とのクリエイター評は、既に揺るぎないものになっていると思います。
―
お次は神楽ひかり(CV:三森すずこ)、大場なな(CV:小泉萌香)の「RE:CREATE」(2018)をレビュー。アニメ第8話の劇中歌(上掲動画内0:00~)です。昨年リリースされた2枚の劇中歌アルバム、『マチネ』では「恋の魔球」が個人的なトップヒットナンバーでしたが、『ソワレ』での最大のお気に入りは本曲で、僕の中ではこの両曲が一二を争っています。
プログレッシブな楽想を持った実にミュージカルらしいトラックで、長めの間奏を挟んで次々と新しいメロディが顔を出しては消えて行くストーリー性に富んだ展開は、音楽だけには収まりきらない熱量を多分に含んでいることの証左だと絶賛したいです。
この複雑性はアニメでの使われ方を観れば納得で(以降では少し突っ込んだ言及をするのでネタバレ注意)、「ひかり vs ばなな」はある意味ラスボス対決と見てもいいカードであるため、強大な思い同士が激突するレヴューに於いては、刻一刻と状況は変化して二度と同じ様相を呈することはない…というような美学が、楽曲にも反映された結果だと解釈しています。
そんなアニメでの描かれ方ですが、これが途轍もなく格好良くて痺れました。まずこのカードが「孤独のレヴュー」の題字で幕を開けることからして鳥肌ものです(ばなな回の次なので余計に)。両者の剣戟の応酬から始まり、次第にばななが優勢となって赤く燃え盛る舞台。このままひかりが折れるかと思いきや、華恋との約束の成就に意外な解が存在すること(=華恋からの言葉)を糧にして、青き光を纏いし短剣が進化。まさかの第二幕「華、ひらくとき」が開演し、逆様に着水する東京タワー(=約束の象徴)によって上がった巨大な波柱で、画面を支配する色彩が青へと塗り替わっていく鮮やかな舞台演出。「キラめきの再生産」を果たしたひかりが、ワイヤーを使い熟してばななを圧倒し、ポジションゼロを奪取するというフィナーレ。
このドラマチックさが、レヴューソング「RE:CREATE」にも、フィルムスコアリングによってそのままパッケージされていると言いたいのでした。歌詞の流れ(前述の「二度と同じ様相を呈することはない」に寄与するもの)も、ここに示した展開を踏襲するものとなっていて、両者の思いが交錯する立ち上がり("誓った約束のため"~)、ばななのターン("悲しみで廻る世界にさよならを"~)、ひかりの回想シーン("始まりの訪れは不意で"~)…からの覚醒シークエンス("二人の夢が開くわ")、ひかりのターン("一緒に幼い日"~)と、高い戯曲性を誇る音楽であることにも納得です。
このようにどの場面を切り取っても画になる楽曲であるため、全てのセクションが好きと言っても過言ではないのですが、敢えて細かいツボを挙げるとするならば、"始まりの訪れは不意で"と、"もう負けない 諦めない"に続く旋律には、歌詞通りのドキドキやメラメラが窺えて好みのラインでした。
アレンジ面では、第一に0:30~1:03/1:47~1:57/3:06~3:24/4:34~4:47で度々登場する、電子系のサウンドによる意外性。第二に2:14~2:40で主旋律を踏襲していたピアノが、2:41から異なる展開にシフトした際に覚える、止まっていた時間が動き出した感。第三に3:25~3:33でボーカルの跳ね感を演出している、鍵盤によるグルーヴィーなバッキング。第四に4:57~5:22のオケが最も輝いている、瑞々しくシンフォニックなセクション。第五に5:40~5:50で鳴り響く、勝利と祝福を告げるような鐘の音が予感させるクライマックス。…などが、タイムを表示してまで特筆したいお気に入りの箇所です。
―
 | 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」EDシングル Fly Me to the Star 2,000円 Amazon |
最後はその他のフェイバリットナンバーを雑多に紹介します。アニメのED曲「Fly Me to the Star」(2018)は、各話で歌い手が異なっていたため、楽曲が抱える激しい切なさを各人がどう歌い上げるのかといった観点での楽しみ方が可能でした。その中では変化球となりますが、ばなな回に歌なし(「Fly Me to the Star #7」)を持ってきたのはハイセンスが過ぎるだろうと思います。
同シングルの中では、c/wの「ロマンティッククルージン」(2018)もなかなかに好みでした。キャッチーな旋律とポップな音遣いによるアウトプットは、「ディスカバリー!」の項に書いた「普通のアニソンっぽい」感じを更に強めたような、ある意味ではらしくない仕上がりな気もしますが、嫌いではありませんし、作品のイメージを損なうものでもなかったので、作品自体の包容力と展開可能性が高いのだろうと推測します。
舞台の1stシングル曲「99 ILLUSION!」(2018)にも、CMで聴いて良いと思ったゆえに手を出してみましたが、同曲も「Star Divine」や「星のダイアローグ」に匹敵するレベルで、作品の世界観を王道に反映させた、歌劇にぴったりの良曲でした。男声も入れたコーラスの圧の強さは、流石に舞台用にチューンされているなと感じましたけどね。
―
字数制限の都合上割愛しようとしたものの、やはり言及したくなってしまったため、本当のラストとして星見純那(CV:佐藤日向)、愛城華恋(CV:小山百代)の「The Star Knows」を簡単にレビューします(上掲動画内0:37~)。同曲は幕開けから終劇までの約6分間、ただただ険しいところが魅力で、キリンのオーディションが「奪い合い」であることを序盤で示すのに効果的な楽想であったと評せるでしょう。
迫真の歌声と鋭利なメロディラインが印象的な前半は、星見純那というお誂え向きの名前を持った少女の渇望の大きさと、放たれる矢の鋭さに圧倒されるような納得の仕上がりです。華恋との応酬が始まり二つの主旋律がぶつかり合う後半も、この時点では未だ状況に翻弄されるばかりであった華恋が、愈々真剣に目覚めなければならないと自覚したからか、荒っぽいボーカルディレクションを思わせる必死さがあって好みでした。
―
以上、【'18夏アニメ・アニソン(格好良い系)編・その1】、実質的に【少女☆歌劇 レヴュースタァライト編】でした。書き出す前から長くなる予感はありましたが、まさか一記事丸々を一作品に使うことになるとは予想外です。その代わり内容は非常に濃く出来たので、悔いはありません。
以降は「第n弾」の数字が当初の予定からひとつ後ろにずれるため、本企画の終了予定記事は第十九弾に変更となります。次は同クール同テーマの【その2】を執筆しなければならないため、未だに夏から抜け出せないのがもどかしいですが、この現状では全記事が書き終わるのは2月中のこととなってしまいそうですね。…すみません。