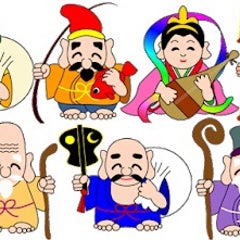音楽でも聴きながらご覧下さい。
おはようございます鉄太郎です。
昨日の我が熊本は朝から快晴でしたが、動いていない車のフロント硝子は凍ついていた。
私は寒さに負けず6時55分発(日頃より一本早いJRの電車)に乗車して朝の通勤をした。
デブなので寒さには強いのかも知れません。
さて、本日は日本の履き物文化についてお話いたしましょう。
日本の履物は縄文時代から使われていたそうだ。
縄文時代に使われていた履物は、足を包み込む「モカシン」のような形状だったといわれています。
(モカシンとは一枚の革で作られた靴みたいなもので、古来の原形は一枚革で足を包むようにされたもの。後にU字形の甲革を縫合するタイプかな?)
古代から使われていながら、靴よりも草履(ぞうり)が発達したことにはどのような理由があるのか?
まず、考えられるのが「家の中では靴を脱ぐ」という日本の文化。
家に出入りするときに履物を着脱しなければならないので、靴ではなく草履のほうが便利。
そのため、日本では靴よりも草履が発達したと考えられるのです。
また、日本ならでの気候も関係していると思われます。
我が日本では湿度が高く靴を履いていると足が蒸れてしまいます(水虫になる?)。
このことから、蒸れにくく通気性のよい草履が発達したと思われるのです。
もともと草履は天然のイ草で作られていますし、イ草素材の草履である。
イ草は吸水性に優れ、足の裏から分泌される汗や皮脂を吸収する働きがあり、長時間履いていても足の裏がべたつくことがないので、蒸れにくく快適に過ごすことができるのです。
また、しっかりとイ草が編みこまれているので程よい硬さがあり、健康的にもよいとされ、足の裏に適度な刺激が与えられることも、イ草を使った草履が人気の理由だったのかもしれません。
イ草は畳の原材料。最近は家に和室がないというご家庭も珍しくありませんが、昔は
イ草の草履なら、履いている間はずっと畳に触れ続けられ、畳の感触に落ち着きや癒しを感じると感じたのでしょう。
また、草鞋(わらじ)は、奈良時代に中国から藁の履物が伝わり、平安時代に爪先で鼻緒を挟むよう改良されて誕生したのが草鞋です。
稲ワラでつくられ、ヒモを足首まで巻きつけで結びます。 (江戸時代などの旅の履き物ですね)
また、木や竹の台に鼻緒をつけた履物が下駄です。 平安時代や奈良時代は地方の豪族が権威の象徴として履き、江戸時代は裕福な層が雨天時の汚れを防ぐために使用していたとされています。
また、下駄は日本の伝統的な履物で、古墳時代の中頃(約1500年前)に中国大陸から日本に伝わったとされています。
洋式文化の靴については、江戸末期から明治時代の初期コロナで、最初に洋式の靴を履いたのは、坂本龍馬だといわれています。
私はどちらかというと下駄派です。勤務先には履いて行けませんが、学生時代に新宿で米国人に「下駄」「下駄」と言われてネクタイと交換したことを思い出します。(酔っていたので帰りは西武新宿駅から裸足で乗車して帰宅した。人めは気にならなかったほど酔っていた)
私は高校時代から札付きのワルだったので下駄履きでしたね。
今はアメリカでは9.5インチ(日本では27.5センチ)の靴を履いています。
(足はデカいし体もデカい。更に態度もデカいです)
さて、本日は火曜日。本日も「明るく」「元気に」「笑顔で」過ごしていきましょう。
本日も皆様に少しの幸せが届くよう心よりお祈りいたしております。
鉄太郎。