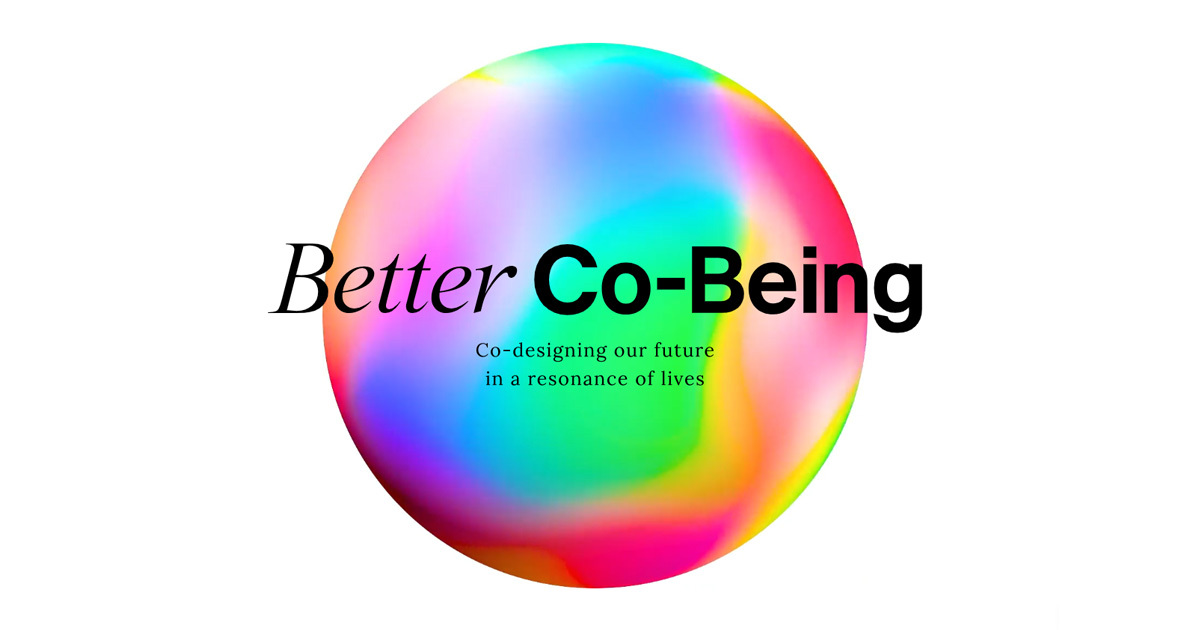先日、仕事帰りにふらっと大阪・関西万博へ。
今回の目的は…「EXPOサンセットビアテラス」!
西ゲートを入って右手、くら寿司を通り過ぎた先にある団体休憩所に、このサンセットビアテラスがあります。西エリアの活性化を目的に設けられた、期間限定の特設スポットです。
ビールが飲めるということで、夕方のんびり過ごすのにちょうどいいかも、と思って立ち寄ってみました。
風も光も、心地いい時間
私が訪れたのは18時すぎ。
ちょうど日が傾き始めるころで、夕焼けと海風が気持ちいい時間帯でした。
席は十分に空いていて、周囲を気にせずゆったり。
遠くには明石海峡大橋も見えて、まさに“サンセットビュー”を楽しめるロケーションです。
暑さが和らぐ夕方以降、ここでひと息つくのはかなりおすすめです。
食事はキッチンカー or 持ち込みスタイル。でもちょっと注意点も…
この日食べたのは「らぽっぽ」のキッチンカーで買った軽食。
お値段は…まぁ、“安定の万博価格”ですね(笑)。
このエリア、いわゆる「ビアガーデン」ではないので、クラフトビールがずらり並ぶ…みたいな感じではなく、ドリンクは限られた種類のみの販売でした。
「ビアテラス」という名前から、勝手にビール天国を想像していたので、ここはちょっと期待外れかも…。
ただ、周辺の西エリアでテイクアウトしたフードを持ち込んで食べることは可能。
一方で、万博会場内の他エリア(リング内など)からの持ち込みはNGのようです。
夕日と潮風を感じる“おとな時間”。混雑避けてまったり派に◎
-
開放的な席で夕景が楽しめる、特別感あるエリア
-
ドリンクの選択肢は少なめ。ビアガーデンとはちょっと違う
-
周辺でテイクアウトして持ち込むスタイルが◎
「がっつり食べて飲む!」というよりは、「夕日を眺めながらゆっくり過ごす」場所として活用するのが正解かもしれません。
のんびり派の方は、ぜひ一度立ち寄ってみてくださいね。
夕暮れの風景に癒されます。