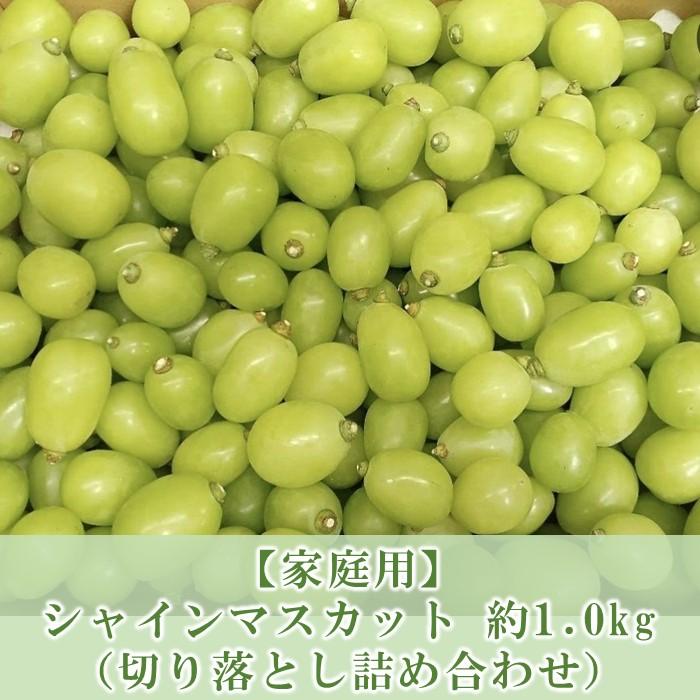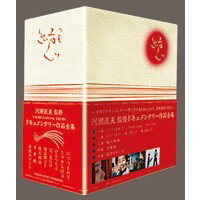平日午前、ひとりでリベンジ訪問
「関西パビリオン」には開幕間もない頃にも行ったのですが、そのときは事情があって館内を全部は見られず…。ずっと心残りになっていたので、先日、平日の午前にリベンジしてきました。
子どもは学校が始まっている時期。たまたま空いた一日を「ここだ!」と密かに計画し、今回はひとりでの訪問です。
館内は府県ごとにブースが分かれており、どこも展示内容がかなり充実しています。人気のブースでは順番待ちが発生したり、混雑時には列に並ぶことさえできないことも。全部を丁寧に回ろうとすると、2時間近くかかることもあるそうです。
加えて、館内にはトイレがありません。一度出ると再入場できないため、スタッフさんからも入場前に強めに説明されます。私もこの日は朝から水分を控え、近くにある通称「2億円トイレ」を済ませてから挑みました(笑)。
滋賀県ブースの幻想的な映像体験
特に楽しみにしていたのは、知人から「いいよ、いいよ」とおすすめされていた滋賀県のブース。ここは入場人数を制限しつつ、映像と連動して450個の球が上下に動く仕組みです。
桜が舞う彦根城、夜の川辺を飛び交うホタル、琵琶湖の水面のきらめき…。それぞれの場面が光の球の動きとシンクロして表現され、まるで映像に包まれているような没入感がありました。
特に花火のシーンでは球が赤く輝いて迫力満点。元々癒し系の映像ですが、この仕掛けが加わることで、心地よさも倍増するように感じました。海外パビリオンにも負けておらず、この滋賀県の演出はは間違いなく満足度上位に入るのではないでしょうか。
恐竜王国・福井県ブースの大迫力
前回は列が混雑しすぎて体験できなかった福井県ブースにも今回は入ることができました。
ここは「恐竜王国」を全面に押し出した展示。来場者は懐中電灯のようなデバイスを持ち、恐竜化石に光を当てると“発掘”できるというインタラクティブな仕掛けがあります。
最大の見どころは、恐竜時代の福井を再現した全方位スクリーン。暗闇の中から巨大なフクイティタンやフクイラプトルが現れ、来場者のすぐそばに迫ってくるような演出です。デバイスを恐竜に向けるとその部分が照らし出されるので、まるで懐中電灯で探検している感覚。小さなお子さんでも楽しめる工夫がされていました。
次は子どもと一緒に行きたい
会期も終盤に近づき、混雑は以前よりも増しています。ただし、当日予約枠も各時間帯に分けて比較的多く開放されているため、時間を合わせればまだチャンスはありそうです。
今回はひとりで堪能しましたが、次回はぜひ子どもと一緒に再訪したいと思える充実した関西パビリオンでした。