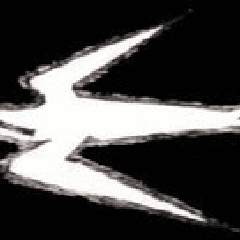京都の近代化の先駆け 山本 覚馬(やまもと かくま)
山本 覚馬(やまもと かくま)
文政11年(1828) - 明治25年(1892)
会津藩士、砲術家
京都府顧問 府議会議員(初代議長)
明治3年(1870年)「京都府大参事・河田佐久馬」の推挽により京都府庁に出仕し、当時、京都府政の実権を握っていた槇村正直(のち京都府令・第二代知事)の顧問として初期の京都府政を指導した。
槇村知事の下で、小中学校・女学校・病院・医学校などの設立に力を尽くした他、大阪と北陸を結ぶ「京都鉄道の敷設願書」を当局に提出するなど、開明的諸政策を推進、有能な人材にも支えられ、京都の近代化に大きく貢献した。(近代京都の父と称される。)
日本で最初の博覧会となった「京都博覧会」を支援し、明治6年(1873年)、日本人による日本で最初とみられる※英文案内記「The guide to the celebrated places in Kiyoto & the surrounding places for the foreign visitors」を著す。
※英文案内記
翻訳すると「外国人観光客向けに京都の名所や周辺スポットをご案内」の
観光ガイドのようでした。文中の「kiyoto」は当時の綴りのようです。
今は「kyoto」です。「世界の京都」がきっと見えていたのでしょう。
明治8年(1875)アメリカ人宣教師ML.ゴードンを通して、キリスト教を深く信じるようになり、ゴードンから紹介された新島 襄(にいじま じょう)「同志社英学校(現:同志社大学創立者)に協力して同志社大学・今出川校地(元薩摩藩邸)の敷地を譲った。「妹・八重(やえ)は「新島 襄」の夫人で、新島と協力して同志社を創立した。
新島 襄が亡くなった後は、同志社臨時総長を務め発展に尽力、明治23年(1890)ハリス理化学館が竣工した。明治25年(1892)に自宅で永眠。
(エピソード)
危機一髪!
「会津藩主・松平容保」の上洛に従い砲兵隊を組織。(当時に視力を失う)「鳥羽・伏見の戦い」で捕えられ薩摩藩邸に幽閉される。幽閉中に建白書※『管見(かんけん)』を口述筆記し、薩摩藩主・島津忠義に上程した。藩主側近の小松帯刀、西郷隆盛らに丁重な処遇を受ける。
明治元年(1868年)新政府の岩倉具視(後の右大臣)ら要人に認められ、翌年釈放された。以後、新政府に協力することになる。
※『管見』(かんけん)は、政治、経済、教育等22項目にわたり将来の日本のあるべき姿を論じた建白書である。自分の見解(管見)と謙称している。
(思想家・横井小楠が富国・強兵・士道(経済、国防、道徳)の確立を
唱えた「国是三論」に酷似しているが、さらに発展させている。)
三権分立の「政体」に始まり、大院・小院の二院制の「議事院」「学校」「変制」封建制から郡県制への移行や世襲制の廃止、税制改革まで唱えた「国体」「建国術」「製鉄法」「貨幣」「衣食」女子教育を勧めた「女学」遺産の平均分与の「平均法」「醸造法」「条約」「軍艦国体」「港制」「救民」「髪制」寺の学校への開放を唱えた「変仏法」「商律」「時法」太陽暦の採用を勧めた「暦法」西洋医の登用を訴えた「官医」と内容は多岐にわたり、将来を見据え優れた先見性に富んでおり、明治新政府の政策の骨格とも繋がる。
同志社大学(今出川キャンパス)「礼拝堂~クラーク記念館」
同志社大学(今出川キャンパス)彰栄館
クリスマスのためのイルミネーション
2014.12.14(撮影 京りんたろう)
◎リンク