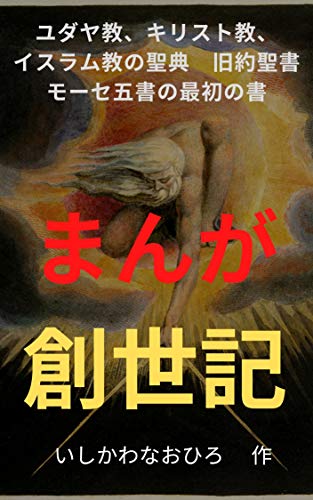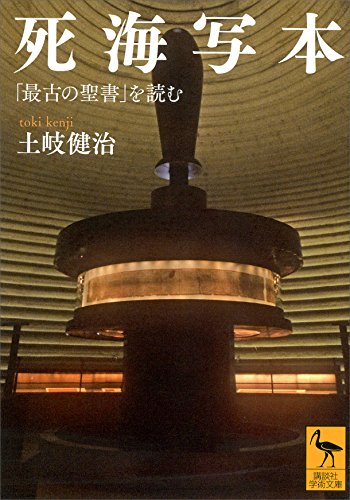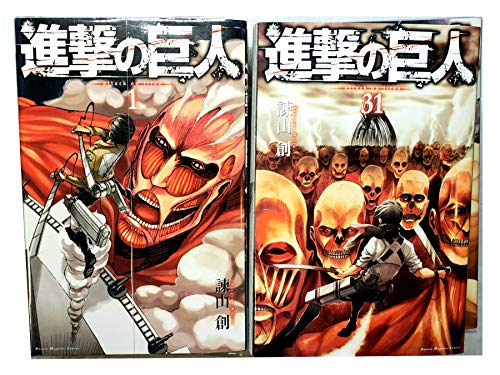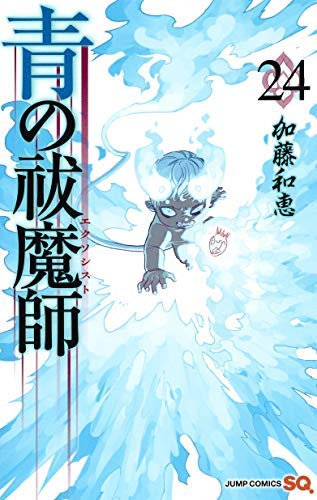こんにちは、なぎさです。
去年の私の手帳にババっと走り書きしたのですが、
がん患者さんに多い精神疾患は
- 適応障害(32%)
- うつ病(6%)
- せん妄(4%)
緩和ケア病棟で多い精神疾患は
- せん妄(28%)
- 適応障害(8%)
- うつ病(3%)
とあります。
この%はどこから来たのか…参照元がメモしていなかったので申し訳ないです。
ということで、今回はがん患者さんと適応障害、これとどう付き合っていくのかという話です。
適応障害はザックリ説明しますと、ある特定の原因によってストレス過多になって、それに適応できず、日常生活に支障がでている状態です。
例えば気分の落ち込みや不安感、眠りづらくなった、イライラする、なんだかよくわからない焦る気持ちがある…などが現れて、普段通りの生活がしづらくなります。
治療方法としては【まずはストレスの原因になっている問題を取り除くこと】です。
取り除くことによって出ていた諸々の状態が急速に緩和します。
これは私たちでも出来そうなこともありますね!
私も経験がありますが例えば職場の人間関係で、〇〇さんにひどく高圧的な態度を取られる、侮辱される、除け者にされる…これらからくるストレスによって適応障害を起こす場合があります。
私は裏で看護師が患者さんを呼び捨てにして侮辱しながらクスクス笑っていたことや、無視されたり嘲笑されることに適応できませんでした。
普段私はがん患者さんと接しているのでこの側面から見た私の意見ですが、がん患者さんに多い適応障害はなぜ起きるのか?といえば、言わずもがな、がんに関連する諸問題かと思います。
例えばがんであることを告げられたストレス。
早期発見であればあまり適応障害を起こさないかもしれませんが、金銭的余裕がなく治療を受けるのに躊躇せざるを得ない場合など、放置していていいのか治療したほうがいいのか、治療したいけどする余裕がないなどのストレスに曝されます。
また治療をすることに家族がよい顔をしないケースもあります。
そうなると治療と自分の命を天秤にかけることになり、ひどいストレスとなります。
また余命告知を受けたというストレスも考えれます。
唐突に突き付けられた自分の人生の期限を、人はそう易々と受け止められません。
これだけでも強いストレスですが、さらに、これからどうするのか?どうなるのか?どうすればいいのか?を考えなければならない現実もあります。
さて、適応障害の治療法はストレス因(ストレッサー)を取り除くことでしたね。
過去の私のように職場の人間関係に適応できず適応障害になってしまった時、
ストレッサーを取り除く
→ 職場の人間関係と距離を置く、自分から切り離すことが必要
→ もうここに居続ける必要はない。や~めた!
で退職したところ、本当にあっという間に精神状態が安定しました。
では、がん患者さんの適応障害のストレッサーの引き離しとは何でしょうか?
病気の根治ですね。
確かに治ってしまえばストレッサーとさようならできます。
ですが、根治を望めない場合はどう引き離せばいいでしょうか?
私はとても難しいと思うのです。
手術で取り除いたり、抗がん剤や放射線照射でがん細胞を直接叩いたりしますが(標準治療といいます)、治療中も嫌でもがんと付き合って生きて行かねばなりません。
また再発が絶対にないなら治療終了でホッとできますが、実際は再発の可能性を考慮し定期的に数年間の経過観察をしなければなりません。
自分を肉体的に苦しめているがんによって精神的にも苦しめられている。この憎き対象はこの体の中にいる。コレからそう簡単には離れられないのです。
では、このようにストレッサーの切り離しが難しい場合どうすればいいのでしょう。
対症療法と、認知の変容、行動の変容が必要になってくるでしょう。
眠れない時は眠りやすくするお薬や眠りを持続させるお薬を処方してもらう。
気分の落ち込み、抑うつ気分によって生活に支障がでているのであれば抗うつ剤などで落ち込む気持ちを少しUPすることもあります。
ではこのお薬だけでがんに関わる諸問題は解決するでしょうか?しませんね。
がんはやっぱりまだ体の中にいるのです。
では認知(物事の受け取り方)を変えてみましょう…という場合、前提として「認知の歪み※がある」というのがあります。※認知の歪みはそのうち記事で書きますね!
極端に言えば、人から「頑張ってるね」と言われて「ありがとう」「そうかなー、ヘヘ(n*´ω`*n)」でなく、「なにそれ嫌味?」「バカにしてんの?」「頑張ってないってホントは言いたいわけ?」と受け取るようなもの。
受け取り方おかしいでしょそれ…というものですね。
本人にとっては普通の受け取り方ですが、冷静に客観的に考えると、ズレた考え方や偏った考え方になっているものです。
がんだと分かりました。stageはⅣだった。肝臓、肺、リンパ節、脳など転移している…と突き付けられた現実が大きい時、
「私、死んじゃうの…?」
「どうしよう」
「やだ、まだ生きてたいのに…」
など苦しんでいる方の認知は歪んでいるのでしょうか。
私は歪んでいないと思うのです。
患者さんのその状況で、その環境で、突然のこの状態で、その認知になるのは当然ではないかと思うのです。
この状態で認知を変容しましょう、というのは少し違うのではないかと思います。
それよりも、そう認知していることをこちらが受容し共感することで患者さんは楽になるのでは?と。
しかし「私が昔門限も守らず遊んでたからバチが当たった」とか「定期検診してたけどそれだけじゃ足りなかった、もっと検診受けるべきだった」というのは認知が少し歪んでいます。
そこは「罰として病気になるのではないですよ」「検診と検診の間に進行することもあるんですよ」などの正しい情報の伝達によって認知の修正はされる必要があります。
では行動の変容を促しますか?
私はこれこそ避けたい。
既に患者さんは日々の生活で精いっぱいです。
ストレッサーを切り離せない状況で日常生活を送りつつ、倦怠感や疲労感、食欲不振、味覚障害、悪心(吐き気)、嘔吐、便秘、下痢など身体症状に苦しんでおられる方もいます。しかもこれらの症状が出ているけど家事をしなければならないと無理をしている方もおられます。
(休ませてあげてほしいです…本当に…)
1時間立っているのが辛かったり、横になっているだけでもシンドイ方だっておられる。
腹水や胸水で苦しくなる方もおられるのが現状です。
そんなストレスだらけの状態の患者さんに「こう行動してみましょう!」は酷です。
これ以上の負担をかける必要はないと思います。
ですから、指示的な心理療法はこのような患者さんには不向きですと私は言いたいです。
「この本を読んで来てください」とか「ストレスを感じる事に対してあなたがどう思ったかを紙に記録してきてください」とか「この用紙に回答してください」などの【宿題】は負担が大きいのです。
ただ、たまーに私の扱う実存的領域(スピリチュアル)ではなく、前世や守護霊やパワースポットやナントカカラーとかのスピリチュアルに傾倒される方もおられます。
この〇〇があるから病気が治るはずだから普通の治療は受けなくてもいいと思っているとか、実際に標準治療なんて絶対に嫌だ、〇〇をかざしたら治るって~~の△△先生が言ってた!みたいなことがあります…。
そういう方の場合、それによってQOL(生活の質)が維持できるのなら良いのですが、傾倒しすぎて妄信的になっている場合には行動の変容ができるようにもっていくことはあります。
ではでは、じゃあ何もせずに眠剤とかだけちょっとあればそれでいいのでしょうか。
あとはがんの治療頑張ってね、だけでいいのでしょうか。
何か困ったら緩和ケアの先生に相談してね、それで何か薬もらってね、でいいのでしょうか。
私は違うと思います。
患者さんが思いを全部吐き出せる場所が必要だと思います。
家では病気による痛い、苦しい、つらい、悲しいと言い出しづらい現実があります。
家族だから言えばいいと思う方もおられますが、実際に家族が病気になって「ごめんね、だるいから寝てるね」と言われたら「え?ごはんどうするの?」「誰が子供の世話するの?」とイラッとする人もいますし、「痛いとかだるいとか、そんな事言われても私には何もしてあげられないから、どうもしようがない」と気分が悪くなる人もいます。
この先のことや、体調を崩して入院することになったらどうするかとか、死について話をしようとしても「滅多なことを言わないで」「そんなこと言わずに!頑張って治療しないと!」「そういう話やめて…つらくなるから」と聞いてもらえない場合もあります。
このような、心の奥底にあるモヤモヤしたシンドイ気持ちを全部吐き出してもよい場所、全部聴いてくれる場所・人が必要なのです。
何度も同じことを繰り返し言っても「さっきも聞きました」と言わずに毎回聴いてくれる人が必要なのです。
私はフォーカシングという心理療法を一部改変して対話に適用しています。
「つらい」という思いに「何がつらいですか?」「何故つらいのですか?」と直接的に問わず、対話を通して患者さんから発せられたキーワードになる言葉から「今お話してくださった〇〇があなたがつらくなる理由のひとつですか?」のように尋ねます。
「つらい」の他の表現方法「さみしい」「せつない」なども対話の中から見つけていき、最終的に患者さんが「つらい」「苦しい」と思っているモノは何なのか、「私は〇〇が~~と感じるのか」と気付いていただけるようにもっていって、”ではこれから生きるためにその〇〇とどう向き合っていくか”を一緒に考えます。
ですから肉体的な負担はありません。
私はとにかく自然にこの流れを作るよう努力していますので、患者さんはお気持ちを全部吐き出せて「スッキリできた!」「モヤモヤしてたのがなんだかちょっとわかった!」になっていただけるのではないかと思います。私と話をしてなんだか楽になると言っていただけるのですが、これをしているからです。
具体的にご自身が何をどう苦しいと感じておられるのか、こう思ってたけど実はこうだったのかと気付く。
以前も書きましたが、「死ぬのが怖い」とご自身では思っていたのですが対話を通して「我が子と離れるのが淋しくて仕方がない」という感情だったと気付くようにです。「死そのものではなく、死によって自分が完全消滅すると思っているその消滅が怖い」と具体的に気付くような感じです。
このように具体的に”何か”がわかることによって、今、自分が何をしたいのか、何を優先させたいのかが明確になります。
確かに病気であること、これからのことには患者さんは闘病中ですから未だ適応できていません。
ですが、病状に無理をせず地に足を付けて生きられます。
そしてチャプレンとしては、何かに縋りたいという気持ちがおありでしたら、ぜひ超越者(神仏)に縋っていただければと思います。
薬に縋ると、その薬が効かなくなった時や副作用が出て中断せざるを得ない時に「もうダメだ」と絶望してしまいます。
先生に縋ると、積極的治療をしない判断がなされた時に「見捨てられた」と絶望してしまいます。
※頼ると縋るは違いますよ。
私たち人間は勝手に相手や物に期待して、勝手に高い要求をして、自分の理想にかなわない反応を示されると、自分勝手に絶望してしまうのです。
神様の場合、絶対的に裏切る事もありませんし見捨てることもありませんから、”藁をも掴む”心理的な危機的状況の時こそ、藁でなく命綱である神様を握りしめていてほしいなと思います。
ちなみに、職場外でカウンセリングもしていますが、この場合お引き受けする相談は主に職場や夫婦の人間関係です。この時はフォーカシングではなく交流分析や認知行動療法をチョイスしてクライアントさんの相談をお聴きしています。