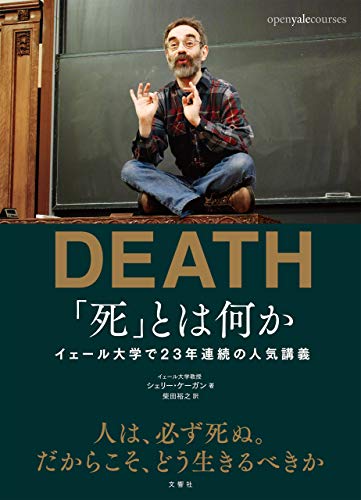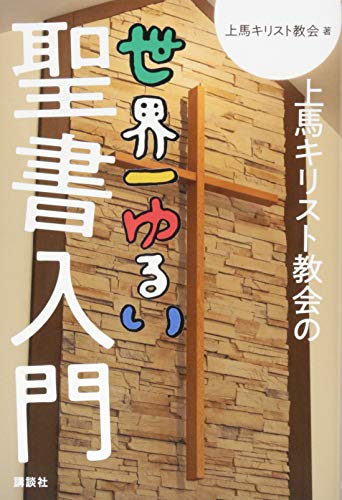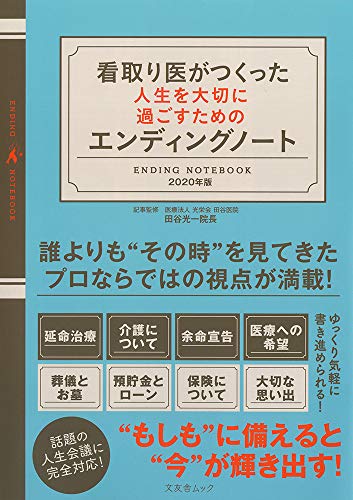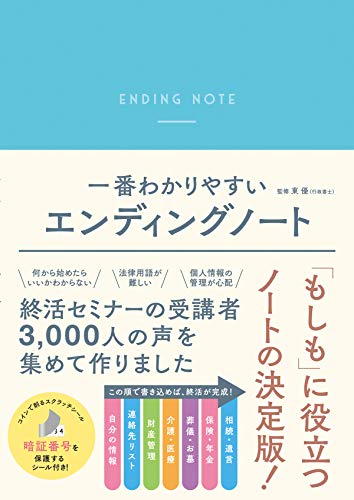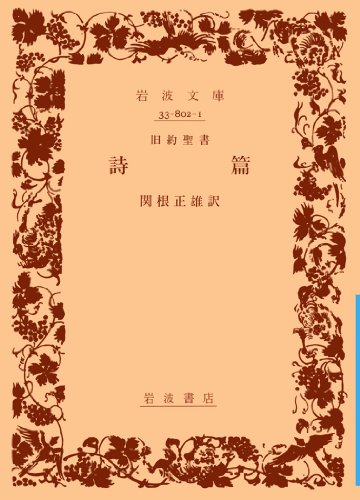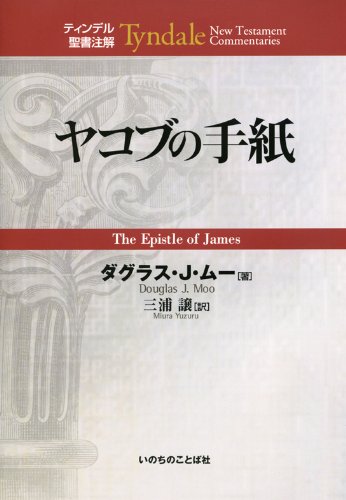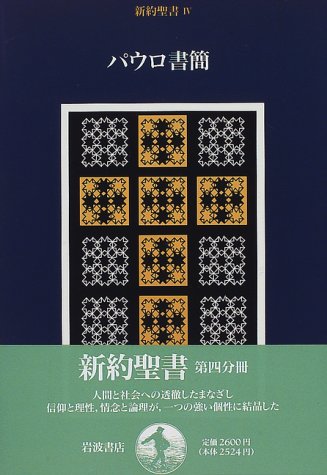こんにちは、なぎさです。
今回は死生観について。
死生観(しせいかん)とは、Wikipediaさんによると「死と生に対する見方をいう。」となっています。
ネットでググると、こちらの老人施設サイトでは死生観についてこう記しています。
●死生観の定義
死生観とは、生きることと死ぬことに対する考え方、または判断や行動の基盤となる生死に関する考えのことです。
誰にでも死は訪れるものですが、死後の世界は未知の世界でもあります。そのため、人の死に対する考え方や価値観などは個人で異なります。
死について考えるきっかけも人それぞれです。
コロナ禍で、スウェーデンでは寝たきりの人がいないというのが話題になりました。
なぜ寝たきりの人がいないのかをざっくり説明しますと、スウェーデンでは自分で食事が出来なくなったら死を迎えるということを受け入れている死生観がある国だからです。
なので「生き長らえようとしない」し「生き長らえさせようとしない」のです。
なぜこのように死を受け入れるのかといいますと、その背景にはキリスト教信仰があります。
キリスト教では、死は自分の最後ではありません。
人は神様のおられる天に元々いました。
そして人として神に喜ばれ生を受ける。
この世で人生という旅をする。
そして肉体の死をもって、元々の故郷である天に帰るのです。
ここには輪廻転生はありません。
一度きり、天で霊の状態で存在し、地上に人として生まれ、人生を進み、霊となり天に帰るのです。
死ですべてが終了するのではなく、その先があるので、死が不浄であらゆる面においての絶望的なものではないのです。
死の先に天での安寧が約束されており、神様のすぐそばで誰からも事件・事故・病など何からも攻撃されない約束があります。
そこで安心して休むことができるのです。
なので「安らかにお眠りください」であり、帰天(天に帰る)・召天(天に召される)と表現します。完全終了ではないのです。
亡くなる時は家族や友人などを家に招き、傍にいて、自然に息を引き取る時まで過ごす。
これを何代も繰り返しているので、自分の番が来た時に「あぁ私もそろそろか。〇〇こっちにおいて、いいかい、〇〇するんだよ」のような遺言を残し、逝けるのです。
このような生活習慣ですから、どうにかして生き続けなければならないという死生観ではないので、死を受け入れているのですね。
これを死が不浄のもので忌避すべきものだとする視点から考えると、彼らの考えは異常と感じます。
呼吸が止まっても人工呼吸器を使えば心臓は動き続けるのに。
食事がとれなくなったなら胃瘻で栄養与えれば生きられるのに。
点滴で栄養送れば。
長生きしないと。
医療機器と医療技術で延命できるのに、やらないなんて人命(人権)を侵害している。
高齢者や傷病者を見捨てている。優しくない。
色々な考え方ができます。
死は誰にでも訪れます。
私にもあの人にもこの人にもあなたにも。
生きているものはすべていずれ、その細胞の活動を停止させます。
形あるものはいずれ、風化し、崩れていきます。
私は、死を忌避しないでほしいと思います。
ですが、死に憧れ、死を美化するのは危険だと思います。
自殺はおススメしません。
職業柄、縊死(首吊り)やoverdoseの方など見ていますが、本当に…。
私たちの命は貴重です。
私たちはみんなが一人しかいない、絶滅危惧種のようなものです。
ですから簡単に命を消してはなりません。
あなたの存在は神が尊いと見ておられれるくらい貴重なものです。
単純に、私たちはいずれ死を迎える者であることを自覚し、だからこそ今を生きることを大切にしてほしいですし、どうやって死を迎えたいかも考えてよいのだと思います。
死を意識したことがないから何とでも言えると言われてしまうかもしれません。
ですが私も死を意識したこと…というか、死にかけたことがあります。
血圧が40/(測定不能)mmHgに落ち、意識レベルはJCS(ジャパンコーマスケール)だとⅢかそれくらいでしょうか。
もう疲れて眠いのです。声も出ない。
そして「聞こえますか!」とか「手を握ってください!」とか声をかけてほしくない。
周囲で看護師や医師が私の血圧がどれくらいだ、反応がどうだとバタバタしているのです。
つまりこの状態でも耳は聴こえています。
私はこの時「なるほど私の血圧はいまそれくらいなんだ。」「じゃぁもうアレかな。眠いし、もう静かしてくれてもいいのに」と思っていました。
手を握られていたりした感覚はありませんでしたが、誰が何を言ったのかは覚えています。
また、私は現在は寛解中ですが膠原病と思わしきなんだかよく分からない状態を持病で持っていて、数年に一度ひどい倦怠感と筋肉と関節痛、長期微熱に悩まされますが、寝たきりにまでなった時はさすがに死を意識しました。
食事ができず、箸が重たく感じて持てない。体中の痛みに泣いて過ごしていました。
幸い命に係わるものではなかったのですが、「もうやだ、ホントにもう嫌だ。こんなに痛いならもう死にたい。死ねば痛いのから解放されるのに」と思っていました。
現在の私の死生観でも、いざ大病を患えばやはり怖いです。
死のその先があるのはわかっていても、怖いのです。
いえ、怖いではないですね…今の私は死を意識したら、寂しいと感じます。
今、触れ合っている人と、この体で直接的に触れられなくなる。これがたまらなく寂しいのです。
なぜこう寂しいのかというと、私が大切に思う人たちが周囲にいるからです。
いないと、寂しとは思わないのです…。
この寂しい、切ない、孤立している気分になるというのを否定しない。
そう思っていいのです。
そう思うご自分を受け入れてください。
自分はこう感じてるんだなと受け入れてください。
私にはこれほど離れがたい大切な人たちがいるんだなと。
その上で、死をどう迎えるかを考える。
だからこそ、どう生きるのかを考えるのです。
死ぬために考えるのではなく、生きるために死を考えるのですね。
そして生きることで、落ち着いて死に向き合うことができることにもなります。
一人ひとり、死生観を考えるタイミングも違えば状況も違います。
健康体で考えるのと闘病中に考えるのでは内容は全然違います。
それでいいと思います。
ご自分のタイミングで、ご自分なりの死生観をもって、生きましょう。
メメントモリmemento moriです。
「自分が(いつか)必ず死ぬことを忘れるな」、「死を忘るなかれ」
というラテン語です。
死を意識するからこそ、懸命に生きられます。自堕落になっていられないのです。
怪我や病で死を意識しておられる方々が、意識しておられるからこそ生きられますように。
しかしくれぐれも、頑張らずに生きることです!
体は100%ですでに生きて頑張っていますからね。
心は手抜きしすぎ?と思うくらいで丁度良いですよ。