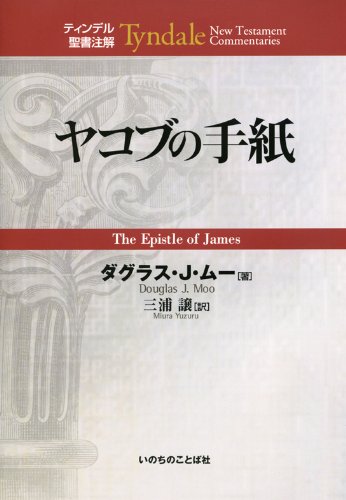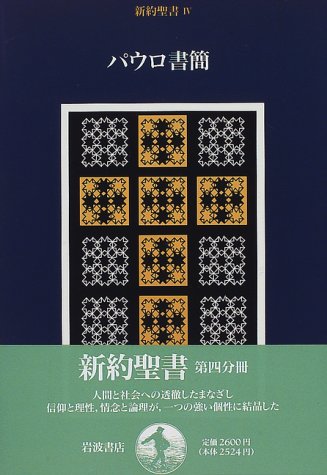こんにちは。
メンタルケア心理士®でチャプレンのなぎさです。
今日は新約聖書にある「ヤコブの手紙」という書のお話。
聖書は旧約聖書39巻、新約聖書27巻の合計66巻を1冊にまとめたものです。
新約聖書を掲載順に読んでいくと、「ヤコブの手紙」までの19巻まで一貫して信じるだけで救われるという内容で書かれています。
しかし、この「ヤコブの手紙」ではまるで行動をしないと救われないとしか読めないような聖句が出てくるのです。
人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことが分かるでしょう。
─ヤコブの手紙2:24
これはいったいどういうことでしょう?
信じたら救われるという初期設定ではあるけど、結局は、信者になったらキリスト教が決めている数々の規定とかを実行しないと本当は救われないのか?という疑問が出てきます。
新約聖書で掲載されている順序は、それぞれの書が執筆された年代順ではありません。
新約聖書で信じるだけで救われる(信仰義認)を明確に書いている書の多くをパウロという人物が手掛けていますが、そのパウロさんの書いた書簡※よりも「ヤコブの手紙」の執筆時代は古く、西暦48~49年頃だと推定されています。
※「ローマ人への手紙」57~58年頃、「コリント人への手紙第一」55年頃、「コリント人への手紙第二」56~57年頃、「ガラテヤ人への手紙」52~55年頃、「エペソ人への手紙」61年頃、「ピリピ人への手紙」50年代後半~60年代初め、「コロサイ人への手紙」57年頃、「テサロニケ人への手紙第一」50~52年、「テサロニケ人への手紙第二」第一執筆の数か月後、「テモテへの手紙第一」66年頃、「テモテへの手紙第二」67年頃、「テトスへの手紙」67年頃、「ピレモンへの手紙」60年頃、「ヘブル人への手紙」95年頃?─出典:新実用聖書注解、Wikipedia
そしてこの「ヤコブの手紙」を書いたヤコブさんは、主イエスの実弟です。
主イエスは30歳で公生涯と呼ばれる宣教活動に入りました。ということは、それまで実家で家族と共に暮らしていたということです。
ヤコブさんは主イエスと一緒に生活をしていたのですね!
同じ家で生活し、同じ言語で喋って、同じ社会環境で育っていました。ですから、会話の内容も兄弟ですから共通項が多いです。
ここから、この「ヤコブの手紙」に書かれている言葉の意味は、主イエスが幼少期から公生涯を終えるまで使っていた言葉…すなわち、福音書で主イエスが語った原語と同じ意味を持つことがわかります。
「義と認められる」の「義」はδικαιοσυνην(dikaiosyninディカイオシニン)という単語が使われています。δικαιοωディカイオーという単語の受動態です。(70人訳聖書ではλογιζομαι(logizomai)=勘定される→みなされるという予定的な意味の単語を使用)
パウロのいうδικαιοσυνηνとこの書の著者、ヤコブのいうδικαιοσυνηνは意味が違います。
主イエスとヤコブはこの言葉を「神様に喜ばれる」とか「神様に受け入れられる」という意味で使っています。
これは当時の一般生活で極々普通に使われていた用語の意味なのだそう。
一方、パウロさんは、「ヤコブの手紙」よりも後の時代に自分の書簡の中でこの単語を使用しています。
新約聖書でパウロさんがよく使う「義と認められた」の「義」は、ヘレニズム文化(ギリシャの原語や文化、世界観など)をベースにした「正義」「誠実」「正しさ」を指します。
これは、パウロが主イエスとヤコブの言う「神に喜ばれる」という一般用語の意味を「神様に義と認められる=救われる」という宗教的な専門用語に昇華させたのですね。
「ヤコブの手紙」ではこの2章24節は躓きやすい箇所だと言われています。
ここをパウロ的に解釈せずヤコブ的に解釈した表現をすると
人は行いによって神様に喜ばれて受け入れられるのであって
になります。パウロは義認論で「義」を使っていますが、ヤコブは義認論とかそういうのは毛頭にもなく、単純に喜ばれるかどうか嬉しいと思ってもらえるかどうかなのです。
つまり、
「イエス様を信じたし、もう私は救われたんだから、今更何かしなくてもいいや~」
ではなく、信じた結果に出てくる無償の愛の行動、隣人愛があると神様は喜んでくださるよ──ということになるのですね。
『主イエスを信じて生活してたら心が少し楽になった、苦しみをどん底と思わなくて少し光が見えた。ほんのちょっとだけど困ってる人に手を差し伸べてあげられそう。』
例えばこういう行動があったとして、パウロ的に解釈すると、「困ってる人に手を差し伸べない人は救われない」になってしまうのですが、主イエスとヤコブの言う意味で解釈すると「手を差し伸べられる時に差し伸べてあげられたら、それって神様が喜ぶよね!」になるということです。
パウロさんの数々の書簡は「どうしたら救われるのか?」がテーマになっています。
そのテーマのまま「ヤコブの手紙」を読むと信じるだけで救われる(信仰義認)なのか?行動をしないと救われないのか(行為義認)?と矛盾を感じるのですが、この「ヤコブの手紙」は「信仰生活はどうやって送っていくんだろう?」というテーマです。
テーマが違うこと、こういうテーマだというのを押さえて読むと、矛盾せずにスッキリ理解することができます。
この箇所で信じる事に躓いてしまう人はおられると思います。
あ、そうなんだ!となってくだされば幸いです![]()