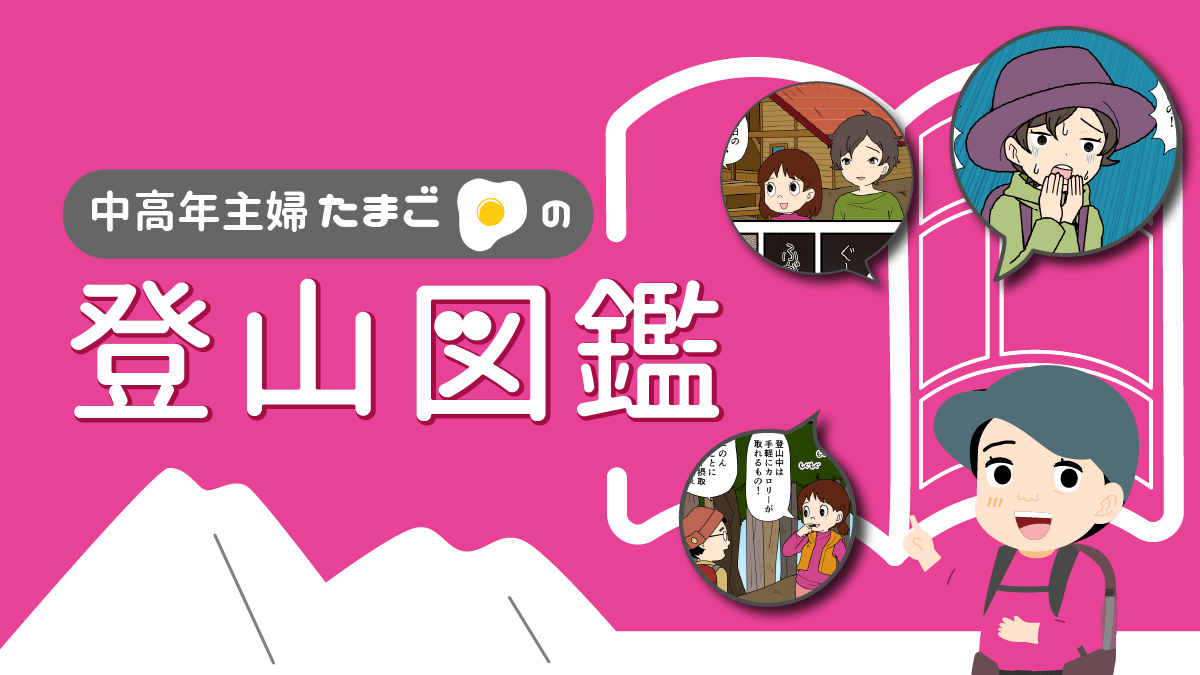「登山のコースタイムの大問題」
登山を始めてみようと思い立って、
一番困るのが、
・そもそも自分は体力的に登れるのだろうか?
・コースタイム通りに行けるのだろうか?
と言う体力と時間の問題が非常に重くのしかかって来ます。
非常に大切で恐い問題なので、
最初に断言しておきます。
もしここで重く感じられないなら、
登山と言う趣味は止めておいた方が無難です。
危険過ぎます。
そうして、最初に挙げた疑問について、
果たしてどうなのだろうか?と思いながら、
実行してみると、
初心者にとっては異常事態が発生する訳です。
それがリンクを貼った動画になります。
時間通りに行けない大問題です。
何故行けないのか?
何がおかしいのか?
その疑問に答えてくれている貴重な動画であります。
そもそも地図やガイドブック、公的なサイトに載っているタイムは、
意外にバラバラです。
どれが正しいのか?と考えて行きますと、
一番大切なのは、動画でも言ってくれていますが、
「正解は存在していない」と言う恐ろしい結論になるのであります。
その人の体力や荷物の重さ、天候、人数、技術的難度等々、
様々な要素が入って来ますので、
この時間で行かないといけない、と言う正答は存在していない、と。
しかし、動画では言ってませんが、
登山をする以上、明確な安全対策上の絶対的タイムリミットはあります。
「日没までには下山している(もしくは予定の山小屋に到着する)」
ここを外してしまった場合、
ビバークもしくは遭難となってしまいます。
例外的に夜中でも登る富士登山がありますが、
通常の山での夜間登山は非常に危険でやってはいけない事の筆頭になっています。
そもそもコースタイムはどんな基準で決まっているのか?と言いますと、
何と各製作会社でまちまちなのであります。
一番有名な昭文社の「山と高原地図」の定義では、
「40~60代(または60代)の登山経験者が、
2~5人のパーティーで夏山の晴天時」に登った時の時間となっています。
すると、何となく、この地図に記載されている時間通りに歩けると思ってしまう人が多いでしょう。
しかしここに落とし穴があります。
ほぼ全ての他のコースタイムもそうなのですが、
「そもそも休憩や食事時間は含まれていない」のであります。
また、いくら60代と言っても「登山経験者」と言うのが大変なクセモノなのであります。
「慣れた経験者は異常に速い」
そして決定的に危険なのが、
「人間にはパワー動機と呼ばれる勝った時に感じる根本的な快感本能」が備わっている、
と言う恐ろしい問題です。
要するにもしタイムが設定でもされていようものなら、
「どうだい!!オレ様はタイムよりも1時間も早く登れたぜっ!!」と、
自慢をする連中が多数出て来る現実です。
これは非常に危険な感覚なのですが、
残念ながら人間はこの種のパワー動機から逃れるのは大変な困難を伴います。
この感覚は登山においてだけは絶対に無視しないと命に関わる大問題になります。
では、ここでおそらく登山としては最も人気があり多くの人が一度は是非と憧れる富士山で考えてみます。
一番人気の吉田ルートと二番人気の富士宮ルートでチェックしてみます。
掲載した図は富士登山の公的サイトである「富士登山オフィシャルサイト」のコピーです。
富士登山は1泊2日が基本ですので、
1日目に八合目まで行くとします。
どのくらいで行けるのでしょうか???
吉田ルートのタイムを合算しますと210分、3時間半となっています。
富士宮ルートのタイムでは205分、3時間25分となっています。
要するに経験者が休みなく行ったら3時間半で八合目に到着出来ると言う訳です。
当然休憩が必要ですから、休憩を入れたら4時間で行ける???
食事が必要だから4時間半くらい???
実はここに正解はありません。
いや、正解は1つだけあります。
それが前述した通り、
日没前に到着していれば良い、です。
富士登山の場合は高山病と言う厄介な問題がありますので、
ハイペースで行ったら最後、自滅する確率が非常に高くなります。
ちなみに吉田ルートの時の私は6時間くらいかけて登っています。
(この時はヤマレコをまだ使っていなかったので正確には分からない)
富士宮ルートの時は何と6時間22分かけて登っています。
ヤマレコのペースでは1.5~1.6「ゆっくり」と表示されていて、
これはコースタイムの1.5~1.6倍の非常にゆっくりとしたペースで登っている事になります。
多くのベテランは私のタイムを笑ってしまうでしょう。
いくら何でも遅過ぎる、と。
しかし私は日没前に到着しています。
今回の須走ルートでも6時間くらいかかってます。
しかし日没の2時間半以上前に到着しています。
つまり私は自分の足が遅いのを、
富士登山をする前の別の低山登山により分かっているため、
自分のペース配分を組み立てて、その通りに実行したのであります。
もしベテランが「遅過ぎるよ。もっと早く歩けないの?」と言って来たら、
答えは決まっています。
「歩ける訳がない。」です。
さらに心の奥底ではこう言います。
「あんたのオレ様一番発言には付き合っていられない」と。
この感覚はマラソンをやると非常に良く理解する事が出来ます。
マラソンの世界では大抵の場合、
特に大会に出る人達の間ではタイムが非常に重要になっています。
42.195kmを大会で走り切るタイムは、
6時間以下に設定されていて、
それ以上時間のかかる人はもうダメです、
と、足切りされるラインになっている大会が多いです。
マラソンは市街地で行われますし、
この種のパワー動機的要素が強く、
つまり競技として成立しています。
しかし登山は競技ではありません。
夜になってしまった = ビバーク
疲れて身動き出来なくなった = 遭難
徹底的に自分のペースや体力を知り、
それを実行していないと冗談抜きに死の危険に晒される訳です。
そうして厄介な事に、
パワー動機に拘る人は非常に多く、
そんな人物に介入されたら最後、
命の危険に晒される、と。
このコースタイムは大切ではあるけれど、
問題だらけの非常に危険な世界だと知っておく事が大切かと。
また同様に、登山書に記載されている、
入門、初級、中級、上級と言う分け方にも非常に大きな問題があります。
理由はもちろん前述して来た通り、
パワー動機の対象にされてしまうからです。
初級よりは上級の山を登った方がカッコいいと考える人は多いです。
では誰がそんな級を決めているのか?と言うと、
これがまた明確な基準は存在しておらず、
各登山書やサイトにより違っている現実があります。
最近では何度も書いておりますが、
計算により作られたコース定数(ルート定数)なるものが出て来ています。
これはかなり上手く表されている数値ですので、
自分の過去の経験と山岳専用の登山アプリ、ランニング能力、
コース定数、コースタイムを複合的に組み合わせて、
上手に機能させた時、ようやく自分本来のコースタイムが出来上がって来るのだと思います。
残念ながら現時点では、それを知るのは非常に難しいです。
少なくとも、コースタイムが出て来たら、
余り信用しないで、自分のペースを知るのを最優先させた方が無難です。
それはベテランの速足のタイムであり休憩も食事も抜きの時間なのだ、と。
そして一番大切なのは遅くとも日没までに下山する、です。
余談:
登山を再開してから2年半ほどが経過しています。
改めて学んでみると、
現在の登山の世界は昔から、
体力基準、コースタイム、ナビと言う最も大切な部分がダメダメなのを思い知らされてます。
肝心要のベテランがダメで、
オレ様一番発言が如何に多いか。
幸い新しい基準が出来ているので、
それが浸透するのを期待している現状です。