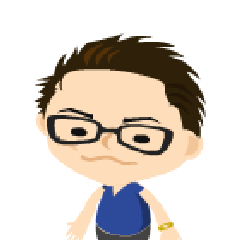ご訪問くださいまして、
有り難うございます。
れっつごうです(^^)
前回まで、
遠藤周作さんが語る
イエスの思想を、
私の解釈も交えて、
紹介してきました。
今回からは、
という本の内容を元にしつつ、
私なりにブッダの思想に
迫ってみたいと思います(^^)
著者は、
仏教思想の第一人者、
有名な中村元先生です。
この本は、
やや専門的ではありますが、
「NHKこころの時代」
のテキストをもとにしているようで、
文章は平易、読みやすいです。
簡単に、
ブッダ(お釈迦様)の生い立ちから、
なぞっていきますね。
ご存知の方も多いと思いますが、
ブッダは、紀元前5世紀ごろ、
(イエス誕生よりも500年も前なんですね)
インド北部(今のネパール南部)
のシャカ族の王子として生まれました。
29歳の時、
城を捨てて出家され、
6年間の苦行のあと、
瞑想により「さとり」をひらかれます。
その「さとり」の内容を、
北インドを中心に、80歳でなくなるまで、
説法して歩かれました。
まず思うのが、
「なぜブッダは出家したのか?」
なぜ、王子としての裕福な生活を捨ててまで、
出家をしたのか。
「四門出遊」の逸話が、
紹介されています。
ずっと宮殿の中で生活していたブッダが、
門から出て外の世界を垣間見ることで、
「人は、老、病、死の苦しみから
逃れられない」
ということに気づいてしまったんですね。
当時、上流階級が、
家から出て修行者になることは
一般的だったようですが、
それにしても、
家族を捨ててまでして出家する理由は、
何だったのか?
別の本になりますが、
興味深い説があります。
岡田尊司さんの
から引用します。
釈迦の母親は、
彼を生んだ直後に亡くなった。
(中略)
自分の出自が、
その出発点から、
母親の命と引き換えに
与えられたものであり、
そのことに
罪の意識を感じていたに
違いない。
釈迦は、
自我に目覚め、
自らの出自について考える
青年のころから、
物思いに耽るようになる。
その憂いを
晴らすことができればと、
王である父親は
釈迦に妻を娶らせ、
子どももできるが、
釈迦の心の沈鬱を
取り去ることはできなかった。
釈迦はついに出家して、
王子の位も、妻子も捨てて、
放浪の旅に出てしまうのである。
その根底には、
母親というものに抱かれ、
その乳を吸うこともなく、
母親との愛着の絆を
結ぶこともなく、
常に生きることに
違和感を覚えながら
育ったことがあったに違いない。
それは、
愛着障害に他ならない。
なるほど・・・
私はなぜブッダが出家したのか、
ずっと疑問だったのですが、
たしかに、
母親がすぐに亡くなったことによる
「愛着障害」も
その要因だったのかも
しれません。
ちなみに、この本
には、
夏目漱石や、クリントン元大統領、
スティーブ・ジョブスなどの偉人も、
愛着障害であり、
それを克服したと紹介されています。
愛着障害を克服した人は、
特有のオーラや輝きを放つと
述べられています。
そう考えると、
ブッダも、
愛着障害だったからこそ、
それを克服することによって
光り輝き、
人類に多大なる貢献をする存在に
なられたのかもしれませんね。
ブッダは出家して、
修行に励むことになるのですが、
当初は、苦行林で、
自ら進んで苦行をします。
断食や、直立不動、息を止める、
墓場で骸骨を敷いて寝る・・・
体に苔が生えていた
といいますから、
想像を絶する苦行ですね(^^;
ガリガリに痩せた苦行釈迦像を、
皆さまも一度はご覧になったことが
あると思います。
しかし、
このような苦行にもかかわらず、
悟りに到達することは
できませんでした。
苦行をやめ、
村の少女スジャータ
(コーヒーフレッシュのスジャータは
ここからきているんですね)
から乳がゆをもらい、
生気を取り戻したブッダは、
菩提樹の下で、
瞑想を始めます。
悪魔の誘惑を払いのけ、
7日間の瞑想ののち、
そこで、ついに、
悟りの境地に至ります。
その教えが、
「四諦」
「中道」
「八正道」
となるのですね。
私はまだまだ浅学の身ですが、
仏教は、
学べば学ぶほど、
本当に、人間の心のありようを
正確に分析されていると感じます。
その中で、
今回は、
「四諦」
の中の「苦諦」
にフォーカスしていきます。
苦諦とは、
生きることは苦しみである
ということ。
一切皆苦などともいいますが、
この「苦」とは、
肉体的、精神的な苦痛という
意味だけでなく、
「思うとおりにならないこと」
だといいます。
この「苦しみ」
ということばは、
インド人の概念では、
「うまくいかぬ」
「・・・しがたい」
「・・・するのが難しい」
という意味で、
それが名詞になると
「思うとおりにならないこと」、
つまり、
「苦しみ」「悩み」
をあらわす
「ドゥクハー」
ということばになります。
それが
「漢訳仏典」で
苦と表現されました。
では、
何が、思うとおりにならないのか?
生も苦しみである。
老も苦しみである。
病も苦しみである。
死も苦しみである。
愛さない者と会うことも
苦しみである。
愛する者と別離することも
苦しみである。
すべて欲するものを
得ないことも
苦しみである。
(律蔵)
この「生」「老」「病」「死」が四苦。
ここから四苦八苦という言葉が
生まれるんですね。
「生」「老」「病」「死」
たしかに、
医学の力によって、
多少はコントロールできるようには
なりましたが、
これらは、基本的には、
思い通りにはなりません。
少なくとも、
皆、必ず死を迎えることは、
厳然たる事実です。
どんな権力者も、
死を避けることはできません。
秦の始皇帝が、
不老不死の妙薬を求めたといわれますが、
その思いは叶わないわけです。
もちろん、
他人(人間関係)も、
こちらの思い通りには
なりませんよね(^^;
まずは、これらの現実を、
しっかり見つめよと、
ブッダは述べています(^^;
このように、
人生は、基本的に
思い通りにならないものなのに、
私たちは、それに対して、
悩み、苦しみます。
なぜか?
一つは、
この世のすべてのものが
移り変わる無常なもの
であるのに、
いつまでも
常住であってほしいと願う
執着の心からです。
もう一つは、
我々が
いろいろな欲望を
持っているから
苦しみ悩むのです。
すべては移り変わるのに
つい、執着してしまう。
もっともっとと、
つい、むさぼってしまう。
したがって、
「無常」
(すべてのものが移り変わる)
ということを受け入れて、
「執着」をしない。
際限のない「欲」を捨てる。
ことが必要になるといいます。
有名な、
「犀(サイ)の角のようにただ独り歩め」
(スッタニパータ)
という言葉も紹介されています。
ただ・・・
そうはいっても、
現実世界では、
「執着」を捨てるのはともかく、
「欲」じたいを捨てるのは、
なかなか難しですよね(^^;
欲は、向上心につながることも
ありますし・・・
では、
「人生は、思い通りにならないもの」
ということを、
どう受け止めればいいのか?
別の本になりますが、
(仏教からはちょっと離れます)
(写真は新版です。
今は、リンクを張った完全版が
文庫ででています)
という本に、
とても有益な考え方が、
述べられています。
「人生は、思い通りにならないからこそ
価値がある」
という考え方です。
えっ・・・?
「ならないからこそ」?
「思い通りになればなるほど価値がある」
ではないのか?
いや、
「ならないからこそ価値がある」
というのです(^^;
乗りかかった船ですので、
次回は、
ブッダの教えから、いったん脱線して
飯田史彦さんの、
から、
「人生は、思い通りにならないからこそ
価値がある」
という考え方とはどういうことかを、
今回も最後までお読みくださいまして、
有り難うございました😊