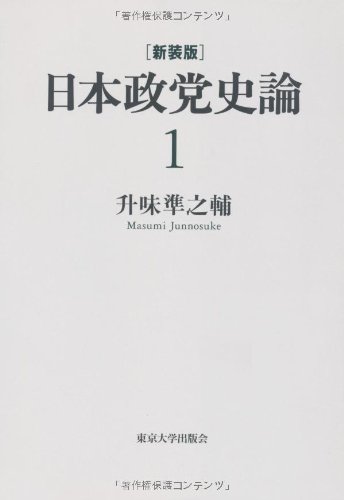升味準之輔『日本政党史論1』(東京大学出版会 1965年)読了。
近現代の日本の政治を知る上で欠かせない政党の歴史を学ぶため、全7巻のうち、まずは第1巻を読んだ。
第1巻は「明治維新から自由民権へ」ということで、
第一章 廃藩置県
第一節 政府と旧藩
第二節 廃藩クウデタ
第二章 征韓論と西南戦争
第一節 征韓論争
第二節 士族の叛乱
第三章 自由民権運動
第一節 士族結社
第二節 豪農結社
第三節 全国運動
という構成になっている。
明治初期当時の史料の引用が結構あり、なかなか読み進めづらいところもあったが、そこはもっとスラっと読めるようになるように努力しなければならないと思った
さて、第一章と第二章に関しては明治維新から西南戦争までの概観を押さえることができる。
そこで、第一章の第二節で、
「薩長を中心とする維新史には、暗い惨めな周辺がひろがっている。その周辺の比較的くわしい記述のある藩の中から秋田藩に簡単に触れておきたい」(p94)
ということで、地元秋田の秋田藩に触れている箇所があったので、政党史とは外れるがそこの感想も書いておきたい。
「『秋田県政史』には、戊辰戦争についての多くの日記・書簡・文書を引用している。その中の一つに、九条総督御側目付戸田主水が、薩長将兵の横暴に憤慨し、総督陣営を去るにあたって上言した文書がある。それを引用しておきたい。時勢におくれて去就にまよううちにおしつぶされた東北諸藩の、藩閥政府に対する怨恨の根がどのようなところから生じているのかを語るものである。」(p97)
とした上で、『秋田県政史』から引用した文書を載せている。
詳しくは実際に引用されている文書を見ていただくのがいいと思うが、要は戸田主水は、戊辰戦争は薩長の私怨私闘であると言っている。会津は降伏すると言っているのにそれが許されない。負けるとわかっていても戦うしか道がない。この絶望感というものは筆舌に尽くしがたい。東北人としては悔しい限りである。自分たちの力のなさを痛感する。
勿論薩長主導の新政府が、外国に対抗できる国家を建設しなければ日本が滅ぼされてしまうということで内乱を早期に終結させなければならず、そのためにある程度の武力を行使しなければならなかったことはよくわかる。しかし、薩長が東北に行った仕打ちというのは果たしてその目的を正当化できるようなやり方であったのか。これは忘れようとしてもそう簡単にできるものではない。
…と話してくると、戊辰戦争における東北の運命というのは、大東亜戦争における大日本帝国と重なって見える。
心のどこかでは、「明治維新以来、薩長主導で行ってきた国づくりは日本を滅ぼしてしまったではないか!薩長ざまあみろ!」と思わないこともないではない。しかし、大日本帝国が滅んだ直接の原因が薩長にあるわけではないので、いいががりというのは重々承知している。その上で、それを一言言っておかないと気が済まない。
ついでに言うと、いつも思っていることだが、東北は古来よりいつも征討される側である(伊治呰麻呂、阿弖流為、安倍貞任、奥州藤原氏、九戸政実、、会津松平家など。神武天皇に敗れたナガスネヒコも東北に逃れたという伝承もある。また、征討という訳ではないが、東北に大きな爪痕を残したという点では、東日本大震災も入れてもいいかもしれない)。
だから、いつか東北が日本を動かす原動力になれればいいと思っている。
二度にわたる消費増税とコロナ禍によって、日本の命脈も風前の灯火のような様相を呈している。
ならば、ピンチをチャンスと捉え、日本の危機に今こそ我ら東北が起つべき時ではないのか、などと思う。
我ら東北人が新しい日本を建設する先駆けたらん、と思う次第。
…長々と政党とあまり関係のない話をしてしまったが、どうしても触れておきたいところだったので、ご容赦のほどを。
第三章 自由民権運動
について若干触れたいと思う。
正直なところ、自由民権運動については詳しくないのでとても勉強になった。
自由民権運動といっても、学校の授業で習う程度の代表的な結社(立志社、愛国社など)の名前は聞いたことはあっても、それ以外にも全国にたくさんの結社があったのは知らなかった。
そして、士族結社だけではなく、豪農結社というのもあるというのも分かった(豪農結社の中には、地元秋田にも「秋田立志会」というものがあって、明治初期の地元の歴史を知るきっかけにもなるかと思った)。
本書は自由党の解党で終わるが、この自由民権運動の流れがこの後どうなっていくのか、第2巻を読むのがが楽しみである。
最後に、自由民権運動は、その内実はともかく、関わった人々のエネルギーというものは大きかったのだろうと思う。
何かを為すには一人の力では限界がある。仲間を作らなければならない。
一人一人の力は微力であっても、倉山塾長も言っている通り、決して無力ではない。
そうしたところで、先ほどの東北の話にもなるが、数だけ多くても質が低いのはよくないが、質が高くても数が足りなければ、大きな力にはならない。
一人でも多く仲間を増やし、「くにまもり」に資することが大切だ。
そのために、日々できることを少しずつやっていかねばならない。
だいぶ自由民権運動とは離れたところの話をしてしまったが、このようなことを考えさせられた一冊だった。