書き易いけど使いどころに困る格好良いペンを買ったよ。
最近毎日秋葉原から上野まで歩いているのですが、ある日の会社帰り、御徒町のガードの万年筆や高級ボールペンを扱っている某お店の前を歩いていると、なんだか妙に魅力的なデザインのペンを発見。
なんだろう?
ボールペン?
メタルと木目のデザインが格好良い。
あ!
これ、ピニンファリーナのデザインだ!
お値段は・・・定価16,000円のところ・・・販売価格12,000円(税込)か・・・。
ちょうど良いペンは無いか探しているところだったので、12,000円だったら・・・良いか!?
と、思い切って買ってしまいました。
それが、これ。

あ、これ、外箱ね。
で、箱を開けると・・・

今度は木の箱。
箱にはピニンファリーナのロゴ!
これも結構格好良いもんだ。
ちなみにこの箱はそのままペン立てになります。
で、箱の横のプラスチック板をスライドさせると、いよいよペン本体が登場!

見てくださいよ。
格好良いでしょ?
ちなみに、ペン立てに立てるとこんな感じ。

うん、お店ではこんな感じに展示されてたんだよ。
で、一目惚れしちゃったわけですが、やっぱり良いなぁ・・・
と、ここまでデザインべた惚れのご報告だったわけですが、問題はこのブログのタイトルになっている「書き易いけど使いどころに困る」というところでございます。
書き易くて良いペンだったら会社に持って行って仕事に使おうかな・・・と思ったのですが、このペン、万年筆でもボールペンでも無いペンなのです。
以前テレビでもやったらしいので知っている人も多いのだと思いますが、コレはいわゆる「インクの必要が無く半永久的に書けるペン」なのです。(私は知らなかったのですが)
なんでも、ペン先の金属が紙との摩擦で紙に移ることで線が書け、しかも金属の消耗が非常に少ないために半永久的に使える・・・と言うことのようです。
確かにペン先を見てみると、ボールが無くインク溜りもありません。

ホント、どこまで書けるんだろう・・・こんなんで(笑)
と、いうわけで、紙を3種類用意して実際に書いてみたところ、こんな感じになりました。

【普通紙(OAコピー用紙)】
・筆圧にもよるが、結構普通に線が書けます。
・線の濃さはHB~B位かな?
・書き心地も多少ゴツゴツするもののなかなか良い感じ。
【写真用紙(ピクトリコプロ フォトペーパー】
・普通紙に比べるとかなり線が薄い(3H~6H位?)。
・書き心地も紙との摩擦抵抗が大きく書きづらい。
【年賀はがき(インクジェット用の表)】
・ビックリするほど線が書けない(10H以下?)。
・線に感じるのはペン先で圧迫した溝か?
・書き心地は写真用紙ほど悪くないが、線が書けなきゃ意味が無い。
こんな感じです。
ね?
デザインは超私好みで良く、「半永久的に書ける」というのも魅力的・・・・なのですが、こんなにも使いどころに困るペンは無いな・・・と(笑)
一番ペンで文字を書く機会が多い会社では紙がメモ用紙やポストイットも含め、このペンで線が書ける紙だけとは限らないしなぁ。
やっぱり家で、通常はインテリアとして、時に筆記用具として・・・という使い方が一番良いのかな・・・
う~ん・・・・使いどころに悩んでしまいます。
三菱鉛筆のJETSTREAM PRIMEシリーズに、このピニンファリーナのような洗練されたデザインの「大人が使って恥ずかしくない」デザインの高級ボールペンが出れば躊躇無く買うんだけどなぁ・・・

楽天市場での購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
なんだろう?
ボールペン?
メタルと木目のデザインが格好良い。
あ!
これ、ピニンファリーナのデザインだ!
お値段は・・・定価16,000円のところ・・・販売価格12,000円(税込)か・・・。
ちょうど良いペンは無いか探しているところだったので、12,000円だったら・・・良いか!?
と、思い切って買ってしまいました。
それが、これ。

あ、これ、外箱ね。
で、箱を開けると・・・

今度は木の箱。
箱にはピニンファリーナのロゴ!
これも結構格好良いもんだ。
ちなみにこの箱はそのままペン立てになります。
で、箱の横のプラスチック板をスライドさせると、いよいよペン本体が登場!

見てくださいよ。
格好良いでしょ?
ちなみに、ペン立てに立てるとこんな感じ。

うん、お店ではこんな感じに展示されてたんだよ。
で、一目惚れしちゃったわけですが、やっぱり良いなぁ・・・
と、ここまでデザインべた惚れのご報告だったわけですが、問題はこのブログのタイトルになっている「書き易いけど使いどころに困る」というところでございます。
書き易くて良いペンだったら会社に持って行って仕事に使おうかな・・・と思ったのですが、このペン、万年筆でもボールペンでも無いペンなのです。
以前テレビでもやったらしいので知っている人も多いのだと思いますが、コレはいわゆる「インクの必要が無く半永久的に書けるペン」なのです。(私は知らなかったのですが)
なんでも、ペン先の金属が紙との摩擦で紙に移ることで線が書け、しかも金属の消耗が非常に少ないために半永久的に使える・・・と言うことのようです。
確かにペン先を見てみると、ボールが無くインク溜りもありません。

ホント、どこまで書けるんだろう・・・こんなんで(笑)
と、いうわけで、紙を3種類用意して実際に書いてみたところ、こんな感じになりました。

【普通紙(OAコピー用紙)】
・筆圧にもよるが、結構普通に線が書けます。
・線の濃さはHB~B位かな?
・書き心地も多少ゴツゴツするもののなかなか良い感じ。
【写真用紙(ピクトリコプロ フォトペーパー】
・普通紙に比べるとかなり線が薄い(3H~6H位?)。
・書き心地も紙との摩擦抵抗が大きく書きづらい。
【年賀はがき(インクジェット用の表)】
・ビックリするほど線が書けない(10H以下?)。
・線に感じるのはペン先で圧迫した溝か?
・書き心地は写真用紙ほど悪くないが、線が書けなきゃ意味が無い。
こんな感じです。
ね?
デザインは超私好みで良く、「半永久的に書ける」というのも魅力的・・・・なのですが、こんなにも使いどころに困るペンは無いな・・・と(笑)
一番ペンで文字を書く機会が多い会社では紙がメモ用紙やポストイットも含め、このペンで線が書ける紙だけとは限らないしなぁ。
やっぱり家で、通常はインテリアとして、時に筆記用具として・・・という使い方が一番良いのかな・・・
う~ん・・・・使いどころに悩んでしまいます。
三菱鉛筆のJETSTREAM PRIMEシリーズに、このピニンファリーナのような洗練されたデザインの「大人が使って恥ずかしくない」デザインの高級ボールペンが出れば躊躇無く買うんだけどなぁ・・・

楽天市場での購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
スーパーツィーターを追加しました
2016年
新年あけましておめでとうございます。
本年もどのくらい更新ができるかはわかりませんが、くだらないことばかりを書き綴っている当ブログをどうぞよろしくお願い申し上げます。
さてさて、昨年末、暮れも暮れの12月29日にメインのオーディオシステムにスーパーツィーターを追加いたしました。
実は、冬のボーナスが出る少し前から(苦笑)色々と物色をしたのですが、現行品はなかなか食指が動くようなものがありませんでした。
・やけに高価だったり。
・許容入力が20~30W程度でメインスピーカーの許容入力と大きな開きがあり、アンプの出力を考えても20Wの許容入力では、実は聴こえない帯域の音が大きく歪んでいるのではないかと不安になってしまったり。
唯一、ELACの『4PI PLUS.2』は良いかな?と思ったけれど、周波数特性を見ると、上は53KHzまでしか出ないのが難だな・・・と。

で、あれでもないこれでもないとやっていた時に、ヤフオクを覗いていたところ、TANNOY生産終了品のスーパーツィーター『ST-200』が出品されておりました。

というわけで、何度もST-200が出品される度に入札を繰り返してきたのですが、まぁ最後の最後でことごとく競り負けてしまい、全然落札できません。
ついには、ST-200が出品一覧から姿を消してしまいました・・・
そんな時、ST-200の兄弟機で、筐体がウォールナット無垢材からアルミダイキャストに変更され、セッティング範囲がやや制限された『ST-50』が出品されてきたので、ゴム系樹脂でコーティングされているのがチョット気になりましたが、気合を入れて落札をしたのでありました。
で、そいつが12月29日に届いてきたわけであります。
30日は朝から栃木で餅つきで、夜から翌朝まで吉祥寺のMEGで毎年恒例の持ち寄りCD、レコードかけまくりイベントなので、何とか29日中に接続&動作確認をしなければなりません。
というわけで、まずはカットオフ周波数を18KHzに、レベル調整を93dBにして、取り急ぎ買っておいた銀コートOFCの切り売りケーブルでMEDEAとTS-50を接続し、早速音出しをしてみました。(まぁ、可聴領域外の音を鳴らすスピーカーなのでチェックもクソもないのですが)


まずは通常のCDでどれだけ音が変わるか。
よく「CDは20~20KHzの音までしか入っていない」と言われるけれど、最近のCDプレイヤーやDACはアップコンバートをして20KHz以上の音を仮想復元しているものが多いので、そういう機器を使っていればスーパーツィーターは十分に力を発揮できます。
まず聴いてみたのは、チェリスト長谷川陽子さんの「ノルウェーの森」のXRCD盤。


ノルウェーの森 / 長谷川陽子(XRCD)
HMVでの購入はコチラ (通常CD盤)
(通常CD盤)
Amazonでの購入はコチラ (XRCD)
(XRCD)
1曲目の「ノルウェーの森」の出だし、パーカッションの鈴の音で音に歴然の差が出ました。
ST-50を付けた後の音は、高音域の音がうるさくならずに粒立ちが明らかに明瞭になりました。
さらに、空間表現が上がり、音が部屋の壁を通り抜けてさらに奥に、さらに横に伸びていき、消えていく様になりました。
また、チェロとパーカッションの低音の解像度も上がり、チェロの弦の生々しさも僅かながら増し、MEDEAのMangerユニットの表現力もかなり引っ張られている感じです。
お次は同じくCD盤から、ジャズのシンバルを聴いてみることに。

SPIRAL CIRCLE / HELGE LIEN TRIO
disk unionでの購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
7曲目の「TAKE FIVE」はオーディオイベント等でもデモンストレーションで使用されることが有りますが、最初の1分ちょっとのドラムソロが明瞭で迫力満点、シンバルやパーカッション等の中~高音とバスドラムの腹に来るようなドスッとキレよく沈む低音が音質チェックには持って来いなのです。(演奏も良いよ)
で、ST-50を接続する前も、生々しく眼前で展開するドラムソロがたまりませんでしたが、ST-50を接続して聴き直すと、生々しいだけで無く、煌びやかに炸裂するシンバルやパーカッションの音の粒立ちがよりいっそう良くなり、バスドラムの低域の伸びや粒立ちも一聴して分かるほどに増してきました。
これだけだと、なんだかドンシャリのただ派手な音に変わってしまったように思われてしまいそうですが、そんなことは全く無く、むしろボリュームを上げても無用な刺々しさが無くなりました。
ドラムソロの後に出てくるベース、ピアノも音の立ち上がりが明瞭になりました。
よぉし、今度はSACDのジャズです。
新録の物では無く、日本のハイエンドオーディオメーカー「ESOTERIC」がBLUE NOTEのマスターテープからSACD用に徹底的に再マスタリングしたSACD-BOXで聴き比べをしてみました。

6 Great Jazz / V.A.(BLUE NOTE)
Amazonでの購入はコチラ
このSACD-BOXから、キャノンボール・アダレイの名盤「SOMETHIN' ELSE」。
1曲目の「枯葉」のピアノとベースで奏でられるバースがグッと生々しく、古いアナログマスターならではのノイズも鮮明になり、最良のアナログ盤を聴いているような(マスタリングが違うので比べられませんが)、もしくはラッカー盤を聴いているような錯覚に陥ります。
さすがはSACDと言うべきなのか、しかし、CDとして聴いても(SACDとCDのハイブリッド盤なので)同じような傾向で、グッとアナログチックにし、しかしながら曖昧なところの無い明瞭な音の粒立ちに、最初に聴いたときにはチョット鳥肌が立ちました。
マイルスのミュートトランペットも、今まで以上に管の輪郭がハッキリと浮かび上がり、キャノンボールのアルトサックスもリードの振動が寄り明瞭に見えるような、レコーディング時のスタジオの空気の流れが再現されるような粒立ちの良さに暫く聴き惚れました。
あとは、最近、FacebookとInstagramでの写真が可愛いピアニストのアリス=紗良・オットの作品で聴き比べ。

PICTURES / アリス=紗良・オット
Amazonでの購入はコチラ
本作ではムソルグスキーの「展覧会の絵」をピアノソロで引き上げています。
サンクトベルクのマリインスキー劇場コンサートホールでのライブ録音なので、いかに劇場の空気感、スケール感を感じられるか、そして、ステージ上のアリス=紗良・オットの演奏が見えてくるか・・・。
ST-50追加前でも、ホールの空気感やステージ上にたたずむ生々しい程のアリス=紗良・オットとピアノの存在を感じることができていました。
そこにST-50を追加すると・・・おぉ、ステージの見晴らしが今までよりも少し良くなり、更にピアノの音の粒立ちがよくなったので、今まで以上にアリス=紗良・オットの存在感が増しました。
スーパーツィーターを追加すると、広域ばかりが誇張され、乾いた音になるのではないかと思う方もいるかもしれませんが、いやいや、ライブの生々しさ、湿度、熱気、それらがよりきめ細やかに表現され、結果として音に艶が増した印象があります。
また、このCDでは特に、ボリュームを絞った時の空間表現が増したのが大きな収穫でした。
お次はアリス=紗良・オットが参加をしたオーラヴル・アルナルズとの2015年の共作作品です。


ショパン・プロジェクト / アルナルズオーラヴル&アリス=紗良・オット
HMVでの購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
この作品は、オーラヴル・アルナルズがショパンの様々な作品を彼なりに解釈し、様々な楽器、エフェクトなどの手法を用いて表現をしています。
この試みに賛同をしたアリス=紗良・オットがピアニストとして参加をしています。
ちなみに、オーラヴル・アルナルズは大学ではクラシックを学んでいたものの、その後はメタルバンドのドラマーとして活躍をしていたという異色(?)のミュージシャンです。
そんなアルナルズが意図をもって、楽器を組み合わせたり、本来であればレコーディングに入れないようなレコーディングノイズ等を作品に盛り込んでくるわけですから、それらをできるだけ詳らかに再現をして聴き取らなければ、彼の作品を堪能できたうちには入らない・・・ということになります。
微細なノイズの再生など、プアなオーディオではなかなか出来ないので、オーディオ機器の腕の見せ所・・・というわけです。
というわけで、いかに静寂を表現し、その中で楽器の旋律と、背後のノイズやエフェクトを団子にしないで再生できるかが重要になってきますが、ST-50、万歳!!
静寂表現や静寂の中でも背後で動いている空気感の再現、これはスーパーツィーターの恩恵を最大限に味わえる所です。
見事にMEDEAのMangerユニットの生々しい再生音にST-50の静寂や空気管の表現が違和感なくミックスされ、この作品の世界観に没頭することができました。
と、まだまだ聴き込めてはいませんが、今回の投資はかなり成功したんじゃないでしょうか。
金額的にもギリギリ10万円以下で済んだし。
あとは、とりあえずで買って繋いだスピーカーケーブルをどうするか・・・かな。
でも、スーパーツィーターのケーブル交換、どれほどの効果を発揮するのか・・・楽しそうでもあり、辛そうでもあり。(可聴範囲以上の音の変化だから・・・)
ちなみに、今回のスーパーツィーター追加のおかげで、スピーカーやその他の機器の設置等、ちょっと再調整の必要が出てきそうです。
ビッグバンドやフルオーケストラでの楽器の定位がほんの少し、曖昧になってしまった。
ただ、多分、このくらいならスピーカーの設置位置の微調整で何とかなると思うんだけどなぁ・・・。

新年あけましておめでとうございます。
本年もどのくらい更新ができるかはわかりませんが、くだらないことばかりを書き綴っている当ブログをどうぞよろしくお願い申し上げます。
さてさて、昨年末、暮れも暮れの12月29日にメインのオーディオシステムにスーパーツィーターを追加いたしました。
実は、冬のボーナスが出る少し前から(苦笑)色々と物色をしたのですが、現行品はなかなか食指が動くようなものがありませんでした。
・やけに高価だったり。
・許容入力が20~30W程度でメインスピーカーの許容入力と大きな開きがあり、アンプの出力を考えても20Wの許容入力では、実は聴こえない帯域の音が大きく歪んでいるのではないかと不安になってしまったり。
唯一、ELACの『4PI PLUS.2』は良いかな?と思ったけれど、周波数特性を見ると、上は53KHzまでしか出ないのが難だな・・・と。

で、あれでもないこれでもないとやっていた時に、ヤフオクを覗いていたところ、TANNOY生産終了品のスーパーツィーター『ST-200』が出品されておりました。

というわけで、何度もST-200が出品される度に入札を繰り返してきたのですが、まぁ最後の最後でことごとく競り負けてしまい、全然落札できません。
ついには、ST-200が出品一覧から姿を消してしまいました・・・
そんな時、ST-200の兄弟機で、筐体がウォールナット無垢材からアルミダイキャストに変更され、セッティング範囲がやや制限された『ST-50』が出品されてきたので、ゴム系樹脂でコーティングされているのがチョット気になりましたが、気合を入れて落札をしたのでありました。
で、そいつが12月29日に届いてきたわけであります。
30日は朝から栃木で餅つきで、夜から翌朝まで吉祥寺のMEGで毎年恒例の持ち寄りCD、レコードかけまくりイベントなので、何とか29日中に接続&動作確認をしなければなりません。
というわけで、まずはカットオフ周波数を18KHzに、レベル調整を93dBにして、取り急ぎ買っておいた銀コートOFCの切り売りケーブルでMEDEAとTS-50を接続し、早速音出しをしてみました。(まぁ、可聴領域外の音を鳴らすスピーカーなのでチェックもクソもないのですが)


まずは通常のCDでどれだけ音が変わるか。
よく「CDは20~20KHzの音までしか入っていない」と言われるけれど、最近のCDプレイヤーやDACはアップコンバートをして20KHz以上の音を仮想復元しているものが多いので、そういう機器を使っていればスーパーツィーターは十分に力を発揮できます。
まず聴いてみたのは、チェリスト長谷川陽子さんの「ノルウェーの森」のXRCD盤。

ノルウェーの森 / 長谷川陽子(XRCD)
HMVでの購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
1曲目の「ノルウェーの森」の出だし、パーカッションの鈴の音で音に歴然の差が出ました。
ST-50を付けた後の音は、高音域の音がうるさくならずに粒立ちが明らかに明瞭になりました。
さらに、空間表現が上がり、音が部屋の壁を通り抜けてさらに奥に、さらに横に伸びていき、消えていく様になりました。
また、チェロとパーカッションの低音の解像度も上がり、チェロの弦の生々しさも僅かながら増し、MEDEAのMangerユニットの表現力もかなり引っ張られている感じです。
お次は同じくCD盤から、ジャズのシンバルを聴いてみることに。

SPIRAL CIRCLE / HELGE LIEN TRIO
disk unionでの購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
7曲目の「TAKE FIVE」はオーディオイベント等でもデモンストレーションで使用されることが有りますが、最初の1分ちょっとのドラムソロが明瞭で迫力満点、シンバルやパーカッション等の中~高音とバスドラムの腹に来るようなドスッとキレよく沈む低音が音質チェックには持って来いなのです。(演奏も良いよ)
で、ST-50を接続する前も、生々しく眼前で展開するドラムソロがたまりませんでしたが、ST-50を接続して聴き直すと、生々しいだけで無く、煌びやかに炸裂するシンバルやパーカッションの音の粒立ちがよりいっそう良くなり、バスドラムの低域の伸びや粒立ちも一聴して分かるほどに増してきました。
これだけだと、なんだかドンシャリのただ派手な音に変わってしまったように思われてしまいそうですが、そんなことは全く無く、むしろボリュームを上げても無用な刺々しさが無くなりました。
ドラムソロの後に出てくるベース、ピアノも音の立ち上がりが明瞭になりました。
よぉし、今度はSACDのジャズです。
新録の物では無く、日本のハイエンドオーディオメーカー「ESOTERIC」がBLUE NOTEのマスターテープからSACD用に徹底的に再マスタリングしたSACD-BOXで聴き比べをしてみました。

6 Great Jazz / V.A.(BLUE NOTE)
Amazonでの購入はコチラ
このSACD-BOXから、キャノンボール・アダレイの名盤「SOMETHIN' ELSE」。
1曲目の「枯葉」のピアノとベースで奏でられるバースがグッと生々しく、古いアナログマスターならではのノイズも鮮明になり、最良のアナログ盤を聴いているような(マスタリングが違うので比べられませんが)、もしくはラッカー盤を聴いているような錯覚に陥ります。
さすがはSACDと言うべきなのか、しかし、CDとして聴いても(SACDとCDのハイブリッド盤なので)同じような傾向で、グッとアナログチックにし、しかしながら曖昧なところの無い明瞭な音の粒立ちに、最初に聴いたときにはチョット鳥肌が立ちました。
マイルスのミュートトランペットも、今まで以上に管の輪郭がハッキリと浮かび上がり、キャノンボールのアルトサックスもリードの振動が寄り明瞭に見えるような、レコーディング時のスタジオの空気の流れが再現されるような粒立ちの良さに暫く聴き惚れました。
あとは、最近、FacebookとInstagramでの写真が可愛いピアニストのアリス=紗良・オットの作品で聴き比べ。

PICTURES / アリス=紗良・オット
Amazonでの購入はコチラ
本作ではムソルグスキーの「展覧会の絵」をピアノソロで引き上げています。
サンクトベルクのマリインスキー劇場コンサートホールでのライブ録音なので、いかに劇場の空気感、スケール感を感じられるか、そして、ステージ上のアリス=紗良・オットの演奏が見えてくるか・・・。
ST-50追加前でも、ホールの空気感やステージ上にたたずむ生々しい程のアリス=紗良・オットとピアノの存在を感じることができていました。
そこにST-50を追加すると・・・おぉ、ステージの見晴らしが今までよりも少し良くなり、更にピアノの音の粒立ちがよくなったので、今まで以上にアリス=紗良・オットの存在感が増しました。
スーパーツィーターを追加すると、広域ばかりが誇張され、乾いた音になるのではないかと思う方もいるかもしれませんが、いやいや、ライブの生々しさ、湿度、熱気、それらがよりきめ細やかに表現され、結果として音に艶が増した印象があります。
また、このCDでは特に、ボリュームを絞った時の空間表現が増したのが大きな収穫でした。
お次はアリス=紗良・オットが参加をしたオーラヴル・アルナルズとの2015年の共作作品です。

ショパン・プロジェクト / アルナルズオーラヴル&アリス=紗良・オット
HMVでの購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
この作品は、オーラヴル・アルナルズがショパンの様々な作品を彼なりに解釈し、様々な楽器、エフェクトなどの手法を用いて表現をしています。
この試みに賛同をしたアリス=紗良・オットがピアニストとして参加をしています。
ちなみに、オーラヴル・アルナルズは大学ではクラシックを学んでいたものの、その後はメタルバンドのドラマーとして活躍をしていたという異色(?)のミュージシャンです。
そんなアルナルズが意図をもって、楽器を組み合わせたり、本来であればレコーディングに入れないようなレコーディングノイズ等を作品に盛り込んでくるわけですから、それらをできるだけ詳らかに再現をして聴き取らなければ、彼の作品を堪能できたうちには入らない・・・ということになります。
微細なノイズの再生など、プアなオーディオではなかなか出来ないので、オーディオ機器の腕の見せ所・・・というわけです。
というわけで、いかに静寂を表現し、その中で楽器の旋律と、背後のノイズやエフェクトを団子にしないで再生できるかが重要になってきますが、ST-50、万歳!!
静寂表現や静寂の中でも背後で動いている空気感の再現、これはスーパーツィーターの恩恵を最大限に味わえる所です。
見事にMEDEAのMangerユニットの生々しい再生音にST-50の静寂や空気管の表現が違和感なくミックスされ、この作品の世界観に没頭することができました。
と、まだまだ聴き込めてはいませんが、今回の投資はかなり成功したんじゃないでしょうか。
金額的にもギリギリ10万円以下で済んだし。
あとは、とりあえずで買って繋いだスピーカーケーブルをどうするか・・・かな。
でも、スーパーツィーターのケーブル交換、どれほどの効果を発揮するのか・・・楽しそうでもあり、辛そうでもあり。(可聴範囲以上の音の変化だから・・・)
ちなみに、今回のスーパーツィーター追加のおかげで、スピーカーやその他の機器の設置等、ちょっと再調整の必要が出てきそうです。
ビッグバンドやフルオーケストラでの楽器の定位がほんの少し、曖昧になってしまった。
ただ、多分、このくらいならスピーカーの設置位置の微調整で何とかなると思うんだけどなぁ・・・。

TW-S9のUSBケーブルを変えてみた
音楽を再生するたびに「ほぉ~っ!」と感心させられるOlasonicのUSBスピーカー「TW-S9」なのですが、感心するたびに「なにかもう一工夫してさらに音を良く出来ないか・・・」と考えてしまうわけです。
足回りに関しては既に御影石のインシュレータを敷いて対策をしているので・・・次はやはり、ケーブルか・・・?
・・・と、いうわけで、今回、こいつを買ってTW-S9付属品のUSBケーブルを聴き比べをしてみることに致しました。

オーディオファンなら知っている人も多いケーブルメーカー「AudioQuest」のCARBON USB2.0 A→B(1.5m) です。
です。
約1.5万円で購入できますが、TW-S9との価格差を考えるとちょっと割高かな?(それにしても、先日買った外付けの4TBのHDDとほぼ同額って・・・)
このケーブルの特徴は、導線に5%厚のシルバーコーティングを施した長粒状銅(LGC)を使用し、カーボン合成繊維を使用した3層ノイズ消散システムにより、ノイズを信号グランドにつながる層に到達する前にこのエネルギーの大部分が吸収および反射する・・・というもの。
ちなみにケーブル本体はこんな感じ。

コネクタカバーがプラスチック製なのがちょっと残念ですが(通電による発振を抑えるならやはりメタルカバー?)、これだけ蘊蓄の詰まったケーブルなのだから(笑)、おまけで付いているケーブルとは異なる音を聴かせてくれるに違いありません。多分。
付属品のケーブルとAudioQuestのCarbonを並べるとこんな感じ。

存在感が圧倒的に違うのが良い。
ただ、Carbonの方はケーブルがやや硬く取り回しがし辛いので、配線にはちょっと注意が必要かも。
さて、まずは既存の付属品ケーブルを繋いでTW-S9でいろいろと聴いた後、すぐにケーブルをAudioQuestのCarbonに繋ぎ替えます。
で、色々と聴き比べてみました。
まずはコチラ。
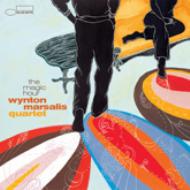

The Magic Hour / Wynton Marsalis
HMVでの購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
ジャズトランペッターのWynton Marsalisの2004年の作品で、1曲目の「Feeling Of Jazz」のウッドベース、スネアドラムのリムをたたく音、そしてヴォーカルと、聴き所が沢山あり作品としてもバラエティに富んで楽しい作品なので、オーディオチェックの時には良く聴いています。
で、肝心の付属品ケーブルとCarbonの差は・・・というと、まず、出だしのベースの低音の解像度がグッと高くなりました。
そしてさらに、ドラムのリムを叩く音もシンバルを叩く音も、音の伸びが非常にスムーズになり、特にシンバルに関してはボリュームを上げても「うるさい!」と感じることは無くなりました。
ただ、このCDのボーカルに関しては、少し大人しくなってさらにステージが少し奥に下がった感じがします。
なるほど、この1枚を以てしてもUSBケーブルで音が大きく変わることが分かりました。
というわけで、楽しくなって次のCDへ。

Hot Five / Torbjörn Zetterberg
HMVでの購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
こいつの3曲目、「Familyfarm Blues」のドス黒く暴れまくるベース、バリトンサックスをボリュームを上げて聴いたときの圧倒される感じが最高。
この曲はボリュームを上げると、下手なシステムでは五月蠅くなるし爆音に細かな音が埋もれるしろくな事が無いのですが、まず、TW-S9は付属品のケーブルでもこの曲をそれなりにしっかりと聴かせてくれます。
これがCarbonにケーブルを変更すると、解像度が上がったため、付属品ケーブルでは埋もれがちになっていたピアノやシンバルの細かいニュアンスまでちゃんと浮き上がってきました。
そしてなにより、ボリュームを上げても不要な刺々しさが無くなり、音圧の持つ説得力だけがしっかりと感じられ、近所迷惑を考えなければもっとボリュームを上げて聴きたいくらいです。(上げ過ぎるとスピーカーが傷みそうですが)
お次はクラシック。
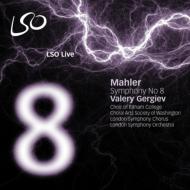

マーラー 交響曲8番「千人の交響曲」 / ゲルギエフ指揮・ロンドン交響楽団
HMVでの購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
この楽曲は壮大で、独唱も有り合唱も有り、とにかく細かく緻密に音像を描けないシステムでは音が団子になって全然音楽にのめり込めなくなってしまいます。
ケーブルを変える前までは、確かに、いい音で、しっかりとステージを表現していました。
しかし、ケーブルを変えてみたら付属品ケーブルでは描き切れていなかったステージの奥行き、コーラス一人一人の声の粒立ちに気付きます。
特に最後のトラックが再生されると・・・静寂の中コーラスだけがステージの奥で囁くように歌う出だしで、改めてこのスピーカーの真価を実感できました。
いやはや、これはもう、付属品ケーブルには戻れません。
そうなってくると・・・今度は左右のTW-S9を繋いでいるステレオミニプラグケーブルも交換したくなってきました。
なにせ、こちらはアナログケーブルなので寄り音質に影響が有るのでは無いか・・・と・・・。
というわけで、後日、ステレオミニプラグケーブルを交換して視聴録をUP致します!
足回りに関しては既に御影石のインシュレータを敷いて対策をしているので・・・次はやはり、ケーブルか・・・?
・・・と、いうわけで、今回、こいつを買ってTW-S9付属品のUSBケーブルを聴き比べをしてみることに致しました。

オーディオファンなら知っている人も多いケーブルメーカー「AudioQuest」のCARBON USB2.0 A→B(1.5m)
約1.5万円で購入できますが、TW-S9との価格差を考えるとちょっと割高かな?(それにしても、先日買った外付けの4TBのHDDとほぼ同額って・・・)
このケーブルの特徴は、導線に5%厚のシルバーコーティングを施した長粒状銅(LGC)を使用し、カーボン合成繊維を使用した3層ノイズ消散システムにより、ノイズを信号グランドにつながる層に到達する前にこのエネルギーの大部分が吸収および反射する・・・というもの。
ちなみにケーブル本体はこんな感じ。

コネクタカバーがプラスチック製なのがちょっと残念ですが(通電による発振を抑えるならやはりメタルカバー?)、これだけ蘊蓄の詰まったケーブルなのだから(笑)、おまけで付いているケーブルとは異なる音を聴かせてくれるに違いありません。多分。
付属品のケーブルとAudioQuestのCarbonを並べるとこんな感じ。

存在感が圧倒的に違うのが良い。
ただ、Carbonの方はケーブルがやや硬く取り回しがし辛いので、配線にはちょっと注意が必要かも。
さて、まずは既存の付属品ケーブルを繋いでTW-S9でいろいろと聴いた後、すぐにケーブルをAudioQuestのCarbonに繋ぎ替えます。
で、色々と聴き比べてみました。
まずはコチラ。
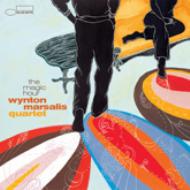
The Magic Hour / Wynton Marsalis
HMVでの購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
ジャズトランペッターのWynton Marsalisの2004年の作品で、1曲目の「Feeling Of Jazz」のウッドベース、スネアドラムのリムをたたく音、そしてヴォーカルと、聴き所が沢山あり作品としてもバラエティに富んで楽しい作品なので、オーディオチェックの時には良く聴いています。
で、肝心の付属品ケーブルとCarbonの差は・・・というと、まず、出だしのベースの低音の解像度がグッと高くなりました。
そしてさらに、ドラムのリムを叩く音もシンバルを叩く音も、音の伸びが非常にスムーズになり、特にシンバルに関してはボリュームを上げても「うるさい!」と感じることは無くなりました。
ただ、このCDのボーカルに関しては、少し大人しくなってさらにステージが少し奥に下がった感じがします。
なるほど、この1枚を以てしてもUSBケーブルで音が大きく変わることが分かりました。
というわけで、楽しくなって次のCDへ。

Hot Five / Torbjörn Zetterberg
HMVでの購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
こいつの3曲目、「Familyfarm Blues」のドス黒く暴れまくるベース、バリトンサックスをボリュームを上げて聴いたときの圧倒される感じが最高。
この曲はボリュームを上げると、下手なシステムでは五月蠅くなるし爆音に細かな音が埋もれるしろくな事が無いのですが、まず、TW-S9は付属品のケーブルでもこの曲をそれなりにしっかりと聴かせてくれます。
これがCarbonにケーブルを変更すると、解像度が上がったため、付属品ケーブルでは埋もれがちになっていたピアノやシンバルの細かいニュアンスまでちゃんと浮き上がってきました。
そしてなにより、ボリュームを上げても不要な刺々しさが無くなり、音圧の持つ説得力だけがしっかりと感じられ、近所迷惑を考えなければもっとボリュームを上げて聴きたいくらいです。(上げ過ぎるとスピーカーが傷みそうですが)
お次はクラシック。
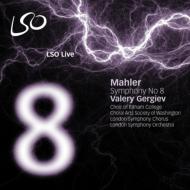
マーラー 交響曲8番「千人の交響曲」 / ゲルギエフ指揮・ロンドン交響楽団
HMVでの購入はコチラ
Amazonでの購入はコチラ
この楽曲は壮大で、独唱も有り合唱も有り、とにかく細かく緻密に音像を描けないシステムでは音が団子になって全然音楽にのめり込めなくなってしまいます。
ケーブルを変える前までは、確かに、いい音で、しっかりとステージを表現していました。
しかし、ケーブルを変えてみたら付属品ケーブルでは描き切れていなかったステージの奥行き、コーラス一人一人の声の粒立ちに気付きます。
特に最後のトラックが再生されると・・・静寂の中コーラスだけがステージの奥で囁くように歌う出だしで、改めてこのスピーカーの真価を実感できました。
いやはや、これはもう、付属品ケーブルには戻れません。
そうなってくると・・・今度は左右のTW-S9を繋いでいるステレオミニプラグケーブルも交換したくなってきました。
なにせ、こちらはアナログケーブルなので寄り音質に影響が有るのでは無いか・・・と・・・。
というわけで、後日、ステレオミニプラグケーブルを交換して視聴録をUP致します!