盲目のレコーディングエンジニア
先日、雑誌ジャズ批評の取材で、盲目のレコーディングエンジニア、加藤弘之さんにお会いしてきました。

加藤さんは自ら「MUSIC STUDIO JAZZIN」というスタジオを作り、ミュージシャンの練習場として提供されるだけではなく、ジャズボーカリストのMAYAさんのデビュー作「Why try to change me now?」や、2作目「She's Something」、その他多数のレコーディングも行われました。
そして、いよいよ自らジャズ専門レーベル「JAZZIN」を立ち上げ、第一弾として、12月17日に下記の2枚のCDを発売します。
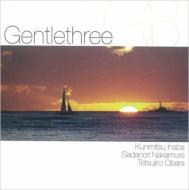

Gentle Three/Gentle Three
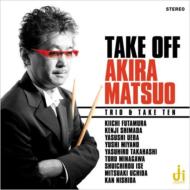

松尾明 / Take Ten/Take Off
なるほど、レコーディングエンジニアと言うよりも「レコーディングアーティスト」と言った方が良さそうだな・・・などと思いながらお話を伺っておりました。
詳しくは12月発売のジャズ批評147号をご覧下さい。

加藤さんは自ら「MUSIC STUDIO JAZZIN」というスタジオを作り、ミュージシャンの練習場として提供されるだけではなく、ジャズボーカリストのMAYAさんのデビュー作「Why try to change me now?」や、2作目「She's Something」、その他多数のレコーディングも行われました。
そして、いよいよ自らジャズ専門レーベル「JAZZIN」を立ち上げ、第一弾として、12月17日に下記の2枚のCDを発売します。
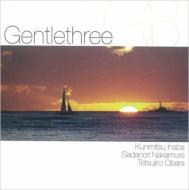
Gentle Three/Gentle Three
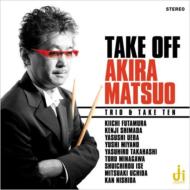
松尾明 / Take Ten/Take Off
なるほど、レコーディングエンジニアと言うよりも「レコーディングアーティスト」と言った方が良さそうだな・・・などと思いながらお話を伺っておりました。
詳しくは12月発売のジャズ批評147号をご覧下さい。
ズズズ〜ン!
この世は
“辛いもの”と
“辛くないもの”の
2つで構成されている
いやぁ、先日のブログの通り、モランボンの「ユッケジャンクッパ」に、凶悪ホットソース「The Source」をほんのチョット(箸の先に本の少し付いたか付いていないか位)入れたらもう、辛いの辛くないのって・・・・
「こんなの食えるかぁ~!!」
と、眼を剥きながらも、口内の粘膜と唇全体が真っ赤になりながら、痛みをこらえつつ完食しました。
辛さこそ異常な程に増したものの、もともとのユッケジャンクッパの旨味自体は損なわず、そう言う意味では美味しく頂けたのが原因でしょうか。
でも、痛い・・・痛い・・・・・
それはそうと、吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のHP管理人をされているH氏に送って頂いたCDをご紹介。
演奏者はその名も「ざ・低音一家」。
女性3人のグループで、全員がコントラバスを演奏するというなんとも珍しいトリオ。
クラシックでもジャズでも非常に重要な位置付けにありながら、それ単体としてはあまり脚光を浴びていない(?)コントラバスだけで演奏を成立させようというのが何とも面白い。
メンバーは、リーダーでコントラバス担当の廣田昌世さん、コントラバス担当の岡田亜矢子さん、コントラバス担当の東ともみさんの3人。
(わざわざ担当楽器の紹介をする必要も無いけれど・・・)
そう言えば、コントラバスグループというと、L’orchestre De Contrebassesというコントラバス6人組のCD「Bass Bass Bass Bass Bass & Bass 」や、池松宏さんの「Nova Contrabass!
」や、池松宏さんの「Nova Contrabass! 」というアルバムの中で6人編成のコントラバスグループの演奏が入っているのは知っている(持っている)けれど、3人と言うのは無かったなぁ。
」というアルバムの中で6人編成のコントラバスグループの演奏が入っているのは知っている(持っている)けれど、3人と言うのは無かったなぁ。
あ、他にもコントラバス(ウッドベース)のソロアルバムだったら、安カ川大樹さんの「Let My Tears Sing 」っていうのもあった。あれは好演奏&高音質盤ですよ。
」っていうのもあった。あれは好演奏&高音質盤ですよ。
というわけで、ざ・低音一家のデビューCD「Luna de gris」を聴かせて頂きました。

Luna de gris / ざ・低音一家
■1曲目『ななころびやおき』
廣田さんのオリジナル曲。
非常に軽快でまさに始まりの曲にふさわしいメロディー。
2人が弓でメロディーを奏で、1人がピッチカートでリズムを刻む。
これがなんともジャズテイストで自然と体が揺れてきます。
アルコの2人の音には特にジャズを感じないのだけれど、3人が合わさると・・・なんとスウィングしているのでしょう。
このアルバムで一番好きかもしれない1曲。
■2曲目『九月の雨』
3人がピッチカート奏法で臨んだ1曲。
出だしはコントラバスの胴をパーカッションの様に叩いて雨音を表現しています。
コントラバスの弦以外の表現としては良くある手法ですが、パタパタとちゃんと雨音の様に聴こえてくるのが良い感じです。
全編弓を使わない演奏なので、緩急が付き辛いと言うのはあるのでしょうが、メインのメロディーが美しいので曲としてのまとまりはしっかりしています。
ただ、個人的にはもう少し「弾き過ぎ」ても良かったんじゃないかな?とも思ったり・・・
■3曲目『アイ・ガット・リズム』
ジャズでも良く演奏されるジョージ・ガーシュインの名曲「I got rhythm」。
これもリズミカルにいくのかな・・・と思ったら、アレ?アルコのアドリブから始まりました。
そのままリズムを得る事無く2分17秒・・・待ちに待ったところでようやく「I got rhythm」の名の通り、非常にリズミカルでスウィングした演奏へと変わって行きます。
最初のリズムの無い演奏はこの爽快感への助走だったのでしょうか。
ピッチカートのリズムが加わると、さすが、コントラバス独特の弦の豊かな低音と、小気味良いリズムに体が動いてきます。
ただ、個人的にはもうちょっと早くリズムが欲しかった・・・(笑)
■4曲目『水曜日の男』
再び廣田さんのオリジナル曲。
出だし、ちょっと技巧に走り過ぎた?
ともあれ、本編が始まると、その面白気なメロディーに「水曜日の男」がただ者ではないのが伺えます。
そのメロディーが延々と続き、いつの間にか頭の中でリピートしてしまっているところが恐ろしい。
新手の麻薬曲?
■5曲目『ザネリのように』
廣田さんの曲が続きます。
コントラバスの超高音(フラジオレット奏法?)。これもまた、チェロにもヴィオラに出せない独特の音色です。
これとコントラバス本来の低音、ピッチカート奏法が混じり合う出だし、非常に幻想的で素敵です。
そして急にコントラバスらしい弓が弦を擦る音が登場し、場面を転換させます。
出だしの幻想的で厳かな印象から、怠惰な雰囲気を醸し出した、心地良く空を飛んでいる様なイメージに変わります。
技術もさることながら、曲がイイ。
■6曲目『職人の休日』
コチラも廣田さんの曲。
出だしは何とも朗らか優しい日差しが窓からアトリエを照らしているような、優雅なイメージで始まります。
そこから、まるで誰かが喋っているかの様な、擬人的なアルコが入ってから優雅な休日が終わり、慌ただしくなっていきます。
ただ、慌ただしくも陽気な活気があり、非常に楽し気。
ストーリーがしっかりとした1曲になっていて好感が持てます。
■7曲目『あなたが欲しい』
コチラはエリック・サティの名曲。
聴けば「あぁ!この曲ね!」と誰もがうなずく曲です。
この曲を聴くと、ファミコンのゲーム「バイナリィランド」を思い出す・・・(笑)
そんな曲を非常に巧妙に料理し、3人のコントラバスのピッチカートが見事に聴かせます。
なるほど、こういう風に聴かせられるのは初めて。
素晴らしいアレンジです。
■8曲目『ルナ・デ・グリス』
再び廣田さんの曲。
暗いムードの曲ですが、なんと美しいメロディーでしょう。
このバラードはコントラバスで奏でられるからこそ、ここまでの艶やかさと切なさを表現できるのでしょう。
参った。
この曲は胸に刺さってくる。
切ない、そして苦しい・・・でも、やめられない1曲。
■9曲目『プレリュディオ・エス・プロセシオン』
日本語にすると『前奏曲「S」行列』。
ざ・低音一家のリハーサルスタジオのイニシャルらしく、こちらも廣田さんの曲。
非常に低い「重低音」が印象的。
ただ、難曲です。
非常に内向的で小さく、小さく力を発してきます。
まるでこれから盛大な何かが始まるかの様な、「嵐の前の静けさ」とも言える演奏が長く続き、多少リズミカルになったかと思えど、すぐに弦をバチで弾くかの様な力強さで収束し、再び重低音の内向的な雰囲気の、暗いイメージに戻って行きます。
なるほど、曲の構成も見事。
ただ・・・難曲です。
■10曲目『カサ<家>』
最後も廣田さんの曲で締めです。
夕方、影が長く伸びた路を歩いて家を目指す・・・そんなイメージがすぐに沸いてくる曲です。
歩いているのは自分一人。
ちょっと寂しい感じもあったり、それでいてホッとする感じもあったり。
この曲も素晴らしい。
演奏もシンプルだからストレートにメロディーが、曲の印象が入ってきます。
さようなら。
良い曲です。
いやはや、良いCDを紹介して頂きました。
Hさん、どうもありがとうございました!
ここで敢えて言いましょう。
この世は
“低音のもの”と
“低音でないもの”の
2つで構成されている
“辛いもの”と
“辛くないもの”の
2つで構成されている
いやぁ、先日のブログの通り、モランボンの「ユッケジャンクッパ」に、凶悪ホットソース「The Source」をほんのチョット(箸の先に本の少し付いたか付いていないか位)入れたらもう、辛いの辛くないのって・・・・
「こんなの食えるかぁ~!!」
と、眼を剥きながらも、口内の粘膜と唇全体が真っ赤になりながら、痛みをこらえつつ完食しました。
辛さこそ異常な程に増したものの、もともとのユッケジャンクッパの旨味自体は損なわず、そう言う意味では美味しく頂けたのが原因でしょうか。
でも、痛い・・・痛い・・・・・
それはそうと、吉祥寺のジャズ喫茶「MEG」のHP管理人をされているH氏に送って頂いたCDをご紹介。
演奏者はその名も「ざ・低音一家」。
女性3人のグループで、全員がコントラバスを演奏するというなんとも珍しいトリオ。
クラシックでもジャズでも非常に重要な位置付けにありながら、それ単体としてはあまり脚光を浴びていない(?)コントラバスだけで演奏を成立させようというのが何とも面白い。
メンバーは、リーダーでコントラバス担当の廣田昌世さん、コントラバス担当の岡田亜矢子さん、コントラバス担当の東ともみさんの3人。
(わざわざ担当楽器の紹介をする必要も無いけれど・・・)
そう言えば、コントラバスグループというと、L’orchestre De Contrebassesというコントラバス6人組のCD「Bass Bass Bass Bass Bass & Bass
あ、他にもコントラバス(ウッドベース)のソロアルバムだったら、安カ川大樹さんの「Let My Tears Sing
というわけで、ざ・低音一家のデビューCD「Luna de gris」を聴かせて頂きました。

Luna de gris / ざ・低音一家
■1曲目『ななころびやおき』
廣田さんのオリジナル曲。
非常に軽快でまさに始まりの曲にふさわしいメロディー。
2人が弓でメロディーを奏で、1人がピッチカートでリズムを刻む。
これがなんともジャズテイストで自然と体が揺れてきます。
アルコの2人の音には特にジャズを感じないのだけれど、3人が合わさると・・・なんとスウィングしているのでしょう。
このアルバムで一番好きかもしれない1曲。
■2曲目『九月の雨』
3人がピッチカート奏法で臨んだ1曲。
出だしはコントラバスの胴をパーカッションの様に叩いて雨音を表現しています。
コントラバスの弦以外の表現としては良くある手法ですが、パタパタとちゃんと雨音の様に聴こえてくるのが良い感じです。
全編弓を使わない演奏なので、緩急が付き辛いと言うのはあるのでしょうが、メインのメロディーが美しいので曲としてのまとまりはしっかりしています。
ただ、個人的にはもう少し「弾き過ぎ」ても良かったんじゃないかな?とも思ったり・・・
■3曲目『アイ・ガット・リズム』
ジャズでも良く演奏されるジョージ・ガーシュインの名曲「I got rhythm」。
これもリズミカルにいくのかな・・・と思ったら、アレ?アルコのアドリブから始まりました。
そのままリズムを得る事無く2分17秒・・・待ちに待ったところでようやく「I got rhythm」の名の通り、非常にリズミカルでスウィングした演奏へと変わって行きます。
最初のリズムの無い演奏はこの爽快感への助走だったのでしょうか。
ピッチカートのリズムが加わると、さすが、コントラバス独特の弦の豊かな低音と、小気味良いリズムに体が動いてきます。
ただ、個人的にはもうちょっと早くリズムが欲しかった・・・(笑)
■4曲目『水曜日の男』
再び廣田さんのオリジナル曲。
出だし、ちょっと技巧に走り過ぎた?
ともあれ、本編が始まると、その面白気なメロディーに「水曜日の男」がただ者ではないのが伺えます。
そのメロディーが延々と続き、いつの間にか頭の中でリピートしてしまっているところが恐ろしい。
新手の麻薬曲?
■5曲目『ザネリのように』
廣田さんの曲が続きます。
コントラバスの超高音(フラジオレット奏法?)。これもまた、チェロにもヴィオラに出せない独特の音色です。
これとコントラバス本来の低音、ピッチカート奏法が混じり合う出だし、非常に幻想的で素敵です。
そして急にコントラバスらしい弓が弦を擦る音が登場し、場面を転換させます。
出だしの幻想的で厳かな印象から、怠惰な雰囲気を醸し出した、心地良く空を飛んでいる様なイメージに変わります。
技術もさることながら、曲がイイ。
■6曲目『職人の休日』
コチラも廣田さんの曲。
出だしは何とも朗らか優しい日差しが窓からアトリエを照らしているような、優雅なイメージで始まります。
そこから、まるで誰かが喋っているかの様な、擬人的なアルコが入ってから優雅な休日が終わり、慌ただしくなっていきます。
ただ、慌ただしくも陽気な活気があり、非常に楽し気。
ストーリーがしっかりとした1曲になっていて好感が持てます。
■7曲目『あなたが欲しい』
コチラはエリック・サティの名曲。
聴けば「あぁ!この曲ね!」と誰もがうなずく曲です。
この曲を聴くと、ファミコンのゲーム「バイナリィランド」を思い出す・・・(笑)
そんな曲を非常に巧妙に料理し、3人のコントラバスのピッチカートが見事に聴かせます。
なるほど、こういう風に聴かせられるのは初めて。
素晴らしいアレンジです。
■8曲目『ルナ・デ・グリス』
再び廣田さんの曲。
暗いムードの曲ですが、なんと美しいメロディーでしょう。
このバラードはコントラバスで奏でられるからこそ、ここまでの艶やかさと切なさを表現できるのでしょう。
参った。
この曲は胸に刺さってくる。
切ない、そして苦しい・・・でも、やめられない1曲。
■9曲目『プレリュディオ・エス・プロセシオン』
日本語にすると『前奏曲「S」行列』。
ざ・低音一家のリハーサルスタジオのイニシャルらしく、こちらも廣田さんの曲。
非常に低い「重低音」が印象的。
ただ、難曲です。
非常に内向的で小さく、小さく力を発してきます。
まるでこれから盛大な何かが始まるかの様な、「嵐の前の静けさ」とも言える演奏が長く続き、多少リズミカルになったかと思えど、すぐに弦をバチで弾くかの様な力強さで収束し、再び重低音の内向的な雰囲気の、暗いイメージに戻って行きます。
なるほど、曲の構成も見事。
ただ・・・難曲です。
■10曲目『カサ<家>』
最後も廣田さんの曲で締めです。
夕方、影が長く伸びた路を歩いて家を目指す・・・そんなイメージがすぐに沸いてくる曲です。
歩いているのは自分一人。
ちょっと寂しい感じもあったり、それでいてホッとする感じもあったり。
この曲も素晴らしい。
演奏もシンプルだからストレートにメロディーが、曲の印象が入ってきます。
さようなら。
良い曲です。
いやはや、良いCDを紹介して頂きました。
Hさん、どうもありがとうございました!
ここで敢えて言いましょう。
この世は
“低音のもの”と
“低音でないもの”の
2つで構成されている
変革と改良
海の向こうのジャズの国では、ついに差別の歴史を塗り替える黒人大統領が誕生し、変革の時代へと突入するようです。
それはさておき、日本ではソニー・ミュージックエンタテインメントが1982年に発売されて以来、ずっと変わらずに発売され続けてきている音楽CDに新しい技術を投入し、改良を施して高音質化を達成したというニュースが出ました。

音楽CDは、登場から25年以上経過し、既に「古いメディア」と認識され、これを上回る高音質且つ大容量のDVD-AudioやSACDが登場しているにもかかわらず、現在でも主たる音楽供給メディアとして活躍しています。
これまでも多くのメーカーが音楽CDの規格のまま音質を向上させようと、製造過程を一新したxrcd、先日もブログで紹介した素材を一新して高音質化を図ったSHM-CDなどなど・・・他にも様々なアプローチで、音楽CDの高音質化を目指してきたわけです。
そんな中、ソニーが新しく発表した技術が、Blu-rayディスクの製造で使用されている素材と製造技術を音楽CDに応用し、高音質化を図ろうと言うものでした。
その名も、「Blu-spec CD」
最初、このBlu-spec CDという名前を見た時に「えっ!?DVD-AudioやSACDに続いて、また新しい音楽メディア規格を作ったのか!?迷惑な話だなぁ。」と思ったのですが、良く記事を読んでみると、あくまで既存の音楽CD規格に準拠し、通常のCDプレイヤー(CDラジカセ含む)で再生可能な音楽ディスクとのことで、ホッとしました。
更に良く記事を読んでみると、なるほど、製造過程でCDよりも微細な加工が必要なBlu-rayの製造技術と素材(高分子ポリカーボネート)を使う事で、CDのピット(音楽信号の溝)をより正確に加工できる仕組みのようです。
確かに、これなら普通のCDよりも読み取り精度が上がり、結果として音質が向上する気がします。
(なぜ高音質になるのかについては、書くと長くなるので割愛。)
そんな「Blu-spec CD」ですが、12月24日に60タイトルが発売になるそうです。
そのラインナップの中に、これまた以前ブログでご紹介した『フライデイ・ナイト・イン・サンフランシスコ~スーパー・ギター・トリオ・ライヴ! (Blu-spec CD) 』が含まれています。
』が含まれています。

フライデイ・ナイト・イン・サンフランシスコ~スーパー・ギター・トリオ・ライヴ!
このアルバム、発売時にはレコードだったわけですが、オーディオマニア必聴のアルバムだったそうです。
とにかく音が凄い!
また、3人のギターの神、ジョン・マクラフリン、パコ・デ・ルシア、アル・ディ・メオラが共演しており、演奏も壮絶です!
正直、鳥肌が立つ程の超絶演奏。
まぁ、詳しくは以前のブログをご参照ください。
とにもかくにも、早速オーダーです。
あの壮絶な演奏が、Blu-spec CDになったらどのような衝撃を与えてくれるのか・・・今から非常に楽しみです。
それはさておき、日本ではソニー・ミュージックエンタテインメントが1982年に発売されて以来、ずっと変わらずに発売され続けてきている音楽CDに新しい技術を投入し、改良を施して高音質化を達成したというニュースが出ました。

音楽CDは、登場から25年以上経過し、既に「古いメディア」と認識され、これを上回る高音質且つ大容量のDVD-AudioやSACDが登場しているにもかかわらず、現在でも主たる音楽供給メディアとして活躍しています。
これまでも多くのメーカーが音楽CDの規格のまま音質を向上させようと、製造過程を一新したxrcd、先日もブログで紹介した素材を一新して高音質化を図ったSHM-CDなどなど・・・他にも様々なアプローチで、音楽CDの高音質化を目指してきたわけです。
そんな中、ソニーが新しく発表した技術が、Blu-rayディスクの製造で使用されている素材と製造技術を音楽CDに応用し、高音質化を図ろうと言うものでした。
その名も、「Blu-spec CD」
最初、このBlu-spec CDという名前を見た時に「えっ!?DVD-AudioやSACDに続いて、また新しい音楽メディア規格を作ったのか!?迷惑な話だなぁ。」と思ったのですが、良く記事を読んでみると、あくまで既存の音楽CD規格に準拠し、通常のCDプレイヤー(CDラジカセ含む)で再生可能な音楽ディスクとのことで、ホッとしました。
更に良く記事を読んでみると、なるほど、製造過程でCDよりも微細な加工が必要なBlu-rayの製造技術と素材(高分子ポリカーボネート)を使う事で、CDのピット(音楽信号の溝)をより正確に加工できる仕組みのようです。
確かに、これなら普通のCDよりも読み取り精度が上がり、結果として音質が向上する気がします。
(なぜ高音質になるのかについては、書くと長くなるので割愛。)
そんな「Blu-spec CD」ですが、12月24日に60タイトルが発売になるそうです。
そのラインナップの中に、これまた以前ブログでご紹介した『フライデイ・ナイト・イン・サンフランシスコ~スーパー・ギター・トリオ・ライヴ! (Blu-spec CD)

フライデイ・ナイト・イン・サンフランシスコ~スーパー・ギター・トリオ・ライヴ!
このアルバム、発売時にはレコードだったわけですが、オーディオマニア必聴のアルバムだったそうです。
とにかく音が凄い!
また、3人のギターの神、ジョン・マクラフリン、パコ・デ・ルシア、アル・ディ・メオラが共演しており、演奏も壮絶です!
正直、鳥肌が立つ程の超絶演奏。
まぁ、詳しくは以前のブログをご参照ください。
とにもかくにも、早速オーダーです。
あの壮絶な演奏が、Blu-spec CDになったらどのような衝撃を与えてくれるのか・・・今から非常に楽しみです。