マコモダケ
ドコモダケ(嘘
さて、今日はマコモダケについてです。
マコモダケとは:イネ科マコモ属の多年草マコモの若芽のこと。
マコモダケという植物ではないらしい。
ちなみにマコモを漢字で書くと「真菰」。
主な分布地域は東アジアや東南アジアで、日本では全国の水辺で見られるという。
特に水田で栽培されその大きさは1.5メートルから2メートルほどになるという。
このマコモダケの根に近い茎の部分が食用になる。
はじめは稲苗と同じように一本の苗なのだが、幼茎のうちに黒穂菌という食用菌に寄生されると茎がどんどん肥大化し食べられるようになるらしい。
その部分は筍のようになっていて先端の部分はかたく、取り除いてから、軟らかい根元部分を食べるのだそうだ。
乳白色の茎は柔らかくて煮込むとトロリとした口あたりになり、炒めもの、スープ、煮込み料理などの中華料理に最適らしい。
その他にも中国、ベトナム、タイ、ラオス、カンボジアなどのアジア各国で食用とされるらしく、薬用としても使われることがあるという。
その効果は解熱、便秘、糖尿、高血圧、貧血、アトピーなど。
日本での歴史も中々に古く万葉集にも登場するという。
意図的ではなく、昔から水田に気付くと生えていた感じなんでしょうなぁ・・・
しかし、日本に元から自生しているものは茎が肥大せず、マコモダケにはならないらしい。
マコモダケになるのは食用として中国などから輸入された系統だということだ。
うーん・・・いつ頃から入ってきたんでしょうなぁ・・・
ちなみに、三重県の菰野(こもの)町では名産品としてマコモダケを『コモノダケ』として売っていたらしいのですが、『こものだけ』という同じ名前のキノコが存在したらしく、キノコじゃないほうを普及しようとした際に『まこもだけ』という名前に改名したそうです。
- 「2010年」―NTTドコモの未来ビジョン「MAGIC」
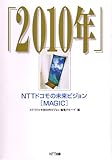
- ¥1,680
- Amazon.co.jp
チンゲンサイ
アイヤー!!ソレハナイアル!
チンゲンサイ:アブラナ科アブラナ属の1~2年草または多年草(野菜)。カブやコマツナと同種。
中国野菜の代表格として日本に浸透している。
このチンゲンサイ、原産地は地中海沿岸のトルコからバルカン半島の高原でシルクロードによって中国にわたってからいろいろな種に派生したらしい。
日本には1972年の日中国交回復後に輸入されたようで昭和58年に農水省により葉柄の色について整理されたという。
もともと玉にならないハクサイをタイサイ(体菜)と呼び、さらにその中で茎の白いものをパクチョイ(白菜)茎が緑色のものをチンゲンサイと呼ぶことになったという。
うーん・・・これは知りませんでした。チンゲンサイって二種類あるんですね。
収穫に時期は5~12月とされていて特に旬は秋だという。
だが、現在ではハウス栽培の活用により年中収穫できるようになっている。
過程でも簡単に栽培できるらしく、プランターで作っている人もいるんだとか。
その栄養価はなかなか優れているようで、ビタミンA、ビタミンC、ベータカロチン、カルシウム、カリウム、鉄分、食物繊維などを含む。
アルカリ性のミネラルが豊富な緑黄色野菜なんだとか。
しかも、加熱による栄養の損失が少ない野菜とされ、炒め物、スープや煮込み料理などで食される。
さらに、漢方・健康素材としても使用され、熱冷まし、胸のむかつき、整胃整腸、便通を良くする、成人病予防、皮膚や粘膜の老化防止等の効果があるという。
また二日酔いの時は、チンゲンサイの青汁が効果的だという。
坦々麺とか野菜炒めに入っているイメージしかありませんが、結構健康的な野菜なんですなぁ。
ちなみにチンゲンサイを150g採ると、1日に必要なビタミンAとCの半分以上が採れるらしいです。
・・・・そんな食べる?
ギバサ
ギバチャン!
さて、今日はギバサについてです。
ギバサとは:ヒバマタ目ホンダワラ科に属する海藻。
秋田県などで採れ、わかめやもずくと同様に普通に食されているらしい。
特に日本海側の県ではよく食べられていて、山形県では「ギンバソウ」、新潟県では「ナガモ」と呼ばれるらしい。
沖縄を除く日本各地の沿岸に分布しているのだとか。
日本海に面している沿岸海域は、厳しい冬の季節風や波が強く、昆布などが育ちにくかったため、その代替品として食べ始められたらしい。
食べ方は、味噌汁の具や、酢の物、粘り気が出るように刻んで醤油などをかけて食べるんだそうだ。
他の海藻類と同じく、ポリフェノールやフコイダン、ミネラルを豊富に含み近年では健康食品としても重宝されているという。
太平洋側ではあまり食べられていないようではあるが、宮城県のお釜神社には藻塩焼き(もしおやき)という海藻を煮詰めて塩を取り出す神事があり、それにはアカモクが使用されているという。
海藻好きのオイラとしては気づいたら食べているのかもしれません。
皆さんも海藻サラダ食べる時にこれは何かなと疑問を持ってみてください。
たぶん、よくわかんないよ。
- 赤ちゃんと僕 DVD-BOX
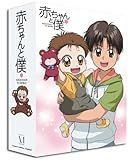
- ¥21,168
- Amazon.co.jp
石細胞
この石頭がっ!!
石細胞とは:読み方は「せきさいぼう」。
梨などを食べると感じるシャリシャリとした感触の原因。
その名の通り細胞の一つで、主に植物の皮、特に野菜や果物の皮の部分に多く存在するという。
植物の細胞構造の細胞膜がリグニン、ペントザンという物質が蓄積して硬くなったものらしい。
梨などはそれが果肉の部分に多量に存在していることから、果肉を食べるとシャリシャリするってこと。
その役割は通常、石細胞が集まった付近の組織を硬くすることで自分の身を保護するためだとか。
梨の場合はまだ実が熟す前には種子のまわりに多く存在し、大切な種子を守っているという。
しかし、実が熟すと、石細胞は果実全体に散らばるという。
うーん・・・身を守っているはずなんですが逆にその食感が人間に気に入られてしまうとは・・・・
もちろん梨の実全体が石細胞というわけではなく、果実は果汁をたっぷり含んだ「柔細胞」からできている。
他の果実はこの柔細胞がほとんどなのだが、梨はその中に石細胞を満遍なく含んでいる。
つまり、この石細胞の割合が多いと硬い梨になるってことだ。
ちなみに、果実の肥大期に乾燥した気候が続くと、石細胞は大きくなるという。
また、人間の体内に入った石細胞は人間の胃腸では消化されず、腸を刺激し便通を良くするのだとか・・・
うーん、丈夫ですなぁ石細胞。
腸内の余計な物もこそぎ落としてくれそうな気がします。
ちなみに、歌舞伎界のことを「梨園」と呼ぶのは
唐の時代に玄宗皇帝が梨の花の咲きあふれる中で役者に芝居を教えたという話からきているそうです。
- 梨ジュース(ペットボトル)

- ¥410
チャトランガ
クソ忙しくて更新ができませんでした。
申し訳ないです。
年末まで忙しさが続きそうなのでさらにペースが乱れますが手が空いたときは更新しますので引き続きよろしくお願いします。
さて、気を取り直して今日はチャトランガについてです。
チャトランガとは:日本に昔からある将棋の元になったとされるボードゲームのこと。
もちろん、というかやはりというかチェスの起源にもなっているらしい。
そのチャトランガの発祥の地はなんとインド!
サンスクリット語で「Chaturanga」は「4つ (chatur) の部分・要素 (anga)」という意味があるらしい。
成立した時期はいまいち不明で文献などによるとBC2000年頃から行われていたのではないかとも言われているらしい。
将棋やチェスの元になっていると聞くと、どんな闘い方だったのか気になるところではありますが。
このゲームが生まれたときには、相手の王を討つようなルールではなく、
スゴロクのようにサイコロを振って決められたルートを通り盤の真ん中まで早くたどり着いた方が勝ち!
といったようなゲームだったらしい・・・
うーん・・・あまり面白くなさそうですなぁ・・・
その後、ルールが変更されていき8×8の盤を使用するチャトランガが生まれたという。
だが、チャトランガの成立はまだ完成していなかったのだ!
実はチャトランガには二人制のものと四人制のものが存在しているという。
二人制が対面の相手を倒すのに対し、四人制は自分の右隣の人を倒すのだとか・・・→check
しかも将棋などにはない同盟などの変則的なルールも盛り込まれているらしい。
・・・何かこち亀でこんな様な話を呼んだことがあるような気がします。
また、この将棋の起源になっているチャトランガの起源は昔のインドで戦争好きの王に戦争をやめさせるため、位の高いお坊さんが戦いを模したゲームを作ったのが始まりだそうです。
まぁ今で言う戦争シミュレーションゲームですな。
どこぞの北の国の人もゲームで満足してて欲しいです。
後継者は正男でお願いします。
- ハチワンダイバー 1 (1) (ヤングジャンプコミックス)/柴田 ヨクサル

- ¥530
- Amazon.co.jp
大良牛乳
かぁ~大漁!!
大良牛乳とは:読み方はだいりょうぎゅうにゅう。
普通の牛乳のことでは無く、中国広東省仏山市順徳区大良鎮の特産である乳製品のこと。
この大良牛乳が名産の大良付近は前述の通り、広東省にある。
特に大良は広東料理の一部になっている順徳料理の中心地で、乳を使用する料理や食品が特徴的なんだそうだ。→check
大良牛乳も元は大良発祥ではなく、金榜郷という近辺の地域の特産品で金榜牛乳餅(きんぼうぎゅうにゅうへい)というものだったらしい。
それを大良市街でも作るようになって、大良牛乳と呼ばれるようになったらしい。
その作り方はこうだ。
タンパク質を固めるために水牛や牛の乳に酢と食塩を加える。
そして、固まったものを木型に乗せて、円盤状にプレスして固める。
この円盤状になったものを塩水の中に保存して完成。
販売時は瓶詰めにして、漬けてあるものごと販売するんだそうだ。
気になる味はかなり塩味の強いチーズのようなものらしい。
よく漬かっているものは、タンパク質の一部がアミノ酸に変性し旨味がでてくるんだとか。
食べ方はそのまま、もしくはお粥、おかず、料理の隠し味として食べられるらしい。
うーん・・・牛乳でできたものでは箸が進まない気がしますなぁ・・・
しかも驚くことに中国内でも一部の地域で流通しているだけらしく、知名度が低いらしい・・・
ちなみに、同じ大良発祥のものの中に牛乳プリンも含まれているそうです。
- オホーツク牛乳プリン(8個セット)

- ¥2,730
湯たんぽ
湯たんぽってどう書くか知ってるかい?
今日は、湯たんぽについてです。
湯たんぽとは:ご存知、日本に古くから伝わる暖房器具。
陶器・金属、ポリエチレン、プラスチック、天然ゴムなどの素材で作られていて、容器にお湯を注いで密封し暖をとる。
冒頭の問題であるどう漢字で書くかの答えは・・・・
湯湯婆!!
湯婆婆では無いです。もう一度。
湯湯婆!!
なぜこの字なのかというとその歴史からきているという。
この湯たんぽ実は中国が発祥の地らしい。
唐の時代、この暖房機器は眠るときに妻の代わりに抱きしめて暖を取るものであった。
その名を「湯婆」(tangpo)「タンポ」
この時代の中国語で「婆」とは「妻」の意味で、「暖かい妻」という意味であったのだ。
それが日本に伝わったのが室町時代。
日本では意味が伝わりにくいので「湯」という文字をつけて湯湯婆になったという。
むぅ・・・あのお婆さんは宮崎駿氏がここらへんからとったのかもしれませんなぁ。
金属製の物が使われだしたのは大正時代以降、それまでは陶器製の物が使われていたという。
現在ではいろいろな素材の物が使われているが、近年のエコブームなどの影響や遠赤外線効果があるということで陶器製が見直されているらしい。
ちなみに、あの徳川綱吉も湯たんぽを使っていたらしく、当然のことながら犬型だったそうです。
- 萬年 銅製湯たんぽ 2.4L カバー付

- ¥9,800
- Amazon.co.jp
テールワッグ
グワッグワッグワッ!
テールワッグとは:カナダで生まれたアクセサリーの一つ。
ヘルメットの上にかぶせるだけで、ほらカワイイ。

このテールワッグを開発したのはカリン・クリンスマン氏。
彼は数年前、スキー中に木に激突する事故を起こした。
その時、彼を守ってくれたのがヘルメットだったのだそうだ。
その時以来彼はスポーツのときなどにヘルメットを身に着けることの重要性を知った。
そして彼は自分の子供たちにもヘルメットをかぶることを強要したらしい・・・
うーん・・・たぶん子供としたら口うるさくヘルメットをかぶれという親は嫌でしょうなぁ・・・
やはりというか子供たちは、ヘルメットをかぶることを嫌がったという。
そこで思いついたのが子供たちがカワイイ・カッコイイと感じさせるヘルメットカバー!
デザインは虎、亀、恐竜、クマ、ウサギ、テントウムシなどその数30種類以上。→check
子供たちはその中から気に入ったものをチョイスするわけだ。
素材も柔らかく寒い日にも暖かいフリース製。
後ろの部分にスリットが入っていてゴーグルを着けるときにも邪魔にならない親切設計らしい。
このテールワッグを着けることは子供が喜ぶことはもちろん、親が子供を見失わないようにという役目もあるという。
うーん・・・たかがヘルメットカバーですがこう書き連ねるとなんだか興味がわいてきます。
これからの冬に向けていかがでしょうか?
ちなみに価格は30ドルぐらいだそうです。
- 【LAZER】 マックス★子供用ヘルメット

- ¥3,685
鮭節
山伏!!
鮭節(サケブシ)とは:鰹節の技術を応用して、鮭から造られた節。
その味わいはカツオ節よりうま味があり、酸味が少なく後味がさっぱりしているという。
実はこの鮭節、素材を有効利用するための知恵から生まれたらしい。
鮭はご存知の通り、河川で生まれ太平洋で成長し、河川に帰ってきて繁殖を行う。
この河川を登り始める頃、鮭の身体に変化が現れるのだ。
川に入り始めると鮭のオスは両顎の前端が突き出して鈎状に曲がり自分の子孫を残すための戦闘準備に入る。
また、婚姻色と呼ばれる、赤や茶、焦げ茶の斑模様が浮かび上がってくる。
オスは縦方向にまだら、メスは横に太い線が入り全体に黒っぽくなる。
この姿がブナの木肌に似ていることから、ブナサケと呼ばれるようになると言う。
ブナサケになった個体は赤い身から赤身が取れて、しだいに白っぽい身になるらしい。
そもそも、鮭の身が赤いのは海で餌としているオキアミが赤い色素を含んでいるからなんだとか。
この身に蓄えられている色素が体表や卵に引き継がれていきドンドン色が抜かれてしまうらしい。
そうするともちろん味の方も悪くなり、市場価値が下がってしまう。
通常、採卵後のブナザケは、薫製や味噌漬け等で調理されていたがそれは一部で、大半は農業用肥料などに回されていたという。
そこで、何か方法が無いかと研究し、ブナサケを美味しく利用するのが鮭節なのだという。
鰹節は原料魚の脂質含量が低いほうが良質な節ができるらしく、身から脂も抜けたブナサケはぴったりだったのだ。
現代ではこの鮭節から醤油なども作られ始め、様々な有効利用への開発が進んでいるらしい。
今のところ原料自体が安価なので安くていい商品ができているらしいのですが、そのうち高級鮭節などが出てきそうです。
まぁ、まだまだ先でしょうけどね。
- 東京鰹節物語/稲葉 美二
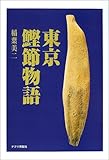
- ¥3,360
- Amazon.co.jp
ラクダ
ほぁぁぁらくだ。
さて、今日はラクダについてです。
ラクダとは:偶蹄目ラクダ科ラクダ。
現存している種は、ヒトコブラクダとフタコブラクダの2種のみ。
こぶの中身は脂肪でその重さは約50kgもあり、代謝水と呼ばれる水分を作り出すことができるらしい。
両方とも身体の大きさはあまり変わらず、
体高:190-230cm
体重:450-650kg
と結構な巨体なのだ。
また、熱に対する対策も十分に備えていて、水の摂取しにくい環境では汗として体内の水分が失われるのを避けるため、自らの体温を40度くらいに上げて、極力水分の排泄を防ぐようになっているという。
体内の水分も人間が一割を失うと危険になるのに対し、四割まで失っても大丈夫らしい。
ヒトコブラクダは主に西アジア、北アフリカ、中近東に生息。
現在、野生種は存在しないとされていて、家畜として飼われている個体群のみ。
フタコブラクダは中央アジアに生息。
野生種も存在しているが2002年、国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧種に指定されている。
つまり、ラクダは結構数が減っている動物らしい。
そんな2種のラクダだが交配もできるという。
その名も、ブフト!
また雌のブフトはフタコブラクダと戻し交配することができ、
ヒトコブラクダの血を25%、フタコブラクダの血を75%引く乗用のラクダがつくられる。
ハイブリッド化されたこのブフトはどちらの種よりも体格で勝るため重宝されるという。
ちなみに、こぶの数は1つらしい。
また、ラクダはアラブ世界では交通手段であり食品であり服飾などの素材でもある。
アラビアンナイトなどでもイメージが浮かぶが、昔は重い荷物を背負い隊商を組んで砂漠を移動していた。
背中に300kg近い荷物を載せ1日に30~40kmを歩き水なしで一週間くらい歩くことができるという。
肉や皮も食料や織物・服などとして使用されていた。
まぁモンゴルの馬のように余すところ無く使用されていたってこと。
人間の世界が発展するにつれても未だ家畜として扱われています。
風情のあるキャラバンはもう無いのでしょうが、ラクダにとってはいい事ですなぁ。
- グンゼ 快適工房 申又(白・ラクダ) M・Lサイズ 【5000円(税別)以上送料無料】
- ¥682
- 布団・水着・安全靴のテンテンの森




















