飲むと残るアレ
たまに飲むカルピス。美味いですよね。
カルピス、ヤクルトなどを飲むと残るアレとは:乳酸菌飲料のようなものを飲んだ後に喉の奥にひっかるような白い塊のこと。
触るとぬめっていて、気分的には微妙な気持ちになる。
身体にいいイメージの強い乳酸菌飲料だが正直アレはいただけない。
飲んでいるものの中にはアレに近いものは入っていないので、実はアレは口の中で生成されたものらしい。

それは乳酸菌飲料に含まれる『カゼイン』という乳タンパク質、
唾液中に含まれる『ムチン』という糖タンパク質が混ぜ合わさりアレが出来上がるのだそうだ。
ちなみにムチンは動物の分泌する粘液に大体含まれていて細胞の保護や潤滑物質としての役割をはたしているらしい。
そのメカニズムは、
まず、酸性である乳酸菌飲料に含まれるカゼインが口の中で弱酸性の唾液と混合する
この時、唾液の中にもムチンが含まれているので、それもブレンドされる。
この混合物が等電点を通過する時、変性が起きて固形物になる。
これがアレの正体。
さらに、この物質が生成されるには個人差があって、唾液の成分によって出来やすい人と出来にくい人に分かれるらしい。
その人の体調などによっても変わるので、今日は一杯出たとか、出なかったとかって事にもなるという。
まぁ所詮、タンパク質の塊なので飲んでもまったく害はないです。
実はこの工程はヨーグルトの製造工程でもおこっているらしく、あの中に今回のアレが混ざっているようです。
ただし、固形になっているヨーグルトの中に入っているものなので気付かれないんだとか・・・
うーん・・・こんなことを聞くとちょっと微妙ですなぁ・・・
ちなみにカゼインに酸を加えたりして加工することで象牙に似た外観のプラスチックができるそうです。
- カルピスファンタジーギフト<F-20>
- ¥2,100
- シャディOnline
リコリッシュ
これなんでしょう?
実はこれ、食べ物なんです。
今日はリコリッシュについてです。
リコリッシュとは:欧米などで古くから親しまれているが、日本人には好き嫌いがはっきり分かれるお菓子。
薬草として使用されてきた甘草が使用されているため、独特の薬のような香りがする。
また、その姿も黒く、グミともキャンディともいえないような形をしている。
まぁ、上記のような形状なので自転車のタイヤチューブといっても・・・
そもそも、甘草(カンゾウ)は英名を「リコリス」といい地中海地方、小アジア、ロシアを原産とするマメ科の多年草。
根を乾燥させ、薬や甘味料として使用されていたらしい。
その中にある成分グリチルリチンの甘味は砂糖の50倍で、あのルートビアでも使用されているという。
そのリコリスを菓子に配合し販売をしたのがイギリスのBassetts社。
記録によると発売を開始したのは1899年のことだという。
・・・100年を超して販売されている・・・
オイラにとっては何でなくならなかったのかが不思議です。
しかも、リコリス本来の歴史はさらに古く古代メソポタミア時代や古代エジプトの遺跡などからも発見されているという。
現代でも生薬として、アーユルヴェーダや漢方などで下剤効果、肝機能障害、抗アレルギーなどの効果の為に使用されているらしい。
その風味が非常に独特な為、好き嫌いが非常に分かれる。
ヨーロッパでは子供から大人まで幅広く食されるが、苦手な人のため?外側をカラフルな糖衣で包んだフレーバーが添加してあるものも販売されているらしい。
リコリス100%のものはカーボンブラックで着色され、何人も寄せ付けないような光沢を帯びた真っ黒な色をしている。
うーん・・・正直この黒さは引きますなぁ・・・
ちなみに、リコリスは歯磨き粉、ハーブティー、タバコ、ガム、醤油などにも入っているものもあるそうです。
- リコリス

- ¥525
シャリュモー
ぼくの大好きなクラーリネット!
さて、今日はシャリュモーについてです。
シャリュモーとは:フランスで発達した円筒形木管楽器の一種。
後にオーボエやクラリネットへと進化した。
その構造はシングルリードとマウスピースを備え、円筒形の内管を持っている。
現代のクラリネットなどと基本的な構造は同じらしい。
この楽器の起源はササン朝ペルシアのころ、軍隊が合図を行うために使っていたものが元になっているらしい。
それが、ヨーロッパに伝わってフランスのジャン・オットーテールらによって室内用楽器として改良が加えられていったという。
そして、18 世紀の後半まではオーケストラで使用されていたが、どんどんキーが追加されて、現在のクラリネットに近い姿になっていった。
ちなみに、クラリネットは18世紀の初め頃、ドイツ人のクリスチャン・デンナーが、シャリュモーを改造して作成したらしい。
名前の由来はリードの部分に葦が使われているので「葦、砂糖黍」を意味するラテン語のカラムス(calamus)からこの名が付いたという。
実はこの楽器、各国で呼ばれ方が違う、
フランス語では「シャリュモー」
英語では「ショーム」
イタリア語では「チャラメッラ」
ポルトガル語では「チャラメラ」
そして、日本語では「チャルメラ」
!!
そう、実はあのチャルメラ。
フランスの楽器と聞いたのでどんな貴族風かと思いきや・・・
流しの屋台でお馴染みのチャルメラでした。
日本には安土桃山時代に伝わり、ポルトガル人が「チャラメラ」と呼んだことから、「チャルメラ」と呼ぶようになったという。
現在、日本では製造されておらず、購入できるものは中国・東南アジアなどの輸入品だという。
うーん・・・意外な結びつきです・・・
「シャリュモー」と聞くとどんなのだろうとわくわくしますが、「チャルメラ」と聞いたときのこの「ああ・・・」みたいな気持ち・・・
同じ楽器なのに・・・
ちなみに定番のあのメロディーは「ソラシーラソー ソラシラソラー」で片手で簡単にふけるそうです。
- チャルメララーメン丼レンゲ付き
- ¥1,071
- パーティー本舗
ショートブレッド
ヘイ!ショートッ!!→check
ショートブレッドとは:スコットランドの伝統的な菓子。
クッキーやビスケットに近く、このまま食べるが、お菓子作りのベースとしても活用できる。
最大の特徴は液体を一切使わないで作るということ。
たった4つの材料でできてしまうことから、おやつなどとして振舞われることが多いらしい。
その4つの材料とは小麦粉、バター、砂糖、塩。
うーん、実にシンプル。
作り方は
①ボールにバターとグラニュー糖を加え、白っぽくなるまで泡だて器でかき混ぜる。
②薄力粉と塩を2~3回に分けて加え、木べらで混ぜ合わせる。
③十分に生地が馴染んだら手でまとめて、ラップでくるむ。
※ただし、混ぜすぎると焼きあがりが固くなりすぎるらしい。
④冷蔵庫で冷やし、好みの形になるように整える。一般的な形は一口サイズの長方形で表面にフォークなどで窪みをつける。
⑤こんがりしない程度にオーブンで10分程焼く。
これで完成。
ん?どこかで見たことがあると思ったら、
実は大塚製薬のカロリーメイトはショートブレッドから着想を得ているらしいです。
当然4種の材料だけでなく様々な素材を入れて栄養調整食品として仕上げてあります。
確かにあの形だったらちょっとした時に食べやすいですからなぁ。
ちなみにショートブレッドの「ショート」は、「短い」ではなく、お菓子などがポロポロした状態のことを指すそうです。
- 大塚製薬 カロリーメイト ブロックフルーツ味 4本入×30個セット
- ¥4,977
- モリス通販
超五十連勝力士碑
強力の神に・・・・
超五十連勝力士碑とは:読み方は「ちょうごじゅうれんしょうりきしひ」。
日本で古来より続く大相撲の本場所で50連勝以上を達成した力士の偉業を讃えて建立された石碑。
この石碑がある場所は江戸勧進相撲発祥の地として知られる富岡八幡宮。
もともと相撲は京・大坂で開催されていたが、貞享元年(1684年)、幕府より年2回の興行が許可されてから富岡八幡宮の境内で開催されるようになったと言う。
特に明治以降は相撲と神道の結びつきを強める為、富岡八幡宮での相撲をとったらしい。
そこで、相撲の“聖地”であった八幡宮の境内に記念碑を立てることになったのだとか。
実は超五十連勝力士碑のほかにも相撲関連の碑が以下のように建立されているらしい。
横綱力士碑
大関力士碑
強豪関脇力士碑
釈迦ヶ嶽等身碑
巨人力士碑
巨人手形碑
超五十連勝力士碑
出羽海一門友愛之碑
その中でも超五十連勝力士碑 はまだ新しく千代の富士が連勝記録を作っている頃に立てたと言う。

その形は珍しい11角柱で正面に碑銘、以下右回りで力士の名が刻まれている。
その人数は現在のところ
谷風梶之助 (2代)63連勝
梅ヶ谷藤太郎 (初代)58連勝
太刀山峯右エ門56連勝
双葉山定次69連勝
千代の富士貢53連勝
の5名のみ。
むぅ、あの強いイメージのある千代の富士でも53連勝・・・
かなりのハードルの高さです。
果たして6人目の猛者が刻まれるのは誰なのか!!
- つっぱり大相撲

- ¥2,700
- Amazon.co.jp
トゥインキー
ああ、ツインビーね。
トゥインキーとは:世界のアメリカが誇るジャンクフードの一つ。

このトゥインキーを指して、”究極のジャンクフード”ということもあるらしい。
ちなみに長さ10cm×幅2.5cmのサイズで約145キロカロリー。
開発が行われたのはアメリカのホステス社。
1930年代にシカゴ近郊のとあるベーカリーのマネージャー、ジェームズ・デュワー氏が作ったのだそうだ。
当初、このベーカリーではストロベリーショートケーキに使用するスポンジケーキのみを生産していた。
しかし、イチゴのシーズンが終わると仕事が激減してしまう。
そこで考えたのがイチゴを中に入れるのではなくバナナクリームを中に注入した製品。
これがトゥインキーの大元になっているのだそうだ。
その後、順調に販売をしていたが第二次世界大戦の影響でバナナの輸入が規制されまたピンチになった。
そこで今度は普通のクリームを使用するようになって、そのままクリーム入りのものをスタンダード品として販売しているのだとか。
その代わり期間限定でバナナクリームトゥインキーを販売するようになり好評を博したと言う。
そして2007年6月にホステス社はバナナクリームのトゥインキーの復刻を宣言し、常時生産されることになった。
さらにこのキング・オブ・ジャンクフードは進化を遂げる。
ニューヨークのブルックリンでレストランを経営するクリストファー・セル氏が「フライド・トゥインキー」を発明したのだ。
うーん・・・ただでさえカロリーの多いこの食べ物を更に油で揚げるとは・・・なんたる暴挙。
が、このフライド・トゥインキーは大衆の絶賛を受けることになり、全米の各地の物産祭や飲食店にも拡大。
一大ムーブメントを起こしたらしい。
このようなトゥインキーには逸話や都市伝説がいくつも出来上がっているのだとか。
①トゥインキーは数十~百年間傷まない
②トゥインキーの中のクリームは8年経つと発酵してアルコールになる
③トゥインキー70周年のときに2万個を使ってバースデーケーキが作られた
などなど・・・
どれが本当でどれが嘘かわかりませんが、そういうことを言われるくらいメジャーなモノらしいです。
アメリカに行ったらトゥインキー。
ジャンクフード好きならトゥインキー。
オススメです。
- おませなツインキー
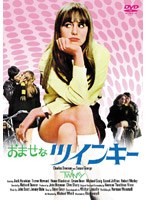
- ¥3,591
チェシャ猫
チェシャ猫とは:不思議の国のアリスなどでお馴染みのニヤリと笑った顔がステキな猫。
当然だが、実在の猫の種類の一つではない。
元々、英語には「不気味な得体の知れない笑いを浮かべる」といった表現を
“grin like a Cheshire cat”
「チェシャーの猫の様ににやにや笑う」
といったように表現する慣用句があるらしい。
これがチェシャ猫の語源になっているという。
チェシャーの猫のチェシャーが意味するものは、英国北西部の地域のチェシャー州のこと。→check
主に小さな町や村が多数集まった農業地帯でチェシャーチーズや塩の生産で歴史的に有名なところだという。
ここに住んでいる猫がチェシャーの猫。
何故、その猫達といえばにやつき顔・笑顔といえるようになったのか?
実はここに住んでいる猫は奇妙な病気のせいで顔が微笑むように引きつって・・・・
というのは嘘で。
本当の理由はいくつかの説があるらしい。
①前述したようにチェシャーチーズの生産地であるこの地域には酪農製品がたくさんある。
それを狙うネズミ達が多いため、それらを餌にしている猫がホクホク顔になっている。
②ネズミに狙われることが多かったチーズをどうにか守ろうと思ったある人が、
チーズ自体を猫の形に似せてチーズを作って、成功した。
③チェシャー州の貴族の紋章が笑う猫に似ていた。(本当は獅子の紋章だったらしい)
などが挙げられるという。
本当の理由がわからないのが、謎のチェシャ猫っぽくていいと思います。
意外と、昔にこの地域にしか存在していなかった猫がモデルになっているかもしれません。
- チェシャ猫はどこへ行ったか―ルイス・キャロルの写真術/桑原 茂夫

- ¥1,325
- Amazon.co.jp
鼈甲
亀は万年。
さて、今日は鼈甲についてです。
鼈甲とは:読み方は「べっこう」
櫛、かんざし、帯留め、ブローチなどに加工されて普及した海亀の甲羅から作製される工芸品。
あの徳川家康の眼鏡もこの鼈甲でできていたらしい。
この鼈甲の「鼈」は元々はスッポンを表す言葉で、
江戸時代の庶民が自分は贅沢をしていませんよというために「これは鼈(スッポン)の甲羅」と言っていたことから、鼈甲という呼び名が一般化したという。
しかし、本当はこの鼈甲がとれる亀はタイマイといい主に珊瑚礁の発達した浅海にしか生息しない希少種なのだ。→check

タイマイは熱帯域には幅広く分布するが日本での生息地は南西諸島付近で、太平洋での分布北限らしい。
しかも現在ではワシントン条約によってタイマイの貿易が禁止されているのだとか。
一方でキューバでは、タイマイを食用として捕獲し国家管理下で数トンの鼈甲の原料を持っているのだとか・・・
だがワシントン条約の為に貿易はできないという。
うーん・・・鼈甲って今は貴重なんですなぁ。
そんな鼈甲は意外と知られていないが以下の種類が存在する。
白甲『しろこう』:甲羅の中でも白っぽい部分、腹甲及びふち甲の飴色の甲羅だけで作られた物。
希少価値が高いので高級品になっている。
なかでも尾の部分の尖った三角形の甲羅を爪甲と言い白甲の中で最高の価値がある
赤甲『あかこう』:全体に赤みを帯びた部分のみで作られる物。
自然の甲の斑(斑)で赤色がかったものでつくられるので、白甲についで高価。
黒甲『くろこう』:斑点のある背甲の黒い部分のみを選り集めて作られた物
黒一色の物は真黒(シンクロ)と呼ばれ、高価になる。
茨布甲『ばらふこう』:一般的に言う鼈甲のこと。
白甲の部分が多く“ふ”と呼ばれる斑点がある物を上茨布甲と呼び、白甲・赤甲に次ぐ高級品になる。
これは知らなかった鼈甲といったら黄色に濃褐色の斑点があるアレだけかと思っていましたが・・・
人気の秘密は軽く、肌あたりのやわらかなこと、模様のパターンが同じものがないことがあげられるらしい。
また縁起がよいとされる亀の製品のためということもあるらしい。
ちなみに口裂け女の大好物はべっこう飴です。
- べっこう飴 (京の露)
- ¥315
- 京の飴工房
セカンドバッグ
へい!セカーンッ!!
セカンドバッグとは:手で抱えて持つことができる小型の鞄。
おじさんたちが良く持ってふらふらしているので、おじさんのバッグといったようなイメージが非常に強い。
そもそも、何でバッグ一つしか持っていないのにセカンドバッグと言うか調べた。
実は、昔は本当に”second"第2のバッグだったらしい。
従来は大型のバッグの中に入れておいて、その大型のバッグを持ち歩くのに不便な時などに必要なものだけを入れて使用していたという。
それが段々と大きなバッグではなくセカンドバッグだけを持ち歩くようになり、巷にセカンドバッグを持つ人々が溢れたのだ。
その当時のセカンドバッグはダサいデザインの物が非常に多かったという。
ちなみにセカンドバッグは英語ではクラッチバッグ( clutch bag )と言うらしい。
まぁ、スーツのパンツなどに財布やケータイ、手帳などをすべてポケットに入れてしまうと型が崩れるのを嫌う人は意外と重宝しているらしいのですが、オイラとしてはセカンドバッグはちょっとねぇ・・・・って感じです。
ちなみにアタッシュケースは大使館員の書記官や駐在武官が書類を携帯するのに使用していたことから、
駐在武官(仏:attache)のケース→アタッシュケースになったと言います。
- ゼロハリバートン:【正規輸入品】 アタッシュケース CEM ポリッシュブルー /
- ¥78,750
- 男のこだわり名品館ZEED


















