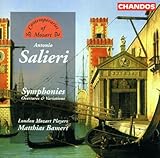まとめ買いしたCDの中からボッケリーニ
の一枚を聴いた後に予告しましたように、
お次に取り出だしたるCDはアントニオ・サリエリ
の作品集でありますよ。
始まりはプーシキン
かもしれませんけれど、ピーター・シェーファーの「アマデウス」によって
モーツァルト
に嫉妬する凡庸な作曲家として有名になってしまったサリエリです。
それだけに?このCDも「モーツァルトと同世代の作曲家シリーズ」の一枚ということに
なっているのですなあ。
同じシリーズに取り上げられている作曲家といいますれば、
ゴセック、ピフル、コジェルフ、ギロヴェッツ、そしてウェスレーという具合で、
辛うじてゴセックはガボットで知られているものの、それ以外は「誰?それ…」的でもあろうかと。
そんな中でサリエリの知名度は相当に高いのはやはりシェーファーの戯曲、
そして映画のおかげでありましょう。
ですが、その映画「アマデウス」による刷り込みがあまりに効果絶大であったために、
サリエリはモーツァルトの暗殺者としてばかり記憶されてしまうのはとんだ災難でもあろうかと。
モーツァルトという光をくっきりさせるために必要な陰の役回りが振られてしまったわけで。
それでも、長年にわたってウィーンで宮廷楽長を務め、
ベートーヴェン
やシューベルト
、リスト
らの指導にもあたった人物であることに
改めて目を向けてみれば凡庸で片付けてしまってはいけないのでしょう、おそらく。
おそらくサリエリは音楽の改革者ではなかったですが、
当時の聴き手の側からしてみれば必ずしも斬新な音楽を求めていたわけではないでしょうから、
技法を極めた作曲家としての自分が書きたい音楽を書き始めるようになったモーツァルトよりも
安定的に楽しい音楽、心地よい音楽を提供し続けるサリエリの評価が高かったのは当然かとも。
(聴衆のための音楽を書くように諭したパパ・モーツァルトはまさにその時代の人ですな)
18世紀後半から作曲技法は加速度的な展開を見せていったわけですが
(すぐに袋小路に突き当たってしまうと言えないこともないですね)
そのことを知っている現代人はすっかり音楽に深遠なものを求めたがるようになってもいる。
ですが、当時のことを思えばもっと素朴に音楽を捉えていいのだろうと思うわけです。
それこそ「苦悩を通じての歓喜」という音楽でなしに「苦悩はちょいと脇にのけておいての歓喜」、
そんな感じで聴ける音楽を一概に切って捨ててしまうのはどうかと。
もちろん精魂傾けて主題労作に取り組んだベートーヴェンにしてみれば、
世の中でロッシーニ
の軽薄な音楽に大衆が熱狂するさまを苦々しく思っていたでしょうけれど、
どちらが良い悪いという優劣の話をするのでなくして、どちらの良さをも思えばいいのでしょう。
とまた前置きが長いですが、サリエリ作品集を聴いておもうところですけれど、
ベートーヴェンの音楽を聴いて単純にワクワクしたり、楽しいと感じたりしたとすれば
上っ面しか聴いてない的に思われるかもしれないところながら、
その単純なわくわく感を積極的に醸す音楽なのだろうなということではなかろうかと。
そうした点ではロッシーニの音楽に繋がっていく流れの上流のひとつと言えましょうか。
後にロッシーニ・クレッシェンドと言われるような盛り上げ方のように思えるところもありますし。
管弦楽法の妙というよりは、楽器の個性の違いを捕まえたメロディーの受け渡しで
バリエーションをつけるようなあたりも大衆受けしやすいところでしょう。
こうした曲作りをサリエリ自身、どう考えていたかは分かりませんけれど
聴き手を喜ばせることこそ音楽の使命とは思っていたのではなかろうかと。
このCDに収録されている7曲のうち6曲までが「ニ長調」で書かれているのですよね。
調性の個性としてはWikipediaにはこんなふうにあるのですよ。
バロック時代から初期ロマン派時代にかけて、弦楽器の響きが最も良く、トランペットとティンパニが使える調として重要視され、祝典的行事のために盛んに書かれた。…倍音の響きが豊かな調であり古くから華麗で明るい響きが得られる調とされている。
そんなニ長調の曲はもっとも受けのよい調子として多用されたのかもしれませんですね。
こうしたところでも、音楽という日常使いのものを多くの者が「いいねえ」という形で提供するのに
サリエリは秀でていたと見るべきなのかも。
とまれ、そうした曲がいっぱいに詰まったCDは概して楽しく、
ちとティンパニがどこどこと響くもののBGMにしても悪くはない。
だからといって、積極的にもっともっと他にも
サリエリの曲を聴いてみたいとなるわけではないのですが、
手元において時折取り出してはちょっと気持ちを浮き立たせるのにいい。
お気に入りは一曲めの歌劇「タタールの大王フビライハーン」序曲ですかね、個人的には。
ということでサリエリの作品集を聴いてきましたけれど、
同時に購入したCDの中にはモーツァルトもありましたので、
次の機会にはモーツァルトを取り上げることにいたしましょうか。