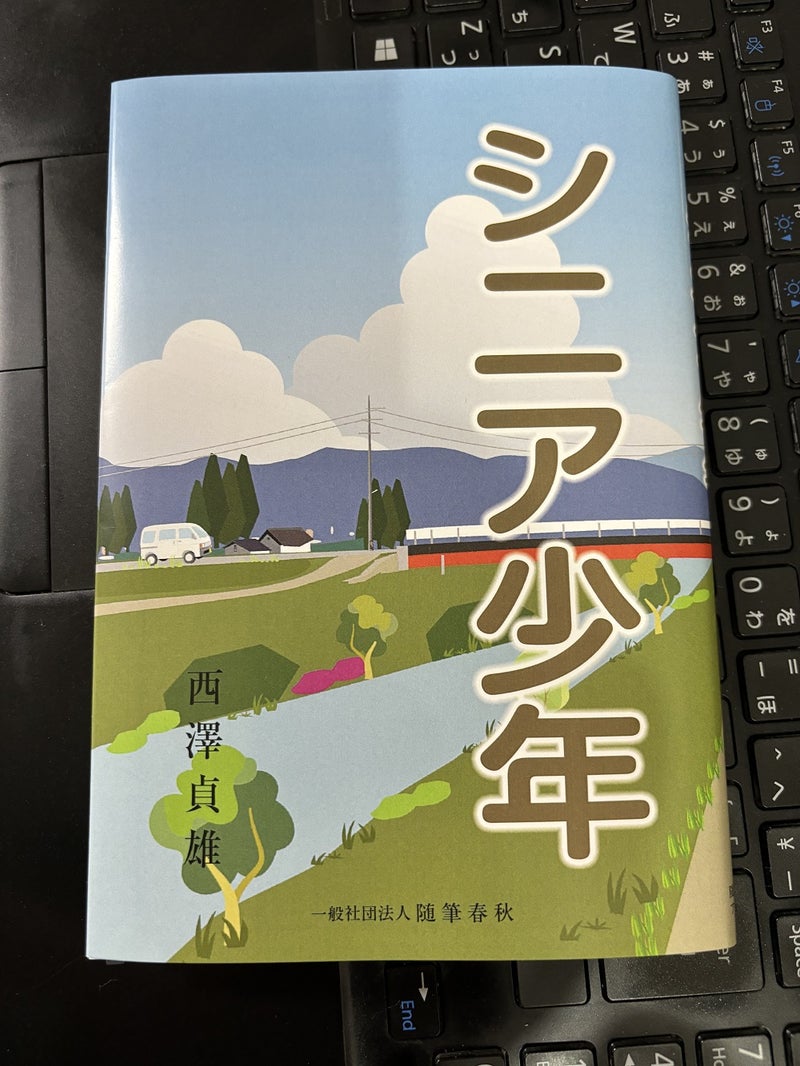今さら改まって言うことでもないのだが、私たちは〝地球〟という天体に暮らしている。その形状は球体で、自ら回転(=自転)しながら太陽の周りを回っている(=公転)。太陽の周りを一周すると一年になるわけで、その間に地球は三六五回自転する。
私たちは、そんな知識を子供の頃から摺(す)りこまれてきた。だが正直な話、日常生活を送っている分には、球体であることも、回転していることも実感に乏しい。
私は現在、札幌に暮らしている。郊外に向かって車を走らせると、ほどなく広々とした平野が開けてくる。走っても走っても尽きない広大な大地である。また、はるか彼方まで広がる水平線は、紛れもなく平坦なもので、これが球体の一面だとはとても思えない。
時に地震に見舞われ、大きな災害がもたらされる。地球の動きを感じるのはこんな地震のときくらいで、自ら回転しているとは、俄(にわ)かに信じがたい。朝になれば太陽が昇り、夕方には沈んでいく。それが日常の営みであり、動いているのは太陽の方である。だが、それこそが地球が回転している証拠なのだ。頭ではわかっているのだが、「回転しているのに、球体なのに、どうして海の水はこぼれ落ちないのか」、そんな思いが、拭(ぬぐ)っても拭っても、あとからあとからジワリと沁(し)み出してくる。
「水平線から現れる船を見てみろ。マストから見えてくるだろう。地球が丸いからだ」
中学の理科の授業で、窓の外に広がる水平線を指さした先生が、得意気に言っていた。このように私たちは教え込まれ、コペルニクス的転回を強いられてきた。だが、この年になっても、天動説への未練はまとわりついてくる。
「……それでも地球は回っている」と言ったガリレオガリレイは、たいした男だと思う。
回転しているのは地球だけではない。地球を含めた惑星が、自転しながら太陽の周りを回っている。一番外側の冥王星(めいおうせい)は、現在では準惑星に格下げされたので、水・金・地・火・木・土・天・海の八個が、太陽系の惑星となっている。
くどいようだが、もう少し続ける。
地球に月(衛星)があるように、ほかの惑星にも衛星がある。木星には四十八個の衛星があるという。見上げた夜空は、どんな光景だろう。大小さまざまな月が四十八個も出ていると、さぞや気持ちの悪いものに違いない。それら衛星もまた、自転しながら惑星の周りを公転している。もちろん太陽も自転しており、太陽系を含む銀河系も回転している。
驚くのはその自転速度だ。地球は秒速四六六メートル、太陽は秒速一八九〇メートル、月は秒速四・六四メートルで回転している。公転速度は、さらに高速になる。地球は毎秒二九・八キロメートルで、月は秒速一・〇一キロメートル、太陽が銀河系の中心を回る速度は、秒速二二〇キロメートルになる。
つまり我々が暮らす地球は、高速回転をしながら猛烈なスピードで太陽の周りを公転しつつ、その太陽もろともさらに超高速で、銀河系の中心の周りを回っているというのだ。銀河系もまた、ほかの星雲ともども猛烈な速度で、宇宙の果てへと飛び散っているのだろう。その始まりはビッグバンのあった一三八億年前だという。しかしそれとて、現時点で我々人間が知り得た範囲内のことなのである。
一九七七年に打ち上げられたNASAの惑星探査機ボイジャー一号は、二〇二四年二月の時点で、地球から二四三・七億キロ離れたところを秒速一七キロで飛び続けている。地球から光が到達するのに二十二時間三十五分を要する距離で、光年に換算すると〇・〇〇二五七六光年だという。一光年は、光のスピードで一年かかる距離で、約九兆五千億キロメートルになる。ボイジャー一号は、四十七年もの間、高速飛行を続けているのに、まだこの距離なのである。
現在判明している最も遠い天体は、三四八・一億光年の彼方にある。光のスピードで三四八億年かかるというわけだ。いったい、宇宙というものは、どうなっているのだ。途方もない、人知を超えた世界だということだけはぼんやりとわかる。
カタツムリやアリが世界一周をするのに、どれほどの時間がかかるだろう。バクテリアは……と考えると、私たちが宇宙に思いを巡らせ、途方に暮れるのと同種のニュアンスを覚える。彼らは、私たちが飛行機や新幹線、自動車などを使って長距離を高速で移動していることを知らない。地球の反対側の人とリアルタイムで会話ができるということも。
幼いころ、忙(せわ)しなく巣穴を出入りしているアリや、ゆっくりとした動作で移動するカタツムリなどをよく眺めたものだ。彼らはしゃがんで覗き込んでいる我々にすら気づいていない。もしかして、私たちも同様に、その上の世界を知らないのではないか。ハッとして天を仰ぎ見る。私たちの営みを覗き見ている存在もあるのだろうか。それが‶神〟なのか……、そんな思いが過(よぎ)る。新興宗教の勧誘の論法も、このようなところから入っていくのだろう。
見上げてごらん夜の星を/小さな星の小さな光が/ささやかな幸せをうたってる
歌手の坂本九は、飛行機事故に巻き込まれ亡くなった。死んだら星になるとは思わないが、無意識のうちに空を仰いでしまう。死者の魂は空の上にあるということを、私たちは本能的に嗅(か)ぎ取っているのかもしれない。
私たち人類は、長い間、田畑や海で働いてきた。狭い世界の中で男女が出会い、愛し合い、子供を産み育て、家庭を護り、やがて老いていく。そうして死んでいった者もまた、生きている人々の拠(よ)り所となり、死後もなお一体となって暮らしてきた。それが人間の営みだった。
時代が変わっても大差はない。私たちは出会いと別れを繰り返しながら、生を終えていく。この壮大な宇宙の中で起こっていることや、仕組みを理解しないまま、生没を繰り返してきた。そしてこれからも、そんな営みが続いていく。
いずれかの時代で、高度な地球外生命体と接触し、知識や技術が飛躍的に向上することになるだろう。長距離空間を瞬間移動することが日常になっているに違いない。そんな時代から眺めると、今の私たちの生活は縄文時代とさして変わらぬものと映るだろう。
地球が太陽の周りを八十回から九十回ほど公転している間に、人間の寿命は尽きてしまう。私が幼いころは、人生五十年と言われていた。宇宙の壮大さに比べたら、人間もカタツムリもバクテリアも、まったく同じ同レベルの存在なのだ。
だから、限られたこの期間内を楽しく生きるべきなのだろう。こうしている間にも、私たちの持ち時間は、刻々と削られていく。私たちの未来は、‶残された時間〟なのであり、それはあと僅(わず)かしかない。年老いた父母を敬い、パートナーを愛し、子供や孫があればそれを慈しみ、友達と楽しいひと時を過ごす。
六十代も半ばになると、誰が先に逝ってしまうかは、運命にゆだねるしかない。すでに私たちの祖父母は死に絶えていない。悲しい別れは、必ず訪れる。
詩人西條八十(やそ)の墓碑には、次のように刻まれている。
「われらふたり、たのしくここに眠る、離ればなれに生まれ、めぐりあい、みじかき時を愛に生きしふたり、悲しく別れたれど、また、ここに、こころとなりて、とこしえに寄り添い眠る」
出会いと別れを繰り返す人生の中で、出会った伴侶との理想的な括(くく)りである。かくありたいものだ。
2024年6月 初出 近藤 健(こんけんどう)
ランキングに参加しています。
ぜひ、クリックを!
↓

エッセイ・随筆ランキング
■ 近藤 健(こんけんどう) HP https://zuishun.net/konkendoh-official/
■『肥後藩参百石 米良家』- 堀部弥兵衛の介錯人米良市右衛門とその族譜 -
http://karansha.com/merake.html
□ 随筆春秋HP https://zuishun.net/officialhomepage/