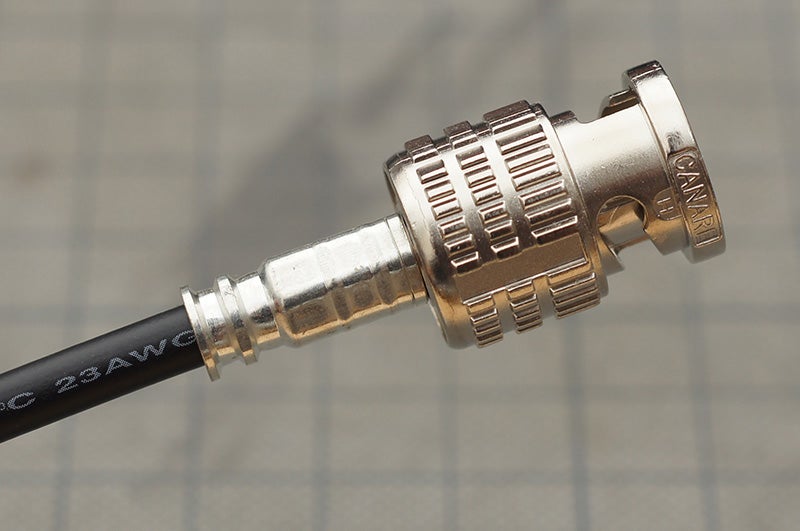SmaartのUIを踏襲したオフライン仮想DSPエディタのSmaart Data Modelerの紹介です。Eclipse Audioが協力しており、同社のスピーカプリセット交換ファイル、LPIF形式での書き出しが可能です。普段Smaartを使っている方は同じUIで操作が可能です。
DSPのシミュレートは2024年7月現在、下記のメーカに対応しています。但し、注意しなければならないのはあくまでDSPのフィルタシミュレートであって、連携機能が保証されているわけではありません。
- Biamp Tesira
- Blaze Audio
- BSS
- Lake Mesa
- Linea Research
- Marani
- Pascal Audio
- Powersoft
- QSC Q-SYS
- Ram Audio
- RMS Acoustics
- Symetrix
スプラッシュスクリーン
Smaart Data Modeler公式サイト:
動作イメージの動画。オフラインでこの動作ができるのは面白い
動作イメージ(静止画)
より複雑な補正
Smaart V9.4.0で正式に搭載された計測した後でもディレイが変更できるPlot Time Reference機能だが、先行でSmaart Data Modelerに搭載されていた。上記はSmaart V9.4.0
BOSE 802IIIのノンEQと推奨EQの適応
BOSE 802IIIのノンEQと推奨EQの適応の動画
実際の位置で測定してみるとそこそこフラットであることが伺える。※低域の75Hzの盛り上がりはたぶんDSP側の設定
実際に購入して使ってみると、「DSPにそのまま書き出せなくない?」という事実に気が付きます・・・。Q-SYS(QSC)かSysmetrixに書き出せたらなぁ・・・と思うのですがLPIFファイルのインポートが非対応です。うーん・・・
Symetrix Composer 8.5ではLPIFデータの直接の読み込みは非対応
Symetrix SymNet Designer v10.0(旧DSPの編集ソフトウェア)ではSmaart Live!との連携があった。※右下にID設定がある。この場合はAPI連携となる(やったことは無い)
QSC Q-SYS Designer 9.4でもLPIFデータの直接の読み込みは非対応。はたまた他に手があるのを見過ごしているのか・・・
そもそも、Symetrix SymNet Designer v10.0(旧DSPの編集ソフトウェア)ではSmaart Live!とのAPI連携があったのです。それが、次期バージョンのComposerになって廃止されました・・・。
大した労力でもないので連携は諦め手打ちするとして・・・では、どういったシーンでSmaart Data Modelerが役に立つのか・・・・・個人的に一番大きいなと思うのは、「現場でのピンクノイズ送出時間を短縮したいケース」です。通常のスピーカ調整であればピンクノイズを送出しつつ調整を重ねて・・・と、調整の時間中はスピーカから音が流れ続けます。一旦、計測データだけ取れてしまえばSmaart Data Modelerを経由することで粗調整は先に済ませておくことが可能であると思います。ただ、その作業に見合うだけの価値がSmaart Data Modelerにあるのか?は現在の仕様では判断に迷うところです。決して安くはないですからね。
※なぜそのような調整を行ったのか?を見て分かるデータとして後々に活用できる点も利点だが、それは会社の規模による・・・
RMEも最新のデュアルDSP搭載機種にはRoom EQがあり、近年はユーザが手軽にスピーカ補正用途のPEQを扱えるようになった。機材メーカの数だけDSP調整のGUIがある為、結局は手打ちで良いのかもしれない・・・
うーん、個人的にはこういうソフトって「音が聴けない」のが最大の不満なんですよね・・・
記事の為に購入してみました。今後のさらなるバージョンアップに期待します。
ちなみに、国内代理店では下記の用途と説明しています。
参考リンク:音響特機公式サイト
・システム調整ツールとして
Smaart Data Modelerを使えば、Smaartを使って収集した測定データを、バーチャルにモデリングすることができます。この方法なら、実際の音響システムに接続せず、さらには現地に足を運ばずとも作業が可能となります。調整後、設定をDSPに実装すれば調整が完了します。
・学習ツールとして
実際のデータを使ってシステム調整をテストできるため、技術を磨きたい学生やプロにもぴったりのツールです。マルチポジションのスピーカーEQ、カーディオイドサブウーファー、メインとサブウーファーのアライメント調整など、さまざまなことを試すことができます。
・実験的なツールとして
音響調整後のデータを使用し、今後に活かすことができます。調整終了後にも「この場合は?」「あの場合は?」と試すことができるので、今後の音響改善に活かしたり、現地では達成できなかった実験的な試みも仮想的に実施できます。