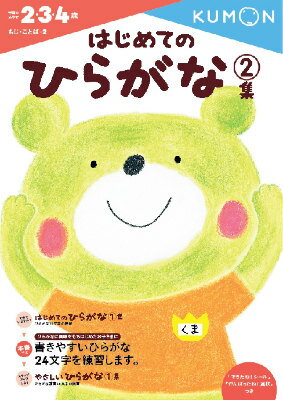#家庭で育つ学び
勉強が得意でも好きでもなかった私が、いまは息子の勉強をそばで見守っています。
まさか自分が“教える側”になるなんて——昔の自分に話しても、きっと信じてもらえないでしょう。
こんにちは。
このブログでは、家庭での学びや、親子の会話の中で生まれる小さな気づきを綴っています。

思い返せば、きっかけは息子がまだ保育園のころ。
まわりの子がスラスラと字を書いているのに、息子だけがうまく書けず、胸の奥がズンと重くなりました。
「どうしたらいいんだろう」——その戸惑いから、私の“学びとの向き合い方”が静かに変わっていったのです。
私は今、思春期の息子の勉強を日々サポートしています。このブログでは、主に幼児期から小学校6年生くらいまでの勉強サポートのこと、実際にやってよかった遊びや教材などについて書いています。
今日は「そもそも、なぜ私が息子の勉強をサポートするようになったのか」について、少し書いてみようと思います。

私は、正直、もともと人の世話やサポートには興味がそれほどなかった。
くもんに通っていた3.4才の子を持つ知り合いのママ友に、「今たし算や漢字習ってどうするの〜?、小学校ですることなくなるんじゃない?」なんてバカにしたような発言までしていた私が、どうして勉強サポートをしようと思いたったのか…。(今思えば本当に失礼な発言だったと思います💦)
「興味、関心が一番!だよね…?」
息子が小学生に上がる前、保育園でひらがなや数字の簡単な数え方などを先生が教えて下さっていた。
スイミングには通わせていたけれど、勉強を習わせたり、教えたりするつもりはなかった。息子の興味、関心を一番に考えたかったから。

「み、みんなすごい…!もうちょい教えとけば…💦」
しかし、保育園(年長さん)のとある参観日。
私は衝撃をうけた。
あまりにもひらがなが、他の子と比べて書けていないことに焦ってしまった。
他の子、特に女の子は、きれいな文字を書いていて、お手紙交換も難なくやってのけていた。
だけど、息子ときたら、文字も覚えていないばかりか、書いた字はガタガタ、書き順もめちゃくちゃ。鏡文字も…。
今から思えば、迷路などをもう少し早い段階でさせていればよかったなと思うのだけれど…。
「問題集やってみよか〜」
私は親として焦りを覚え、次の日には本屋さんの問題集コーナーへと走ってた。
その年の12月頃、市販のくもんの問題集を買ってきて、「やってみよか〜」と勉強感を出さず、私の心のあせりも表には出さず、息子に渡してみた。何にでも好奇心旺盛だった息子は、上手い具合に「うん」と言ってくれ、私と毎日問題集に取り組むことになった。

「おわりに」
こんな風に、私が勉強に目を向けるきっかけになったのは、他の子との「比較」からはじまりました。
でも、それがだめだったとは思ってはいません。
むしろ、その一歩がなければ、今のように息子の勉強サポートを続けることができなかったかもしれないと思っています。
今回は、息子の勉強サポートをするきっかけについて書いてみました。
最後まで読んで下さってありがとうございました。
あのときの小さな焦りも、いま思えば“はじまりの合図”でした。
子どもを通して、私も少しずつ学ぶようになったのかもしれません。
読解力についてのおすすめの記事は、こちらです。
遊びが学びに変わる、おすすめの記事はこちらです。
幼少期に、こういうのをもう少し熱心にさせとけばよかったな…と、のちのち思いました。
↓
🕯️ 木製デスクライト:やさしい灯りで、リビング学習を心地よい空間に。
🌏 地球儀:見るたびに世界が広がる、学びのインテリア。
🌿 小さな観葉植物:グリーンの癒しで、集中力とリラックスをプラス。
🪵 ナチュラル素材のデスク:シンプルで温かみのあるデザイン。
📚 木製トレイ・オーガナイザー:整理整頓を助ける、ナチュラルな収納アイテム。
フォローしていただけると嬉しいです🤗