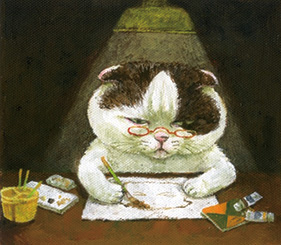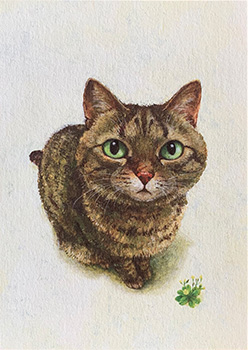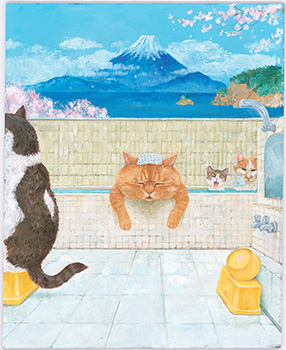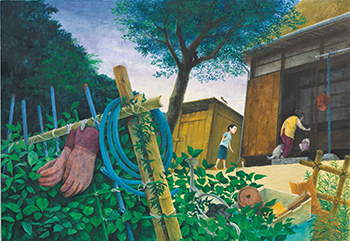トスカニーニ/ニューヨークフィル
ベートーヴェン交響曲第7番
曲目/ベートーヴェン
交響曲第7番イ長調op.92
1.第1楽章 11:29
2.第2楽章 8:42
3.第3楽章 7:09
4.第4楽章 6]56
指揮/アルトウーロ・トスカニーニ
演奏/ニューヨーク・フィルハーモニック
録音1936/4/9,10 カーネギーホール
伊JOKE SM1119
もう50年以上も前に、イタリアへ旅行した折に購入したレコードです。たまたま入店したレコード店に、このトスカニーニのジャケットがやけに目についたので購入したものです。当時はベートーヴェンの交響曲第7番一曲だけ収録されていることはあまり気にしなかったように思います。何しろそれまで名前だけは知っていましたがトスカニーニのレコードは一枚も持っていませんでした。そういう意味ではフルトヴェングラーも似たような状況でしたが、多分ウラニアの音源と同じベートーヴェンの交響曲第3番だけは持っていたでしょうか。まあ、本場のイタリアでトスカニーニのレコードが手に入ったということだけで購入したものです。
録音は良くありませんが、聴き終わってまず「完璧」という言葉が思い浮かぶような名演です。このレコードを聞いてその後、トスカニーニのベートーヴェン交響曲全集を購入したのですが、そちらは1950年代のNBC交響楽団との録音で、このニューヨークフィルハーモニーとはイメージが違ったのでのちには手放した思い出があります。まあ、それだけトスカニーニの録音の中ではこの一枚がインパクトがあったということになります。
第1楽章の序奏は、同時代のほかの巨匠と同様、ゆっくり、威厳をもって開始されます。一時期はやや遅いテンポで肥大化させた演奏が多かった時代がありますが、ここはテンポの設定・そのフォルムの構成において、理想的な第7交響曲の姿を実現しています。それでいて、リズムを弛緩させないがっしりとさせた構成で強靭なアタックでポコ・ソステヌートからヴィヴァーチェへと繋いでいます。こういう演奏を聴くとカラヤンがトスカニーニを模倣したというのが理解できます。とにかく第1楽章から風格のある演奏です。
これに対する第2楽章は第1楽章とは打って変わってあっさりした表現に見えますが、それもこの第1楽章あってのことです。のちに不滅のアレグレットとして有名になるこの楽章をそれほど感傷的ではなく淡々とリズムを刻んでいきます。「のだめカンタービレ」で一般には第1楽章が有名になりますが、小生など第7番はこの第2楽章が肝だと思っています。それが証拠に初演の時のアンコールはこの第2楽章が再演されています。この時代のニューヨークフィルにはこのトスカニーニを始めフルトヴェングラー、メンゲルベルク、のちにはワルターなどが登場し黄金期を築いていた時代です。木棺もしっとりとしたいい演奏を披露しています。
そして第3楽章。主部のプレストでは、トスカニーニのもとで鍛え上げられたニューヨーク・フィルのアンサンブルの妙を聴くことができます。弦楽器はユダヤ系のメンバーが多かったこともあり緻密なアンサンブルを披露しています。トリオは、トスカニーニ流の猛スピードで駆け抜けますが、推進力があります。ニューヨーク・フィルの水準の高さにも驚嘆させられます。
第4楽章も、安定感のある音楽運びで、爆演に走ることなく、かなり早いテンポを取っているのに・まるで激することなく冷静にオケを統率して一糸の乱れさえ見せません。この第4楽章、同一リズムが執拗に反復され、アウフタクトである2拍目にアクセントが置かれています。これは現代のロックやポップスにおけるドラムスの拍子のとり方と同じです。このためリズムに推進力が生まれ、この楽章はこの調子でスピード感のある熱狂的な雰囲気が延々と続きクライマックスを形作っていきます。このトスカニーニの解釈はまったく古さを感じさせません。
感動的なフィナーレです。
トスカニーニは1928年から七年間、ニューヨークフィルの常任指揮者を勤めました。したがってNYPを指揮したベートーヴェンの七番は決別直前のものである。オーケストラの各楽器のソロは名人芸ぞろいの上、アンサンブルもしっかりと整っていて、現在でも模範とするにたる名演である。
トスカニーニの演奏については、ここ最近頻繁に取り上げているが、今日はその中からベートーヴェンの交響曲第7番をご紹介したい。この曲、もポピュラーになったが、もともと名作で、SP、LP時代には、トスカニーニやフルトヴェングラーのレコードが時に奪い合いになるほどよく売れたという話だ。名盤も多く、トスカニーニ(1936、1950年代盤)、フルトヴェングラー(1943、50年盤)、カルロス・クライバー(1976年、1983年)などと伝説の巨匠たちが、複数の演奏を残しており、聴き比べの面白さにも事欠かない。
今回ご紹介する、トスカニーニとニューヨーク・フィルの演奏は、トスカニーニ特有の気迫、情熱とともに、客観性、造形にも優れる、この曲の古典的名演と形容できる。トスカニーニには、1950年代のNBC響との「全集」からの録音もありますが、ニューヨーク・フィルの指揮者最後の年となったこちらの盤石な演奏のほうに軍配を上げるものです。
下の録音は今までのいかにもSPという音ではないマスタリングになっていて非常に聞きやすくなっています。