前回 は、
重い高山病にかかってしまった中高年の男性がいる
との連絡を受け、現場に駆けつけた、
というところまでお話をしました。
7合目半ばの現場には、
男性が意識のない状態で横たわっていました。
「これは早く運ばなければ大変なことになる」
私たちにも緊張が走ります。
1人は持ってきた酸素ボンベを口にあてがい、
残りの4人でタンカを持ちます。
高山病にかかってしまった場合、最も有効なのは、
一刻も早く高度を下げること
です。
たったそれだけの事で、
ウソのようにケロッと治ってしまう人がほとんどなのです。
とはいえ、この男性のように、
あまりにも重症化してしまった場合は、
どうなるか全くわかりません。
男性に酸素を吸わせながら、
夜間で混雑する富士山の登山道を大急ぎで下っていきます。
富士山は、
山頂でご来光を見るのを目的に登る人が非常に多く、
昼間よりも夜間の方が混雑します。
夏の富士山は日本で唯一、眠らない山なのです。
男性の奥さんも、
とても心配そうにすぐ後をついてきていました。
そして、
30分ほど下った頃でしょうか。
男性が意識を取り戻したのです。
「ああ、良かった・・・」
とはいえ、
まだまだ話ができる状態ではなく、全く予断の許さない状況。
引き続き、急いで男性を下まで運んでいきます。
すると、男性の容態はさらに良くなったようで、
泣きながらお礼を言い始めたのです。
「ありがとうございます・・・。ありがとうございます・・・。」
そばにいた男性の奥さんも、泣きながらお礼を言っていました。
実は、この仕事をやる前は、
遭難者救助の仕事があるなんて、
全く聞かされていなかったのです。
ところが、
常駐する6合目の安全指導センターに到着し、最初の救助要請が来た時、
なぜか当たり前のように救助活動をやることになっていました。
・昼間の巡回登山
・1日の報告書の作成
・センター内の掃除
・関係者10人分の食事の用意と後片付け
・登山者数のカウント調査(早朝と夜に1時間ずつ)
など、これら一連の仕事をこなすだけでも十分に大変でした。
そのうえ、
これら全部の仕事よりもきつい遭難者救助を行うことに、
私は少なからず不満を抱いていました。
体には常に疲れがが残っていて、
毎日がギリギリの状態だったのです。
でも、この男性をタンカで運び、
涙で顔をクシャクシャにしながらお礼を言われた時、
「俺はなんてくだらないことを考えていたんだろう。この人を助けることができたんだから、それでいいじゃないか」
こんな仕事は聞いていないとか、
そんなことはどうでもよくなったのです。
人の命を助ける仕事に関わることができる
ただそれだけですごく貴重な経験をさせてもらっている
この時以来、素直にそう思えるようになりました。
その後は、男性を無事に6合目まで下ろし
男性は車で病院へと運ばれていきました。
このように、
高山病というのは、重症化すると命に関わることもあります。
もしかかってしまったら、すぐに高度を下げること
これに尽きますが、
そうなってしまったら登頂することはできません。
富士山に登頂するためには、
いかに未然に高山病を防ぐか
これが非常に大切なのです。
次回 は、
高山病の症状について
です。
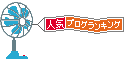
人気ブログランキングへ